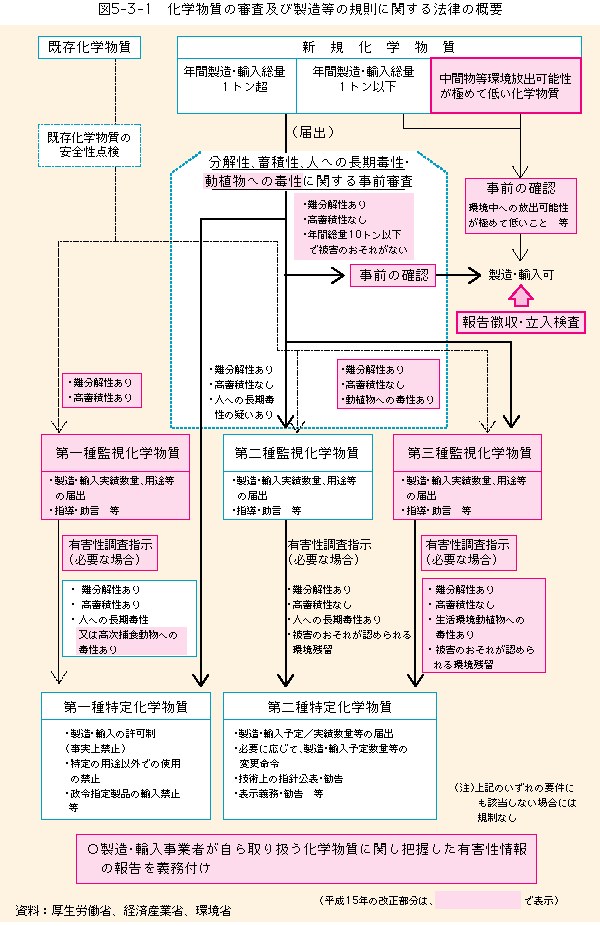
1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組
化学物質審査規制法は、新たな工業用化学物質(新規化学物質)の有害性を事前に審査するとともに、化学物質の有害性の程度に応じて製造・輸入などについて必要な規制等を行うものです。
平成15年5月の改正により、環境中の動植物への被害の防止が法律の目的に加えられ、分解性、蓄積性、人への長期毒性に加えて、新たに動植物への毒性も考慮した審査・規制が行われることとなりました。また、1)難分解・高蓄積性の既存化学物質に関する規制(第一種監視化学物質の制度)、2)環境中への放出可能性に着目した審査の特例(低生産量新規化学物質(難分解性ではあるが高蓄積性でなく製造・輸入数量が年間10t以下である化学物質)や中間物(他の化学物質の原料として使用され、全量が他の化学物質に変化する化学物質)等の特例)、3)事業者が入手した有害性情報の報告の義務付けの制度も導入されました。この改正法は16年4月に施行されました。
平成16年度は、新規化学物質の製造・輸入について431件(うち低生産量新規化学物質については194件)の製造・輸入の届出があり、審査を行いました。
また、昭和49年の化学物質審査規制法公布時に製造・輸入されていた化学物質(既存化学物質)等の安全性点検を行っており、そのうち平成16年度には分解性・蓄積性に関する試験を45物質、人への健康影響に関する試験を35物質、生態影響に関する試験は42物質に対して行いました。
こうした事前審査等を通じて、平成17年3月末までに、第一種特定化学物質としてPCB等13物質、第二種特定化学物質としてトリクロロエチレン等23物質、第一種監視化学物質として酸化水銀(II)等22物質、第二種監視化学物質としてクロロホルム等842物質を指定し、製造・輸入等について必要な規制を行っています(図5-3-1)。