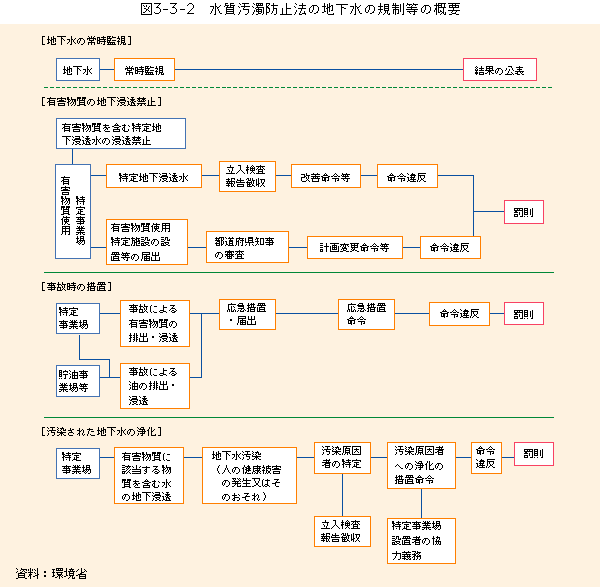
3 水環境の安全性の確保
(1)水道水源の水質保全対策
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)に基づき、平成16年末までに6県11か所から該当県に対して水道原水水質保全事業の実施の促進の要請がなされ、これらを受けて、9か所に都道府県計画が、1か所に河川管理者事業計画が策定されました。
(2)地下水汚染対策
地下水汚染の未然防止対策については、水質汚濁防止法に基づき、トリクロロエチレン等有害物質を含む水の地下への浸透の禁止、都道府県知事による地下水の水質の常時監視等の措置がとられています。また、汚染された地下水の浄化のためには、水質汚濁防止法により、都道府県知事が汚染原因者に対し汚染された地下水の浄化を命令することができることとなっています(図3-3-2)。
環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」等を活用し、地域の実情に応じた取組を推進しました。また、硝酸性窒素による地下水汚染が見られる地域において浄化技術の実証調査を実施し、効果的な浄化手法の確立に向けた取組を行いました。
(3)有害物質による汚染底質除去対策
ダイオキシン類による底質汚染については、底質環境基準を超えた水域において、底質の除去等の対策又はその検討を行いました。水銀による底質汚染については、暫定除去基準を超えた水域の対策は、平成2年7月末で終了しました。なお、このほかに自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されています。PCBによる底質汚染については、16年11月に佐世保港(佐世保市)の底質の除去を終了したことにより、対策を講じる必要がある79のすべての水域の対策が終了しました。
(4)漁業公害等調査
水銀やダイオキシン類等有害物質の魚介類中での蓄積状況把握、蓄積機構解明、試験方法検討などの調査のほか、二枚貝等が体内に蓄積する貝毒のモニタリング手法の検討、内湾域における発電所の取放水による漁業の影響についての検討等を行いました。
(5)農薬汚染対策
農薬については、水質汚濁の未然防止を図る観点から、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき水質汚濁に係る登録保留基準を定めており、平成16年度においては、6農薬(うち基準値改正1農薬を含む。累計133農薬)の基準値を設定しました。さらに、農薬による生態系への悪影響の未然防止に係る取組を強化するため改正した水産動植物に対する毒性に係る農薬登録保留基準について、17年4月の円滑な施行に向け、登録申請の際に必要な試験法の整備等の体制づくりを行いました。