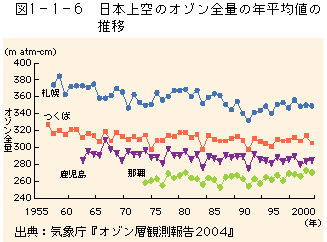
2 オゾン層の破壊
(1)問題の概要
CFC、HCFC、ハロン、臭化メチル等のオゾン層破壊物質によりオゾン層が破壊されていることが明らかになっています。オゾン層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外線(UV−B)が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害を発生させるおそれがあるだけでなく、植物やプランクトンの生育の阻害等を引き起こすことが懸念されています。
オゾン層破壊物質は化学的に安定なため、大気中に放出されると対流圏ではほとんど分解されずに成層圏に達します。そして、成層圏で太陽からの強い紫外線を浴びると、分解され、塩素原子や臭素原子を放出します。これらの原子が触媒となり、オゾンを分解する反応を連鎖的に引き起こします。
オゾン層の破壊は、その被害が広く全世界に及ぶ地球規模の環境問題であり、いったん生じるとその回復に長い時間を要します。
(2)オゾン層等の現況と今後の見通し
オゾン層は、熱帯地域を除き、ほぼ全地球的に減少傾向が続いています。日本では、札幌、つくば、鹿児島、那覇及び南鳥島でオゾン量の観測が行われており、札幌、つくば、鹿児島で長期的な減少傾向がみられ、その傾向は札幌において最も大きくなっています(図1-1-6)。
また、2003年(平成15年)の南極域上空のオゾンホールは、過去最大規模に発達しました(図1-1-7)。近年の状況を見ると、オゾンホールの規模は、やや鈍化したものの長期的には拡大の傾向が続いており、南極域のオゾン層は依然として深刻な状況にあります。
オゾン層破壊物質のうち、北半球中緯度におけるCFC-12の大気(対流圏)中濃度については、1990年代後半以降ほぼ横ばいです。一方、代替先の一種であるHCFC及びHFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。
有害紫外線の量については、日本においては1991年(平成3年)の観測開始以来、明らかな増加傾向はみられていません。しかし、同一条件下では、オゾン量の減少に伴い有害紫外線の地上照射量が増加することが確認されていることから、1970年代に比べてオゾン量が減少している地域においては、有害紫外線量は増加しているものと考えられます。
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(モントリオール議定書)のアセスメントパネルの報告(2002年(平成14年))によると、
1) 成層圏観測における塩素総量はピークかそれに近いが、臭素量は依然として増加していること
2) 化学・気候モデルでの予測では、成層圏のハロゲンが予想どおり減少すれば、南極域のオゾン層は2010年(平成22年)頃に回復に向かい、今世紀中頃には1980年(昭和55年)レベルに戻ること
3) 観測データが蓄積されるにつれ、オゾン量の減少が紫外線放射量の増加をもたらしていることが確証されつつあることなどが報告されています。