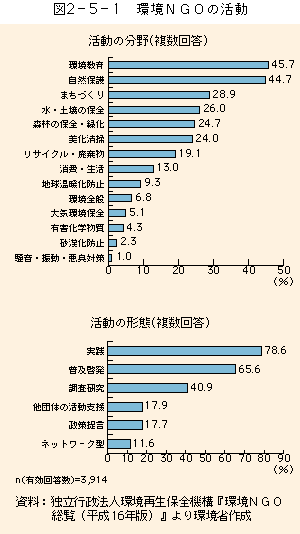
2 市民団体による環境の人づくり
「環境NGO総覧(平成16年版)」(独立行政法人環境再生保全機構)によると、環境NGOの活動分野は、「環境教育」が45.7%と最も多く、「自然保護」(44.7%)、「まちづくり」(28.9%)、「水・土壌の保全」(26.0%)と続いています(図2-5-1)。
市民団体による環境教育・環境学習に関する活動内容は、教材開発、講師派遣、プログラム実施、 コーディネート等多岐にわたっており、環境教育・環境学習の対象も市民、学校、児童、企業向け等、個々に適したプログラムを提供しています。
こうした市民団体による環境教育・環境学習は、一人ひとりに環境への配慮や自発的な環境保全活動を促す上で重要な役割を果たしており、さらなる取組が期待されます。
(1)市民団体が行う環境教育
任意団体として活動している岩手子ども環境研究所は、岩手県葛巻町にある廃校を、持続可能な地域づくりを楽しみながら学ぶ場所「森と風のがっこう」として再利用し、伝統的な知恵や文化、自然エネルギーの利用等についての学ぶ場を設けています。「森と風のがっこう」では、伝統的な知恵や文化、自然エネルギーの利用等について学ぶ講座が開かれています。この「がっこう」には太陽光発電、風力発電、ペレットストーブ等自然エネルギーを体験できる施設があり、参加者に、自然エネルギーの利用について生活の中から考えてもらいます。また、葛巻町教育委員会と共催で、自然の中で子どもが遊びと学びを体験する「子どもオープンデー」を毎月開催しています。この講習会では、森の中へ出かけ、じっくり葉っぱを見て、触って、匂いを嗅ぐという、遊びの要素だけでなく観察し実感する要素も取り入れたプログラム等を行っています。(http://www5d.biglobe.ne.jp/~morikaze/)
(2)環境学習の支援、コーディネート
特定非営利活動法人(NPO法人)環境学習研究会は、東京都が実施した環境学習リーダー講座の修了生30名によって設立された団体です。この研究会による授業支援は、先生たちと一緒に授業を作ることに特徴があり、研究会のスタッフが事前に学校を訪問して授業の位置付けを確認し話し合いを行い、その後、先生と研究会それぞれが授業案を考えた上で授業内容を検討します。また、協賛企業との協働による教育も行われており、例えばごみをテーマにした授業を行うときは、協賛企業の一つである飲料メーカーの社員が授業を行います。
また、この研究会では、環境ネットワークマガジン「ecok東京」を、都内の全小・中・高等学校に隔月で無料配布しています。この情報誌には、環境学習に活用できる情報や教材等を紹介するとともに、授業の事例なども掲載しています。単に情報を提供するだけでなく、掲載された内容を実践したい学校に対して、編集部である研究会が、コーディネートやアドバイスを行っています。(http://www.ecok.jp/)