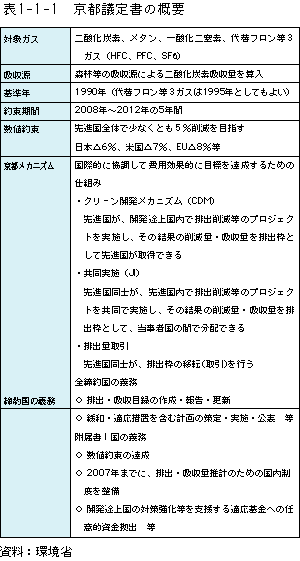
1 京都議定書が発効した
平成9年12月に京都で開催された、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3。以下「京都会議」という。)において、日本が議長国として取りまとめ、全会一致で採択された京都議定書が、平成17年2月に発効しました。これを機会に、京都議定書とは何かを振り返り、発効の意味を考えます。
(1)数値約束を定めた京都議定書
京都議定書は、気候変動に関する国際連合枠組条約(以下この章において「条約」という。)に明記されている、「共通だが差異ある責任及び各国の能力に従い」「先進国が率先して気候変動に対処すべき」との考え方に基づき、先進国及び市場経済移行国(附属書I国)の温室効果ガス排出量の削減に関する具体的な数値約束を初めて定めた画期的なものです。この議定書は、目標達成のための政策・措置の選択が各国に委ねられたこと、各国の数値約束が差異化されたこと、森林等の吸収源による二酸化炭素吸収量を算入すること、京都メカニズムが導入されたことなどの点でも重要な意味を持っています(表1-1-1)。
(2)多くの国が締結して発効した
京都議定書の具体的運用ルールは平成13年に開催された条約の第7回締約国会議(COP7)において、マラケシュ合意として正式に文書化されました(表1-1-2)。
マラケシュ合意により、各国では議定書批准の準備が整い、EUや日本などの主要な先進国の締結が進みました。そして、平成16年11月にロシアが批准したことにより、発効の要件が満たされました(図1-1-1)。