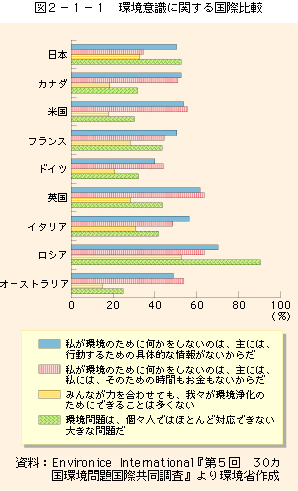
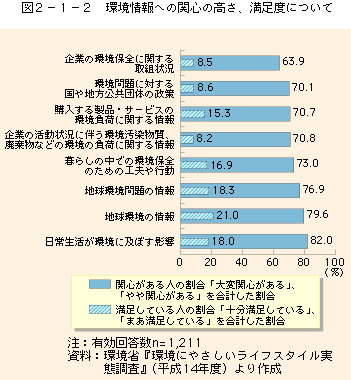
|
第2章
|
くらしを深める「環境の心」 |
| 第1節 社会で育む「環境の心」 |
|
1 環境保全の意識と情報
|
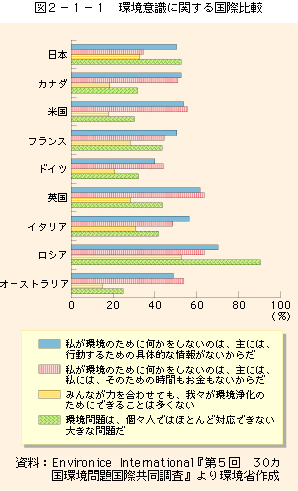 |
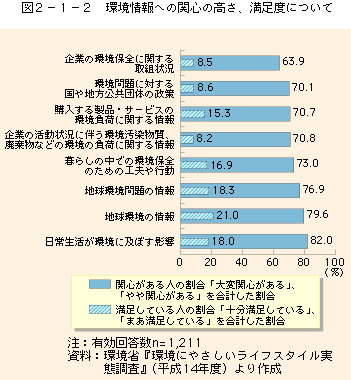 |
|
2 日本に伝わる「環境の心」
|
|
コラム1
|
「共有地の悲劇」と環境問題 |
| 「共有地の悲劇」は、1968年にハーディンが発表した行動モデルで、環境問題との関連などで議論されています。共有地である牧草地で人々が羊を飼っている場合、牧草地の容量内において羊を飼育している限り、問題は生じません。しかし、羊を多く飼育して多くの収入を得ようとその頭数を増やしていくと、やがて牧草地の容量を超え、牧草は枯渇します。 個人にとっては、増やした羊分だけ利益が多くなりますが、その一方、牧草の減少により牧草地全体で見れば損失が多くなります。しかし、後者については全体の中に分散するため、個人の経済的利潤のみを追求した場合には、羊を増やすことの方が合理的な判断となり、このようなことが起こります。 これは環境問題にも当てはまります。例えばエアコンの効いた部屋で快適に過ごしたり、自動車に乗ることは、個人の利益の達成ということでは合理的な判断といえます。しかし、多くの人が同じように行動すれば、結局は地球温暖化が進み、多くの人がその被害を受けます。 |
|
|
コラム2
|
「もったいない」と日本の心 |
「もったいない」という日本語に、私たちが昔から受け継いできた「環境の心」が表れています。広辞苑によれば、「もったい」とは、「物の本体」で、「もったいない」は「物の本体を失する」こととされています。「もったいない」の意味としては「そのものの値打ちが生かされず無駄になるのが惜しい」が挙げられていますが、このほかに、「神仏、貴人などに対して不都合である、不届きである」という意味も記されています。 日本人は、このような「環境の心」を持ちながら、壮麗さよりも簡素で繊細な美を極め、物量よりも風雅な趣を楽しむ生活を貴んできました。「もったいない」は、自然を敬う日々の中で暮らしてきた、いにしえの日本人の子孫として、美しい環境を後の世代に伝える上から、大切にしたい言葉です。 |
|
| 第2節 「環境のわざ」を支える消費と投資 |
|
1 グリーン購入
|
| 環境に配慮された製品やサービスを選択し、購入することを「グリーン購入」と、グリーン購入に取り組んでいる人を「グリーンコンシューマー」と呼びます。グリーン購入は、市場を通しての消費者からのアプローチであり、事業者に対し環境負荷低減への取組を働き掛けていこうとする行動であると同時に、環境対策等に積極的な事業者に対する支援ともなっています。 (1)グリーン購入の状況 国等の各機関のグリーン購入は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)で義務付けられ、取組が進められています。また、多くの都道府県・政令指定都市や大規模な事業者等でも組織を挙げてグリーン購入に取り組んでいます(図2-2-1)。 |
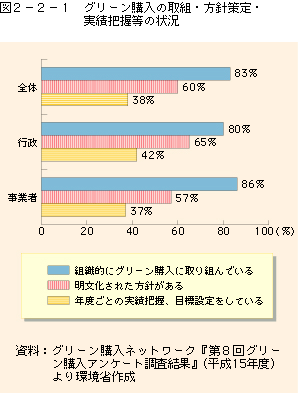 |
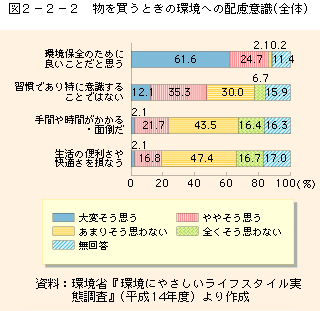 |
 |
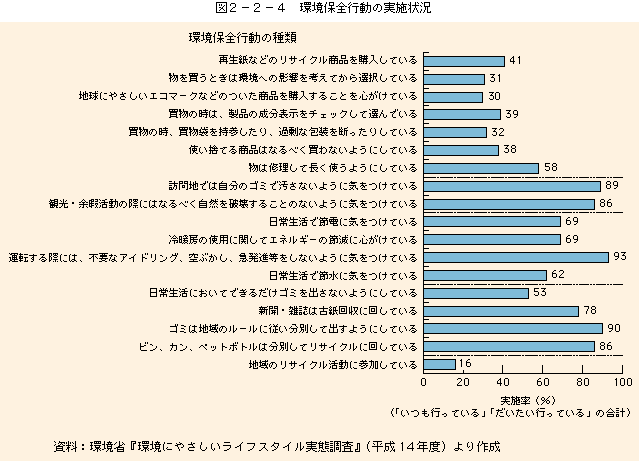
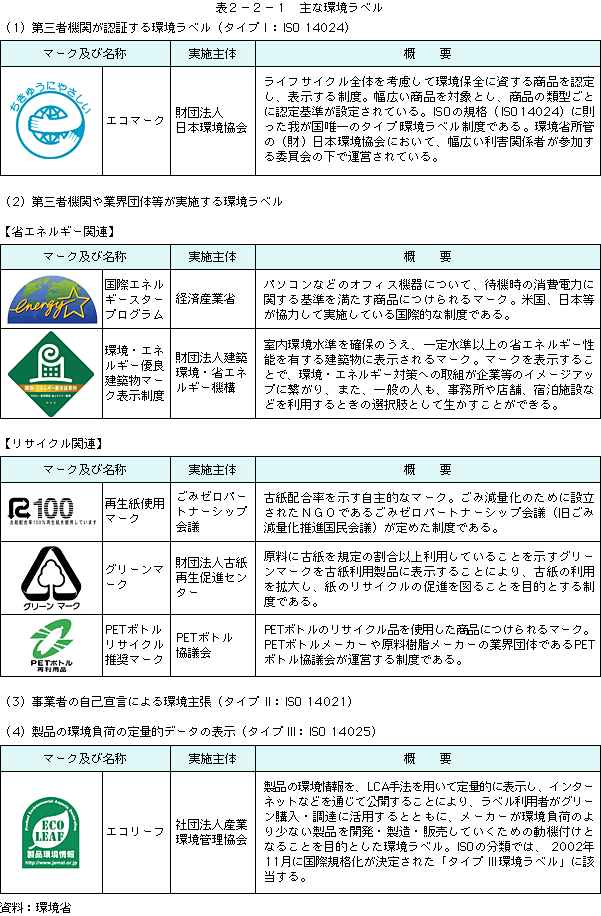
|
2 環境に配慮した投資
|
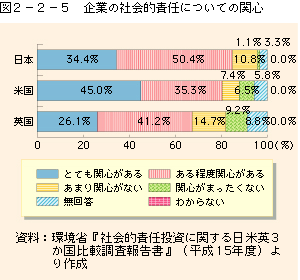 |
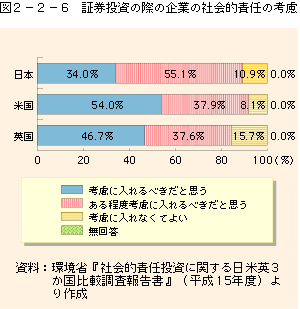 |
| 日本では、社会的責任投資に「関心がある層」の3分の2以上が、また「関心がない層」の半数以上が、エコファンドなどについての情報不足を訴えています(図2-2-7)。今後、情報不足を解消して実際の購買行動へと結びつけるためには、社会的責任投資の内容や考え方の広報、運用報告書の工夫、社会的責任投資に携わる販売員の教育や研修等が有効と考えられます。 | 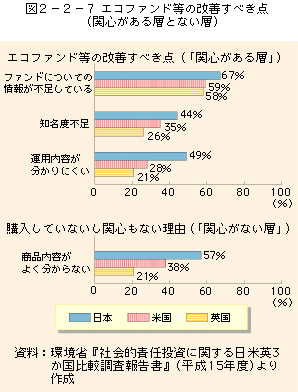 |
| 第3節 くらしの中で環境保全 |
|
1 日常生活からの環境負荷と物質収支
|
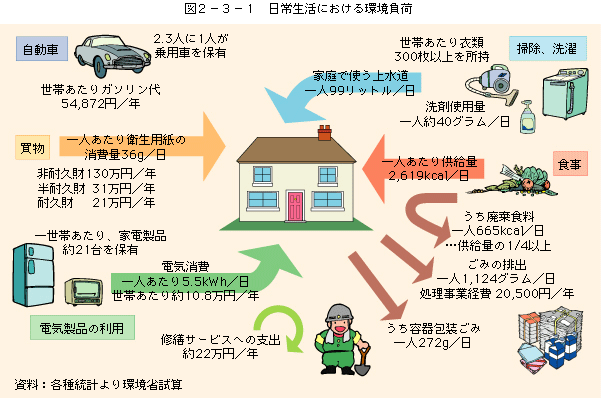
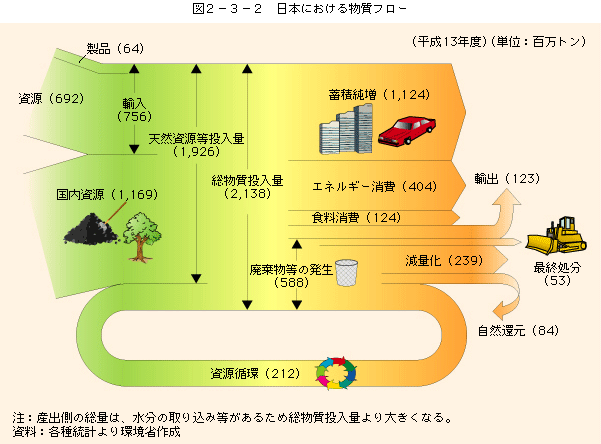
|
2 環境に配慮した行動の提案
|
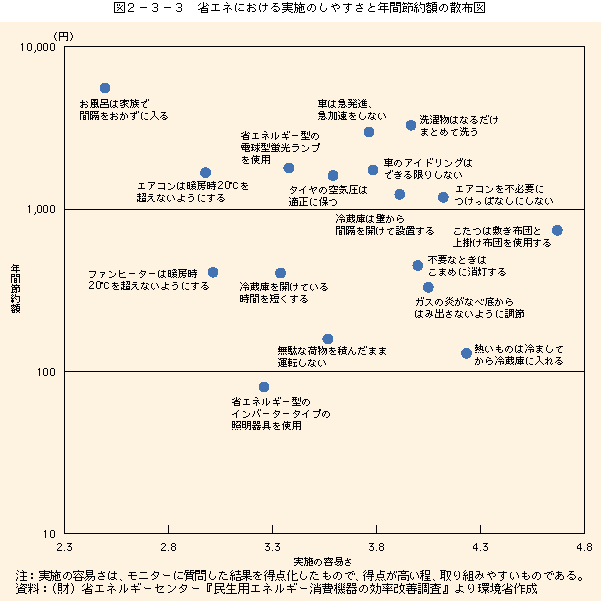
|
(2)食からの環境負荷の低減 最近、季節や地域に関わりなく、さまざまな食品を手に入れることができるようになりました。輸入も含めた食品供給地の拡大が原因の一つですが、加温したビニールハウス等の施設栽培率の増加も一因です。加温栽培には多くのエネルギーを要し、二酸化炭素の排出量を増やしています(図2-3-4)。旬の時期に旬のものを食べることは、自然の移り変わりを意識し失われつつある季節感を回復するとともに、環境にも貢献するくらし方です。 |
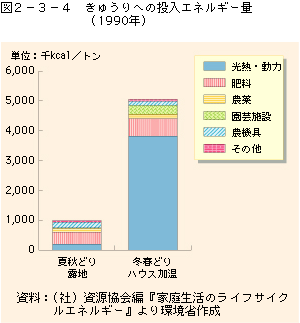 |
|
(4)屋上緑化と壁面緑化 都市部の開発・都市化等により、自然環境が変えられ自然との関わりが減少しています。自然の減少は、潤いやゆとりの喪失だけでなく、大気汚染、生物多様性の減少、防災機能の低下や都市のヒートアイランド現象なども招きます。こうした問題を解決するためには、都市公園や街路樹のみならず、庭園のほか、屋上や壁面など建築物における緑化が必要です。 屋上・壁面緑化は、夏季の室温上昇を抑制し、冷房の省エネに貢献します。また、騒音の低減や建築物の保護、空気の浄化や都市気象の改善にも役立ちます。 |
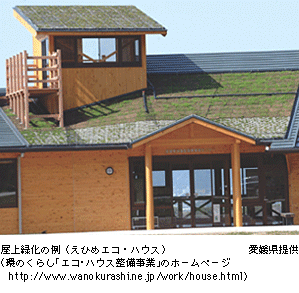 |
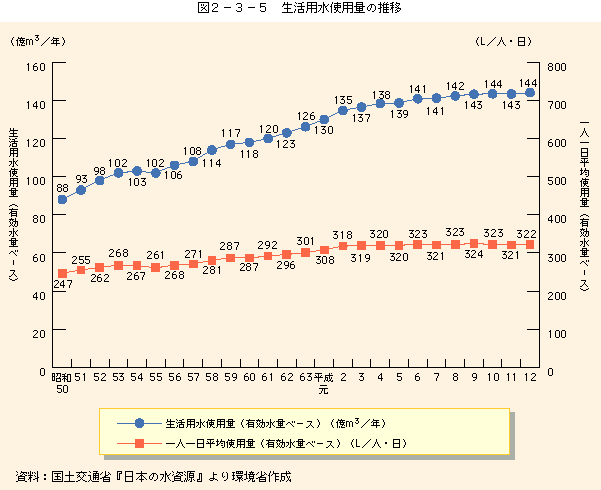
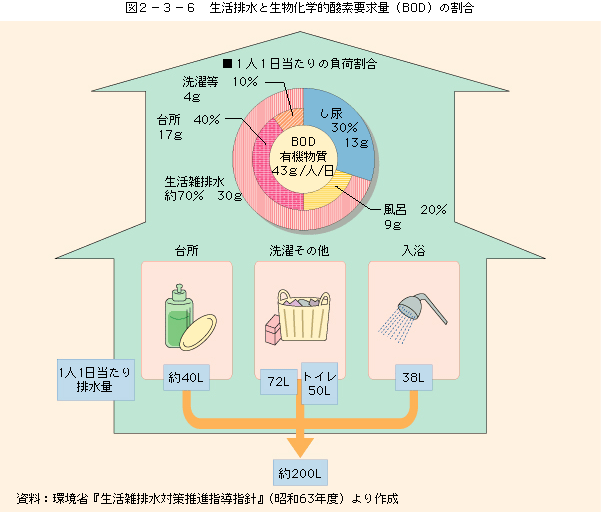
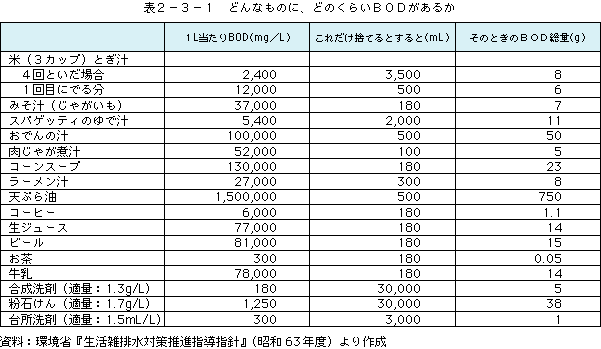
|
コラム1
|
「環のくらし」を目指して |
| 政府は、持続可能な簡素で質を重視する循環型社会としての「環の国」を目指して、「環の国くらし会議」を開催しました。具体的提案を掲載した「私の環のくらし ハンドブック」や、低公害車、省エネ家電、住宅等地球温暖化防止への取組を支援する具体的な商品やその使い方等を紹介した「環のくらし応援BOOK」、「同 Part・2」を作成し、「環のくらし」の実践を呼びかけるメッセージを発信しました。 (「環のくらし」のホームページ http://www.wanokurashi.ne.jp) |
|
|
コラム2
|
鳥や虫の来る庭 |
|
自然と関わる一つの手段として、生物の生息・生育空間であるビオトープがあります。ビオトープは主に学校や公園などで作られてきましたが、最近では、家庭の庭やベランダ、屋上などに、野生の鳥や虫などが来られる小さな草地や水辺、木立などを作る動きがあります。 (「おしえてビオトープ」のホームページ http://www.env.go.jp/nature/biodic/eap61/) 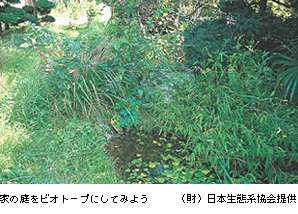 |
|
|
コラム3
|
水洗トイレの音消し水 |
| 水洗トイレは、節水型の機種でさえ一回に8lもの水を必要とします。水道水を供給するためには、水源から取水して浄化し、各家庭に配水するまでに多くのエネルギーが消費され、その結果、二酸化炭素が排出されます。 音を消すためにこの水を流さないように、擬似的な流水音を出す装置が設置され、節水の効果が出ています。 しかし、海外では、そもそも周囲を気にして音消し水を流す習慣はないといわれています。 |
|
| 第4節 環境保全のまちづくり |
|
1 各地域での取組
|
| (1)風力発電を使ったまちづくり(高知県梼原町) 梼原町は、高知県中西部の四万十川の源流域である四国カルスト高原に位置する山間の町です。平成8年度からの風況調査により、風力発電所の建設に最良の条件にあることが実証され、風力発電を中心とした環境保全の取組(「風をおこし、町をおこす」)が進められています。 建設に当たっては、住民との意見交換会を実施し、風力発電によるCO2削減に貢献するだけでなく、売電収益を環境基金とし、住宅用太陽光発電の設置や間伐による健全な森林づくりへの活用など、さらに環境を良くしていこうという取組が行われています。 また、住民の環境に対する意識が高く、「環境整備デイ」などを立ち上げ、次代を担う人材を育成するとともに、千枚田オーナー制度などコミュニティに根ざした環境保全の取組も行われています。 (梼原町のホームページ http://www.town.yusuhara.kochi.jp/) |
 |
| (2)コウノトリと共生するまちづくり(兵庫県豊岡市) 豊岡市は、兵庫県の北東部の豊岡盆地に位置します。日本産の野生のコウノトリの最後の生息地だった豊岡市では、都市像として「コウノトリ悠然と舞い 笑顔あふれる ふるさと・豊岡」を掲げ、まちづくりを行っています。 具体的には、「コウノトリと共生するまちづくり」を目指し、「15の元気メニュー」を市民・事業者・行政等の協働により展開し、農家による「田んぼビオトープ」づくりや「無農薬によるアイガモ農法」、市民による「コウノトリ感謝祭」などを、全市一体となって取り組んでいます。また、平成12年4月には、「豊岡市コウノトリ基金」が設立され、田んぼをコウノトリの生息地にするためなどに活用されています。14年には、こうした取組が功を奏してか、大陸から1羽のコウノトリが飛来し、住みつきました。 (豊岡市のホームページ http://www.city.toyooka.hyogo.jp/) |
 |
| (3)ごみ減量を通じたまちづくり(東京都日野市) 日野市は、東京都のほぼ中央に位置し、市の北部には多摩川が、中央部には浅川が流れ、南部はゆるやかな丘陵地となっています。 日野市では、平成6年の直接請求による環境基本条例の提案、平成10年の公募市民などによる環境基本計画の策定をはじめとして、市民と行政がパートナーシップを組んで身近な環境問題に取り組んでいます。平成12年には、市民と共に「ゴミゼロのまちづくり」を目指して、約3万人の市民に「ごみ改革」の必要性を説明し、分別ごみの戸別収集、ダストボックスの全面撤去を行いました。これらの活動の結果、「ごみ改革」の1年後にはごみの約50%減量を達成し、さらに最終処分場の延命化にも貢献するなど効果を上げています。 (日野市のホームページ http://www.city.hino.tokyo.jp/info/) |
 |
|
(4)川の流域で連携した取組(宮川流域ルネッサンス協議会(三重県)) 三重県のほぼ中央を東西に流れる宮川(延長:90.7km)の流域14市町村(伊勢市、多気町、明和町、大台町、勢和村、宮川村、玉城町、二見町、小俣町、大宮町、紀勢町、御薗村、大内山村、度会町)、県、国関係機関が、宮川流域(流域面積:920km2)の自然・歴史・文化の保全や再生を推進するため、平成12年度に「宮川流域ルネッサンス協議会」を設立し、広域での連携した活動を行っています。 活動内容としては、住民自らが「流域案内人」として地域の魅力を来訪者に伝え、交流を通じて地域の魅力を再発見、探求、創造し、環境意識を高めています。来訪者も流域の豊かな環境を体感することができます。また、水質等水環境調査や住民啓発パンフレットの作成、流域情報誌の発行、子どもへの啓発事業の実施を住民と協働で行う等、流域レベルでのネットワークづくりも展開されています。 こうした事業の推進により、この地域での行事(宮川流域エコミュージアム)への平成14年度の来訪者数は、約2,000人となっています。 (宮川流域ルネッサンス協議会のホームページ http://www.miyarune.jp/) |
 |
|
コラム
|
Tokyo Half Project 東京からのCO2排出の半減を求めて- |
| Tokyo Half Project は、現在の経済活動レベルを維持しつつ、東京都で発生する温室効果ガス(主に二酸化炭素)を半減することを目標に、いかなる技術群の導入が望ましいかを統合的に評価する研究です。東京大学が中心となって、海外の大学を含めた共同の学際的研究プログラムとして実施されています。 この研究は、学際的な温室効果ガス削減対策の国際共同研究として、個別の評価モデルを連結して全体モデルを構築するものです。都市の温室効果ガスの削減には複合的な対策を行っていく必要があり、こうした学際的研究が注目されています。(Tokyo Half Projectのホームページ http://www.thp.t.u-tokyo.ac.jp/) |
|
|
2 環境と経済の好循環のまちづくりに向けて
|