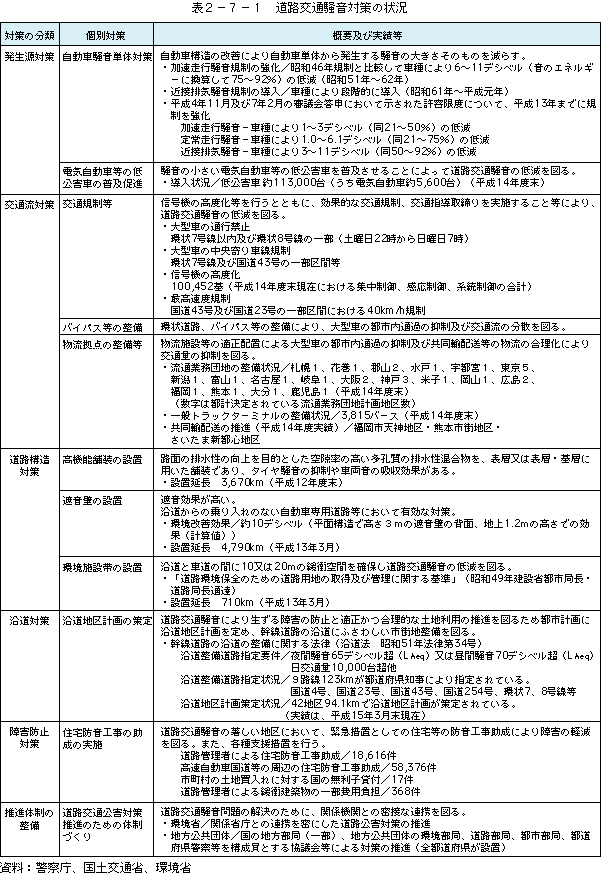
1 騒音・振動対策
(1)騒音規制法及び振動規制法による規制の実施
騒音・振動対策については、主に「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)及び「振動規制法」(昭和51年法律第64号)に基づき、規制等を実施しています。騒音規制法及び振動規制法では、騒音・振動を防止することにより生活環境を保全すべき地域を都道府県知事(指定都市・中核市・特例市にあってはその長)が指定し、この指定地域内にある、法で定める工場・事業場及び建設作業の騒音・振動を規制するとともに、自動車から発生する騒音の許容限度を環境大臣が定め、市町村長が都道府県の公安委員会に対して「道路交通法」(昭和35年法律第105号)の規定による措置を要請することができる要請限度制度が定められています。
(2)工場・事業場及び建設作業による騒音・振動対策
騒音規制法及び振動規制法では、指定地域内にあって金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」という。)と、指定地域内においてくい打ち作業等の政令で定める特定建設作業を伴う建設工事が規制の対象となります。指定地域内の特定工場等の総数は平成14年度末現在でそれぞれ騒音規制法は208,389、振動規制法は120,916で、14年度には、騒音規制法及び振動規制法に基づく改善勧告がそれぞれ5件、1件、苦情に基づく行政指導がそれぞれ905件、136件行われました。14年度に行われた特定建設作業に係る実施の届出件数はそれぞれ64,694件、28,139件でした。14年度には、騒音規制法及び振動規制法に基づく改善勧告及び改善命令は行われませんでしたが、苦情に基づく行政指導がそれぞれ1,312件、495件行われました。建設作業の騒音・振動については、適切な規制のあり方を検討するため、建設作業場から発生する騒音・振動について実態調査を行いました。
(3)自動車交通騒音・振動対策
自動車交通騒音・振動問題を抜本的に解決するため、自動車単体の構造の改善による騒音の低減等の発生源対策、交通流対策、道路構造対策、沿道対策等の諸施策を総合的に推進しています(表2-7-1)。
自動車単体から発生する騒音を減らすため加速走行騒音、定常走行騒音、近接排気騒音の3種類について規制を実施しています。また、暴走族による深夜の爆音暴走を防ぐため、消音器不備、空ぶかし運転等に対する取締りや初日の出暴走など不正改造車両の取締りを強化し、関係省庁が連携して暴走族対策に取り組んでいます。
しかし、幹線道路の沿道地域を中心に環境基準の達成率は依然として低く、一層の騒音低減が必要なため、平成15年度から自動車単体騒音対策検討・調査を開始しました。
また、政府では、道路交通環境が厳しい地域を対象として、警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成される道路交通環境対策関係省庁連絡会議において対策が検討されていますが、この会議において取りまとめた「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針」(平成7年12月)に沿って、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の各種対策の総合的実施を図っています。また、この実施方針を受け、現在までにほとんどの都道府県等で関係行政機関の参加による道路交通騒音対策のための協議会等が開催され、対策が検討されています。
なお、要請限度制度に基づき、自動車騒音について、平成14年度に地方公共団体が苦情を受け測定を実施した199地点のうち、要請限度値を超過したのは30地点で、同様に、道路交通振動については、測定を実施した121地点のうち、要請限度値を超過したのは3地点でした。また、自動車騒音に関して、市町村長が道路管理者に対して意見陳述を行った件数は、平成14年度は7件でした(表2-7-2)。
(4)航空機騒音対策
一定の基準以上の騒音を発生する航空機の運航を禁止する耐空証明(旧騒音基準適合証明)制度については、逐次規制の強化が行われ、昭和53年に強化された騒音基準に適合しない航空機については、平成14年4月1日以降運航を禁止しています。また、緊急時等を除き、新東京国際空港については午後11時から午前6時までの間、大阪国際空港については午後10時から午前7時までの間、航空機の発着を禁止しています。さらに、大阪国際空港においては、午後9時以降定期便のダイヤを設定しないこととしています。
発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(昭和42年法律第110号)等に基づき空港周辺対策を行っています。同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際、大阪国際、福岡等15空港であり、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料の助成等を行っています(表2-7-3)。
また、大阪国際空港及び福岡空港については、周辺地域が市街化されているため、同法により計画的周辺整備が必要である周辺整備空港に指定されており、国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された空港周辺整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画に基づき、上記施策に加えて、再開発整備事業、代替地造成事業等を実施しています。
コミューター空港、ヘリポート等については、環境基準が適用されない小規模なものが多く、平成2年9月に制定したこれらの騒音問題の発生の未然防止を図るために必要な環境保全上の指針を踏まえて、諸施策を実施しています。
自衛隊及び在日米軍の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、消音装置の設置・使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっています。在日米軍における音源対策、運航対策については、日米合同委員会等の場を通じて協力を要請しており、厚木、横田、嘉手納及び普天間の各飛行場における航空機の騒音規制措置が合意されています。
自衛隊等の使用する飛行場に係る周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和49年法律第101号)を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、移転補償、緑地帯等の整備、テレビ受信料の助成等の各種施策が実施されています(表2-7-4)。
なお、平成15年度末現在29飛行場周辺について同法に基づく区域指定がされており、住宅防音工事の助成等が実施されています。
(5)鉄道騒音・振動対策
東海道・山陽・東北及び上越新幹線については、「国鉄改革後における新幹線鉄道騒音対策の推進について」(昭和62年3月閣議了解)及び環境庁長官の勧告等に基づく運輸大臣の通達を受けて、鉄道事業者が対策を実施しました。具体的には、音源対策として、防音壁の嵩上げ、改良型防音壁の設置、レール削正の深度化、バラストマットの敷設、低騒音型車両の開発等各種の騒音・振動対策を実施してきました。
障害防止対策として、騒音レベルが75デシベルを超える区域に所在する住宅及び70デシベルを超える区域に所在する学校、病院等に対し防音工事の助成等を実施し、振動においても、振動レベルが70デシベルを超える区域に所在する住宅等の防振工事の助成及び移転補償等を実施し、いずれも申出のあった対象家屋についてはすべて対策を講じています。さらに、有効な騒音・振動防止対策の開発等を推進しています。
新幹線以外のいわゆる在来鉄道については、新設又は高架化等のように環境が急変する場合の騒音問題を未然に防止する必要があるとの観点から、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」(平成7年12月)(表2-7-5)を踏まえ、騒音対策の適切かつ円滑な実施に努めています。
(6)近隣騒音対策(良好な音環境の保全)
近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約1/4を占めています。近隣騒音対策は、各人のマナーやモラルに期待するところが大きいといえますが、各地方公共団体においても取組が進められ、平成14年度末現在、深夜営業騒音については50都道府県及び政令市で、拡声機騒音については54都道府県及び政令市で条例が制定され規制が行われています。
(7)低周波音対策
人の耳には聞き取りにくい低い周波数の音がガラス窓や戸、障子等を振動させたり、頭痛、めまい、気分のイライラを引き起こすといった苦情は、平成14年度は地方公共団体において全国で91件受け付けられました。このような低周波音問題の改善を図るため、低周波音の感じ方や不快感に関する調査を行うとともに、低周波音問題に対応する際の注意すべき項目について検討しました。