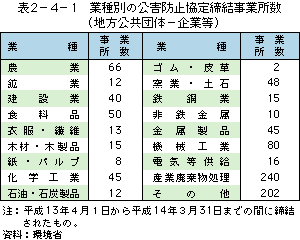
1 地域における環境保全の現状
(1)地域における環境保全施策の計画的、総合的推進
地域環境の保全は、持続可能な社会づくりの基礎であり、地方公共団体は大きな役割を担っています。このため、地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じて、国に準じた施策やその他の独自の環境の保全に関する施策について、国、事業者、住民等と協力、連携しつつ、環境の保全に関する総合的な計画の策定などにより、これを総合的かつ計画的に進めることが期待されています。地方公共団体に期待される役割が円滑に実行されるよう、平成14年度も、国において、地方公共団体に対する必要な協力、連携が図られました。各個別分野についての協力等に係る国の施策については、本年次報告のそれぞれ該当の箇所に掲げるとおりですが、地域における環境保全施策を総合的に推進することに関しては、次のような施策を講じたところです。
1) 平成5年に環境基本法が制定され、これに基づき平成6年に環境基本計画が閣議決定された後、地方公共団体においても、環境基本条例の制定やこれに基づく総合的な地域環境計画の策定に向けた動きが広がりました。さらに、平成12年の環境基本計画の見直しを受け、地方公共団体においてもより実効性のある地域環境計画を策定する動きが広がってきています。
環境省では、平成14年度も、環境計画担当者との意見や情報の交換を行ったほか、総合的な地域環境計画や、指標の策定に対する技術的な支援を行うなど、国と地方のより緊密な連携を図りました。また、持続可能な地域づくりを展開するため、地方公共団体の環境保全施策の総合的体系となる地域環境総合計画策定事業に対して補助を実施しました。
2) 地方公共団体の環境行政を情報面から支援するため、全国の地方公共団体の環境関連情報を、インターネットを利用したホームページ形式により提供するシステム(地域環境行政支援情報システム(知恵の環))の運用を行いました。
3) 環境保全に関する知識の普及・啓発事業を地域において継続的かつ着実に実施していくため、各地方公共団体においてそれぞれ地域環境保全基金が設けられています。この基金により、ビデオ、学校教育用副読本等の啓発資料の作成、地域の環境保全活動に対する相談窓口の設置、環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保全実践活動への支援等が行われています。
4) 地方公共団体による地球環境保全等に関する国際協力の推進に関して、環境省では、環境協力に携わる専門家等の人材の育成や途上国で有効な教材の開発等、途上国を支援するに当たっての基盤整備を行うことを目的として、平成7年度から「技術協力効率化推進事業」を実施してきており、また、平成9年度から環境研修センターにおいて「国際環境協力専門家養成研修」を体系的に行っています。
5) 地方公共団体における環境管理システムに係る導入状況についての調査を行うとともに、地方公共団体に対して環境管理システムの情報提供等を行いました。
6) 地方公共団体が緊急かつ臨時的な雇用の確保を図るために設置された「緊急地域雇用創出特別交付金」を活用し、地域住民や企業退職者、さらには地域環境に詳しい人材が行う森林の下草刈り、「ごみマップ」の作成等の環境関連事業を幅広く推進しています。
(2)地方環境情勢の把握
ア 地方環境情勢の把握体制
環境問題に対処する上で何より肝心なことは、地域の実情、国民の要望を正確に把握し、その結果を各種環境施策に的確に反映することです。このため、環境省では、全国9ブロックに配置している地方環境対策調査官(平成14年度末定員:63名)を活用し、廃棄物の不法投棄現場などの現地調査を行い、また、関係者の意見・要望を聞くなどして地方環境情勢の把握に努めています。
また、環境対策調査官4人で構成される本省の環境対策調査室では、地方環境対策調査官事務所が円滑に事務を遂行しうるよう、適宜適切な指導を行うとともに、国における環境行政の動向等の情報提供、本省各部局と各事務所との連絡調整等の業務を行っております。
さらに、全国7か所において地域環境問題懇談会を実施し、地方公共団体との環境保全に関する意見交換を行い、今後の施策を展開する上での参考としました。
イ 平成14年度における地方環境情勢の把握
(ア)現地調査、地方環境情報の収集
地元新聞、現地調査等により把握した地方環境情報で、地方環境対策調査官から本省に報告された平成14年度の件数は9,000件でした。
(イ)環境モニターからの情報収集
環境問題に関する国民の意見・要望などを全国的に把握するため、全国で約500人の環境モニターを委嘱しています。これら環境モニターから報告された随時の意見・要望等は、環境省の各種施策の企画、立案等に活用されています。平成14年度の報告件数は903件でした。
(ウ)全国的な環境事情に関する調査
次の調査を実施しました。
1) 全国環境事情 環境問題について都道府県別に分類、整理
2) 地方環境保全施策 都道府県及び政令指定都市の単独経費により実施された環境保全施策について分類、整理
3) 環境問題に関する訴訟状況調査 環境問題に関する訴訟事例を分類、整理
(エ)環境省関係の法令施行状況調査
都道府県及び政令市における騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に係るそれぞれの施行状況に関する調査を実施しました。
(オ)その他
以上のほか、地方環境対策調査官事務所では、NGO/NPO、地方公共団体、地域企業などが一堂に会した各種会議や環境施策PRのための環境展などの行事の開催、また、相談窓口などを通じて、環境問題に関する情報や国民の要望の把握に努めました。
(3)地方公共団体の環境保全対策
地方公共団体においては、環境保全に関連した条例等の下、地球温暖化、循環型社会、環境への負荷の少ない交通、健全な水循環、化学物質、生物多様性等の分野において、地域の特性に応じたさまざまな施策が実施され、国においても、本年次報告書のそれぞれの該当箇所に掲げたとおり協力、支援しました。
また、平成15年度の地方財政対策において、ソフト事業費について地域環境保全・創造事業及びリサイクル推進対策事業として合わせて2,930億円程度が計上され、地方交付税措置等の充実が講じられています。
ア 環境行政担当組織及び職員の現況
都道府県・政令指定都市に関しては、平成14年3月31日現在、公害等(廃棄物、下水道関係等を除く。市町村についても同じ。)担当職員数は6,719人、自然保護担当職員数は2,131人となっています。
また、市町村に関しては、平成14年3月31日現在、公害等担当職員数は、9,527人、自然保護担当職員数は、3,643人となっています。
イ 条例の制定状況
地方公共団体の環境保全関連条例は、1)環境基本条例、2)環境保全条例・公害防止条例、3)自然環境保全(自然保護等)条例、4)その他の環境保全関連条例(環境影響評価条例を含む。)の4つに大別されます。
環境基本条例は、環境基本法の理念に沿い、地方公共団体の環境保全施策に関する最も基本的な事項を定めた条例をいい、環境保全条例・公害防止条例、自然環境保全(自然保護等)条例は、それぞれ主に公害防止分野、自然環境保全分野における地方公共団体の基本的姿勢を示すものであり、平成14年3月31日現在、都道府県・政令指定都市のうち、前者については53団体、後者については51団体が制定しています。
その他の環境保全関連条例としては、環境影響評価条例、空き缶の散乱防止条例等があります。
ウ 総合的な地域環境計画の策定状況
環境基本法の制定と環境基本計画の策定を契機として、地方公共団体においても、環境についての基本理念を明らかにした総合的な地域環境計画の策定が進んでおり、平成13年度末現在で、都道府県・政令指定都市のすべてで策定されています。
また、市町村では、平成13年度末現在、426団体において策定されるに至っています。
エ 地方公共団体の事業者・消費者としての環境保全に係る行動の取組状況
地方公共団体は、通常の経済主体としての側面も有しており、自らの経済活動に伴う環境負荷の削減が強く期待されるものです。こうした観点から、多くの地方公共団体では、省資源・省エネルギー活動等のさまざまな環境負荷低減のための取組を内容とする計画や行動のための指針が策定されるに至っています。
オ 公害防止協定の締結状況
平成13年4月〜14年3月までの間に締結された公害防止協定数は、約931件となっており、協定締結の事業所数を業種別に見ると表2-4-1のとおりとなっています。これによると、第2次産業の業種のみではなく、産業廃棄物処理やサービス業の第3次産業を中心とした「その他」に分類される業種が約5割を占めています。
これらの協定のうち、住民も当事者として参加しているものは131、住民が立会人として参加しているものは60となっています。
カ 公害対策経費
平成13年度において、地方公共団体が支出した公害対策経費(地方公営企業に係るものを含む。)は、5兆2,342億円(都道府県9,960億円、市町村4兆2,382億円)となっています。これを前年度と比べると、2,826億円(都道府県970億円減、市町村1,856億円減)、5.1%の減となっています(表2-4-2)。
公害対策経費の内訳で見ると、公害防止事業費が4兆8,596億円(構成比92.8%)、次いで一般経費(人件費等)が1,864億円(同3.6%)等となっています。
さらに、公害防止事業費の内訳をみると、下水道整備事業費が3兆5,852億円で公害対策経費の68.5%と最も高い比率を占めており、次いで廃棄物処理施設整備事業費が1兆846億円(構成比20.7%)となっています。