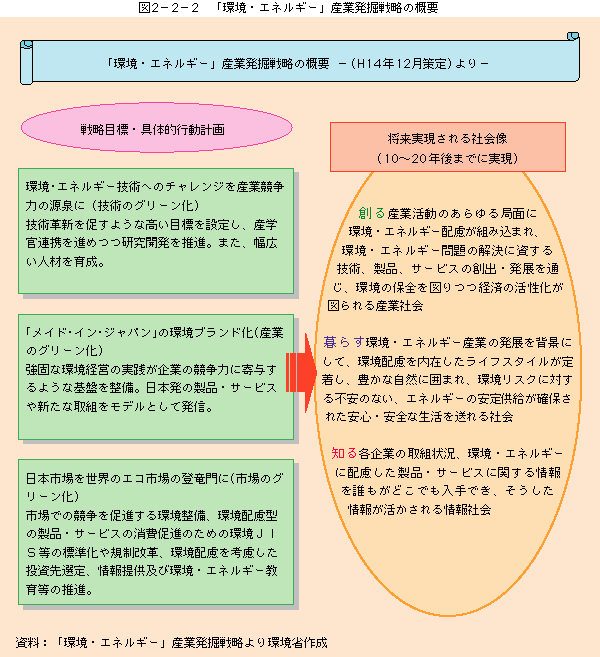
7 環境保全のための具体的行動の促進
(1)環境産業の振興
環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境への負荷の少ない持続可能な社会の実現を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。
経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002(平成14年6月25日 閣議決定)においては「30のアクションプログラム」の一つとして環境産業の活性化が位置付けられるとともに、この具体化を図るため「環境・エネルギー」産業発掘戦略を平成14年中に策定することとされました。
これを受けて、平成14年8月に民間有識者の参画を得て、官民合同のタスクフォースを設け検討を行い、1)技術のグリーン化、2)産業のグリーン化、3)市場のグリーン化について戦略目標や具体的行動計画を示した「環境・エネルギー産業発掘戦略」を平成14年12月に取りまとめました(図2-2-2)。
また、環境省においては、「環境ビジネス研究会」において、環境ビジネスに関連する企業等の経営トップの方々からヒアリングを行い、平成14年8月に環境ビジネスの振興策について取りまとめたほか、平成14年11月に「環境と経済活動に関する懇談会」を設置し、環境産業の振興のみならず、より幅広い観点から、環境と経済の統合にむけた基本的考え方と、具体的な施策について検討を開始しました。
(2)民間団体等による環境保全のための活動の推進
近年、欧米諸国を中心として、民間団体による地球環境保全のためのさまざまな活動が活発となっています。わが国においても、国内の環境保全にとどまらず、開発途上国を中心とした海外で植林や野生生物の保護などの環境保全活動を展開する民間団体が増えており、これらの活動に対する国民各界の関心も高まってきました。地球環境保全のためには、こうした草の根の環境協力や幅広い国民の参加による足元からの行動が極めて重要であり、特にわが国においては、自らの経済社会活動の見直し、開発途上国への支援強化の両面で民間団体(いわゆるNGO)の活動の強化が必要であることから、これらの活動を支援することが喫緊の課題となっています。
平成12年12月に閣議決定された環境基本計画においては、各主体の自主的積極的行動のための主要な施策として、「環境保全の具体的行動の促進」を掲げ、「民間団体の活動の支援」を行っていくこととしています。
また、環境大臣の諮問を受け、中央環境審議会において、環境保全活動の活性化方策について審議が行われ、平成14年12月に「環境保全活動の活性化方策について(中間答申)」が取りまとめられました。
環境省では、地域環境保全基金等による地方公共団体の環境保全活動促進施策を支援するため、関連する情報の収集、提供等を行いました。
また、すぐれた政策提言を環境政策に反映することを目的に「NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム」を開催しました。
政府の出資及び民間の出えんにより環境事業団に設けられた「地球環境基金」により、国内外の民間団体が国内や開発途上地域において行う緑化・リサイクル、野生生物の保護等の活動に対する助成や人材の育成等を目的として「地球環境市民大学校」等を開催するなどNPOキャパシティビルディングのための事業を行いました。このうち、助成事業については、平成14年度において、各方面の民間団体から寄せられた合計587件の助成要望に対し、226件、総額約8億円の助成決定が行われました(表2-2-2)。
さらに、里山林や都市近郊林について、「森林と人との共生林」の整備に向けた条件整備、NPO等を対象とする公募モデル事業の実施や「里山利用林」の設定や「森林の育て親」の募集等を通じた参加型の保全・利用活動を推進しました。
加えて、一般市民が参加して森林の整備・保全活動を行う森林ボランティア活動を促進するため、みどりの募金等による活動への助成等を実施しました。
(3)事業者における公害防止管理制度の実施の推進
工場における公害防止体制を整備するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年6月1日法律第107号)によって一定規模の工場に公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防止に関して必要な専門知識及び技能を有する公害防止管理者等の選任が義務付けられており、約2万の特定工場において公害防止組織の整備が図られています。
同法に基づく公害防止管理者等の資格取得のために国家試験が、昭和46年度以降毎年実施されており、平成14年度の合格者数は6,005人、これまでの延べ合格者数は28万1,065人です。
また、国家試験のほかに、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者が公害防止管理者等の資格を取得するには、資格認定講習を修了する方法があり、平成14年度の修了者数は4,033人、これまでの修了者数は23万5,034人です。
(4)各主体のパートナーシップの下での取組の促進
さまざまな立場の主体が複雑に関係している今日、持続可能な社会を実現するためには、社会を構成する各主体が相互に連携・協力して環境保全に向けて取り組むことが重要です。このため、環境省では、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援のための情報や交流機会を提供する拠点として、国連大学との共同事業として同大学本部施設内(東京)に「地球環境パートナーシッププラザ」を開設しています。また、環境保全についての助言・指導を行う人材を確保するため「環境カウンセラー登録制度」に基づき、平成14年度までに環境カウンセラー3,279名(事業者部門1,994名、市民部門1,285名)の登録を行い、その資質の向上と相互の情報交流の促進を目的とした研修を開催しました。
(5)脱温暖化型ライフスタイル(環のくらし)への転換の促進
地球温暖化問題をはじめとする環境問題においては、国民一人ひとりが排出する環境負荷物質について特に注目されており、環境問題を引き起こしている現代のライフスタイルを、環境にやさしく、かつ私たち自身にとっても、より人間らしい豊かなもの(環のくらし)に変革していく取組が求められています。そのため、環境省では、地球温暖化防止の観点から国民一人ひとりのライフスタイル変革を促すことを目的とした「環の国くらし会議」を平成14年8月(第2回)、12月(第3回)に開催し、地球温暖化防止に向けた取組の推進について、消費者のライフスタイル変革の視点から検討するとともに、国民的な取組の促進に向けて、家庭で身近に取り組める事例の紹介等の情報発信を行いました。また、全国地球温暖化防止活動推進センターを中心にして、普及啓発活動を積極的に推進しています。
(6)環境負荷の少ないライフスタイルへの転換の促進
内閣府においては、地球環境と調和したライフスタイルの形成促進のため、省資源・省エネルギー国民運動の展開を図るとともに、各種の普及啓発活動等を行いました。