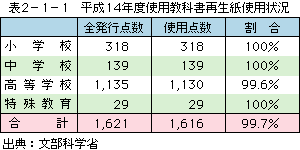
1 学校教育における環境教育
学校教育においては、環境を大切にし、より良い環境づくりや環境の保全に配慮した望ましい行動がとれる人間を育成するといった視点を重視して、従来から、児童生徒の発達段階に即して小・中・高等学校を通じて、社会科や理科、保健体育科、技術・家庭科などの教科等の中で環境に関する学習が行われています。さらに、平成14年度から実施されている新しい学習指導要領においても、各教科等における環境にかかわる内容の一層の充実を図るとともに、体験的な学習や問題解決的な学習を重視するなど環境教育について改善・充実を図りました。
各学校では、身近な地域の環境についての学習や豊かな自然環境の中でのさまざまな体験活動を通して、自然の大切さを学ぶ学習など各種の取組が進められており、これらの取組を支援し、環境教育の一層の振興を図るため、環境のための地球学習観測プログラム(GLOBE)モデル校の指定(24校)、環境教育推進モデル市町村の指定(36地域)、環境学習フェアの開催や環境教育担当教員講習会の開催(全国2地区)などの事業を実施しました。
また、環境への負荷を低減するための教科書の使用、施設づくりを通じて、児童生徒の環境教育に寄与しています。平成14年度に小・中・高等学校等で使用された教科書においては、99.7%の教科書に再生紙が用いられています(表2-1-1)。さらに、公立学校において太陽光発電等環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進に関するパイロット・モデル事業(平成14年度87校指定)を実施しました。また、国立学校施設や私立高等学校等の学校施設においても環境に配慮した施設づくりとこれを活用した環境教育を行うための整備を実施しました。
また、国有林のフィールドを学校等の体験学習の場として利用できる「遊々の森」の設定を推進するとともに、全国の森林管理局・署に森林環境教育に関する相談窓口を設置しました。環境省においては、環境についての学習の推進を図るため、主に小中学生を対象とした職場訪問を随時受け入れたほか、新宿御苑にて環境学習会を実施するなど、平成14年度には延べ644人の児童、生徒に対して環境教育活動を行いました。