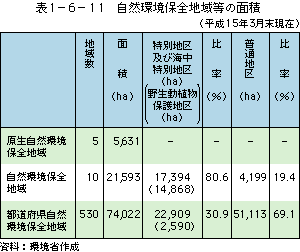
3 原生的な自然及びすぐれた自然の保全
(1)原生的な自然の保全
ア 原生自然環境保全地域の保全
人の手が加わっておらず、原生の状態が保たれている自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づき、自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している地域を「原生自然環境保全地域」に指定し、厳格な行為規制等により原生的な自然の保全を図っています。平成14年度末現在、遠音別岳、十勝川源流部、大井川源流部、南硫黄島及び屋久島の5地域5,631haが指定されています。
イ 世界遺産地域の保全
世界遺産一覧表に記載された、自然遺産の屋久島、白神山地について平成7年に策定された管理計画に基づき、入山者の増加に対応した保全対策を講じるなど、引き続き適切な保護・管理を行いました。屋久島及び白神山地では、世界遺産センターにおいて遺産地域の管理、調査研究等を行うとともに、普及啓発事業を実施しました。
ウ 自然公園の特別保護地区の保全
国立・国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、その区域内に特別保護地区を指定することができるとされており、平成14年度末現在で、国立公園内に272,131ha、国定公園内に66,487haが指定されています。
エ 森林生態系保護地域の保全
主要な森林帯を代表し、又は地域特有の希少な原生的な天然林を保存するため国有林野内に設定した森林生態系保護地域の適正な保護・管理を行いました。平成14年4月1日現在26か所、約32万haが設定されています。
(2)すぐれた自然の保全
ア 自然環境保全地域の保全
自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域以外の区域で、高山性植生や亜高山性植生が相当部分を占める森林や草原、すぐれた天然林が相当部分を占める森林等であるなど、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として指定し、行為規制や保全事業を計画的に行い保全を図っています。平成14年度末現在、10地域21,593haが指定されています。
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要な地域を、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとされており、平成14年度末現在、530地域74,022haが指定されています(表1-6-11)。
イ 自然公園
自然公園は、自然環境の保全に資するとともに、野生体験、自然観察や野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしています。
自然公園には、わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園があります。
平成14年度末の自然公園の数と面積は、国立公園については28か所2,058,095ha、国定公園は55か所1,343,864ha、都道府県立自然公園は308か所1,963,830ha、面積を合計すると5,365,789haとなり、国土面積の約14%を占めています(図1-6-9、図1-6-10、表1-6-12)。
また、近年の自然公園を取り巻く状況の変化、生物多様性国家戦略の見直しの動き等を踏まえ、平成14年4月に自然公園法(昭和32年法律第161号)の改正が行われました。改正の主な内容は、国及び地方公共団体の責務として生物の多様性の確保を追加するとともに、1)特別地域等の保護の強化を図るため、規制行為として環境大臣が指定する物の集積又は貯蔵、環境大臣が指定する動物の捕獲等、環境大臣が指定する区域内への立入り等の追加、2)生態系の維持とその適正な利用を図るために利用人数等の調整を行う利用調整地区制度の創設、3)草原や里地里山などの二次的な自然風景地の保護を図るため土地所有者等との協定に基づき民間団体が自然の風景地の管理を行う風景地保護協定制度の創設、4)地域に密着した公園管理を推進するために民間団体を公園管理団体として指定する制度の創設などです。
自然公園全体の利用者数は、昭和50年から昭和58年の間はおおむね横ばいの状況であり、昭和59年以降は徐々に増加傾向を示し、平成5年以降はやや減少傾向にあるといえます。平成13年の利用者数は、国立公園が3億6,800万人、国定公園が2億9,697万人、都道府県立自然公園が2億6,976万人となっています(図1-6-11)。
ウ 自然公園の区域及び公園計画の見直し
(ア)公園区域及び公園計画の見直し
自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため公園計画を定めることとされていますが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公園計画の全体的な見直し(再検討)を行っています。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直し(点検)を実施することとしています。
平成14年度においては、西表国立公園の再検討、支笏洞爺国立公園(洞爺湖地域)の一部変更ほか7公園について公園区域及び公園計画の見直しを行いました。また、国定公園についても、比婆道後帝釈国定公園(島根・広島県地域)の再検討、南房総国定公園の点検ほか3公園の公園区域及び公園計画の見直しを行いました。なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園があるため、公園計画を定めるよう助言を行いました。
(イ)海中公園地区の指定
海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境大臣が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものです。
平成14年度末までに、国立公園に33地区、国定公園に31地区、合計64地区2,664.2haの海中公園地区が指定されています。
(ウ)乗り入れ規制地域の指定
近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車、モーターボート等の乗り入れによる植生や野生生物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立・国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域において、車馬もしくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されています。
平成14年度末までに国立公園に31地域、国定公園に14地域の合計45地域25万1,514haの乗り入れ規制地域が指定されています。
エ 自然公園における自然保護
(ア)風致景観の保護
a 行為規制
自然公園内には、風致景観の保護のため、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区が指定されています(表1-6-13)。これらの地域において各種行為を行う場合は、環境大臣又は都道府県知事の許可が必要であり、その際、自然公園法施行規則に規定する許可基準の適用等により、風致景観の適正な保護に努めています。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における各種行為の許可申請のうち環境大臣の権限に係る件数は表1-6-14のとおりです。また、普通地域においても一定の行為は環境大臣又は都道府県知事への届出を要することとしています。
b 風致景観の管理手法の検討調査
自然公園の風致景観の核心部を構成する貴重な自然を有する地域の保護管理を図るため、地域特有の生態系に変化をもたらす要因の解明調査等を行い、保護管理手法の樹立に努めています。平成14年度は、大山隠岐国立公園鏡ヶ成地区における湿原の管理方針に係る調査等を実施しました。
(イ)自然公園における環境保全対策
a 地球環境への配慮
自然公園等において、太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を行いました。
b 自然環境の復元
国立・国定公園内の植生、動物、自然景観等の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設等の整備を行いました。
c 美化清掃活動
自然公園の利用者のもたらすゴミは、単に美観を損ね、悪臭の発生などの環境汚染を引きおこすだけでなく野生生物の生態にも悪影響を及ぼすことがあります。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の自然環境を清潔に保持するため、現地において地方自治体及び美化清掃団体と協力し清掃活動を行いました。
また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行いました。
d 特殊植物等の保全事業
国立公園内に生育している貴重な植物で、その生育環境と一体的に保護する必要のあるものの保全対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)において、植生復元等を実施しました。
e オニヒトデ等駆除事業
国立公園の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、異常発生しているオニヒトデ及びシロレイシガイダマシ類の駆除を行いました。
f 自動車利用適正化対策
自然公園内のすぐれた自然環境を有する地域への自動車乗り入れの増大により、植生の損傷、快適・安全な公園利用の阻害等自然公園の保護と利用両面にわたる種々の弊害が生じているため、国立公園内における自動車利用適正化要綱に基づき、自家用車等に代わるバス運行等の対策を講じました。
g 特定国立公園重点管理等事業
国立公園内の貴重な生態系の適正な保護を図るため、吉野熊野国立公園大台ヶ原のトウヒ林及び利尻礼文サロベツ国立公園のサロベツ原野の保全対策等の事業・調査を継続しました。
また、知床国立公園及び中部山岳国立公園白馬地域等において、関係森林管理署の協力を得て重点管理事業を実施しました。
h 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業
国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において自然環境保全活動の質の向上を図ることを目的として、自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用することによって、支笏洞爺国立公園支笏湖における湖底のゴミ回収や磐梯朝日国立公園雄国沼湿原における高山植物の違法採取の監視、その他、山岳地における登山道の簡易な補修、投棄ゴミの処理などを行いました。
i 山岳環境浄化・安全対策緊急事業費補助
国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対策を図るため、山小屋事業者がし尿・排水処理施設等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助し、対策実施を推進しました。平成14年度には、富士山等において整備を行いました。
(ウ)管理体制の強化
国立公園の管理については、自然保護事務所等を各国立公園に設置し、地方公共団体、民間団体の協力を得て、その適正を期していますが、近年の国立公園を取り巻く諸情勢の変化に対処するため、平成14年度も以下のような地域の特性に応じた管理体制の強化に努めました。
a 自然保護事務所等
国立公園内における風致景観を保護管理し、公園事業者に対する指導、公園利用者への自然解説等広範囲な業務を行うため、自然保護事務所を置くとともに、自然保護官を公園の各地区に配置しています。平成14年度末現在の自然保護官定数は218人です。
また、各公園ごとに地域の実情に即した適切な管理を行うため、管理計画を作成しており、平成14年度は、大山隠岐国立公園等4公園4地域について管理計画を作成しました。
国立公園事業の執行に係る建築物の建替えに伴う廃材等の不法埋立てが見られたため、公園事業者及び工事請負業者に対する指導、工事履行状況の確認を今まで以上に図ることとしました。
b 民間団体の活動
1) (財)自然公園財団は、自然公園の美化清掃、公園施設の維持管理、自然保護思想の教化普及等の事業を中部山岳国立公園上高地地区、十和田八幡平国立公園八幡平地区等21支部(事業所)において実施しました。
2) 公益信託自然保護ボランティアファンドは、自然公園の美化清掃、動植物の保護・調査、自然解説などの活動を行っているボランティア19団体に対する助成を実施しました。
(エ)自然保護のための民有地買上げの推進
国立・国定公園内の風致景観の維持並びに国設鳥獣保護区内の野生鳥獣の保護及び生息地等保護区内の国内希少野生動植物種の保護とこれらの地域における民有地の所有者の有する私権との調整を図るため、都道府県が行う買い上げについて、補助を行っています。
平成14年度末現在、70地区8,078ha(事業費141億97百万円)が買い上げられています。
オ 生息地等保護区
種の保存法に基づき国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域である生息地等保護区の指定を進めることとしています。
平成15年3月末現在7の生息地等保護区が指定され、生息・生育状況調査や巡視等の管理業務が行われています。
カ 鳥獣保護区
野生鳥獣の捕獲を禁止し、生息環境の改善に努めるなど、野生鳥獣の保護を図る地域として鳥獣保護区を設定し、さらに必要に応じて特別保護地区を指定することとしています。平成15年3月末現在、56の国設鳥獣保護区(49.5万ha)、3,796の都道府県設鳥獣保護区(306.4万ha)が設定されており、その合計面積は355.9万haで国土面積の9.5%を占めています。また、44の国設鳥獣保護区と551の都道府県設鳥獣保護区に合計26.4万haの特別保護地区が指定されています(表1-6-15)。
キ 史跡、名勝、天然記念物
動植物種及び生態系を中心としたわが国を代表する自然を保全するため、古墳、貝塚、城跡等の遺跡で歴史上又は学術上の価値の高いものを史跡に、庭園等の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いものを名勝に、動植物、地質鉱物等で学術上価値の高いものをそれぞれ天然記念物に指定し、現状変更等には、文化庁長官の許可を要することとしています。平成15年4月1日現在の指定件数は、史跡1,502件(うち特別史跡61件)、名勝321件(うち特別名勝35件)、天然記念物965件(うち特別天然記念物75件)となっています。また、史跡等の保存上、特に必要がある場合は公有化を図るとともに、当該史跡等の活用を図るため、整備等の保護事業を行いました。さらに、国土開発等による天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と連携して、特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業など21件について保護増殖事業を実施しました。
ク 保安林等
保安林について、すぐれた自然環境の保全を含む公益的観点から計画的な配備、適正な管理等を行っています。さらに国有林野においては、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定し、その適切な保護管理を行いました。平成14年4月1日現在821か所、約55万2千haの保護林が設定されています。
ケ 都市の緑地保全
都市における緑地を保全するため、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)に基づき緑地保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買い入れ等を推進しました。
また、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)に基づき指定された近郊緑地保全区域内において、特に枢要な部分を構成している緑地は、近郊緑地特別保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買い入れ等を推進しました。
さらに、風致に富むまちづくり推進の観点から、風致地区指定の推進を図りました。
コ ナショナル・トラスト運動による保全
募金活動等を通じた幅広い国民の自主的参加により良好な自然環境地等の取得、管理を行い、保全を図ろうとするナショナル・トラスト活動は、現在、和歌山県田辺市の天神崎をはじめとして全国各地において推進されています。
こうした活動は国民自らの手による自然保護活動として極めて有意義なものであり、さらに普及、定着していくことが期待されます。