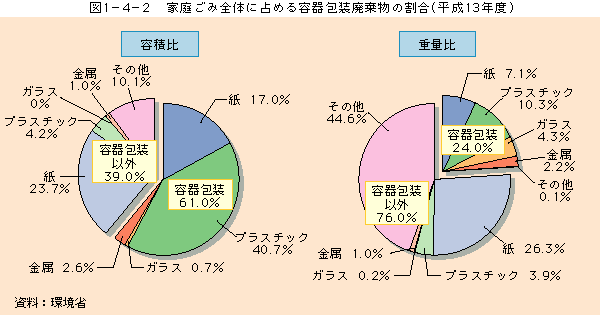
3 循環資源の適正な循環的な利用の推進
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律について
平成9年に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 昭和45年法律第137号)に基づき、一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合していることを環境大臣が認定し、認定を受けた者については業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられました。これまでに自動車用廃タイヤのセメントの原材料利用及びコークス炉利用、シールド工法に伴う建設汚泥の高規格堤防の築造材としての利用、廃プラスチック類の高炉還元剤としての利用、廃プラスチック類のコークス及び炭化水素油としての利用及び廃肉骨粉のセメント原材料利用がこの再生利用認定制度の対象となり、平成14年度には、建設汚泥の再生利用1件、廃タイヤの再生利用37件、廃肉骨粉の再生利用11件及び廃プラスチックのコークス及び炭化水素油としての再利用8件を認定しました。
(2)資源の有効な利用の促進に関する法律について
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法 平成3年法律第48号)に基づき、複写機の製造における再生部品の使用や自動車、オートバイ、パソコン、ぱちんこ遊技機材等の3R(リデュース、リユース、リサイクル)配慮設計といった対策を推進しました。
資源有効利用促進法は、平成13年4月に施行され、事業系パソコンと小型二次電池について、事業者による自主回収・リサイクルといった対策を講じました。
事業系パソコンと小型二次電池について、事業者による自主回収・リサイクルを推進するとともに、家庭系パソコンの回収・リサイクルシステムのあり方について産業構造審議会パソコン3Rワーキンググループ及び環境省パソコンリサイクル検討会において検討を行い、報告書をまとめました。
(3)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について
市町村における分別収集計画と再商品化計画は5年を一期とし、3年ごとに見直すこととされており、平成14年度において法施行後2度目の見直しを行い、平成15年度を初年度とする平成19年度までの分別収集計画と再商品化計画を策定しました。
全面施行から3年が経過し、本法の施行に伴う効果を検証するため平成13年度からの3か年事業として、一般廃棄物の発生量の削減効果や最終処分量の減量効果等について評価し、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)施行前後における市町村の分別収集に伴う廃棄物処理コスト等を把握する実態調査を行いました。さらに、分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村による分別収集計画の策定の支援、分別収集の手引の作成、再商品化技術の開発、再商品化によって得られたものの需要の拡大、必要な調査研究や説明会等により、容器包装リサイクル法の普及・啓発を行いました(図1-4-2)。
(4)特定家庭用機器再商品化法について
平成13年4月1日から施行されている特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、これまでのところおおむね順調に施行されており、平成14年度に全国の指定引取場所が引き取った廃家電4品目は、合計約10,150千万台に達しています。
平成14年11月には、中央環境審議会家電等リサイクル専門委員会及び産業構造審議会電気・電子機器リサイクルワーキンググループにおいて、家庭用冷蔵庫の断熱材フロンの回収・破壊等の義務付け等家電リサイクル法におけるフロン対策の強化を図る旨の方向性が示されました。
また、製造業者等においては、リサイクルが容易な製品設計や材料の選択等の取組を開始しています。
(5)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法 平成12年法律第104号)については、平成14年5月30日に、建設工事の実施に当たっての分別解体等及び再資源化等の義務付けや、発注者・受注者間の契約手続の整備に関する部分を含めて完全施行されました。建設リサイクル法の施行に当たっては、事業者等に対する説明会の開催や10月のリサイクル推進月間に合わせ全国一斉パトロールを実施するなど、法の普及啓発などにつとめました。また、建設リサイクル法の円滑な施行を図るため、再資源化施設の稼働状況等を提供する「建設副産物情報交換システム」の全国運用を平成14年春から開始するとともに、建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を定めた「建設リサイクル推進計画2002」の策定や、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適正に実施するために必要な基準を定めた「建設副産物適正処理推進要綱」の改訂を行いました。このほかに、平成14年12月からダイオキシン規制が強化されたこともあり、木材チップの需要動向や焼却施設の稼働状況等を的確に把握するため、地域ごとにおける建設発生木材の再資源化等の実態調査を行いました。
(6)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法 平成12年法律第116号)が平成13年5月に施行され、同法に基づく食品関連事業者等の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、登録再生利用事業者制度、再生利用事業計画認定制度等を活用した優良なリサイクル業者の育成、計画的なリサイクルの実施を推進しました。
また、生産・流通・消費の各段階を通じた食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、同法の普及啓発を実施するとともに、民間の技術開発の支援、先進的な食品リサイクルシステムの構築等を実施しました。
(7)使用済自動車の再資源化等に関する法律について
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法 平成14年法律第87号)が、平成14年7月に公布されました。この法律は、使用済自動車を適正に処理し、資源として有効に利用するため、自動車製造業者をはじめとする関係者に適切な役割分担を義務付けることなどにより、新たな自動車リサイクルの仕組みを構築しようとするものです。各主体の責務など一部の規定は、平成15年1月から施行となりましたが、法律全体が動き出す完全施行は、公布後2年6か月以内とされています。現在、平成16年末頃の完全施行を目指し、中央環境審議会と産業構造審議会が合同で各種の基準のあり方をはじめ、制度の詳細に関する検討を進めています。
(8)エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法について
最近の資源エネルギーの利用をめぐる経済社会的環境の変化にかんがみ、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)が改正されました。具体的には、従来からの国内の省エネルギー対策、リサイクル対策、特定フロン対策に加え、海外で行われるエネルギー起源CO2の排出抑制事業や、リデュース、リユース対象の実施が支援対象事業に追加されました。
(9)その他の取組について
下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)については、コンポスト化、建設資材化による再生利用等を推進するとともに、再生利用推進のための各種調査研究等を行いました。
農業集落排水事業の実施においては、発生汚泥を有機質肥料等とするリサイクルなどを推進しました。
また、リサイクルの一層の促進を図るため、リサイクルに関連する経済的手法のあり方についての検討がそれぞれ進められました。
(10)都市再生プロジェクトの推進
平成13年6月14日の都市再生本部決定に基づいて、大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築に向けた取組が開始されました。第1段階のプロジェクトとして、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県)を対象とした検討が行われました。平成13年7月には、関係7都県市及び関係各省から構成される「首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会」が設置され、平成14年4月には、7都県市による中長期計画の策定に向けた取りまとめを行いました。この取りまとめでは、国の基本方針より前倒しした廃棄物の減量化目標の設定、臨海部に立地する既存産業の集積や既存インフラの活用を踏まえた廃棄物処理・リサイクル施設の集中立地を行う拠点の形成、トラックによる端末的輸送手段と海上輸送、鉄道及び河川舟運が適切に組み合わされた環境負荷の小さい効率的な静脈物流システムの構築等を行うこととしています。
さらに、平成14年7月には、首都圏に次ぐプロジェクトとして、近畿圏(滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県及び和歌山県)においても、関係9府県市及び関係各省から構成される「京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会」が設置され、平成15年3月には、9府県市による中長期計画策定に向けた取りまとめを行いました。この取りまとめでは、国の基本方針を上回る最終処分率の設定、大阪湾広域臨海環境整備センターを中核とした廃棄物・リサイクル施設の整備及び静脈物流システムの構築、循環型社会形成に向けた環境産業の育成、不適正処理対策の実施等を行うこととしています。
(11)総合的な静脈物流システムの構築に向けた港湾における取組
循環型社会の実現を図るため、広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流の拠点となる総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)*として、室蘭港・苫小牧港、東京港、神戸港、北九州港の4か所を指定(一次指定)しました。
(12)ゼロ・エミッション構想の推進
地域における資源循環型経済社会構築の実現に向けて、ゼロ・エミッション構想推進のため「エコタウン事業」を実施しており、平成14年度まで全国17地域におけるエコタウンプランを承認し、それぞれの計画に基づくリサイクル関連施設整備事業等に対するハード面の支援、及び環境関連情報提供事業等に関するソフト面での支援を実施しました。