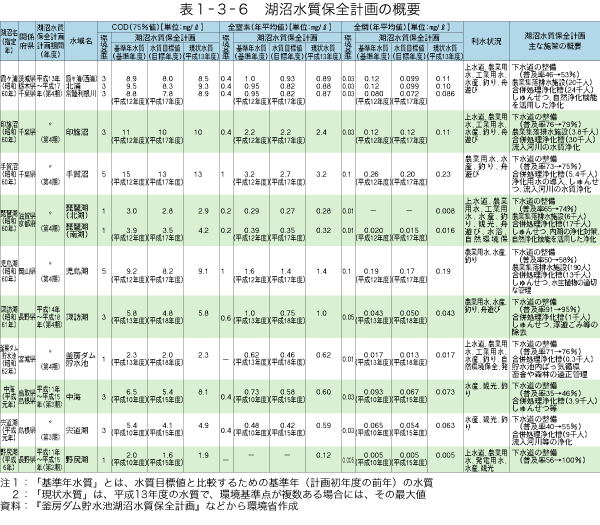
4 閉鎖性水域などにおける水環境の保全
(1)湖沼
湖沼は、富栄養化に伴い、水道水の異臭、漁業への影響、透明度の低下などの問題が生じており、水質改善対策が急務となっています。湖沼に流入する汚濁負荷の発生源は生活系、産業系、自然系等多岐にわたり、各発生源の影響の度合いは流域の土地利用や産業構造によって異なるため、それぞれの特性に応じた対策が必要です。具体的には、富栄養化対策として、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、現在、窒素規制対象湖沼は201、りん規制対象湖沼は1,200となっています。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準については、琵琶湖(2水域)等合計79水域(78湖沼)について類型指定が行われています。
また、水質汚濁防止法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)によって対策を講じています。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、さらには湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に推進しようとするものです。指定湖沼は10湖沼あり、平成14年度には釜房ダム貯水池及び諏訪湖について、第4期湖沼水質保全計画を策定しました。湖沼水質保全計画の概要は表1-3-6のとおりです。また、水田や都市域等非特定汚染源から発生する汚濁負荷に関する実証調査、健全な水循環のための調査、湖沼の汚濁機構解明や施策の効果の分析・評価について検討を行う調査を実施しました。
(2)閉鎖性海域
ア 富栄養化対策
海域の窒素及びりんに係る排水基準については、閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域に適用することとされており、現在、88の海域とこれに流入する公共用水域に排水する特定事業場を対象として、排水規制を実施しています。また、海域における全窒素及び全りんの環境基準については、上記の閉鎖性海域を対象に類型指定の作業が国及び都道府県において行われているところであり、51海域が指定されています。
イ 水質総量規制制度
広域的な閉鎖性海域については、水質汚濁防止法において、当該水域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制の制度が設けられており、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量を指定項目として、平成16年度を目標年度とした第5次水質総量規制を実施しています。
第5次水質総量規制に係る総量削減基本方針では目標年度における発生源(生活系、産業系、その他系)別の削減目標量等について定められており、平成11年度の負荷量に対し、CODについては東京湾で8%、伊勢湾で8%、瀬戸内海で6%、3水域全体では7%の削減を図ることとなっています。窒素含有量については東京湾で2%、伊勢湾で4%、瀬戸内海で5%、3水域全体では4%の削減を図ることとなっています。りん含有量については東京湾で9%、伊勢湾で8%、瀬戸内海で6%、3水域全体では7%の削減を図ることとなっています(図1-3-12)。その達成のため、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの整備等による生活排水対策、工場等の総量規制基準の強化等の産業排水対策、合流式下水道の改善等その他の諸対策を総合的に推進しました。
また、総量規制の対象の3水域においては、総量規制の水質改善効果を把握するため、当該水域に係る水質、発生負荷量及び削減対策状況等について総合的な調査・解析を行っています。
ウ 瀬戸内海の環境保全
瀬戸内海は、すぐれた自然の景勝地、貴重な漁業資源の宝庫であるという恵まれた自然条件を有する反面、周辺に産業及び人口が集中した閉鎖性水域であることから瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)及び瀬戸内海環境保全基本計画等により、総合的な施策が進められてきています。
瀬戸内海沿岸の関係11府県は、海水浴、潮干狩り等海洋性レクリエーションの場として利用されている自然海浜を保全するため、自然海浜保全地区条例等を制定しており、平成14年12月末までに91地区の自然海浜保全地区を指定しています。
瀬戸内海における公有水面埋立ての免許又は承認に当たって、関係府県知事は、瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならないとされています。瀬戸内海環境保全臨時措置法施行以降平成14年11月1日までの間に約4,600件、約1万2,700ha(うち平成13年11月2日以降の1年間に42件、35.2ha)の埋立ての免許又は承認がなされています。
エ 有明海及び八代海の環境の保全及び改善
有明海においては、水質及び発生負荷量等について調査・解析を行うとともに、平成12年度に深刻なノリ不作が生じるなど有明海の環境悪化が懸念されていることから、有明海の海域環境の改善を目的として各種の調査を実施しました。
また、有明海関係自治体等の要望を受けて第155回臨時国会において成立した有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)に基づき、「有明海及び八代海の再生に関する基本方針」を策定するとともに、国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて両海域の再生に係る評価等を行う有明海・八代海総合調査評価委員会を設置しました。
(3)閉鎖性水域の浄化対策
水質悪化が著しい湖沼においては、底泥からの栄養塩類の溶出等を抑制するため、底泥しゅんせつを実施するとともに、湖沼に流入する汚濁負荷の削減を図るため、流入河川において直接浄化施設の整備を実施しました。
港湾及び周辺海域の環境保全のため、平成14年度には港湾公害防止対策事業(有機汚泥等のしゅんせつ等)を東京港等5港で行ったほか、港湾区域外の一般海域における浮遊ごみ・油の回収事業を行いました。
さらに、閉鎖性が強くヘドロの堆積した海域の環境改善を目的として海域環境創造事業(覆砂、干潟や海浜整備)を三河湾、瀬戸内海の2海域及び大阪港等18港において実施しました。
(4)大都市圏の「海」の再生
都市再生プロジェクト(第3次決定)「海の再生」の実現に向けて、東京湾の海域環境の改善を強力に推進するため、平成14年2月に7都県市及び関係省庁からなる東京湾再生推進会議を設置しました。同推進会議では、「快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい『海』を取り戻し、首都圏にふさわしい『東京湾』を創出する」ことを目標に、東京湾再生のための行動計画を平成15年3月に策定しました。