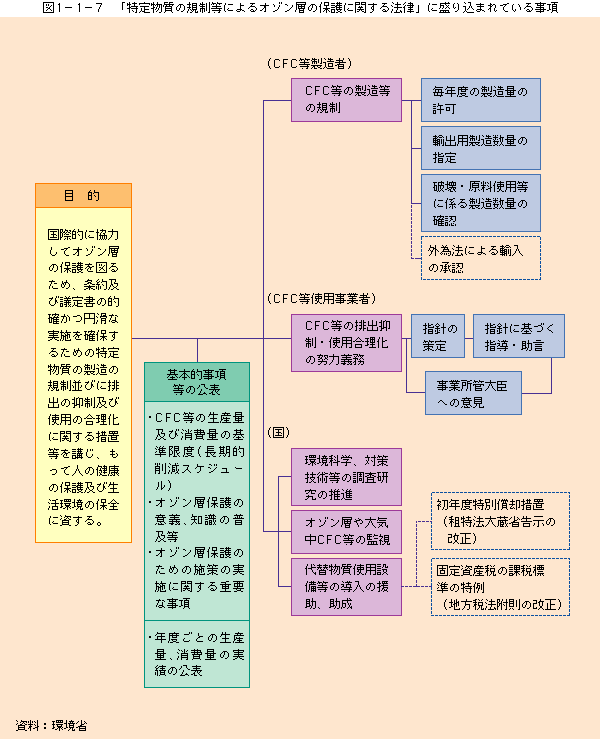
3 オゾン層保護対策
(1)国際的取組とオゾン層保護法
オゾン層の破壊を防止するために、オゾン層の保護のためのウィーン条約*が1985年(昭和60年)3月に、また「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が1987年(昭和62年)9月にそれぞれ採択されました。わが国においてもこれらを的確かつ円滑に実施するため、1988年(昭和63年)5月に特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法 昭和63年法律第53号)を制定するとともに(図1-1-7)、同年9月に条約及び議定書を締結しました。
しかし、その後の科学的知見の集積により、従来のCFC等の規制ではオゾン層の適正な保護に不十分であることが分かり、1990年(平成2年)、1992年(平成4年)、1995年(平成7年)、1997年(平成9年)及び1999年(平成11年)の5度にわたって、議定書の改正等による規制強化が図られました(わが国はすべての改正議定書を批准)。現在の規制スケジュールは表1-1-1のとおりです。
わが国では、オゾン層保護法等に基づき、次のような施策を実施してきています。
ア CFC等の製造等の規制
オゾン層保護法では、モントリオール議定書に基づく規制対象物質*を「特定物質」として、製造規制等の実施により、モントリオール議定書の規制スケジュールに即して生産量及び消費量(=生産量+輸入量−輸出量)の段階的削減を行っています。この結果、ハロンについては1993年(平成5年)末をもって、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン及びHBFCについては1995年(平成7年)末をもって、ブロモクロロメタンについては2001年(平成13年)末をもって、生産等が全廃されています。他のオゾン層破壊物質についても、HCFCについては2019年(平成31年)末をもって消費量が全廃され、臭化メチルについては2004年(平成16年)末をもって、検疫用途等を除き、その生産等が全廃されることとなっています。
イ CFC等の排出抑制・使用合理化
オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に対し、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に努力することを求めており、そのための「特定物質の排出抑制・使用合理化指針」(環境庁・通商産業省告示)を昭和64年に告示し、逐次改正するとともに、その周知普及を図っています。
ウ 国家ハロンマネンジメント戦略及び国家CFC管理戦略
モントリオール議定書締約国会合における決定に基づき、関係省庁で検討を行い、「国家ハロンマネンジメント戦略」(平成12年7月)及び「国家CFC管理戦略」(平成13年7月)を策定し、これに基づく取組を行っています。
(2)CFC等の回収・破壊の促進
CFC等の主要なオゾン層破壊物質の生産は、平成7年末をもってすでに全廃されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、カーエアコン等の機器の中に充てんされた形で存在しているCFC等が相当量残されており、オゾン層保護を一層推進するためには、こうしたCFC等の回収・破壊を促進することが大きな課題となっています。
このため、地域におけるフロン回収等推進協議会、家庭用冷蔵庫の関係業界、カーエアコンの関係業界、業務用冷凍空調機器の関係業界、地方公共団体等による自主的なフロンの回収が進められてきましたが(表1-1-2)(表1-1-3)、平成13年4月からは家電リサイクル法に基づき冷蔵庫及びルームエアコンについて冷媒として用いられているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収が義務づけられるとともに、フロン回収破壊法に基づき、業務用冷凍空調機器*について平成14年4月1日から、カーエアコンについて平成14年10月1日から、これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒として残存しているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収が義務付けられました(図1-1-8)。
また、フロン回収破壊法に基づき回収されたフロン類は、再利用される分を除き、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けたフロン類破壊業者により破壊されることとなっており、平成15年3月31日現在で、許可を受けたフロン類破壊業者は63となっています(表1-1-4)。
(3)CFC等の排出抑制、使用合理化への支援対策等
CFC等の代替品を使用する洗浄設備、冷凍冷蔵関連装置及びフロン回収・破壊設備等については、法人税及び所得税についての特別償却等の税制上の措置を講ずるとともに、これらの関係設備について日本政策投資銀行等による低利融資等の金融上の措置を実施しています。