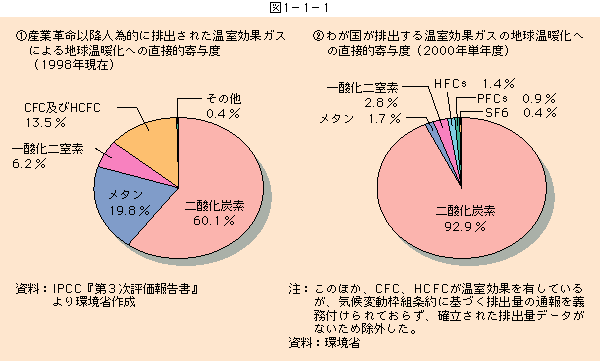
1 地球規模の大気環境の現状
(1)地球温暖化
ア 問題の概要
地球温暖化は、人間活動により、自然界での健全な物質の循環がゆがむことにより生じる環境問題の典型的事例です。
大気中には、二酸化炭素、メタンなどの「温室効果を有するガス」が含まれており、これらのガスの温室効果により、人間や動植物にとって住み良い大気温度が保たれてきました。ところが、近年の人間活動の拡大に伴って二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスが人為的に大量に大気中に排出されることで、温室効果が強まって地球が過度に温暖化するおそれが生じています。特に、二酸化炭素はその人為的な排出量が膨大であるため、温暖化への寄与度は全世界における産業革命以降の累積で約60%を占めています(図1-1-1)。
イ 地球温暖化の現況と今後の見通し
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2001年(平成13年)に取りまとめた第3次評価報告書によると、全球平均地上気温は1861年以降上昇しており、20世紀中に0.6±0.2℃上昇しました。20世紀における温暖化の程度は、過去1000年のいかなる世紀と比べても、最も著しかった可能性が高いとされています。同報告では、過去50年間に観測された温暖化の大部分が人間活動に起因しているという、新たな、かつより強力な証拠が得られたことが指摘されています。
また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造などの動向について一定の前提条件を設けた複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、1990年から2100年までの全球平均地上気温の上昇は、1.4〜5.8℃と予測されています。ほとんどすべての陸地は、特に北半球高緯度の寒候期において、全球平均よりも急速に温暖化する可能性がかなり高いとされています。このような気温の上昇は、過去1万年の間にも観測されたことがないほどの大きさである可能性がかなり高いと指摘されています。
こうした地球温暖化が進行するのに伴い、人類の生活環境や生物の生息環境に広範で深刻な影響が生じるおそれがあります。
ウ 地球温暖化に関する世界的な影響
(ア)海面の上昇
気温の上昇は、海水の膨張、極地及び高山地の氷の融解を引き起こし、その結果として海面の上昇を招きます。この場合、海岸線の後退により多大な影響が生じると考えられます。IPCC第3次評価報告書によれば、20世紀に地球の平均海面水位は10〜20cm上昇しており、1990年から2100年までの間に9〜88cm上昇することが予測されています。2080年までに海面水位が40cm上昇する場合、沿岸の高潮により水害を被る世界の人口は、年平均で7500万人から2億人の範囲で増加すると予測されています。
(イ)経済格差の拡大
IPCC第3次評価報告書によると、地球温暖化によって、多くの開発途上国で経済的損失が生じ、温暖化が進行するほど損失も大きくなることが予測されています。一方、先進国ではわずかな気温上昇では、経済的利益・損失両方とも予測されますが、より大きな温暖化では損失となることが予測されています。この影響予測によれば、先進国と開発途上国の間の貧富の差が広がり、温暖化が進行するほどその格差は大きくなります。
(ウ)食糧危機
IPCC第3次評価報告書によると、中緯度の一部地域での農作物生産にとって数℃以下の温暖化では一般に好影響となりますが、それ以上の温暖化が起きると悪影響となることが予測されています。特に熱帯では、一部の農作物生産は、すでに気温が許容範囲の上限近くにあることから、わずかな気温上昇でさえも、生産量は減少します。また、地球の年平均気温が数℃以上上昇した場合、地球規模での食料需要の増加に対して、食料供給の拡大が遅れることによる食料価格の上昇が予測されています。
(エ)生態系への影響
IPCC第3次評価報告書によると、すでに多くの野生生物の種や個体群が危機に曝されており、気候変化によって、21世紀には、現在「深刻な危機に曝されている」と分類されている一部の種は絶滅し、「危機に曝されている、または脆弱である」と分類されているものの大多数は希少種となって、絶滅に近づくと予測されています。
(オ)健康への影響
生物、食料、水によって媒介する伝染病の多くは、気候変化に敏感であることが知られています。IPCC第3次評価報告書によると、マラリアとデング熱は、現在、世界人口の40〜50%に影響を及ぼしていますが、気候変化によりその伝染可能性の地理的範囲が拡大することが予測されています。また、熱波の増加により熱に関連した死亡や疾病の増加が起こり、洪水の増加により溺死、下痢、呼吸器疾患、特に開発途上国では飢餓や栄養失調となる可能性が増加すると予測されています。
エ わが国における影響
気象庁の観測によると、わが国でも年平均気温はこの100年間で約1.0℃上昇しています。特に1980年代からの上昇が著しくなっています(図1-1-2)。
平成13年3月の報告書「地球温暖化の日本への影響」によれば、今後100年間の気温上昇が、南日本で4℃、北日本で5℃と予測されています。また、オホーツク海の海氷面積の減少や、動植物の生息域の移動など温暖化による自然環境等への影響がすでに現れつつあるとしており、さらに、今後温暖化の進行により、水資源、農林水産業、生態系、沿岸域、エネルギー、健康などの広範な分野にわたりさまざまな影響が生じることが予測されています。
オ わが国の温室効果ガスの排出状況
わが国の2000年度の温室効果ガス総排出量は、13億3200万トン(二酸化炭素換算)です。京都議定書の規定による基準年(1990年。ただし、HFCs、PFCs及びSF6については1995年)の総排出量(12億3,300万トン)と比べ、8.0%の増加となっています。また、前年度と比べると0.2%の増加となっています。
温室効果ガスごとに見ると、2000年度の二酸化炭素排出量は12億3,700万トン、一人当たりの二酸化炭素排出量は9.75トン/人となります。これは1990年度と比べ、排出量で10.5%、一人当たり排出量で7.6%増加したことになります。
二酸化炭素排出量を部門別にみると(総説図1-1-11参照)、2000年度の産業部門からの排出量は4億9,500万トンとなり、1990年度比で0.9%増加しています。2000年度の運輸部門からの排出量は2億5,600万トンとなり、1990年度比で20.6%増加しています。自家用乗用車の台数が1990年から2000年の間に56.0%増加しており、それに伴い、走行量が33.9%も増加しています。また、個々の自動車の燃費は改善している一方、消費者の嗜好の変化により、乗用車は大型化(重量化)(図1-1-3)しており、これらが運輸部門のCO2排出量増加の大きな要因となっています。2000年度の民生(家庭)部門からの排出量は1億6,600万トンとなり、1990年度比で20.4%増加しています。世帯数の増加とともに、一世帯当たりのエネルギー消費量が増加しており、排出量の増加に寄与しています。2000年度の民生(業務)部門からの排出量は1億5,200万トンとなり、1990年度比で22.2%増加しています。延床面積の増加(図1-1-4)が排出量の増加に大きく寄与していますが、床面積当たりのエネルギー消費量はそれほど増加していません。
2000年度のメタン排出量は2,200万トン(二酸化炭素換算)となり、1990年度と比べると17.4%減少しました。特に、廃棄物の埋立による排出の減少が寄与しています。2000年度の一酸化二窒素排出量は3,700万トン(二酸化炭素換算)となり、1990年度と比べると5.0%減少しました。
2000年度のHFCs排出量は1,830万トン(二酸化炭素換算)となり、1995年度と比べると8.4%減少しました。HCFC-22の製造時の副生物による排出が、大きく減少しています。2000年度のPFCs排出量は1,150万トン(二酸化炭素換算)となり、1995年度と比べると0.1%減少しました。2000年度のSF6排出量は570万トン(二酸化炭素換算)となり、1995年度と比べると65.7%減少しました。電力設備からの排出が最も減少しています。
(2)オゾン層の破壊
ア 問題の概要
オゾン層*がCFC*、HCFC*、ハロン*、臭化メチル*等のオゾン層破壊物質により破壊されていることが明らかになっています。オゾン層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外線が増加し、人に対して皮膚ガンや白内障等の健康被害を発生させるおそれがあるだけでなく、植物やプランクトンの生育の阻害等を引き起こすことが懸念されています。
これらは化学的に安定な物質であるため、大気中に放出されると対流圏ではほとんど分解されずに成層圏に達します。そこで太陽からの強い紫外線を浴びて分解され、塩素原子や臭素原子を放出し、この塩素原子や臭素原子が触媒となってオゾンを分解する反応が連鎖的に起こります。
オゾン層の破壊は、被害が広く全世界に及ぶ地球規模の環境問題であり、いったん生じるとその回復に長い時間を要します。
イ オゾン層等の現況と今後の見通し
オゾン層は、熱帯地域を除き、ほぼ全地球的に減少傾向にあり、特に高緯度地域で減少率が高くなっています。わが国では、札幌、つくば、鹿児島、那覇及び南鳥島でオゾン層の観測が行われており、札幌で統計的に有意な減少傾向が確認されています(図1-1-5)。
また、南極では、2000年(平成12年)に過去最大規模のオゾンホールが観測され、2001年(平成13年)にも、過去最大規模に匹敵する大きさのオゾンホールが観測されました(図1-1-6)。
オゾン層破壊物質の大気(対流圏)中濃度については、CFC−11や大気中寿命の短い1,1,1-トリクロロエタンについては、すでに減少傾向を示しています。一方、HCFC及びハロンの大気中濃度は増加の傾向にあります。
有害紫外線量(UV-B量)については、国内の1991年からの観測結果によると、オゾンの減少傾向が確認されている札幌を含め、明らかな増加傾向はみられていません。しかし、晴天時等の同一条件下では、オゾン全量が減少すれば、紫外光の地上照射量が増加する関係にあることが確認されているので、1970年代に比べてオゾン全量が減少している地域においては、有害紫外線量(UV-B量)は増加しているものと考えられます。
UNEP(国連環境計画)等の報告(2002年(平成14年))は、
1) 対流圏(すなわち下層大気)では、オゾン層破壊物質の実効総量は1992年(平成4年)〜1994年(平成6年)のピーク以来、ゆっくりと減少し続けている。
2) 成層圏観測によると塩素総量はピークかそれに近いが、臭素量はおそらく依然として増加している。
3) モントリオール議定書*は機能しており、議定書で規制された物質によるオゾン層破壊は今後10年程度以内に改善し始めると予想される。議定書が完全に遵守されればオゾンホールは今世紀中頃までにはなくなるという予測もあるが、議定書の完全遵守をもってしても、オゾン層は特に今後10年程度は脆弱なままである。
としています。