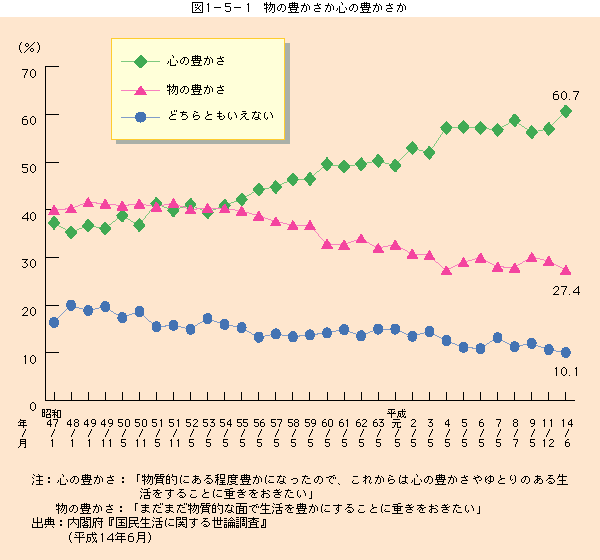
1 持続可能な社会の構築の手がかり
まず、ライフスタイルの変革の下地となる一人ひとりの価値観の変化を見ていくとともに、豊かさのとらえ方を変えた新しい生活が実践され始めていることを概観します。
(1)一人ひとりの意識や行動の変化
経済の発展と科学技術の進歩に伴い、今や私たちは、買いたいものがいつでも手に入る便利で快適な生活をおくるようになりました。わが国の一人当たりのGDPは世界でも最高水準にあり、自家用車保有台数や家電製品など耐久消費財の普及率の高まりが示すように、物質的な豊かさを享受しています。
しかし、物は豊かでも、心が豊かであるとは限りません。実際、高度経済成長期以後、この30年間で「物の豊かさ」より「心の豊かさ」を求める人の割合が、一貫して増加しており、平成14年6月の調査では、「心の豊かさ」を求める人が初めて6割を超えました(図1-5-1)。また、耐久消費財よりも、レジャーや余暇活動、自己啓発や能力向上等に今後の生活の比重が置かれ、物資の豊かさよりも、心の豊かさをはじめ、生活全体が豊かでゆとりがあることを重視する傾向が見受けられます(図1-5-2)。
また、耐久消費財の買い換えまでの使用年数が長期化しているほか(図1-5-3)、中古品市場が拡大しており、約9割の家庭で何らかの中古品を購入しているという調査結果もあります。購入したことのある中古品としては、古くから市場が整備されていた書籍に加え、最近では、衣料や玩具・CD・ビデオ等が増加しています。
このような意識の変化は、大量消費、大量廃棄型の生活から、質を重視した生活への変化が生じていることの一つの現れということができます。
(2)新しいライフスタイルの提案
一人ひとりの意識の変化を背景として、最近では、例えば以下のような、新しいライフスタイルが提案され、実践され始めています。
ここに示した新しいライフスタイルの実践は、必ずしも環境への配慮を中心的な目的として行われているものではありません。しかしその中には、「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へ、地球環境は「無限なもの」から「有限なもの」へ、商品は「量」から「質」へ、環境に配慮した生活は「質素」から「おしゃれでかっこいい」へ等、持続可能な社会の構築に向けて、一人ひとりに求められる発想の転換を表すキーワードが含まれています。
ア シンプルライフ
「シンプルライフ」という言葉が、贅沢で物質的に恵まれた生活に対して、心の豊かさを取り戻すためのライフスタイルを示すものとして広がりを見せており、シンプルな暮らしを提唱する書籍が人気を呼んでいます。具体的には、1)「単なる「節約」ではなく、吟味したものに囲まれて生活する」、2)「安いから買うのではなく、環境への配慮や長期間にわたる使用可能性などを考え、物の価値に見合った値段を払う」、3)「修理やリサイクル等を活用し少しだけ手間をかけて丁寧に生活する」等の生活像の提案が見られます。
こうしたライフスタイルは、必要な物だけを買い、長く使うといったことにより日常生活全体からの環境負荷の低減につながるものといえます。
博報堂生活総合研究所が、首都圏と阪神圏に住む20代から60代の男女2千人を対象に実施した調査によると、「シンプルな暮らし方をする方だ」と回答したのは全体の50.8%と半数を超え、10年前に比べると15.8ポイントの増加となっています。
このようにシンプルライフを志向する傾向は、豊かさのとらえ方を変えライフスタイルを変革していくための下地が整いつつあることを示すものと受け取ることができますが、さらに社会に広がるためには、一人ひとりがこのようなライフスタイルを単なる「節約」や「質素」ではなく「おしゃれでかっこいい」といった観点でとらえていくことも必要です。
イ スローフード
スローフードとは、1986年にイタリアのブラという町で始まった現代人の食生活を見直す運動です。この運動は、1)消えゆくおそれのある伝統的な食材や料理、質の良い食品、酒を守る、2)質の良い素材を提供する小生産者を守る、3)子どもたちを含め、消費者に味の教育を進める、ことを指針に掲げて、各地に残る食文化を尊重し将来に伝えていこうとする取組を進めています。現在では、わが国にもスローフード運動に取り組む団体が設立されるなど、世界で約7万人の会員を集めています。
わが国では、古来から米食や地方の特色ある食材を活かした郷土食がそれぞれの地方で親しまれ、日常の生活の中で自然と「スローフード」が実践されていました。しかし、第1節でもみたように、近年、多くの食料品が海外から輸入されるなど、地理的に遠く離れた生産地から輸送された食品を摂取するようになったことや、食材の季節的な変化(旬)の希薄化により、全国で食事や味の画一化が進みました。こうした傾向は同時に、野菜などを旬の時期を外して収穫するために加温栽培することや工場で大量に作られた食材を遠く離れた消費地まで輸送することなどにより、環境負荷を増大させることにもつながっています(図1-5-4)。
郷土食や地方の特色ある食材等を改めて見直すスローフード運動などの取組の広がりは、環境負荷の低減にも結びつくものといえます。
ウ ローハス(LOHAS)
ローハスとは、健康と持続可能な社会を志向するライフスタイル「Lifestyle of Health and
Sustainability」の略で、環境に配慮したライフスタイルを心がけるのみならず、地球環境の有限性や社会の未来像を視野に入れて持続可能な社会が実現するようなエネルギー、製品、交通手段の選択を心がけるなど、自分自身の日常生活以外のことにも総合的に深い関心を示したライフスタイルの概念です。1998年にアメリカの社会学者ポール・レイと心理学者のシェリー・アンダーソンが、このようなライフスタイルを志向する人々を「カルチュアル・クリエイティブス(Cultural Creatives)」と呼んだのをきっかけに、アメリカの企業が初めて提唱し、この概念に合った家庭用品や衣料品、クリーンエネルギー等を販売しました。
ローハスは、日常品のグリーン購入などの取組にとどまらず、使用するエネルギーを選択することなどにより、生活のあらゆる場面での環境負荷の低減につながるものです。
日本でも、昨年10月、アメリカのローハスの現状を紹介するシンポジウムが開催されるなど関心が持たれ始めています。