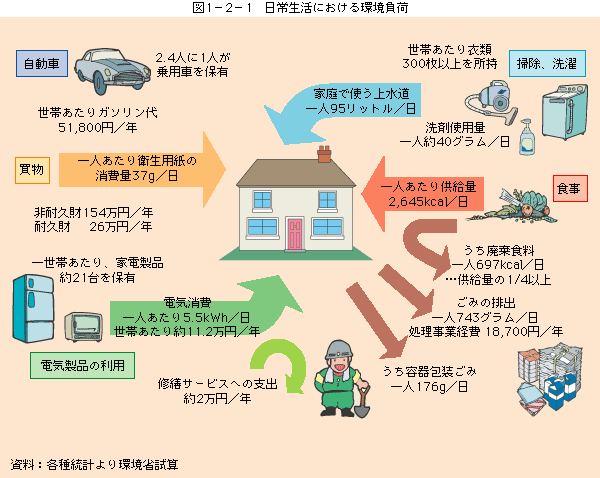
1 日常生活がもたらす環境負荷
私たちは日常生活のあらゆる場面において、少なからず環境に負荷を与えています。(図1-2-1)。
衣食住の各場面を通して、家電製品の使用、車の利用、上水道の使用、使い捨て品の購入等によりエネルギーや資源が消費されますが、エネルギーの消費は二酸化炭素の排出につながり、また、使用された物や資源は最終的には廃棄物として排出されることになります。例えば、住宅に用いられた建材は、住宅解体の際には建設廃棄物として排出される可能性がありますし、供給される食料のうちカロリー計算で約4分の1に当たる量は食べられずに廃棄されています。また、電化製品の待機電力のように、電化製品を使用していなくても知らず知らずのうちにエネルギーが消費されていることもあります。さらに、洗濯、掃除の際に洗剤を利用すれば、排出される生活排水が環境に負荷を与えることになります。
しかし、私たちの日常生活における環境負荷は、こうした直接的なものばかりではありません。私たちの日常生活が全体としてどのような環境負荷を与えているのか、以下で見てみます。
(1)ライフサイクルエネルギーで見た日常生活からの環境負荷
日常生活が与える環境負荷全体を見るに当たっては、私たちの日常生活の場において私たち自身が目に見える形で与える環境負荷にとどまらず、家庭で製品やサービスを使用するまでの、原材料や製品を加工、輸送する際の環境負荷も視野に入れる必要があります。環境負荷の一つの指標としてエネルギー使用を取り上げ、こうした日常生活におけるいわば間接的な環境負荷も含め、日常生活における環境負荷全体を定量的に見てみます。
日常生活における一年分のライフサイクルエネルギー*のうち、1)住宅・製品等の原料調達、製造、輸送等の段階で必要なエネルギー、2)消耗品の製造に必要なエネルギー、3)家庭で消費するエネルギーについて見ていくと、各段階でのエネルギー消費量は図1-2-2のようになっています。1)については、製造段階で大きなエネルギーが必要となりますが、耐用年数を考えて1年間あたりにすると小さくなります。一方、2)、3)については、電気の使用や洗剤の使用等1日におけるエネルギー消費量としては小さいものですが、1年分にすると大きくなります。この結果、日常生活においては冷暖房、照明の使用や自動車の運転等に必要な電気や石油等のエネルギー消費が一番大きな割合を占めています。
また、昭和54年調査と平成6年調査でのライフサイクルエネルギーを比較してみると、全体で約5.5%増加しています(図1-2-3)。その内訳を見ると、上記分類の1)の関係のエネルギー消費量については24%、2)の関係のエネルギー消費量については8%減少しています。これは工場等の省エネルギー化が進んだことによるものと考えられます。他方で、3)の関係のエネルギー消費量、すなわち家庭での電気・ガス・石油の使用量については大幅に増加しています。これは、第1節2で記述したように、家電製品や自動車の普及や生活時間帯の多様化等、社会の変化や私たちのライフスタイルの変化によりもたらされたものと考えられます。
また、製品ごとのライフサイクルエネルギーをみると(図1-2-4)、例えば、製造、使用、廃棄の各段階ごとの負荷割合はさまざまであることが分かります。自動車は使用時のエネルギーがライフサイクル全体の81%にもなり、さらに窒素酸化物などの大気汚染物質も排出します。また、住宅は解体時のエネルギーが全体の約7%となり、解体により発生する建設廃材の処理も考えると、廃棄段階の環境負荷はさらに大きくなります。
このように、日常生活のあらゆる場面からの環境負荷が地球規模での環境問題の原因になっていることを考えると、私たちは、日常生活の中で意識的に環境に配慮した行動をとっていく必要があるといえます。
例えば、製造段階や廃棄段階での負荷については、私たちの日常生活の場から直接的に負荷が発生しているものではありません。そのため、製造段階の負荷を減らすためには、原材料や製造工程・輸送における環境負荷を考えて製品を選択すること、廃棄段階の負荷については、循環システムが構築された製品を選択したり、中古品の有効利用、製品の長寿命化に努めることが必要です。また、使用段階での負荷については、日常生活の場でのこまめな取組が環境負荷の低減につながります。
(2)さまざまな指標で見た日常生活における環境負荷
ライフサイクルエネルギー以外にも、日常生活における間接的な環境負荷をとらえるさまざまな指標があります。
ア フード・マイレージなどで見た環境負荷
英国の消費者運動家(ティム・ラング氏)が、食料の生産地から食卓までの距離に着目し、なるべく近くで取れた食料を食べた方が輸送に伴う環境汚染が少なくなるという考え方に立って、1994年(平成6年)から「フード・マイル」という概念を提唱しています。この概念を参考にして、輸入食料品について「フード・マイレージ(単位:トン・キロメートル=輸入相手国別の食料輸入量×輸出国から輸入国までの輸送距離)」という指標を用いて試算すると、わが国のフード・マイレージは約5千億トン・キロメートル(平成12年)となっており、人口1人当たりで見ると、韓国の約1.2倍、米国の約8.0倍となっています(図1-2-5)。食料自給率の低いわが国では、食料の輸入による環境負荷は諸外国に比べて大きく、また、輸入量の増加とともに大きくなっています。
また、わが国が輸入している農産物などの生産に必要な水は、第3回世界水フォーラム事務局の試算によると、年間約400億m3であり、日本人の平均生活用水使用量で換算すると年間3億人分を上回る量になり、我々はこのように見えない形で世界の水資源を大量に使用しています。
イ エコロジカル・リュックサック
「エコロジカル・リュックサック」は、ドイツのヴッパータール研究所で提案されたもので、私たちが使う製品や、受けるサービスは、それらを作り出すために動かされ、変換される自然界の物質をリュックサックに入れて背負っていると考えて表現されました。
この指標は、ある素材や製品1kgを得るために、鉱石、土砂、水その他の自然資源を何kg自然界から動かしたかによって表わされます。データによれば、鋼鉄は21kg、アルミニウムは85kg、再生アルミニウムは3.5kg、金は540,000kg、ダイヤモンドは53,000,000kgの自然資源を動かすとされています。また、エコロジカル・リュックサックを用いて製品についての環境負荷を考えると、原材料の輸送、加工など、製品を製造するすべての段階にかかわるすべての物質のエコロジカル・リュックサックが加わることになり、原材料のリュックサックよりもはるかに重いリュックサックを背負っていることになります。
近年では、製品の原材料から生産・流通・使用・廃棄(リサイクル)まで、一生を通じてエネルギー使用だけではなく環境に与える負荷を客観的・定量的に評価するライフサイクルアセスメント(LCA)という手法の活用が進められています。私たち自身が日常生活で使用する製品をLCAで評価することが可能となれば、より環境負荷の少ない環境配慮型製品等を選択することができることとなります。つまり、私たち自身の製品選択が直接に、持続可能な社会づくりにつながっていくものと期待されます。