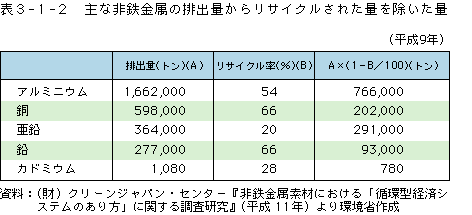
2 環境制約を回避するために
(1)さらなる環境対策の実施可能性
こうした事態を事前に回避するためには、さらなる環境対策への取組が不可欠となっています。
第1章でみたように、わが国は、激甚な公害の経験、2度にわたる石油危機等を通じ、エネルギー生産性、資源生産性を急速に高め、環境効率性の向上に努めてきましたが、さらなる環境対策を進めていくことの可能性について、ここでは、二酸化炭素排出量の削減と資源利用の効率化について具体的にみていきます。
(2)二酸化炭素排出量の削減
エネルギー供給面においては、エネルギー起源の二酸化炭素排出量が全体の約9割を占める状況下、今後、地球温暖化対策との調和と安定供給確保を実現するためには、原子力、新エネルギー等の非化石エネルギーの一層の導入促進が必要です。例えば、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等の新エネルギーは、1次エネルギー総供給の1%を占めるにとどまっています。また、引き続きエネルギー供給の太宗を占める化石エネルギー間における燃料転換を促進し、効率化への要請も満たしつつ、環境調和型のエネルギー供給構造の実現を目指すことが重要です。こうした供給面での対策により、新エネルギー対策では、平成22年度までに1910万kl(原油換算。以下同じ)の新エネルギー導入を図り、追加対策分として約34百万t-CO2の削減が見込まれます。また、燃料転換等の対策として、約18百万t-CO2の削減が見込まれます。
エネルギー需要面の対策は、産業部門における自主的対応と民主・運輸部門における省エネルギー機器・システムの技術開発・導入促進、これに必要な環境整備を中心とします。特に、1990年代の経済的低迷の中で、エネルギー消費の大幅な増加が続く民生、運輸部門については、その増加の抑制が喫緊の課題であり、各種機器の効率改善の強化、エネルギー管理の徹底、住宅・建築物の省エネルギー性能の向上等により対策を強化することが重要です。例えば、新規着工住宅においては断熱性の高い住宅のウエイトが増加していますが、住宅ストック全体で見れば、ほとんど断熱されていないものが依然として約6割を占めています。また、ハイブリッド車等の低公害車が全車両保有台数に占める割合は1%以下で依然小さく(平成13年3月末現在、図1-2-6参照)、鉄道輸送や海上輸送へのモーダルシフト等についてもさらなる対策が必要です。こうした需要面での対策により、平成22年度の効果として、現行対策として約5,000万kl、追加対策として700万klの削減が見込まれます。追加対策による二酸化炭素削減量は約22百万t-CO2と見込まれます。
(3)資源利用の効率化
資源利用については、第1章第1節1(1)でみたとおり、わが国の1年間の総物質投入量は21.3億トンに達しており、一人当たりの隠れたフローを含めた年間総物質使用量は45トン前後と高水準にあります(図1-1-5)。天然資源の消費の抑制と環境負荷の低減を図るためには、排出抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分の優先順位で取組を進める必要がありますが、例えば、このうち再生利用についてみると、ある物質の排出量からリサイクルされた量を除いた物質量は、非鉄金属のうちアルミニウムが約77万トン、亜鉛が約29万トン、銅が約20万トンに達しています(表3-1-2)。同様に、容器包装についてみると、スチール缶が約19万トン、ペットボトルが約24万トンと推計されており(表3-1-3)、資源の有効利用に一層の実施可能性があります。
(4)OECD環境保全成果レビュー
2002年(平成14年)1月、OECD環境政策委員会・環境保全成果作業部会において、対日審査報告書が承認され、わが国の環境政策の進展が評価を受けるとともに、依然として取組が不十分であるとされる分野について指摘と勧告がなされました。具体的には、富栄養化が深刻な水質問題となっていること、多くの動植物種が絶滅の危機にある点について改善がみられないこと、廃残留性農薬の適切な廃棄を促進すべきこと、経済成長と道路交通利用や二酸化炭素排出量の伸びとの切り離し(デカップリング)を行うための需要管理対策等が不十分であること等、先進国中で比較的に環境効率性の高いわが国においてもさらなる取組の実施可能性があることが指摘されました。
(5)技術予測調査
科学技術政策研究所が平成13年7月に取りまとめた第7回技術予測調査によれば、国内の技術専門家により、今後30年間に環境負荷の改善に資するさまざまな技術の実用化や普及が予測されており、これらの技術開発を実現することにより環境の改善が図られることが期待されます(図3-1-7)。