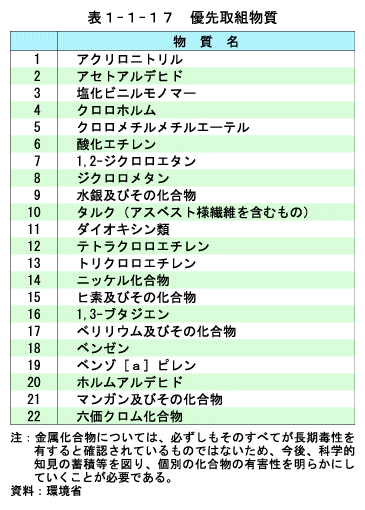
5 多様な有害物質による健康影響の防止
(1)多様な有害物質による大気汚染対策
ア 現況
近年、多様な化学物質が低濃度ではありますが大気中から検出されていることから、その長期暴露による健康影響が懸念されています。昭和60年度から国においてこれらの有害大気汚染物質のモニタリング調査を実施してきましたが、平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、平成9年度から地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングを開始しました。
平成11年度における環境庁及び地方公共団体が実施したモニタリング調査のうち、大気汚染防止法に基づく指定物質*に係る測定結果の概要は表1-1-7のとおりでした(ダイオキシン類に係る測定結果については第1章第5節に示す)。
ベンゼンについて、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における測定結果を平成9年2月に設定された環境基準値(0.003mg/立法メートル)と比較すると、340地点中79地点において環境基準値を超過していました。
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、すべての地点において環境基準値(ともに0.2mg/立法メートル)を下回っていました。
*指定物質
ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン:有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質
イ 対策
(ア)固定発生源対策
有害大気汚染物質による国民の健康被害を未然に防止するため、平成8年5月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質対策が位置付けられました(平成9年4月1日施行)。
これを受け、有害大気汚染物質に関する具体的な対策のあり方について中央環境審議会で審議が進められ、平成8年10月及び12月の2度にわたり答申がなされました。これらの答申においては、1)微量であってもがんを発生させる可能性が否定できず、閾(いき)値*がないと考えることが適切な物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについて、生涯リスクレベル10(-5)(10万人に1人の割合の生涯リスクレベル)を当面の目標とすること、2)有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(234種類)のリストと、優先取組物質(22種類)のリスト(表1-1-17)、3)ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの環境基準設定に当たっての指針値、4)指定物質等の排出抑制のあり方、5)有害大気汚染物質のモニタリングのあり方等の基本的考え方が示されました。
これを受けて、平成9年1月、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを指定物質に指定し、指定物質排出施設を定めるとともに、同年2月には指定物質抑制基準及び環境基本法第16条に基づく環境基準を設定しました。ジクロロメタンについては、中央環境審議会より平成12年12月、大気環境基準の設定に当たっての指針値を年平均値0.15m/立方メートル以下とする旨の答申が取りまとめられました。
さらに、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主的取組を促進するため、平成8年10月、環境庁と通商産業省において「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針」を策定し、12物質(平成9年9月に1物質追加し、計13物質)について事業者団体による自主管理計画の策定を促しました。その後、各事業者団体の策定した自主管理計画を中央環境審議会、化学品審議会の場を通じ、把握、評価しています。また、同様に平成9、10及び11年度の自主管理計画の実施状況についても、中央環境審議会、化学品審議会に報告され、評価されたところです。
また、改正大気汚染防止法において、法施行後3年(平成12年度)を目途に有害大気汚染物質対策の制度のあり方を検討することとされており、中央環境審議会において審議が行われ、従来の事業者団体単位による自主管理をさらに進め、これに加えて、ベンゼンの高濃度地域を対象として、新たな地域単位の自主管理を実施すること等を内容とする答申が平成12年12月になされました。また、化学品審議会において、自主管理による有害大気汚染物質対策の評価と今後のあり方について審議が行われ、同様の内容の報告が平成12年12月になされました。
*閾(いき)値
その暴露量以下では影響が起こらないとされる値
(イ)自動車排出ガス対策
自動車排出ガスに係る有害大気汚染物質対策については、平成8年10月の中央環境審議会中間答申において、1)2輪車の排出ガス規制導入、2)ガソリン軽貨物車等の排出ガス規制強化、3)ガソリン中のベンゼン含有率を1体積%に低減することが示され、同答申に基づき平成10年から平成11年にかけて規制を強化したところです(表1-1-18)。
(2)石綿対策
石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されてきましたが、発がん性などの健康影響を有するため、種類によっては、製造・使用が禁止されています。大気汚染防止法では、石綿を「特定粉じん」と指定し、石綿製品等の製造施設には敷地境界規制等が行われています。平成11年末現在での時点で、特定粉じん発生施設の総数は19百施設です。
また、吹き付け石綿を使用する建築物の解体等作業には作業基準等が定められています。