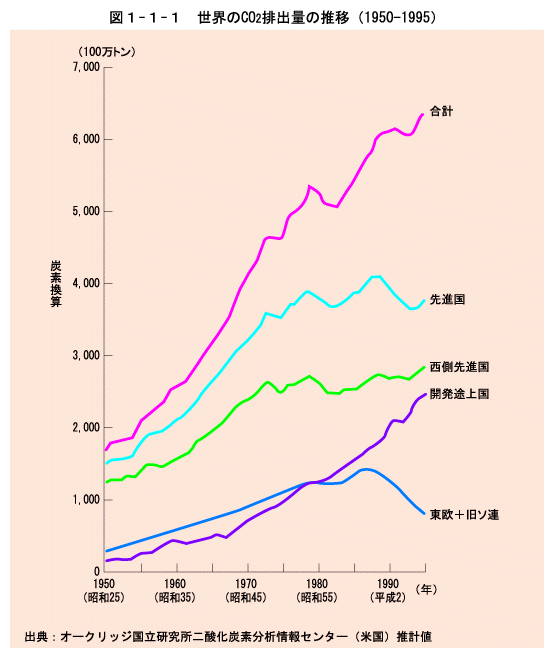
1 大気環境の現状
大気環境問題には、人間活動により地球規模の影響を及ぼす地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨などの問題と、地域レベルでの大気汚染である窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなどの問題があります。
(1)地球温暖化
ア 問題の概要
地球温暖化は、人間活動により、自然界での健全な物質の循環がゆがむことにより生じる環境問題の典型的事例です。
大気中には、二酸化炭素、メタンなどの「温室効果を有するガス」が含まれており、これらのガスの温室効果により、人間や動植物にとって住み良い大気温度が保たれてきました。ところが序説1章2節でみたとおり、近年の人間活動の拡大に伴って二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスが大量に大気中に排出されることで、温室効果が強まって地球が温暖化するおそれが生じています(図1-1-1)。特に、二酸化炭素はその排出量が膨大であるため、温暖化への寄与度は全世界における産業革命以降の累積で約64%を占めています(図1-1-2)。
イ 地球温暖化の現況と今後の見通し
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の2001年(平成13年)の報告によると、1861年以降、全球平均地上気温が0.6±0.2℃上昇しました。20世紀における温暖化の程度は、北半球では過去1000年のいかなる世紀と比べても、最も著しいとしています。同報告は、過去50年間に観測された温暖化の大部分が人間活動に起因しているという、新たな、かつより強力な証拠が得られたことを指摘しています。
また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造などの動向について一定の前提条件を設けた複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、1990年から2100年までの全球平均地上気温の上昇は、1.4℃〜5.8℃と予測されています。ほとんどすべての陸地は、特に北半球高緯度の寒候期において、全球平均よりも急速に温暖化することがほぼ確実です。北アメリカ北部や北アジア及び中央アジアでこの傾向が最も顕著で、全球平均の変化より40%以上急速に温暖化します。このような気温の上昇は、過去1万年の間に例をみない極めて急激な変動であると考えられています。
気温は、日較差や年較差をもって周期的に変動していますが、その変動は大きな問題を起こすものではありません。しかし、全体としての平均気温の上昇はその数値が日較差に比べ微細であっても環境に大きく影響するおそれがあります。気象庁によると、地球表面の年平均気温は100年間の長期傾向では0.6℃上昇しており、2000年(平成12年)におけるそれは、1880年(明治13年)以降で第4位でした(図1-1-3)。この変化には、人の活動による影響が含まれることは否定できません。
こうして地球温暖化が進行するのに伴い、人類の生活環境や生物の生息環境に広範で深刻な影響が生じるおそれがあります。
ウ 地球温暖化に関する世界的な影響
(ア)海面の上昇
気温の上昇は、海水の膨張、極地及び高山地の氷の融解を引き起こし、その結果として海面の上昇を招きます。この場合、海岸線の移動により多大な影響が生じると考えられます。IPCCによれば海面水位は1990年から2100年までの間に9〜88cm上昇することが予測されています。2080年までに海面水位が40cm上昇する場合、沿岸の高潮により水害を被る世界の人口は、年平均で7500万人から2億人の範囲で増加すると予測されています。
(イ)経済格差の拡大
IPCCによると、地球温暖化によって、多くの開発途上国で経済的損失が生じ、温暖化が進行するほど損失も大きくなることが予測されています。一方、先進国ではわずかな気温上昇では、経済的利益・損失両方とも予測されますが、より大きな温暖化では損失となることが予測されています。この影響予測によれば、先進国と開発途上国の間の暮らしぶりの格差が広がり、温暖化が進行するほどその格差は大きくなります。また、世界のGDPについても、わずかな気温上昇では±数%の変化ですが、より大きな温暖化では損失が増加することが予測されています。
(ウ)食糧危機
IPCCによると、わずかな気温上昇では、中緯度での農作物生産にとって好影響となりますが、それ以上の温暖化が起きると悪影響となることが予測されています。特に熱帯では、一部の農作物生産は、すでに気温が許容範囲の上限近くにあることから、わずかな気温上昇でさえも、生産量は減少します。また、地球の年平均気温が数℃以上上昇した場合、地球規模での食糧需要の増加に対して、食糧供給の拡大が遅れることによる食料価格の上昇が予測されています。
(エ)生態系への影響
IPCCによると、すでに多くの野生生物の種や個体群が危機に曝されており、気候変化によって、21世紀には、現在「深刻な危機に曝されている」と分類されている一部の種は絶滅し、「危機に曝されている、または脆弱である」と分類されているものの大多数は希少種となって、絶滅に近づくと予測されています。
(オ)健康への影響
生物、食糧、水によって媒介する伝染病の多くは、気候変化に敏感であることが知られています。IPCCによると、マラリアとデング熱は、現在、世界人口の40〜50%に影響を及ぼしていますが、気候変化によりその伝染可能性の範囲が拡大することが予測されています。また、熱波の増加により熱に関連した死亡や疾病の増加が起こり、洪水の増加により溺死、下痢、呼吸器疾患、特に開発途上国では飢餓や栄養失調となる可能性が増加すると予測されています。
エ わが国における影響
気象庁の観測によると、わが国でも年平均気温はこの100年間で1.0℃上昇しています。特に1980年代からの上昇が著しくなっています(図1-1-4)。
平成9年3月の報告書「地球温暖化の日本への影響」によれば二酸化炭素換算濃度を現在の2倍とした条件の下で、日本においても、水資源、農業、森林、生態系、沿岸域、エネルギー、健康などの分野において温暖化が様々な悪影響を及ぼすことが予測されています。これらの影響の多くは不可逆的なものです。
オ 温室効果ガスの排出状況
(ア)わが国の排出状況
平成12年9月の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」及び「地球温暖化対策推進本部」に報告された、平成10年度の温室効果ガス排出量によると、わが国の二酸化炭素排出量は11億8800万トン、1人当たり排出量は9.39トン(ともに二酸化炭素換算)であり、平成2年度に比べ1人当たり排出量では3.2%、総量については5.6%増加しています。これを部門別にみると、運輸部門が21.1%、民生(業務)部門が16.1%増加している一方で、産業部門は3.2%減少しています(図1-1-5)。
運輸部門のCO2排出量のうち、自家用乗用車の占める割合が最も高く(55.6%)(図1-1-6)、自家用乗用車の保有台数も毎年伸び続ける傾向にあります(図1-1-7)。
(イ)排出削減のための課題
これまでみてきたように、温暖化の影響が顕在化し、取り返しのつかない事態が生ずる前に、予防的見地からいわゆる「後悔しない対策*」を実施していくとともに、それを越えた対策を実施していくことが必要です。
平成12年12月に見直された環境基本計画の中では、1)究極の目標として、「気候変動枠組条約」が目的に掲げる「気候系に対する危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化」させることを目指すこと、2)中長期的な目標として、「各分野の政策全体の整合性を図りながら、温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会の構築」を目指すこと、3)京都議定書におけるわが国の目標である、温室効果ガスの6%削減目標を達成すること、が掲げられています。
しかしながら、最も主要な温室効果ガスである二酸化炭素は、人間活動のあらゆる局面から生じるものであり、その排出の抑制・削減に当たっては、従来の公害対策とは異なった新たな対応を要します。また、その他の温室効果ガスであるメタン、一酸化二窒素、HFC等(いわゆる代替フロン等)についても、それぞれの排出実態を踏まえた対策を実施していく必要があります。このため、序説2章2節3で述べたように、工場、事業所、家庭など、経済社会の中の様々な場所で対策を強化していくことはもちろんとして、各方面の対策を有機的に組み合わせて、将来的には、現代の大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済システムを見直し、変更していく抜本的な取組が必要となっています。地球温暖化のもたらす大きな影響とともに、その対策の困難性から、地球温暖化問題は現在の環境行政の最重要課題の一つとなっています。
このような中、平成9年12月には、京都において気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)が開かれ、京都議定書が採択されました。本議定書では、先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を設定するとともに、目標達成のための国際的仕組みとして京都メカニズム(序説2章2節1参照)を導入すること等が規定されています。京都議定書の2002年までの発効に向けて、議定書の実施に必要となる詳細なルールや手続等について、2000年11月のCOP6で合意すべく交渉が行われたものの合意には至らず、COP6は中断となりました。このため2001年7月に開催が予定されているCOP6再開会合での合意に向けて、引き続き国際交渉の進展に最大限努めるとともに、本議定書の締結に必要な国内制度に全力で取り組みます。
*後悔しない対策
温暖化防止効果以外の面でも大きな効用があり、仮に温暖化が起こらなくても後悔しない範囲の対策
(2)オゾン層の破壊
ア 問題の概要
オゾン層*が人工の化学物質であるCFC*、HCFC*、CFC及びHCFC*、ハロン*、臭化メチル*等のオゾン層破壊物質により破壊されていることが明らかになっています。オゾン層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外線が増加し、人に対して皮膚ガンや白内障等の健康被害を発生させるおそれがあるだけでなく、植物やプランクトンの生育の阻害等を引き起こすことが懸念されています。
これらは化学的に安定な物質であるため、大気中に放出されると対流圏ではほとんど分解されずに成層圏に達します。そこで太陽からの強い紫外線を浴びて分解され、塩素原子や臭素原子を放出し、この塩素原子や臭素原子が触媒となってオゾンを分解する反応が連鎖的に起こります。
オゾン層の破壊は、被害が広く全世界に及ぶ地球規模の環境問題であり、いったん生じるとその回復に長い時間を要します。
*オゾン層
地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10〜50km上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。オゾン層は太陽光に含まれる有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を守っている。
*CFC
クロロフルオロカーボン:いわゆるフロンの一種
*HCFC
ハイドロクロロフルオロカーボン
*CFC及びHCFC
冷媒、発泡剤、洗浄剤等
*ハロン
主に消火剤として使用される。
*臭化メチル
主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸として使用される。
イ オゾン層等の現況と今後の見通し
オゾン層は、熱帯地域を除き、ほぼ全地球的に減少傾向にあり、特に高緯度地域で減少率が高くなっています。わが国では、札幌、つくば、鹿児島、那覇及び南鳥島でオゾン層な減少傾向が確認されています(図1-1-8)。
また、南極では、2000年(平成12年)に過去最大規模のオゾンホールが観測されました。(図1-1-9)。
オゾン層破壊物質の大気(対流圏)中濃度については、CFCが最近減少に転じているほか、大気中寿命の短い1,1,1-トリクロロエタンについては、すでに減少傾向を示しています。一方、HCFC及びハロンの大気中濃度は増加の傾向にあります。
有害紫外線量(UV-B量)については、国内のこれまでの観測結果によると、オゾンの減少傾向が確認されている札幌を含め、観測期間が短いこともあって明らかな増加傾向はみられていません。しかし、晴天時等の同一条件下では、オゾン全量が減少すれば、紫外光の地上照射量が増加する関係にあることが確認されているので、1970年代に比べてオゾン全量が減少している地域においては、有害紫外線量(UV-B量)は増加しているものと考えられます。
国連環境計画(UNEP)の報告(1998年(平成10年))は、すべての締約国が1997年(平成9年)の改正モントリオール議定書*を遵守すれば、
1) 成層圏中の塩素及び臭素濃度の合計(オゾン層破壊物質が分解してできるこれら元素がオゾン層を破壊する)は、2000年より前にピークに達する。
2) オゾン層破壊のピークは、2020年までに訪れる。
3) 成層圏中のオゾン層破壊物質濃度は、2050年までに1980年以前のレベルに戻る。
4) その他の気体(一酸化二窒素、メタン、水蒸気等)の将来の増加又は減少及び気候変動がオゾン層の回復に影響を及ぼす。
と予測しています。
*改正モントリオール議定書
オゾン層の保護のためのウィーン条約に基づき、オゾン層を破壊する物質の削減スケジュール等の具体的な規制措置等を定めたもの。1987年に採択され、1990年、1992年、1995年、1997年、及び1999年の5度にわたって規制強化のための改正等が行われてきた。2000年9月28日現在のウィーン条約締約国数は175か国と1経済機関(EC)、モントリオール議定書の締約国数は174か国と1経済機関(EC)である。
(3)酸性雨
ア 問題の概要
酸性雨*により、湖沼や河川等の陸水の酸性化による魚類等への影響、土壌の酸性化による森林等への影響、樹木や文化財等への沈着等が考えられ、これらの衰退や崩壊を助長することなどの広範な影響が懸念されています。酸性雨が早くから問題となっている欧米においては、酸性雨によると考えられる湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されています。
酸性雨は、原因物質の発生源から500〜1,000kmも離れた地域にも沈着する性質があり、国境を越えた広域的な現象であることに一つの特徴があります。欧米諸国では酸性雨による影響を防止するため、1979年(昭和54年)に「長距離越境大気汚染条約」を締結し、関係国がSOx、NOx等の酸性雨原因物質の削減を進めるとともに、共同で酸性雨や森林のモニタリングや影響の解明などに努めています。
*酸性雨
主として化石燃料の燃焼により生ずる硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの酸性雨原因物質から生成した硫酸や硝酸が溶解した酸性の強い(pHの低い)雨、霧、雪(「湿性沈着」という)や、晴れた日でも風に乗って沈着する粒子状(エアロゾル)あるいはガス状の酸(合わせて「乾性沈着」という)を合わせたものとされている。
イ 酸性雨対策調査結果
酸性雨は、従来、先進国の問題であると認識されていましたが、近年、開発途上国においても、目覚ましい工業化の進展により大気汚染物質の排出量は増加しており、地域の大気汚染に加え、国を越えた広域的な酸性雨も大きな問題となりつつあります。このため、地球サミットで採択された「アジェンダ21」では、先進国のみならず、開発途上国も含めて今後、酸性雨等広域的な環境問題への取組を強化すべきであるとしています。
わが国では、第1次酸性雨対策調査(昭和58〜62年度)、第2次酸性雨対策調査(昭和63〜平成4年度)、第3次酸性雨対策調査(平成5〜9年度)、及び第4次酸性雨対策調査(平成10〜12年度)において、降水、陸水、土壌・植生系の継続的なモニタリング、各種影響等予測モデルの開発、樹木の衰退等と酸性雨との関連が指摘されている地域における降水、大気汚染物質、土壌・植生などの総合的な調査研究の実施、乾性沈着及び生態影響評価手法の検討を行いました。第3次調査での調査結果の概要は次のとおりです。
1) 平成5年度から9年度までの降水中の全地点年平均pHは4.8〜4.9と、第2次調査の結果とほぼ同じレベルの酸性雨が観測された(図1-1-10)。これまで森林、湖沼等の被害が報告されている欧米と比べてもほぼ同程度の酸性度であった。また、日本海側の測定局で冬季に硫酸イオン、硝酸イオン濃度及び沈着量が増加する傾向が認められ、大陸からの影響が示唆された。
2) 酸性雨の陸水モニタリングでは、酸性雨による影響が生じている可能性がある湖沼が確認された。また、これまでに構築したモデルによれば、総合モニタリング調査を継続実施し、実測データ及び文献データが得られている蟠竜湖(島根県)及び伊自良湖(岐阜県)については、土壌に吸着されている陽イオンの量のみでは長期的に緩衝能力を維持することは困難であり、影響予測は鉱物の風化に伴う陽イオンの供給と落ち葉からのイオンの溶出等の植物による緩衝能力の評価などに依存すると考えられた。
3) 土壌・植生モニタリングでは、第2次調査に引き続き原因不明の樹木衰退が確認された。また、土壌理化学性の面からは第2次調査に比べ顕著な変動は見られなかったが、樹木衰退が見られる地点等において、引き続きモニタリングが必要であるとされた。
このように、わが国における酸性雨による生態系等への影響は現時点では明らかになっていませんが、一般に酸性雨による陸水、土壌・植生等に対する影響は長い期間を経て現れると考えられているため、現在のような酸性雨が今後も降り続けるとすれば、将来、酸性雨による影響が顕在化する可能性があります。
(4)光化学オキシダント
ア 問題の概要
光化学オキシダント*は「1時間値が0.06 ppm以下であること」という環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)が設定されています。光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件から見てその状態が継続すると認められるときは、大気汚染防止法の規定によって都道府県知事等が光化学オキシダント注意報を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民、工場、事業場等に対して情報の周知徹底を迅速に行うとともに、ばい煙の排出量の削減又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めることになっています。
*光化学オキシダント
工場、事業所や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や炭化水素類(HC)を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの物質の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている。光化学オキシダントは強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器へ影響を及ぼし、農作物などへも影響を与える。
イ 平成11年度における光化学オキシダントの測定結果
平成11年度において光化学オキシダントは、一般環境大気測定局については648市町村、1,149局で、自動車排出ガス測定局については23市町村、34局で測定されています。
光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況は、例年極めて低く、一般局と自排局を合わせて、昼間(午前5時〜午後8時)の1時間値の最高値が0.06ppm(環境基準)以下であった測定局及び0.12ppm(注意報レベル)未満であった測定局数は、表1-1-1のとおりです。
ウ 平成12年における光化学オキシダント注意報等の発令状況等
(ア)全国の注意報等発令日数
平成12年の光化学オキシダント注意報*の発令は、延べ259日(22都府県)で、平成11年の100日(19都府県)と比べ、約2.6倍に増加しました。光化学オキシダント高濃度の発生は気象条件等に大きく影響されるため、年により大きく増減し、平成12年は過去10年間で最多の発令となりました(表1-1-2)。
平成12年の発令延日数(都道府県を一つの単位として注意報等の発令日数を集計したもの)を月別にみると、7月が最も多く76日、8月(67日)、6月(64日)の順でした。本年も昨年に引き続き、平成元年以来2度目の10月に入ってからの注意報の発令を記録しました。なお、平成12年は光化学オキシダント警報*の発令はありませんでした。
*光化学オキシダント注意報
光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。
*光化学オキシダント警報
各都道府県等が独自に要綱等で定めているもので、一般的には、光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。
(イ)注意報発令のブロック別内訳
平成12年の注意報発令延日数のブロック別内訳をみると、東京湾ブロック*で151日となっており、全体の58%を占めています(図1-1-11)。
*東京湾ブロック
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都6県
(ウ)被害届出人数
平成12年の光化学大気汚染によると思われる被害者の届出人数*は1,479人であり、平成11年の402人に比べ、1,077人増加しました。被害届出人数は年により大きく増減しますが、過去10年間では最多となりました。
*届出人数
自覚症状による自主的な届出による。
エ 非メタン炭化水素の測定結果
昭和51年8月中央公害対策審議会より「光化学オキシダントの生成防止のための大気中の炭化水素濃度の指針について」が答申され、この中で、炭化水素の測定については非メタン炭化水素を測定することとし、光化学オキシダントの環境基準である1時間値の0.06ppmに対応する非メタン炭化水素の濃度は、午前6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmC*の範囲にあるとされています。
*ppmC
炭素原子数を基準として表したppm値
(ア)一般環境大気測定局
平成11年度において非メタン炭化水素は、262市町村、361測定局で測定されています。昭和53年度から継続して測定を行っている6測定局の午前6〜9時における年平均値の経年変化は表1-1-3のとおりです。
(イ)自動車排出ガス測定局
平成11年度において非メタン炭化水素は、123市町村、177測定局で測定されています。昭和52年度から継続して測定を行っている8測定局の午前6〜9時における年平均値の経年変化は表1-1-3のとおりです。
(5)窒素酸化物
ア 問題の概要
一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)等の窒素酸化物(NOx)は、主に物の燃焼に伴って発生し、その主な発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。NOxは酸性雨や光化学大気汚染の原因物質となり、特にNO2は高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。
イ 二酸化窒素の年平均値の推移
平成11年度の二酸化窒素に係る有効測定局(年間測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。以下同じ。)は、一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)712市町村1,460測定局、自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)238市町村394測定局です。
年平均値の推移は図1-1-12のとおりであり、平成11年度は、一般局0.016ppm、自排局0.030ppmと前年度に比べやや減少しているが、長期的にみるとほぼ横ばいの傾向にあります。大気汚染防止法によって、工場等の固定発生源からのNOxの総量規制制度が導入されている東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域における環境基準達成率は、一般局では86.9%、自排局では36.3%となっています(平成10年度は一般局57.9%、自排局16.3%)。
ウ 二酸化窒素における環境基準の達成状況
二酸化窒素に係る環境基準*による長期的評価は、年間における1日平均値のうち低い方から数えて98%目に当たる値(以下「1日平均値の年間98%値」という。)と基準値を比較して行います。
平成11年度の有効測定局について環境基準の達成状況の推移は、図1-1-13のとおりです。
1日平均値の年間98%値が環境基準のゾーンの上限である0.06ppm以下の測定局(環境基準達成局)についてみると、平成11年度は、一般局98.9%、自排局78.7%となっており(図1-1-14)、その割合は平成10年度と比較すると、一般局、自排局とも増加しましたが、大都市地域における環境基準の達成状況は依然低い状況です。
また、平成11年度に環境基準が達成されなかった測定局の分布について見ると、一般局については、東京都、神奈川県及び大阪府の3都府県、自排局については、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び兵庫県などの「自動車NOx法*」の特定地域を有する都府県に加え、石川県、愛知県、京都府、長崎県等、特定地域以外の10道府県にも分布しています。
*環境基準
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること
*自動車NOx法
「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」平成4年6月3日法律第70号
エ 二酸化窒素の環境基準に基づき区分されたゾーン内にある地域の動向
二酸化窒素の日平均値が0.04ppmから0.06 ppmまでのゾーン内にあるとされた地域における二酸化窒素の濃度の動向については、告示第2の2中の現状の水準に当たる昭和52年度及び平成7年度から平成11年度までの状況は表1-1-4のとおりです。
オ 自動車NOx法特定地域における二酸化窒素に係る環境基準の適合状況等
自動車NOx法に基づき、自動車の交通が集中している地域で、固定発生源対策及び自動車単体規制等のこれまでの措置によっては二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域が特定地域と指定され、平成12年度末までの環境基準のおおむね達成を目標に、平成5年より各種施策が実施されてきたところです。しかし、特定地域全体における二酸化窒素に係る環境基準の達成局の割合は、平成7年度から11年度までで33.3〜41.2%(自動車排出ガス測定局)と低い水準で推移しており(図1-1-15)、目標の達成は極めて困難な状況にあります。ただし、平成11年度については前年度までと比べて格段に上昇していますが、気象等の一時的な要因によるところが大きいと考えられています。また、二酸化窒素の濃度の年平均値は、近年ほぼ横ばいの状況にあります(図1-1-16)。
カ 一酸化窒素の年平均値の推移
平成11年度の一酸化窒素に係る有効測定局数は、一般局712市町村1,460測定局、自排局238市町村394測定局でした。年平均値についてみると、平成11年度は、一般局0.010ppm、自排局0.045ppmと平成10年度と比べてやや低くなっています。
参考として諸外国の主要都市の状況をみると、1985年(昭和60年)以降1990年代にかけて、東京やリスボンなど窒素酸化物による大気汚染の状況が悪化している都市がある一方で、ニューヨーク、ブリュッセル、ベルリン、チューリッヒなど改善している都市もあります(図1-1-17)。
(6)浮遊粒子状物質等
ア 問題の概要
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、環境基準の設定されている浮遊粒子状物質*とそれ以外に区別されます。浮遊粒子状物質は微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子があります。一次粒子の発生源には、工場等から排出されるばいじんやディーゼル排気粒子(DEP)*等の人為的発生源と、土壌の巻き上げ等の自然発生源があります。
*浮遊粒子状物質
Suspended Particulate Matter、SPM:大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm(マイクロメートル)(μm=1000分の1mm)以下のものをいう。
*ディーゼル排気粒子(DEP)
ディーゼル自動車から排出される粒子状物質のことをいい、発がん性、気管支喘息、花粉症等の健康影響が懸念されている。その質量、粒子数の大部分はそれぞれ粒径0.1〜0.3μm、0.005μm〜0.05μmの範囲にあるとされている。
イ 浮遊粒子状物質による大気汚染の現況
平成11年度の浮遊粒子状物質に係る有効測定局数は、一般局714市町村1,529測定局、自排局186市町村282測定局となっています。
年平均値の推移は図1-1-18のとおりであり、平成11年度は、一般局0.028mg/立方メートル、自排局0.037mg/立方メートルと平成10年度に比べて減少しており、近年ほぼ横ばいからゆるやかな減少傾向がみられます。
浮遊粒子状物質は発生源が多岐にわたり、また大気中での光化学反応等によって二次的にも生成するなど発生機構が複雑であることから、高濃度地域における環境基準達成に向けた総合的対策の確立を図るため、原因物質の排出実態、二次生成粒子の生成機構等について検討を進めているところです。
諸外国の状況を見ると、ヨーロッパ諸国(スカンディナビア諸国を除く。)は、わが国よりも浮遊粒子状物質の濃度が高い水準となっています。これについては自然発生分も考慮しなければなりませんが、ディーゼル車の比率が高いことがその一因と考えられます。また、浮遊粒子状物質の濃度の推移は、増加している都市が一部あるものの、おおむね低下傾向にあります(図1-1-19)。
ウ 浮遊粒子状物質に係る環境基準の適合状況
浮遊粒子状物質の環境基準の長期的評価においては、年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、年間を通じて1日平均値が0.10mg/立方メートルを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準に適合するものとしています。
長期的評価に基づく環境基準の達成率の推移は図1-1-20のとおりであり、平成11年度は、一般局では90.1%、自排局では76.2%と平成10年度に比べていずれも上昇しています。環境基準を達成していない測定局の分布を見ると、東京都、神奈川県等の関東地域の6都県を中心に、愛知県、大阪府等の11府県、特に大都市地域を中心に分布しています。
エ 降下ばいじんによる大気汚染の現況
物の破砕や選別、堆積に伴って飛散する大気中のすす、粉じん等の粒子状物質のうち比較的粒が大きく沈降しやすい粒子は、降下ばいじんと呼ばれています。平成11年度において長期間継続して測定を実施している測定局は、平成10年度の7測定局から4測定局となり、その年平均値は4.4t/平方キロメートル/月となっています(表1-1-5)。
オ スパイクタイヤ粉じん
昭和50年代の初めからスパイクタイヤが積雪地域で急速に普及し、スパイクタイヤの使用により発生する粉じんが問題となりました。不快感や衣服、洗濯物の汚れだけでなく、人体への影響も懸念されたため、現在はその製造・販売は中止され、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」により使用禁止地域の指定も進み、スパイクタイヤに係る降下ばいじん量は著しく改善しています。
(7)硫黄酸化物等
ア 二酸化硫黄による大気汚染の年平均値の推移
平成11年度の二酸化硫黄*に係る有効測定局数は、一般局691市町村1,551測定局、自排局83市町村101測定局となっています。
年平均値の推移は図1-1-21のとおりであり、平成11年度は、一般局では0.004ppm、自排局では0.005ppmと平成10年度と比較してほぼ横ばい、もしくは減少傾向にあります。諸外国の状況を参考に見ると、二酸化硫黄濃度はおおむね減少傾向にあります(図1-1-22)。
*二酸化硫黄
SO2:硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、四日市ぜんそく等の公害病や酸性雨の原因となっている。
イ 長期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準の適合状況
二酸化硫黄の環境基準の長期的評価においては、年間にわたる1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した値が0.04ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合に環境基準に適合するものとしています。長期的評価に基づく環境基準の達成状況の推移は表1-1-6のとおりであり、良好な状態が続いています。
ウ 短期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準の適合状況
短期的評価においては、1日平均値がすべての有効測定日(1日20時間以上測定が行われた日をいう。以下同じ。)で0.04ppm以下の場合、かつ、1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下の場合に環境基準に適合するものとしています。
1日平均値がすべての有効測定日で0.04ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合は、平成11年度は、一般局99.7%、自排局100%と10年度同様高い水準を維持しています。1時間値がすべての測定時間において0.1ppm以下の測定局数の有効測定局数に対する割合についても、平成11年度は、一般局98.1%、自排局100%と平成10年度同様高い水準を維持しています。
エ 一酸化炭素による大気汚染の年平均値の推移
平成11年度の一酸化炭素*に係る有効測定局数は、一般局118市町村139測定局、自排局203市町村319測定局となっています。
年平均値の推移は図1-1-23のとおりであり、平成11年度は、一般局0.5ppm、自排局0.9ppmと平成10年度と比較して、横ばいとなっています。
*一酸化炭素
CO:燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされている。COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンガスの寿命を長くする。
オ 一酸化炭素に係る環境基準の適合状況
平成11年度においては、平成10年度に引き続き、一般局、自排局ともすべての測定局において環境基準の長期的評価*及び短期的評価*いずれの評価によっても環境基準を達成しています。
*長期的評価
年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した値が10ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しない場合に環境基準に適合するものとしている。
*短期的評価
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20 ppm以下である場合に環境基準に適合するものとしている。
(8)有害大気汚染物質
近年、多様な化学物質が低濃度ではあるが大気中から検出されていることから、その長期曝露による健康影響が懸念されています。昭和60年度から国においてこれらの有害大気汚染物質*のモニタリング調査を実施してきましたが、平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、平成9年度から地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングを開始しました。
平成11年度における環境庁及び地方公共団体が実施したモニタリング調査のうち、大気汚染防止法に基づく指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン)に係る測定結果の概要は表1-1-7のとおりでした(ダイオキシン類に係る測定結果については第1章第5節に示す。)。
ベンゼンについて、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における測定結果を平成9年2月に設定された環境基準値(0.003mg/立方メートル)と比較すると、340地点中79地点について環境基準値を超過していました。
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、すべての地点において環境基準値(ともに0.2mg/立方メートル)を下回っていました。
*有害大気汚染物質
OECDの定義によれば「大気中に微量存在する気体状、エアロゾル状又は粒子状の汚染物質であって、人間の健康、植物又は動物にとって有害な特性(例えば、毒性及び難分解性)を有するもの」とされており、種々の物質及び物質群を含むが、この語は、古くから問題となり規制の対象とされてきたNOxやSOxなどの大気汚染物質とは区別して用いられている。一般に大気中濃度が微量で急性影響は見られないが、長期的に曝露されることにより健康影響が懸念される。日本の大気汚染防止法では、「継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と定義されている。
(9)騒音・振動、悪臭
生活環境の保全上、大気汚染のほか、主に人の感覚に関わる問題である騒音、振動、悪臭が重要課題となっています(図1-1-24)。
ア 騒音・振動
(ア)問題の概要
騒音は、各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題であり、また、その発生源も多種多様であることから、例年、その苦情件数は公害に関する苦情件数のうちの多くを占めています。
騒音発生源の種類ごとに苦情件数をみると、工場・事業場騒音が最も多く、建設作業騒音、営業騒音、家庭生活騒音がそれに次いでいます。
騒音苦情の件数は、ここ10年くらいは減少傾向にあり、平成11年度は12,452件でした。発生源別にみると、苦情の総数の4割近くを占める工場・事業場騒音に係る苦情件数が減少しているのに対して、建設作業騒音に係る苦情が増加しています。また、近年では、拡声機、カラオケ、ピアノ、ペットの鳴き声、自動車の空ぶかし等の都市生活等による騒音も大きな問題となっています(図1-1-25)。
一方、振動の苦情件数は、平成6年度、平成7年度と増加傾向にありましたが、平成11年度は前年度に引き続き減少し2,084件でした。
その内訳をみると、建設作業振動に対する苦情件数が最も多く、工場・事業場振動に係るものがそれに次いでおり、苦情原因として依然大きな割合を占めています(図1-1-26)。
(イ)一般地域における環境基準の適合状況
平成11年度の一般地域における環境騒音の状況について、地方公共団体により測定された環境基準の適合状況は、地域の騒音状況をマクロに把握する地点で66.0%、騒音に係る問題を生じやすい地点等で67.9%となっています。
(ウ)工場・事業場及び建設作業による騒音・振動の現況
騒音については、騒音規制法の指定地域内にあって金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」という。)が規制の対象となりますが、指定地域内の特定工場等の総数は平成11年度末現在で205,915です。また指定地域内において行われる規制対象となる建設作業*の平成11年度実施の届出件数は60,242件です。
振動については、振動規制法の指定地域内にあって金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」という。)が規制の対象となりますが、指定地域内の特定工場等の総数は平成11年度末現在で119,693です。また指定地域内において行われる規制対象となる建設作業の平成11年度実施の届出件数は、26,645件です。
*規制対象となる建ン作業
政令で定めるくい打作業等の特定建設作業
(エ)自動車交通騒音の現状
平成11年度の自動車交通騒音の状況をみてみると、全国の測定地点3,380地点(環境基本法に基づく環境基準の類型地域指定区域内)において、単純にその測定値を平成11年4月より施行された新しい環境基準に照らしてみた場合、基準値を超過していた地点は2,115地点(62.6%)に及んでいます(図1-1-27)。なお、新しい騒音に係る環境基準では、道路に面する地域について、一定の地域ごとに騒音レベルが基準値を超過する戸数及び割合により達成率を評価(以下、「面的評価」という。)することとなっていますが、平成11年度の測定時点では、沿道の建物の立地状況の調査段階にあったため面的評価は実施していません。
また、大都市地域の幹線道路沿道において環境基準値を超過した地点の割合が高くなっています(図1-1-28)。
自動車交通騒音については、都道府県知事等が騒音規制法に基づき都道府県公安委員会に対し所要の措置を要請する際の基準となる要請限度が定められています。平成11年度に地方自治体が苦情を受け測定を実施した176地点(騒音規制法に基づく指定地域内)のうち、要請限度値を超過した地点は45地点でした。
(オ)道路交通振動の現況
道路交通振動については、都道府県知事等が振動規制法に基づき都道府県公安委員会、道路管理者に対し所要の措置を要請する際の基準となる要請限度が定められています。平成11年度に苦情を受け測定を実施した全国133地点(振動規制法に基づく指定地域内)のうち、要請限度値を超過した地点は1地点でした。
(カ)航空機騒音の現況
航空機のジェット化の進展等は交通利便の飛躍的増大をもたらした反面、空港周辺地域において航空機騒音問題を引き起こしました。特に空港周辺の市街化とあいまって、これまで、民間空港2港及び防衛施設4飛行場においては、夜間の発着禁止、損害賠償等を求める訴訟が提起されています。このような航空機騒音問題を解決するため、発生源対策、空港周辺対策等の諸対策を推進しています。
a 環境基準
航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準*」については、地域類型の当てはめに従い、WECPNL*の値を専ら住居の用に供される地域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域については75以下になるようにすることとされています。
*航空機騒音に係る環境基準
昭和48年環境庁告示第154号
*WECPNL
加重等価平均感覚騒音レベル
b 環境基準等の達成状況
航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、環境基準制定当時に比べて騒音の状況は全般的に改善の傾向にあるもののここ数年は横ばいとなっており、平成10年度において約69%でした(図1-1-29)。なお、地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととなっており、平成10年度末現在で、33都道府県、63飛行場周辺において行われています。
また、コミューター空港、ヘリポート等については、環境基準が適用されない小規模なものが多く、平成2年9月に制定したこれらの騒音問題の発生の未然防止を図るため必要な環境保全上の指針を踏まえて、諸施策を実施しています。
(キ)新幹線鉄道騒音・振動の現況
a 環境基準
「新幹線鉄道騒音に係る環境基準*」では、都道府県知事が行う地域の類型当てはめに従い、主として住居の用に供される地域は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシベル以下とし、これが達成され、又は維持されるよう努めるものとしています。地域の類型当てはめは、新幹線鉄道が運行されている22都府県において行われています。
なお、振動については、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」(昭和51年3月)において、振動対策指針値を70デシベルとして、環境庁長官より運輸大臣に対して勧告しています。
*新幹線鉄道騒音に係る環境基準
昭和50年環境庁告示第46号
b 環境基準等の達成状況
騒音については、東海道・山陽・東北及び上越新幹線について、それぞれ環境基準の達成目標期間の最終年の経過後において、その達成状況ははかばかしくなかったことから、東海道・山陽新幹線にあっては住宅密集地域が連続する地域、東北・上越新幹線にあっては住宅集合地域を対象として、当面の対策として75デシベル以下となるよう対策を講じてきました(いわゆる「第1次75ホン対策」)。平成6年度の環境庁による調査の結果、この当面の目標についてはおおむね達成されたため、「第2次75ホン対策」では東海道・山陽新幹線沿線の住宅集合地域及び東北・上越新幹線沿線の住宅集合地域に準じる地域に対象を拡大しました。平成9年度の環境庁による調査の結果、この目標についても、全ての地点で達成されており、平成14年度末を目途に、東海道・山陽新幹線沿線の住宅集合地域に準ずる地域及び東北・上越新幹線沿線の住宅立地地域(住宅が点在する地域を除く。)に対象を拡大した「第3次75デシベル対策」が講じられています。
また、北陸新幹線高崎・長野間については、平成9年度の環境庁による調査の結果、測定地点の46%で環境基準が達成されており、引き続き環境基準の達成に向けた対策を講じています。
振動については、環境庁長官の勧告に基づく振動対策指針値はおおむね達成されており、また、指針値を超過した地点については、関係機関に対し振動対策を一層推進するよう要請しています。
イ 悪臭
悪臭は、人に不快感を与えるにおいの原因となる悪臭原因物質が大気中に放出されることで発生します。悪臭は騒音・振動と同様に感覚公害と呼ばれる、生活に密着した問題です。現在、主に悪臭防止法*により規制が行われています。
悪臭苦情の件数は昭和47年をピークにおおむね減少傾向にありましたが、ここ数年は増加傾向にあります。特に平成10年度はピーク時に匹敵する2万件を超える苦情件数となっており、平成11年度は18,732件と、前年度に比べて1,360件(6.8%)減少した(図1-1-30)ものの、依然として相当に多い状況にあります。発生源別では、畜産農業や飼料・肥料製造工場、化学工場など、かつて問題となっていた業種に係る苦情は減少していますが、「サービス業・その他」に係る苦情の割合が増加する傾向にあります。
*悪臭防止法
昭和46年法律第91号。工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他の悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し国民の健康の保護に資することを目的としている。
(10)その他の大気に係る生活環境の現状
「ヒートアイランド現象」「光害」等が各地で問題となっています。国民が日々の生活においてさわやかで澄んだ空気等、より良い大気環境を享受するため、これらの問題への対策が重要となっています。
ア ヒートアイランド現象
都市部の気温が高くなるヒートアイランド現象*が大都市を中心に起こっています。建築物などが日中蓄えた熱を放出する夕方から夜間にかけてこの現象が顕著に現れます。特に夏季は、冷房による排熱が気温を上昇させ、それによりさらに冷房のためのエネルギー消費が増大するという悪循環を生み出しています。良好な大気生活環境を確保するためヒートアイランド対策が必要となっています。
*ヒートアイランド現象
都市では高密度のエネルギーが消費され、また、地面の大部分がコンクリートやアスファルト等で覆われているため水分の蒸発による気温の低下が妨げられ、郊外部に比べ気温が高くなっている。この現象は、等温線を描くと都心部を中心とした「島」のように見えるため、ヒートアイランド現象と呼ばれている。
イ 光害*(ひかりがい)
過度の夜間照明の使用は、天体観測等の人間の諸活動やほうれん草・水稲等の作物の生育不良、ホタル、ウミガメ、鳥類等の生育に影響を及ぼします。また、夜間の屋外照明は安全確保や防犯のために不可欠ですが、不適切な照明は、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があるのみならず、エネルギーの浪費にもなることから、適切な対応を図ることが必要となっています。
*光害
光害とは、良好な照明環境の形成が、漏れ光(照明器具から照射される光のうち、その目的とする照明対象範囲外に照射される光)によって阻害されている状況又はそれによる悪影響をいう。