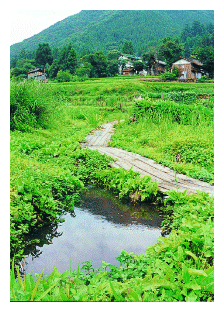
1 身近な地域における環境保全から国際協力まで
個人、企業、NGO、行政などの様々な主体が、環境コミュニケーションにより、相互理解を深め、信頼関係を築き始めています。やがて、情報交換のネットワークが生まれ、複数の主体が環境保全のための共通の目標に向かって協力し合うパートナーシップへと発展していきます。多様な主体によるパートナーシップは価値観や問題意識を融合させ、それぞれの持つ能力や資源を有効に組み合わせることで、問題解決のための大きな原動力となります。現在、環境保全のパートナーシップが形成される場面は、生活に密着した身近な地域における活動からアジア太平洋地域や地球環境問題を視野に入れた国際的な活動まで重層的広がりをみせています。ここでは、各段階におけるパートナーシップの事例をみていきます。
(1)身近な地域に生まれるパートナーシップ
地球環境は地域の環境が無数につながり、相互に依存、影響しあって構成されており、地域での取組は地球環境問題への対応の基礎となります。
また、日常生活そのものが環境負荷の原因となっている今日、ライフスタイルの見直しが課題となっています。私たちが自らの生活と環境との関わりについて認識を深めつつ、足元から取組を進める上で、身近な地域は環境保全への取組の絶好の場と考えられます。 ここでは、身近な地域において各主体が連携してその地域の特性を活かしながら環境保全に取り組んでいるいくつかの事例について考察します。
ア 循環型の地域社会を目指した高知エコデザイン協議会の取組
エコデザインとは、原材料の採取から生産、使用、リサイクル、最終処分という製品のライフサイクルにおけるすべての段階で環境効率を飛躍的に高めようという設計や生産技術のことをいいます。エコデザインによる技術革新は、製造工程の改善、製品の環境効率の最適化、再設計、製品機能、社会システムの一新という過程を経て持続可能社会の実現を目的としています。
高知エコデザイン協議会は、地方の循環型社会構築の具体的推進母体として、企業(中小企業)、行政(地方公共団体)、研究機関(大学)、個人(消費者)が一体となり、平成12年9月全国で初めて設立されたものです。エコデザインされた製品、システムそしてサービスが、消費者、官庁、企業などから優先的にグリーン購入されることにより、企業活動は環境保全への明確な問題意識を持ち始め、環境対策への動機を高めることにつながります。同協議会は、「環境に配慮していない商品やサービスはもはや市場競争力を持ち得ないという社会が目の前に迫ってきている」という考えの下、以下の活動を展開することとしています。
(1)エコデザインに関する全国レベルでの情報収集を行い、会員に周知する。また、高知としての動きを全国に発信する活動
(2)協議会メンバーの企業が提供する製品・サービスを環境面から評価し、環境への配慮が評価されたものについて、協議会として統一ブランドを冠し、共同でPRする活動
(3)企業におけるISO14000シリーズの取得を支援するための活動
(4)環境に配慮した企業経営を県内企業に対して普及啓発させるためのセミナー、勉強会を開催する活動
(5)製品・サービスを提供する企業側とそれを購入し使用する消費者側の代表からなる場(サロン)をつくり、環境に配慮した製品・サービスの提供のあり方について意見交換を行う活動
(6)その他、環境経営に関する各種調査活動
これまで大企業や政府が中心であったエコデザイン・グリーン購入の取組は、地域住民からの取組も加わり、双方向での相乗的な効果が期待されています。
イ 大学まちの持続可能な地域コミュニティづくり
平成8年に早稲田大学周辺連合商店会の有志が中心となって、学生の帰省による夏場の客数減少に歯止めをかけ、商店会や地域の活性化を図るため、大学構内を借りて環境をテーマとするイベントを開催しました。イベントで注目を浴びたのが空き缶回収機で、終了後も空き店舗を利用し、空き缶・ペットボトル回収機、生ゴミの堆肥化装置が置かれた「エコステーション」の開設につながりました。
エコステーションの開設は周辺住民による環境をテーマにした取組を呼び起こし、エコステーション増設など行動の拡大につれて、「大学まち」らしい活性化を目指した地域コミュニティが形成されました。商店経営者、住民、福祉団体、大学教員、行政職員、学生など地域コミュニティの各主体間では情報と意見を自由にやりとりできるような場として電子コミュニティ(電子メールやインターネットといったIT技術を用いた仮想の共同空間)が活用されています。この電子コミュニティ運営の核となっているが「早稲田いのちのまちづくり実行委員会」で、リサイクル活動から環境共生の「まちづくり」へと活動を広げています。
ウ 松の川遊歩道(緑道)の会による緑豊かな道づくり
神奈川県横浜市日吉駅の側に位置する松の川緑道は、市民の遊歩道に対する熱い思いから、市、区、「松の川遊歩道(緑道)の会」、造園設計事務所その他住民が意見を出し合っての設計による整備が行われました。
整備後は「人工的な緑や園芸品種の花を植えるのではなく自生の草花・樹木を重視し、本来の自然の姿を呼び戻すこと」「季節を感じながら快適に安全に歩けること」という考えのもと緑道の会が中心となり、ゴミ拾いや清掃、野草の苗や種の配布、勉強会など様々な活動が行われています。平成8年の緑道植物調査では、自生種を中心に66科281種が確認され、豊かな自然植生が復元されています。
市民の熱意により生み出された緑道は、市民、NGO、行政が一体となった活動が続けられ、安心して歩け、自然と親しむ道として地域の人々にとってなくてはならない存在となっています。
(2)全国的な活動を推進するパートナーシップ
地域における取組を基礎に、同じ状況をかかえ、同じような活動をしている団体間において、地域を越えた国内での情報交換、取組が行われています。
里地ネットワークによる里地保全活動への支援
里地ネットワーク 提供
「里地」とは、雑木林などの二次的自然が多く存在し、農林水産業活動などの自然に対する人間の様々な働きかけを通じて環境が形成されてきた地域、「ふるさとの原型」としてとらえられています。しかし、現在の「里地」では、地域コミュニティの崩壊、農林地の放棄など様々な課題を抱えている一方、大都市では、人口の集中に伴う環境の悪化、社会不安の高まりの中で、自然とのふれあいや心の安らぎが切実に求められています。
平成10年に設立された里地ネットワークは、こうした里地と都市の双方の実状に合わせて、相互に助け合いながら、行政、企業、NGO、大学・研究機関等のパートナーシップにより、里地の持続的発展を図る取組(里地共生事業)の実施を支援するNGOです。里地共生事業に関する情報の収集・提供、ガイドラインづくり、モデル地域における調査研究等により、各地の取組を支援するとともに、広く社会への啓発を行い、里地の自立、ひいては持続可能な社会経済づくりに寄与しようとするものです。
日本各地で里地の保全活動が増えていますが、新たに活動を進めるには地域の実状に合わせたパートナーシップの構築、自立に向けた粘り強い取組への知見が必要となります。技術的助言役として、情報収集発信の場として、里地ネットワークのような地域を越えた支援組織の役割は重要です。
(3)国際的な活動を支えるパートナーシップ
国境を越えて視野を広げて考えていくと、時間や場所の違いを越えて同じような環境問題に悩む地域が世界各地に存在し、様々な環境保全についての対応がなされています。
いくつかのNGOにおいては、同じ地球環境を共有しているものとして連携を図り、地球全体の利益につながる独自の活動が行われています。
ア 地球環境戦略研究機関が展開する持続可能な社会経済システムの研究
財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)は、アジア太平洋地域における持続可能な開発の実現に焦点を当て、新しい政策手法の確立や環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的な研究を行い、その研究成果を実際の政策や行動に具体化させていくことを目的として平成10年に発足し、研究活動や人材開発、情報提供等を実施しています。
平成13年度からは第2期研究プロジェクトとして、7つの研究プロジェクト(「気候政策プロジェクト」、「革新的な都市環境管理プロジェクト」、「アジア太平洋地域の森林保全プロジェクト」、「環境教育プロジェクト」、「長期展望・政策統合研究プロジェクト」、「情報技術革命と環境プロジェクト」、「企業と環境プロジェクト」)が開始されるほか、「アジアの淡水資源管理」「開発途上国における環境産業の育成と先進国・国際機関の支援」についても検討が開始される予定となっています。
特に「企業と環境プロジェクト」については、持続可能な社会経済システムの構築に向けた環境管理システム、環境会計など、事業者の自主的な環境保全活動を分析・評価し、促進のための提言を行うもので、兵庫県に新たに「関西研究センター」を設置して、関西の企業・団体、大学・研究機関、行政とのパートナーシップによる戦略研究を展開することとしています。
イ オイスカによる植林プロジェクトの推進
オイスカは、「物質と精神が調和した繁栄を築く」という基本理念を具体的な活動によって推進していくことを目的として、昭和44年に発足した財団法人です。「持続可能な発展」のため、アジア太平洋の途上国を中心に、住民自らの手による地域開発(特に農業分野での人材育成)、植林を中心とした環境保全活動を推進しています。
熱帯林を中心に進行する森林破壊は、重要な地球環境問題の一つとなっており、地球の温暖化や砂漠化、野生生物種の減少といった問題を引き起こす原因ともなっています。オイスカは開発協力の現場から学んだ体験を踏まえ、昭和55年、アジア太平洋地域の青年たちが自発的に取り組む活動として「ラブグリーンキャンペーン」という植林活動を開始しました。日本国内では「苗木一本の国際協力」を呼びかけ啓発活動を実践、多くの植林ボランティアを派遣して現地の青年とともに汗を流しています。
また、現地の子供たちが植林活動を通じて、木を守り育てる大切さを学び、緑を愛する心を培ってもらおうという目的で、植林活動と環境教育を組み合わせた学校単位の森づくり運動「子供の森」計画を平成3年に開始しました。子供たち自身の手でつくる小さな森は、地域住民を巻き込み、緑化の輪は確実に現地の地域社会へ波及していっています。
これらの植林活動は、日本から技術者、ボランティア、企業の参画、現地から政府、自治体、地域住民など幅広いパートナーシップの下に推進されています。
ウ 世界資源研究所による地球森林観測プロジェクトの推進
地球森林観測プロジェクトは、世界の森林に関する正確な情報を提供するために米国の世界資源研究所が中心となって推進されているもので、世界中の森林データを集めてGIS(地理情報ソフト)化し、インターネットによる情報提供を行っています。
世界の市民活動の積極化、IT技術の進化、ビジネス分野と環境NGOとのパートナーシップの深化などにより、現在、7か国の75グループがインターネットを通じて世界の森林を観測しています。5年以内には、21か国、世界の森林の4分の3を把握できる観測システムを目指しています。
この画像情報は、世界のNGOが森林減少防止の普及啓発活動に使い、各国政府や企業も森林の現況を把握するために利用されています。特に、欧米で有名な家具メーカーでは、木材調達に対し環境配慮を実践するとともに、自らこのプロジェクトへ資金提供することを表明しています。
今日の複雑な因果関係を有する環境問題を解決するために、個人、企業、NGO、行政など様々な主体が環境コミュニケーションを進めながら、それぞれの特徴と役割を発揮し、相互に連携するという、重層的で多様なパートナーシップの構築が今後も重要となってきます。
コラム トンボの楽園
人間活動によって失われたトンボなど身近な小動物の生息環境を復元・回復させようという活動が各地で進められています。
高知県中村市では、トンボの楽園を取り戻すため、地元住民が中心となり、ナショナルトラスト活動*そして草原化が進んだ土地をトンボが繁殖できる水辺へと再生する活動が行われました。
ボランティア活動は地元自治体、企業、市民などの協力により広がりをみせ、トンボ自然公園は現在約4ha、74種類のトンボを数えるまでになっています。
(社)トンボと自然を考える会 提供
コラム 沖縄県宮古地域におけるゼロエミッション*推進の試み
沖縄県では、平成11年度に環境保全と産業振興の両立を目指す「ゼロエミッション・アイランド沖縄」構想を策定し、この成果は平成12年度に「沖縄経済振興21世紀プラン」の中に盛り込まれました。その後、宮古地域では、ゼロエミッション推進に向けたより具体的な検討が行われ、その中間的な成果物として「美島(かぎすま)みやこ・ゼロエミッション宣言」がまとめられました。
島しょという周囲から隔てられた地理的条件、ろ過作用が少ない地層、水を通しにくい岩盤といった宮古地域特有の風土は、社会経済活動に伴う環境負荷の影響を、地下水の汚染、使用済み自動車の不法投棄といった目につきやすい形で環境問題を引き起こしがちです。
そこで、宮古地域では、産業構造やライフスタイルの転換、風、地下水、海及び水溶性天然ガスなどの地域資源の活用により、持続可能な社会経済活動と環境保全の双方が成立し、相乗効果を持つ社会をどうしたらつくれるかを、行政、事業者、民間団体、専門家、地域住民などの方々で検討しているところです。
こうした取組が、島しょ型のゼロエミッションのモデルとなり、わが国の離島やアジア・太平洋の国々にもそのノウハウが紹介されることが期待されます。
*ゼロエミッション
製造工程等から排出される廃棄物を別の産業の再生原料として利用するなどとして、全体での「廃棄物ゼロ」を目指す生産システムのこと。国連大学が提唱した概念