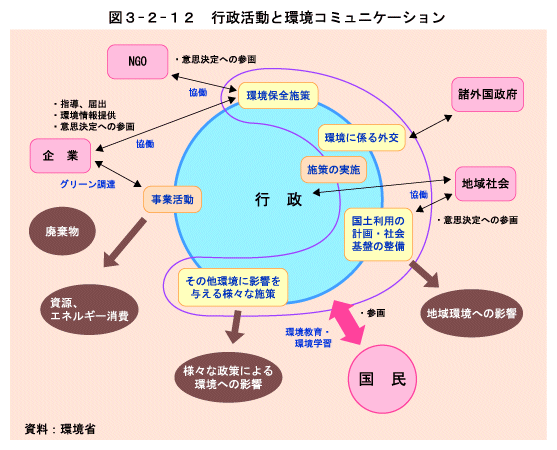
4 行政を中心として見た場合
行政は、環境保全施策の実施などを含む諸活動を通じ、環境に対して様々な影響を与えている主体であるといえます。例えば、各種政策手法の活用や社会基盤整備、国土利用に係る計画の策定などに際しての行政の意思決定は、社会制度の変更や行政活動や個人、事業者などの行動への働きかけを通じて、環境に対して様々な影響を与えています。その影響には、環境保全を推進させる面や環境負荷や環境破壊を生じさせる面があり、その大きさや範囲も様々です。また、行政自らもオフィス活動や各種の事業主体として環境負荷を生じさせています。
行政の実施する施策への環境配慮を進めていく上で、このように環境に重大な影響を与えうる活動や意思決定に当たっては、行政と個人や企業、NGOなどの他の主体との環境コミュニケーションを充実させていくことが重要です。
(1)行政の意思決定と環境コミュニケーション
行政は、図3-2-12のように、その施策や事業活動を通じて、他の主体と様々な環境情報のやりとりを行いながら相互に影響を及ぼし合っています。近年、国民の環境意識の向上などを受け、行政活動が環境に与える影響に強い関心が向けられるようになり、行政の意思決定に当たっては、環境や地域住民の生活への影響などの情報の提供や、それに対する個人、事業者などの意見聴取やその反映といった環境コミュニケーションの推進が不可欠となっています。
ここでは、行政と他の主体との間で、様々な環境コミュニケーションが展開されていることを具体的な取組事例を通してみてみましょう。
ア 環境保全施策を行う上での環境コミュニケーション
環境に直接関わる施策の実施に当たっては、様々な環境コミュニケーションが行われています。国家レベルのものとしては、地球環境問題などについて国際機関や条約などの枠組みを通じて行われる国家間の交渉も、環境コミュニケーションによる国家同士の協働の形態の一つといえるでしょう。
(ア)個人、企業、NGOとの環境コミュニケーション
行政と個人や企業、NGOとの環境コミュニケーションも進展しつつあります。例えば、国の環境基本計画を策定する際にパブリックコメントや地方ブロック別ヒアリングを通じて各主体の意見が取り入れられ、また、特に地方公共団体における環境保全施策の実施に当たっては、積極的に他の主体がその策定の過程に参画する例がみられます。
例えば、環境省では、環境大臣によるタウンミーティングや、経済界、NGOとの懇談会を開催し、他の主体とのコミュニケーションを進めています。
地方公共団体における取組としては、静岡市では静岡市環境基本計画の策定に当たり、市内で活動をしてきた市民団体が「静岡市環境基本計画市民会議」を組織して議論を重ねた上で市民提案を取りまとめるなど、市民の意見を反映させ、行政と市民の協力による基本計画の策定が行われています。
また、神奈川県では、県と消費者、事業者団体等30団体で構成する「神奈川県環境にやさしいくらし県民運動推進会議」が共同して「かながわ環境にやさしいくらし実践マニュアル」を作成し、それに基づく実践事例やデータを収集、分析し、さらに市民にフィードバックすることにより環境情報の提供を行っています。
さらに、長野市では、市民、事業者、行政の三者で構成される「ながの環境パートナーシップ会議」において、同市の環境基本計画の実現に向けた具体的取組、三者の役割分担、手順などを明らかにした「アクションプラン」を共同作業により取りまとめることとしています。
このように、環境コミュニケーションやそれを通じた市民との対話や協働は、市民参加による環境保全施策を実施していく上で欠かせない手段になっているといえます。
(イ)環境教育・環境学習を通じたコミュニケーションの推進
国の環境教育・環境学習施策に加え、市民に対する環境問題の啓発や人材育成を通じて、環境コミュニケーションの活性化を進める地方公共団体もみられます。
例えば、東京都板橋区では、環境問題について自然に取り組んでいくための場として「区立エコポリスセンター」を開設しています。センターでは、様々な環境に関するイベント、講座のほか、インターネットを活用した情報や施設の提供、講師の派遣などによる区民グループの活動支援を行っており、環境情報、学習、体験の拠点として広く活用されています。
また、環境問題を総合的に扱う初の4年制大学として平成13年に鳥取市に開学した鳥取環境大学は、鳥取県と鳥取市が校舎などの施設を整備し、大学と併せて設立された学校法人が運営を行う公設民営方式を取っています。同大学は、学際的な環境問題に対して学問的見地からの考察を行うことを特色とし、地域住民や高校生向けの公開講座も重視しており、地方公共団体における環境教育の拠点施設の新たな形としても注目されます。
イ 様々な分野の行政における環境コミュニケーション
様々な分野の行政も、規制や税制、補助金等様々な施策の実施により、環境に対して直接、間接の影響を与えています。環境への影響を最小限にしようとすれば、これらの行政のあらゆる活動において環境保全の観点からの配慮が必要となります。そうした環境配慮を行っていく上で、行政と他の主体との環境コミュニケーションは重要な手段として活用されることが期待されます。
例えば、諸外国では環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業について、あらかじめ環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき適正な環境配慮を行う環境影響評価制度を有し、その手続の中で、地域住民や専門家など公衆から意見を聞くことが行われており、この様な取組も国と他の主体との環境コミュニケーションの一例だといえます。また、欧米等において、政策(Policy)、計画(Plan)、プログラム(Program)の段階から環境アセスメントを行う中で、公衆からの意見聴取を手続に組み入れている制度や事例もあります。
国内では、環境影響評価法等に基づく環境影響評価が実施されるとともに、近年、上位計画段階等における環境配慮に取り組んでいる事例がみられます。例えば、東京都では、都が策定する広域開発計画や個別計画を対象に総合環境アセスメント制度を試行的に導入しています。この制度では、都民を対象とした説明会の開催や審査会への都民の参加を規定しているほか、社会面、経済面から見て採択可能な複数の計画案の作成を義務付け、これらの比較・評価結果を公表することとしています。
また、横浜市では、市民と行政が協力して地域の課題を解決する「パートナーシップ推進事業」を推進しています。道路づくりや交通マナーづくりなどの身近な地域のまちづくり事業において、構想段階から住民の意見を聞き、住民参加による複数案の検討や環境調査などを経て、施策に反映させる取組が行われています。
ウ 事業活動主体としての環境コミュニケーション
行政が環境に与える影響としては、施策の実施によるものだけでなく、個人や事業者と同じようにオフィス活動や各種の公共サービスの提供といった通常の事業活動によるエネルギー消費や廃棄物の排出などによる影響があります。近年、国や地方公共団体の機関においてこのような環境負荷の低減や環境保全活動を推進するために、ISO14001の認証の取得数が増加しています(図3-2-13)。平成9年度には、3団体、機関に過ぎなかった認証取得件数は、平成12年度には185団体、機関に達しています。このような認証取得団体等では、環境報告書やレポートなど、その取組状況を地域住民に発信する取組が積極的に行われており、東京都水道局や横須賀市などのように、独自に環境会計を実施し、公表しているところもあります。
また、行政におけるグリーン購入の取組も進んでいます。平成12年5月に制定されたグリーン購入法に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針が策定され、国等の各機関は平成13年度から重点的に調達すべき環境物品等の調達の目標を定めてグリーン購入の推進を図ることとなっています。さらに、各機関における調達実績についても、毎年取りまとめて公表されるほか、環境物品に関する情報提供を広く国民、事業者に向けて行うことにより、さらにグリーン購入の普及を図ることとしています。一方、地方公共団体においても、三重県をはじめ、国に先駆けてグリーン購入の実施に取り組んでいる団体が多く見られます。
(2)情報の発信と評価が重要となる
このように、行政の諸活動において環境配慮を織り込むための取組がなされていますが、その一環として、情報公開の推進などによる国民や地域住民などとの環境コミュニケー ションが取り入れられている例が多くみられます。
情報公開法*が施行され、地方公共団体においても、すでに情報公開条例の制定によりインターネットなどの媒体を活用した情報公開が進められるなど、行政情報を公開していく傾向は今後さらに進んでいくものと思われます。一方、パブリックコメント制度を通じ、個人や事業者、NGOが自らの意見を直接行政に発信することも可能となり、このような枠組みの整備により、行政と他の主体との環境コミュニケーションを反映した行政が進められるようになっています。
しかしながら、環境コミュニケーションの一層の充実のためには、単に情報発信や意見の反映を行うだけでなく、発信した情報や実施した施策の効果の把握やその評価が重要です。
例えば、仙台市では、環境負荷低減を図るための率先行動計画の実績について、環境報告書を作成して情報発信を行っていますが、同計画の評価に当たって、全国で初めて外部の専門家による外部環境監査を導入しています。報告書には、監査の結果や指摘事項等についても記載され、地域住民との環境コミュニケーションを意識したものとなっています。
国においても、第1章でも述べたとおり、環境基本計画に基づく施策の進捗状況について、関係府省が行う点検をもとに中央環境審議会が国民各界各層の意見を聞きながら点検することとなっています。その結果は政府に報告されると同時に、環境白書などにも反映されることにより、広く開示されることになります。
また、平成11年4月に定められた「中央省庁等改革の推進に関する方針」(中央省庁等改革推進本部決定)では、各府省において、それぞれの講じる施策について自ら政策評価を行うことを定めており、環境保全施策や環境に関連する施策を含む各種施策について、その費用や効果について評価が行われ、公表されることとなります。
このように、環境保全に関する自主的な取組を引き出す自己評価や第三者評価などの仕組みや評価方法の確立が、行政と個人、事業者、NGOとの環境コミュニケーションの進展の上でも、大きな課題だといえるでしょう。
*情報公開法
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」平成11年法律第42号
コラム 環境大臣タウンミーティング
環境省では、平成13年1月の東京での開催を皮切りに「川口環境大臣と語るタウンミーティング」を全国各地で開催しています。
これは、開かれた環境省として国民各層とのコミュニケーションをさらに図るべく、アメリカ合衆国で一般的となっている公開討論会をモデルとして初めて実施されたものです。ミーティングでは、川口環境大臣が、来場した国民に対して環境省が目指す21世紀の環境行政の理念、施策についてプレゼンテーションを行った後、来場者と川口環境大臣との意見交換が行われました。仙台で行われたタウンミーティングでは、「新たな環境省に期待するもの」をテーマに経済界、NGOとの懇談会が併せて開催されました。出席者からは環境省に対する質問、要望、意見が相次ぎましたが、このような取組も行政と国民との環境コミュニケーションのあり方の一つであるといえるでしょう。