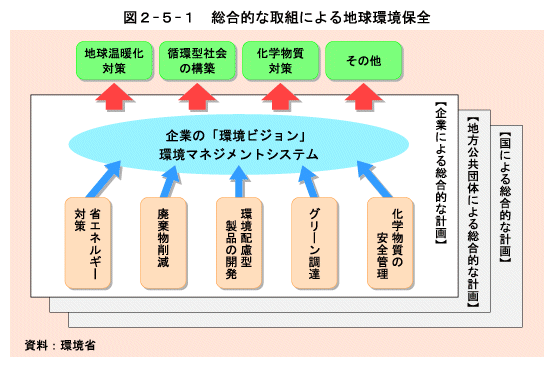
1 環境保全に向けた総合的な取組の動向
持続可能な社会経済活動への変革には、総合的な取組の推進による環境保全の相乗効果が期待されます。本節では、地域環境基本計画や個別企業における環境ビジョンの策定などのように各地、各方面で進められている特色ある取組事例を紹介し、その意義を明らかにします。また、こうした取組を加速する方策として、自動車税のグリーン化や環境保全を目的とする地方税の検討など国内の動きを紹介するとともに、諸外国の動向に触れながら、経済的手法の活用やポリシーミックスなどの必要性を訴えます。
(1)国の取組
ア 社会経済に関する意思決定に環境配慮を組み込む
持続可能な社会を実現するためには、社会経済活動が営まれる各段階、各局面に環境配慮を織り込み、社会の仕組みそのものを転換させる必要があります。環境基本計画は、持続可能な社会を実現するには、各府省ごとの取組のみならず、政府全体での総合的な取組が必要という考え方に基づいて策定されています。あらゆる政策の実施において、国民や事業者などの社会経済活動の前提となっている社会経済システムを十分な環境配慮が行われるようなものに変革していく必要があります。このため、可能な限り、それらのあり方を決定する際の意思決定過程に自律的に環境配慮を織り込む仕組みをつくらなければなりません。
このための有効な手段として、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある各種事業の実施に当たって事前に環境への影響を評価し、環境担当部局や人々の意見を聴きつつ、環境影響を事業計画に反映させる環境影響評価制度があります。わが国においても、環境影響評価法によって環境の保全について適切な配慮をするための仕組みが整備されています。
また、環境基本法第19条にあるとおり、個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策についても環境の保全に配慮することが必要です。
上位計画や政策における環境配慮のあり方について、現状での課題を整理した上で、内容、手法などの具体的な検討を行うとともに、国や地方公共団体における取り組みの実例を重ね、その有効性、実効性の検証を行い、それを踏まえて、環境配慮のあり方に関するガイドラインの作成を図る必要があります。
この様な検討や取組の現状を見つつ、必要に応じて制度化の検討が進められるべきです。上位計画や政策に対する環境配慮として、内容や制度に差異はありますが、諸外国で「戦略的環境アセスメント」と呼ばれる仕組みやわが国の一部地方公共団体において上位計画等における環境配慮の取組が開始されており、これらも参考にして検討を行うことが必要です。
イ 各府省の活動に環境配慮を織り込む
各府省では、環境基本計画に基づき様々な行政活動に環境配慮を織り込む取組が行われています。この取組を総合的なものとするために、府省ごとに環境基本計画の策定が進められています。例えば、旧建設省においては、1994年に「環境政策大綱」が策定され、「ゆとりとうるおいのある美しい環境の創造と継承」、「健全で恵み豊かな環境の保全」、「地球環境問題への貢献と国際協力の推進」という理念の下に、環境影響評価等の充実、環境リーディング事業の推進などの方策が明記されています。
また、旧郵政省では1997年に「郵政省環境基本計画」が策定され、「郵政行政自らが率先して環境保全に関する行動を実行し、環境負荷の少ない社会の実現を目指す」、「環境への負荷の削減に資する情報通信の高度化に努める」、「環境観測等のための情報技術の開発及び国際協力を積極的に推進する」という基本方針が示されました。この中で郵政省は、「すべての年賀葉書に再生紙を使用」したり、「環境観測等のための情報通信技術の開発及び国際協力の推進」として地球環境分野におけるマルチメディア・バーチャル・ラボ(仮想研究所)の構築を行うなど、具体的な施策を示しています。
このように、各府省の独自性を活かし事務事業の環境配慮が推進されることは、担当行政の対象となるすべての主体への環境配慮の連鎖を生み出すことにつながり、持続可能な社会の実現にとって重要な意味を持っているのです。
(2)地方公共団体の取組
地方公共団体においては、住民の生活環境に対する高い関心を背景に、環境政策の基本方針を定める条例の制定や環境に関する総合的な計画の策定、組織体制の整備などのように、環境保全を地域の優先度の高い課題として位置付ける動きが高まっています。また、地方分権推進一括法の成立に伴い地方公共団体への権限委譲が進むことで、地域の政策主体としての地方公共団体の機能が強化されています。このような動きが一層加速され、あらゆる行政分野への環境配慮の積極的な織り込みが図られることを通じて、地域における環境保全への取組がさらに総合化されていくことが期待されています。
各地域での総合的な取組を促進するため、各地方公共団体では環境基本条例*や地域環境総合計画*などが策定されています。さらに、1991年国際環境自治体協議会(ICLEI)が考案し地球サミットの「アジェンダ21」において提唱された、「ローカルアジェンダ21*」の策定がわが国の地方公共団体においても進められています。
こうした地域の環境政策に関する総合的な計画策定の成果は、各施策や事業の推進効果として現れるだけでなく、計画の策定過程においても多く見い出せます。つまり、まちづくりと一体になった具体的な課題を検討することで長期的な視点から見た地域ならではのあるべき姿を描き、さらにその策定過程で地域住民や様々な民間団体の参画を実現させることで、地域の独自性を高め、地域行政への住民参画の土台を整備し、持続可能な地域社会像を明確に打ち出すことが可能になります。
こうした計画の策定過程に着目すると、地域の創意工夫によって様々な取組が行われていることが分かります。例えば、飯田市では、平成8年の地域環境総合計画「21'いいだ環境プラン」策定に当たり、小学生から大人までの市民で構成される「環境調査員(環境チェッカー)」が身近な自然や景観の調査、指標生物による環境調査を実施しました。この調査によって、残したいとされた同市内の自然や景観は計438件あり、この結果は同市の計画策定の基礎資料として活用されました。表2-5-2は当時設定された主な数値目標ですが、この目標に対する進捗状況について、同市では毎年「環境レポート」を発行し、一年間の取組や実績を公表しています。
このほか、具体的な施策や事業に関しても、多くの地方公共団体で地域の特性を生かしたユニークな取組がみられています。
*環境基本条例
環境基本法の理念に沿い、地方公共団体の環境保全施策に関する最も基本的な事項を定めた条例のこと
*地域環境総合計画
地方公共団体の環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めた計画のこと
*ローカルアジェンダ21
ICLEIの定義では、「地域の持続可能な開発の優先課題に対応する長期戦略的行動計画の準備と実施を通じて、アジェンダ21の目標を地域レベルで達成するための市民参加型のマルチセクタープロセス」→講じた施策第5章第1節参照
(3)企業の取組
経済のグローバル化、情報化などの影響によって産業全体が大きな構造変化を遂げたことで、企業の環境保全への取組にも様々な変化が生じています。例えば、海外への直接投資の増加によって企業の環境管理の対象範囲は拡大しています。多国籍化した企業では、国内と同様に海外拠点における環境管理に取り組んでいます。いくつかの先進企業では、各国の環境基準のばらつきに係らず、全世界で一律の自主的な環境基準や目標を設定したり、全世界における拠点の環境管理情報の管理や監査制度など、グローバル化に対応した環境保全活動を積極的に展開しています。
企業の環境保全への取組の形は、過去の公害規制への対応から大きく変化しました。取組の動機を見ても、法規制の遵守にとどまらず、社会的な責任を意識して能動的に取り組んでいる例も多く、自主的な環境保全活動が様々な成果をあげています。
こうした自主的取組においては、各環境分野と企業との関わりを広くとらえ、総合的に環境負荷を低減させることが可能になります。その有効な手段として、多くの企業が環境マネジメントシステムを活用しています。環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001を認証取得した件数は、平成13年2月末には5,585件以上にも上っており、その業種も多種多様となっています。環境マネジメントシステムの中では、その企業にとって重要な環境問題を企業自らが位置付け、到達目標も自らの判断で設定されることになります。これによって企業独自の創意工夫と企業がもつ技術、人材、資金などの資源の有効活用が実現することになります。
また、事業活動によって生み出された商品やサービスのライフサイクルにおいて環境負荷を低減させるため、LCAという手法の活用が進められています。いくつかの先進的企業においては、個別製品の材料比較、設計における解体容易性の検討、流通・販売形態の検討まで、精緻な分析を行い、最適な方策を選ぶという取組がすでに始まっています。また、企業が管理できるライフサイクルの範囲は、従来の固定的な観念から大きく変化し、さらに源流へと、また社会全体における影響の検討へと拡大しています。
企業は業種毎に様々な環境問題と関わっています。従来は主に製造業を中心として取組が進んでいましたが、今日では非製造業においても先進的な業界がみられます。例えば、流通業界では、環境マネジメントシステムの下に、環境配慮型商品の取扱い、廃棄物の削減、省エネルギー、物流の効率化や低公害車導入、企業内外での環境コミュニケーションなど、多くの分野について総合的な取組が進められています。こうして様々な業種の環境対策が進むことで、各業種の特色を生かした環境マネジメント手法の開発や環境負荷の低減に向けた異業種間の連携などが巻き起こり、産業全体における環境配慮の組み込みへとつながることが期待されます。
コラム 国内電機メーカーの策定した環境ビジョン
この企業では、環境経営を推進するための個別の環境分野に関する行動計画だけでなく、上位概念である将来の持続可能な社会に貢献するための方向性としてビジョンを描いています。
その下に、コミットメントを明確にしており、メーカーとして製品ライフサイクルにわたって、新たなビジネス企画や研究開発、情報開示やリスクマネジメント等における環境への取組を示し、その原動力となる3つの課題を挙げています。
こうした企業の将来像を描いた上で、具体的な行動計画を策定し、総合指標として同社の定める基準での環境効率を10年間で2倍に高める目標を設定しています。
コラム 国内電機メーカーの総合的な環境情報管理システム
この企業では、設計・開発及び生産段階で使用する社内の基盤情報システムに、各素材・部品の有害化学物質情報や各素材や工程の温室効果ガス排出量などのLCA情報を統合しています。この情報システムは、環境関連の法規制遵守、化学物質のリスク管理(新規化学物質・設備導入時の事前評価、未評価化学物質の購入規制、安全・衛生・防災対策)のほか、製品開発における総合的な環境配慮に活用されています。
環境に係るデータや情報が急増している現在、社内での環境情報管理の仕組みづくりが企業の重要課題となっています。こうした情報管理システムのノウハウを新たなビジネスチャンスにつなげる企業も見られます。