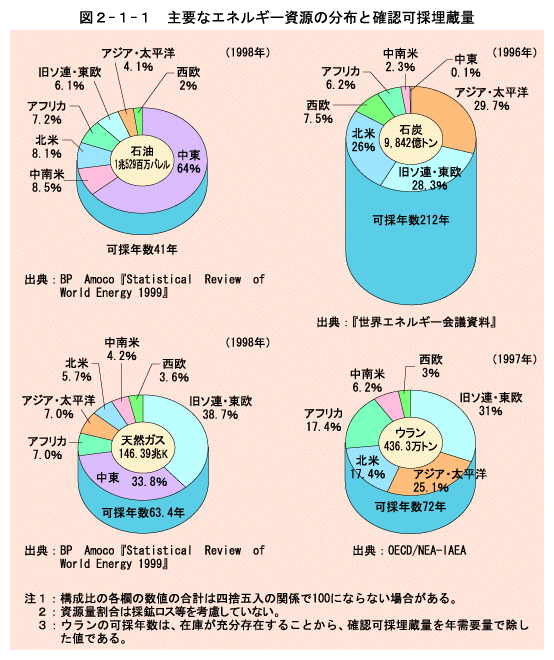
1 地球の環境容量と物質循環上の問題
(1)環境問題の深刻化と環境容量
世界は、人口と経済の両面において増大を続けています。1950年には25億人程度だった世界の人口は、1996年には56億人まで増加しました。また経済規模をみても、世界のGDPの総計は同じ期間で5.5倍に拡大しました。このような先進国を中心とした富の増大は、産業革命以降の大量生産システムに支えられたものといっても過言ではありません。
こうして、人類社会があまりに急激に拡大したことにより、地球の有限性が問題となりつつあります。
第一の問題は、森林の再生や植物枯死体からの化石燃料の生成といった資源の再生能力や資源そのものの有限性です。経済成長のためにこれまで大量のエネルギーが消費され、現在の消費量のペースでは石油があと40年、天然ガスでもあと60年程度で底をつくと考えられます(図2-1-1)。
第二の問題は、微生物による有機物の分解や植物の窒素固定などによる、環境の汚染浄化能力の有限性です。大量生産・大量消費は、資源の浪費とともに、大量の汚染物質を環境中に排出してきました。環境問題はますます深刻化し、現在及び将来の健全な人間社会の存続を脅かす程になっています。
1990年のジャカルタでは、自動車排気ガスを原因とする大気汚染が、汚染が全くない状態と比較して4000人を超える過剰死亡*を引き起こしているほか、多くの市民の呼吸器疾患の原因になったと考えられています。また1945年から1990年までの間に、植生の破壊や過剰な開発、非持続的な農耕などにより引き起こされた土壌劣化が、世界の食料生産高を17%減少させたという試算もあります。
地球温暖化の影響に関する将来予測も深刻です。IPCC*によると、このまま温暖化が進むと、海水の膨張などにより21世紀末には海面が9センチから88センチ上昇すると予想されています。仮に2080年代までに海面が40センチ上昇するとすれば、高潮によって浸水を受ける人口が、全世界で7千5百万人から2億人程度増大すると推計されています。また、海面上昇と熱帯低気圧の強大化によって、アジアの温帯・熱帯の沿岸低地にすむ人々のうち数千万人の人々が移住を強いられると予測されています。マラリアなどの感染症も増大し、より影響を受けやすい途上国と、比較的影響を受けにくい先進国との間の格差がいっそう広がると考えられています。大気中の二酸化炭素濃度が、2050年に産業革命以前の2倍に達すると仮定した時の被害総額は全世界で年間3000億ドルに上ると試算されています(表2-1-1)。
地球は、資源の再生産能力、環境の汚染浄化能力の二つの点で有限です。資源エネルギーや環境の問題が人類社会を脅かしつつあるのは、人間活動がこの二つの限界を超えてしまったためと考えられます。
では、資源と環境の観点から見たとき、地球はどれだけの人間の生活を支えることができるのでしょうか。
WWF*では、ブリティッシュ・コロンビア大学で開発されたエコロジカルフットプリント*を用いて、世界の環境容量(地球が持続可能であるための環境負荷の最大値)を計算しました(表2-1-2)。これによると、地球の一人当たりの面積は2.18ヘクタールであったのに対し、1996年のエコロジカルフットプリントは一人あたり2.85ヘクタールでした。このように世界全体の社会活動は、すでに地球の環境容量を超えてしまっています。わが国について見ると、わが国の国土が一人に対して供給可能な面積は0.86ヘクタールだったのに対し、実際には海外を含めた5.94ヘクタールの環境を踏みつけているとされています。世界全体のエコロジカルフットプリントの経年変化を独自に発表しているWWFの「生きている地球レポート」によれば、既に1970年代に社会経済活動は地球の環境容量を超えてしまっているといえます(図2-1-2)。そして世界中の人々が日本人並みに環境に負荷を与え続けるとすれば、地球がもう1.7個必要ということになります。
国連の世界人口推計(中位推計)では、2050年の世界人口は、アジア・アフリカ地域での急増により1998年の約1.5倍に増加すると予測されています(図2-1-3)。また経済規模も、アジア地域を中心とした中進国・途上国の大幅な成長が見込まれています。現在すでに、人類社会が持続的であるための地球の環境容量を超えていることを考慮すると、これまでの延長線での人類社会の拡大は不可能です。環境容量を所与のものとし、その制約の中で資源やエネルギーの効率的な利用努力を重ねながら、これまでの人類社会の発展の方向性を見直していくことが重要です。
*過剰死亡
実際に汚染に暴露されていない集団の死亡率との差から計算される追加的な死亡者数
*IPCC
気候変動に関する政府間パネル。地球温暖化問題について議論を行う公式の場としてUNEP(国連環境計画)とWMO(世界気象機関)の共催により1988年11月に設置され、千人にのぼる各国の科学者・専門家の検討により科学的、技術的知見を提供している。
*WWF
世界自然保護基金。
1961年に設立された世界最大の自然保護団体で、本部WWFインターナショナルはスイスのグランにある。世界26か国に各国委員会、6か国に提携団体があり、約470万人、約1万社・団体の支援を受け、自然保護活動を行っている。
*エコロジカルフットプリント
食料や木材の供給、森林による二酸化炭素の吸収など、一人の人間が持続的な生活を営むために必要な地球上の面積
(2)物質循環でとらえた環境問題
人類社会の今後の方向性を検討するに当たって、地球の有限性の問題を物質循環の観点から見てみましょう。
地球上の物質は、大気や海流の循環、地殻変動を通じて、大気・海洋・陸地を移動しています(図2-1-4)。これに生物が加わることで、時間的にも空間的にも様々な規模をもった様々な物質循環が構築されています。例えば枯死した植物体のうち、あるものは土中の微生物によって短期間のうちに分解され、またあるものは数万年かけて石油や石炭になると言われています。このように大小様々な物質循環の相互作用が、汚染浄化や資源の再生産の役割を果たし、その結果汚染や廃棄物といった負のストックを減少させ、人間にとって有用な資源などの正のストックを生み出しているのです。
人間活動は、資源やエネルギーの採取、あるいは廃棄物や排気ガスの排出を通じてこの物質循環に関係しています(図2-1-5)。では、私たちの社会経済活動の生み出すフローは、物質循環の観点からどのような問題を抱えているのでしょうか。
第一に、フローが大きすぎるため環境による浄化や資源の再生産が追いつかないという量的な問題があります。大気中の二酸化炭素濃度は、産業革命以前は280ppmv*だったと考えられています。しかし化石燃料の使用や森林の伐採で大量の二酸化炭素が大気中に放出されたことにより、1999年には367ppmvまで上昇しました(図2-1-6)。
第二には、自然では浄化できない物質の排出という質的な問題です。例えば、フロンは自然界には存在しない人工的な化学物質で、人体や生物に無毒ということから多くの産業で使用されました。しかし自然界ではほとんど分解されず、大気中に放出された場合数年かけて成層圏に達し、オゾン層を破壊してしまいます。このようにフロン以外にも、生物等による分解が不可能な化学物質が土壌や水中に大量に放出・蓄積され、問題を起こしているのです。
第三には、物質循環の切断、という問題です。かつて廃棄物は、できる限り農地へ還元するなどして、自然の物質循環に組み込んでいました。現在では社会で使用された物質の多くが、最終処分という決して循環しないフローに組みこまれています。このような循環しないフローが、自然と社会のストックの不均衡を引き起こしています。
多くの社会経済活動が、物質循環を通じて相互に関係しており、環境問題はその中で物質循環の歪みの結果として現われています。環境問題の解決には、この物質循環が円滑に継続できるようライフスタイルの転換や社会構造変革が必要です。地球規模の物質循環の適正化と社会経済における環境効率の向上を基盤とした持続可能な社会の構築に向けて、世界全体が大量生産、大量消費、大量廃棄型の生産と消費のパターンから脱却し、有限な地球との共生関係を築いていかなければなりません。
*ppmv(濃度単位)
容積比100万分の1