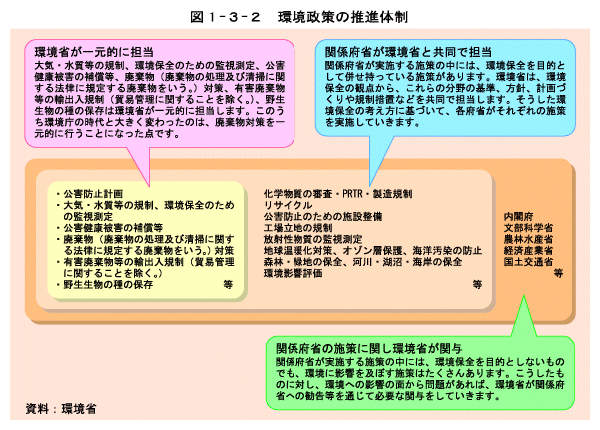
2 わが国の環境政策を推進するための新しい組織体制
(1)新しい府省による環境政策の推進体制
平成13年1月6日、わが国の中央省庁は1府12省に再編されました。これは「肥大化・硬直化し、制度疲労のおびただしい戦後型行政システムを根本的に改め、自由かつ公正な社会を形成し、そのための重要な国家機能を有効かつ適切に遂行するにふさわしい、簡素にして効率的かつ透明な政府を実現する」ことを目指した国の行政組織の大改革といえます。
国の行政は、環境保全の目的に資する施策や、行政のあり方によっては環境への大きな負荷が予想される施策、結果として何らかの環境への影響が生じる行政活動など、様々な形で、かつ広範な分野において「環境」と関わっています。このような「環境」の性質を踏まえると、環境保全を推進していくためには、もとより関係府省がそれぞれの立場で担当行政分野に環境配慮を織り込んでいくことが不可欠であり、この基本的な考え方は今後も一層重要になっていきます。それでは、今回の行政組織改革により国の環境政策の推進体制はどのように変わるのでしょうか。
ア 環境省が担当する分野
新たに独立した環境省は、「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備」に加えて良好な環境の創出を含めた「環境の保全」を図ることを任務とすることが明確になり、次のような行政分野を担当することになりました。
(ア)環境保全に関する施策の総合的展開 環境庁の時代と同様、まず環境省は政府全体の環境保全に関する政策のあり方について責任を負います。環境基本計画を策定し推進すること、環境保全経費の見積もり方針の調整などに代表されるような、環境の保全に関する施策の総合的展開を図ります。
(イ)環境省が一元的に担当する事務
大気・水質等の規制、環境保全のための監視測定、公害健康被害の補償等、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物をいう。)対策、特定有害廃棄物等の輸出入規制(貿易管理に関することを除く。)、野生動植物の種の保存は環境省が一元的に担当します。
イ 関係府省が環境省と共同で担当する分野
関係府省が実施する施策の中には、環境保全を目的として併せ持っている施策があります。環境省は、環境保全の観点から、これらの分野の基準、方針、計画づくりや規制措置などを共同で担当します。そうした環境保全の考え方に基づいて、各府省がそれぞれの施策を実施していきます。
ウ 関係府省の施策に関し環境省が関与する分野
関係府省が実施する施策の中には、環境保全を目的としていないものでも、環境に影響を及ぼす施策はたくさんあります。こうしたものに対し、環境への影響の面から問題があれば、環境省が担当府省への勧告等を通じて必要な関与をしていきます。
(2)環境保全経費からみた環境保全施策のあらまし
次に、環境省が取りまとめた環境保全経費の内訳に着目することにより、予算面から国の環境保全施策のあらましを整理してみます。
平成13年度予算における環境保全経費の総額は3兆484億円で、平成12年度当初予算額(3兆420億円)と比べ、65億円、0.2%の増額となっていますが、これを分野ごとに総額と内訳、主な関係府省を示すと表1-3-1のとおりです。
(3)環境保全施策の効果的実施に向けた課題
すでに述べたとおり、中央省庁再編後も多くの府省が、国の環境保全施策の実施に関わることになります。このため政府としては、閣議のほか関連する閣僚会議や関係府省連絡会議などの場を通じて緊密な連携を図り、次のような課題に適切に対応しながら、環境基本計画に掲げられた環境保全施策を総合的かつ計画的に実施していかなければなりません。
第一に、環境保全施策の実施に関わる各主体との連携や関係府省それぞれの推進体制の強化が重要です。
このため、国は環境保全施策の実施状況を把握し、評価し、自ら活用するほか、環境への取組を進める他の主体に対し環境白書をはじめ様々な手段を通じて情報を提供するため、環境情報の体系的な収集、蓄積や利用を進めていきます。また、第3章でも触れるとおり、環境保全への取組を進めるための地域での住民、事業者、行政などから構成される組織の活動を支援するため、全国的な情報交流を進めることがますます重要になっていきます。
このような取組の基礎として、環境情報の収集の迅速化、情報の分析能力の向上が必要です。
第二に、国の他の計画との間では、環境保全に関し、環境基本計画との調和が保たれたものであることが重要です。
このため、国の他の計画のうち、専ら環境の保全を目的とするものは、環境基本計画の基本的な方向に沿って策定、推進するとともに、その他の計画で環境保全に関する事項を定めるものについては、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図る必要があります。
第三に、環境保全施策を一層推進していくには、目指すべき目標の設定が有効です。
環境保全施策を全体として効果的に実施するため、総合的環境指標を引き続き整備するとともに、総合的環境指標の基礎となる環境に関する統計数値の充実、データベースの整備などに努める必要があります。
また、個別の施策については、環境基本計画の基本的な方向に沿って、必要に応じ具体的目標の見直しを行うとともに、必要な分野については、具体的目標を設定し、個別の計画を策定していく必要があります。
第四に、環境保全施策の進捗状況を確認する重層的な点検体制を整備することが重要です。
まず、中央環境審議会は、国民各界各層の意見も聴きながら、環境基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じ、その後の政策の方向について政府に報告する役割を担います。この点検結果については、毎年の国会に対する年次報告や、環境保全経費の見積もり方針の調整にも反映していく必要があります。
また、中央環境審議会の点検は、関係府省の自主的な点検結果を踏まえて実施することになります。このため、関係府省の点検が、施策の環境改善効果に関する分析、評価を可能な限り含めて実施できるよう、適切な点検手法の開発を図っていかなければなりません。
コラム 環境省のロゴマーク
環境省発足と同時に設定された環境省のロゴマークについて、意味するところを紹介します。
まず、上の緑の三角形は、山、自然界、地球環境を表しています。
次に、中央の水色の楕円は山を映す澄んだ水、海を表わすとともに、様々な人々が協力して人や自然すべてを包んで守っていく愛情を象徴しています。
そして、下の緑の三角形は水面に映る自然の姿で、これによって今日の環境問題の原因となっている人間の活動を示しています。また、水面の上下を一体的に表すことによって、環境問題の解決への取組を、情報を公開しながら皆さんとともに進めていくという姿勢を表しています。
このロゴマーク全体の姿で、環境の大切さを深く心に刻み、それを守るゆるぎない姿勢、環境の世紀に向けての変革への決意を込めています。