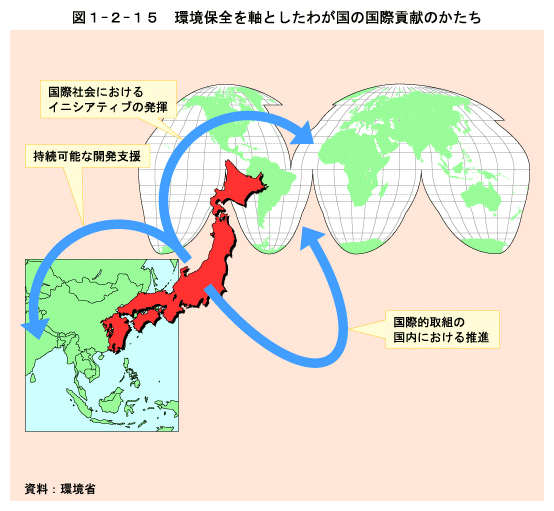
2 「環の国」日本としての国際貢献を目指して
(1)国際貢献のかたち
地球環境問題の解決のためには国際的な協力・取組と強いリーダーシップが必要です。私たちは経済活動などを通じて、地球環境問題に多大な影響を与えていると同時に、地球環境の保全なしには自らの生活環境の維持が保証されない状況にもなっています。わが国の国際的な地位や経済的影響力に照らし、持てる能力を十分発揮しながら国際貢献を行っていくことが課題となっています。ここでは、わが国が国際社会に対し、協力・貢献が期待されていることを三つの観点から考察します(図1-2-15)。
ア 国際社会におけるイニシアティブの発揮
まず、わが国自らが課題提起(アジェンダ・セッティング)を行い議論をリードしていくことが期待されています。課題提起によるイニシアティブとしては、廃棄物問題での「拡大生産者責任*」や化学物質問題での「予防原則」など課題提起とともに問題解決の方向性を示してきたEUの行動が典型例ですが、狭い国土という制約条件を有し、資源を海外に依存しているわが国が、他国に先んじて、国内で顕在化、深刻化する環境問題について問題意識や分析研究結果の発信に努めることは、大きな国際貢献につながります。
提起された課題に対し国際的世論が形成された後、問題解決に向けたルールづくりへの貢献も同様に重要です。経験と知識・技術力をもって議論をリードする役割が期待されています。
*拡大生産者責任
製品の製造者等が物理的又は財政的に製品の使用後の段階で一定の責任を果たすという考え方
イ 国際的取組の国内における推進
国際社会において定められた環境保全への取組の方向性やルールをどのように実行し、成果をあげるかについては、それぞれの国の施策にゆだねられています。国際的な足並みを揃えつつ、一歩先をゆく政策の立案や決定がどの国にも期待されているといってよいでしょう。地球温暖化防止のための経済的手法の導入や拡大生産者責任に基づくリサイクル法、化学物質対策におけるPRTR制度*など、国際的な枠組みに基づいて、各国がそれぞれの国の事情等に適した施策を実施しています。
国内においてより迅速で実効的な環境政策が実施されることは、国際的世論の形成や国際交渉におけるリーダーシップの発揮などにもつながります。
*PRTR制度
→P.66の用語解説参照
ウ 持続可能な開発支援
開発途上国への持続可能な開発支援は、今後ますます重要になります。環境保全を目的とする環境ODA*の推進だけではなく、環境以外の分野に貢献する事業による環境負荷を十分に評価することも重要です。1997年のわが国のODA総額はDAC*加盟国の中でもっとも大きく、その経済的影響や環境への影響はともに多大なものであるはずです(図1-2-16)。
また、途上国への開発支援に当たっては、持続可能な開発支援(環境ODA)を推進するとともに、事業の評価を適切に行うことに配慮する必要があります。わが国のODA事業については、外務省やJICA*(国際協力事業団)、JBIC*(国際協力銀行)により、評価とそのフォローアップが実施されています。
*ODA
(Official DevelopmGent Assistance)
政府開発援助
*DAC
(Development AssiGstance Committee)
開発援助委員会
*JICA
(Japan InternationGal Cooperation AgeGncy)
国際協力事業団
*JBIC
(Japan Bank for IntGernational CooperatGion)
国際協力銀行
(2)わが国にふさわしい国際貢献の取組
わが国が、他国にない「強み」を活かすことによって国際貢献はますます有意義なものになります(図1-2-17)。
*環境保全に関する国際的取組
→講じた施策第5章参照
ア アジア太平洋地域での連携と協働の推進
わが国と地域的・経済的に密接な関係を有し、今後の急速な人口増加と経済成長、それによる環境負荷の増大が見込まれているアジア太平洋地域と、積極的な連携・協働をしていかなければなりません。
アジア太平洋地域では、異なる発展段階が共存し、温暖化ガス排出の増大、産業公害・都市公害の顕在化、自然環境の劣化等の様々な問題が同時に顕在化してきています。このため、この地域における問題の解決は、地球環境問題の解決に向けて重要な意味を持つとともに、環境を共有する地域内各国にとっても、国家の存立に直接の影響を与える問題として、避けることのできない極めて重要な課題となりつつあります。
しかしながら、地域全体の環境に関する科学的な知見の蓄積はわずかであり、必ずしも環境問題に係る共通認識の醸成が進んでいるとはいえません。さらに、環境の悪化は、社会・経済発展と分かちがたく結びついていますが、農業、エネルギー、水などに関する幅広い社会・経済政策と、環境政策を統合する試みは立ち遅れています。
これらの問題を単に各国あるいは特定の地域や特定の環境分野に限られた問題としてとらえるだけでは、十分な対策は期待できず、環境破壊と貧困問題の悪循環を断ち切ることは困難です。したがって、地域にふさわしい持続可能な開発のあり方を明らかにしつつ、地域全体の環境保全施策を、アジア太平洋地域の各国家が存続・発展するための「環境安全保障」のための地域戦略として位置付け直し、地域全体で取り組むことが重要です。
このような認識に立ち、環境省では、「アジア太平洋地域イノベーション戦略」の推進を提唱しています。このイノベーション戦略は、地域内の諸国が共同して、1)統合的モニタリングと環境・経済統合モデルによる分析・評価に基づき、2)本地域が持続可能な発展を果たすための環境戦略を検討し、3)その成果を世界に発信するとともに、戦略の推進に取り組むものです。
具体的には、まず、地域的な衛星データネットワークを構築して、アジア太平洋地域の統合的モニタリング・評価体制の確立を目指します。次に、このモニタリングデータを活用して、環境・経済統合モデルによる環境負荷や環境資源のトレンドの分析・評価を行い、政策形成に役立つ戦略的データベースの作成を目指します。さらに、これらの分析・評価に基づき、情報技術などの新たな手法の活用や、政策の統合など、革新的な地域環境戦略オプションの検討を行います(図1-2-18)。
これらの成果は、アジア太平洋地域のイニシアティブとして全世界に向けて発信されるとともに、地域内の各国が、協働してイノベーション戦略を策定・推進していく重要な土台となることが期待されます。
イ 企業やNGOによる活動の支援
わが国の環境NGOの国際会議への参画や、NGOや地方公共団体による海外地域に根づいた支援活動がすでに実施されています。こうした多様な主体による活動は、わが国の国際的取組の厚みと広がりを増すものとして期待されます。このため、これらの活動がより円滑に展開されるよう、国による積極的な側面支援が重要といえます。
企業においても、植林や技術交流などの海外への環境貢献を継続的に実施している例は多く見られます。さらに、企業のグローバルな事業展開や輸出製品そのものを通じて、環境保全に役立つ技術やノウハウを提供・普及していくことも忘れてはなりません。これらのようなグローバルな事業展開を行っている日本企業の取組は、すでに現地法人等を通じて国際的に展開し始めています。環境省が行った「環境にやさしい企業行動調査」によれば、海外展開をしている企業(520社)のうち27%が海外事業展開に当たっての環境配慮を経営方針や環境方針等に明記しており、また36%が事業展開先に環境保全対策のための技術支援や情報提供をしています。
一方で、企業の環境保全への取組状況を公表する手段として環境報告書*が重視されつつありますが、環境報告書の記載対象範囲には、連結企業や海外法人も含むことが期待されています。企業の環境保全意識も高まっていることから、海外における環境保全の取組がより進展することが予想されます。「カイゼン」が海外で広まったのと同じように「グリーン購入*」や「環境会計*」などの考え方やシステムが、日本から発信する国際標準として貢献できる可能性も大きいといえます。そのためには、環境保全の規制やガイドライン等により、企業の取組を適時、適切に誘導する施策が求められます。
*環境報告書
企業等の事業者が、最高経営者の緒言、環境保全に関する方針・目標・行動計画、環境マネジメントに関する状況(環境マネジメントシステム・環境会計・法規制遵守・環境適合設計その他)及び環境負荷の低減に向けた取組等について取りまとめ、一般に公表するもの
*グリーン購入
市場に供給される製品・サービスの中から環境負荷が少ないものを優先的に購入すること
*環境会計
企業等が事業活動における環境保全対策のためのコストとそれにより得られた効果を可能な限り定量的に把握し、分析し、公表するための仕組み
ウ わが国の「強み」を活用した国際支援
従来の意味での「貢献」活動や、企業の事業活動を通じての国際貢献、いずれの場合にも、他国より優位なわが国の「強み」(技術、知識と経験)を活かした貢献をすることが期待されます。
すでに取り組まれているものとしては、社団法人産業環境管理協会が、わが国の公害防止管理者制度を参考として、タイにおけるエネルギー・環境技術普及協力のためのプロジェクトを行っています。
この21世紀において、わが国の「強み」を活用した国際支援をますます有意義なものにするために、一層の技術開発や先進的な環境施策を推進するとともに、他国の範となるようなライフスタイルや事業活動の変革の実績をつくることを目指さなければなりません。新たな環境基本計画の下、国民、企業、NGO、地方公共団体、政府、それぞれの蜻フがそれぞれに課せられた責務を認識し、それぞれの「強み」を活かしながら自律的に変革を進めていくことが重要です。