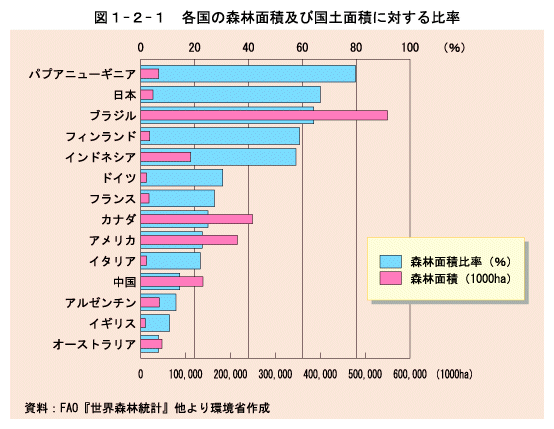
1 環境保全の実績から見た日本の特徴
(1)日本の環境を見つめ直す
ア 日本に与えられた自然環境
総理府(内閣府)が平成10年に行った「社会意識に関する世論調査」によれば、全体の34.8%の人が「日本の誇りは美しい自然である」と回答しています。わが国の自然環境ははどのような特徴を持っているのでしょうか。
南北に長く位置する日本の国土は、温暖な気候と適度な降水量の条件の下、四季の自然に恵まれています。もとより丘陸地を含む山地の面積は国土の約4分の3を占める地形のため森林の占める割合も高く(図1-2-1)、天然林も多く残されています。また、リアス式海岸に代表されるように海岸線が長く、起伏の大きい標高差をもつ地形という特徴を持つため、生態系も豊かです(表1-2-1)。
また、長い歴史の中で、私たちは自然豊かな里山で、自然と共生しながら生活を営むことにより、わが国は、自然の恵みを享受しながら同時に自然を守ってきた歴史を歩んできたといえます。
イ 高度成長期の産業公害の経験
明治以降の産業近代化以降、経済成長は様々な公害問題を引き起こしてきました。明治時代に足尾銅山鉱毒問題のほか、都市地域の工場からのばい煙がすでに問題となっていました。こうした公害の被害が甚大となり社会問題にまで発展したのが、昭和30〜40年代のいわゆる4大公害*などです。
政府は戦後の経済復興を最優先した時代から昭和30〜40年代の高度成長期に至るまで、経済発展を優先した政策の下、公共投資を産業基盤の整備に集中させました。また企業においても経済効率の追求を重視し、製品や生産工程における環境配慮及び公害防止への投資が少なかった時代です。こうした社会背景の中、起こるべくして起こったともいえる公害問題に対し、政府は急速に環境規制を強化することにより、企業の公害防止投資や技術開発を促し、公害問題の収束に効果をあげました(図1-2-2)。
規制の強化は段階的なものでしたが、企業にとっては1973年(昭和48年)の石油危機による経済混乱状況の中での公害防止投資を迫られることになりました。環境負荷の大きな産業は少なからぬ負担を強いられたにもかかわらず、投資負担を吸収するための企業の経営合理化努力や、政府系金融機関による特利融資計画*などの側面支援などにより、公害の克服と経済成長との両立を実現させ、後に「日本の奇跡」と呼ばれるようになりました。
このようにして、大気環境や水質環境の状況は改善されてきていますが、人々にもたらした深刻な被害への救済の問題は依然残されています。公害は、過去のものとなったわけではありませんが、他国に例を見ないわが国の経験を真摯に分析した上で、その試行錯誤によって得られた教訓を効果的に国際社会に還元させていくことは、私たちの責任であるといえます。
*4大公害
水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく
*特利融資計画
民間金融機関の金利が9%以上の時期に、政府系金融機関が6.85−8.0%の金利で融資を行った。
ウ 世界から見た日本の環境の現状
昭和50〜60年代には、産業活動を原因とする典型7公害*の深刻な状況は収束してきましたが、自動車排気ガスによる大気汚染問題は深刻になり、また一方で、廃棄物処理問題や地球温暖化問題などの新しい問題が生じています。
NOx濃度などに代表される環境について国際的に見ると、わが国の状況は必ずしも良い面ばかりではありません(図1-2-3、図1-2-4)。
わが国は限られた国土面積の中で多くの人々の生活を維持し、活発な経済活動を行っているという特徴があります(図1-2-5)。そのため、他の国々に比較し、都市における廃棄物対策や大気保全に関する政策について特に先進的な取組や対策技術の積極的な普及が求められているのです(表1-2-2)。
例えば、GDPに対する最終エネルギー消費量や都市ごみ排出量を、主要先進国において比較すると、日本は他国より値が小さい状況にあります(図1-2-6、1-2-7
)。これは、少ない環境負荷で付加価値を生み出すという意味で、環境効率が高いことを示しています。このような高い環境効率を実現したわが国の取組は、地球環境問題の改善にも貢献し得るものであるといえます。例えば、ごみ問題の解決にむけたリサイクル技術は、資源枯渇対策に資するものですし、産業における生産工程の合理化は、エネルギー消費すなわち二酸化炭素排出削減につながるものです。
地球環境問題の解決に当たっての課題の一つとして、今後の経済発展が見込まれる途上国における環境負荷の増大が挙げられますが、途上国の環境効率の向上に貢献することができれば、このような問題の解決の一助となります。
しかしながら、高い環境効率の実現を通じて環境負荷の総量も削減しなければ、地球環境問題の解決にはつながりません。わが国における環境負荷、特にエネルギー消費量は、GDPあたりでは低減しつつあるものの総量では増大する傾向にあります(図1-2-8、1-2-9
)。高い環境効率を可能とする技術を諸外国に広め、各国の環境負荷の低減に資するとともに、わが国自らも環境負荷の総量を削減する努力を続けていかなければなりません。
さらに、わが国は、資源・エネルギー消費という面からの環境効率の向上を目指す一方、国際分業といった経済合理性の下に、天然資源を他国に依存するようになっています。 また、わが国の産業の特徴であった加工貿易は、海外で採取した資源を国内で加工し製品を輸出するもので、いわば、資源採掘と消費(使用)、廃棄に伴う環境負荷を海外で発生させていた経済ともいえます。つまり、地球環境全体からみれば、わが国の高い環境効率は、サービス産業の成長や海外生産の拡大などにより変化しているものの、こうしたいわば特異な産業構造によって実現したものであるという面にも考慮が必要です。
このように、わが国はエネルギーや資源の輸入と工業製品の輸出を経済基盤の一部としていることもあり、経済的にも、地球環境への負荷の上でも、世界で大きな影響を与える地位にあることから、あらゆる場面で世界全体に視野を広げていくことが不可欠です。しかしながら、現状は必ずしも国際社会に対して胸を張れる状態とはいえない面もあります。今後、グローバル化がさらに進み、経済、社会の広い分野における国際交流が活発になることを踏まえ、持続可能な社会の構築を目指して、自らの足元を見つめ直すとともに、積極的に国際社会に貢献していくことが重要です。
*典型7公害
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7項目。環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定されている。
(2)日本が国際社会に示すことができるもの
わが国の製造業が、国際社会に対し競争力と影響力を持ち得た要因としては、QC活動*に代表される生産管理と製品の性能や生産性の向上を実現した技術開発力が挙げられます。ここでは、同じ視点から環境の分野において国際社会に示すことができるわが国の「強み」を検討していきます。
*QC活動
Quality Control
製品やサービスの品質を維持するための活動。QCサークルと呼ばれる事業所内の全員参加の仕組み等を用いた改善活動を指すことが多い。
ア 生産管理手法から発展した環境管理手法の導入実績
1996年(平成8年)10月に発行した環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001*は、世界各国で認証取得が進んでいます。わが国の認証取得の件数は、1999年(平成11年)12月時点で世界第一位を誇っています(図1-2-10)。国内での認証取得件数はその後も中小規模の事業所やサービス業への普及もあいまって、2001年(平成13年)2月末には5,585件に達しました。
また、製品やサービスの品質管理・向上を目的として、現場の従業員が工程改善に取り組むQC活動も多くの工場で普及しています。 もとは品質管理のための活動ですが、無駄やムラをなくすという面から、環境管理にも効果をあげています。
一方、わが国にはISO14001が普及する前から、「公害防止管理者制度*」によって企業の環境管理が進められてきた実績があります。
QC活動の用語「カイゼン」などは、すでに英語として使われるほどに海外でも知られていますが、これらの活動があったことが、わが国における環境マネジメントシステムの普及の基礎になっているものと考えられます。
*ISO14001
環境マネジメントに関する国際規格で、企業活動、製品及びサービスの環境負荷の低減など継続的な改善を図る仕組みを構築するための要求事項を規定
*公害防止管理者制度
特定工場に公害防止のための組織の設置を義務付けるもので、昭和46年から法律によって規定された。
イ 環境効率向上を支えてきた技術
産業技術力や商品開発力も日本が海外に誇ることのできる代表的なものです。
環境効率を向上させるためには、少ない環境負荷で高い付加価値や機能を実現する技術が必要です。産業公害や石油危機を契機に向上した公害防止技術や省エネ技術は、公害防止機器などに応用され、アジア方面への輸出を伸ばすなど、わが国の有望な産業の一つとなっています(図1-2-11)。
最近では、廃棄物やリサイクル関連の規制を受けて、家電製品の分解工程の自動化やプラスチック分別技術など日本独自の技術開発も進んでいます。規制や法律の施行ノよってビジネスチャンスが生まれ、新しい技術開発が促進されることは、特許の出願件数の推移からも見ることができます(図1-2-12)。日本経済新聞社による「21世紀の新技術・研究開発調査」では、コージェネレーションシステムや高効率ガスタービン、リサイクル型焼却炉(ガス化溶融炉など)、生分解性プラスチックなどの技術水準が、欧米やアジアに対し優位である、又は将来優位になると報告されています(表1-2-3)。
また、現在のわが国の輸出品の主体は「消費財*」から「資本財や生産財*」に移ってきています。具体的には、高度な加工装置や半導体、電子部品などです。IT化の進展により、特に情報機器等に使用される電子部品の需要が増大してきており、この分野で消費エネルギー効率等を向上させることができれば、国際社会への貢献にとどまらず、わが国の産業競争力の向上にもつながるといえます。
*消費財
家計で購入される製品
*資本財や生産財
企業等の生産手段や製品の部品・材料として使用される財
ウ 環境政策の社会的枠組みの構築とそれを支える環境意識の高まり
新しい環境省を中心とした環境政策の推進などにより、持続可能な社会に向けた枠組みが着実に構築されることが期待されます。
平成12年には、新しい環境基本計画の策定や「循環型社会形成推進基本法*」の成立など、わが国の環境政策の枠組みを整えるための動きが相次ぎ、新しい環境政策への第一歩を踏み出しました。
これらの枠組みをさらに具体化させ、効果を確実なものにしなければなりませんが、こうした変革により、国内の環境保全への取組が一層進展することが期待できます。
例えば、国等の各機関が自ら基準を定めて環境物品*の調達を推進する「グリーン購入法*」の施行により、これらの環境物品に対する需要が高まり、企業はより環境物品等の開発、生産を積極的に行うようになると考えられます。さらに、多数の環境物品が市場に供給されることで、一般の消費者もより多様な環境物品をより低価格で手にすることが可能となるでしょう。
また、省エネ法においては、トップランナー方式*の導入により、環境保全に向けた企業の技術開発を促進する施策を実施しています。
これらに代表される日本独自の手法を交えた取組の推進によって、政府の政策と企業間の自由な競争による相乗効果が生み出され、世界に先駆けて持続可能な社会を実現することにつながっていくことが期待されます。
さらに、企業や市民の環境保全への意識が高まっていくことは、このような経済社会への変革を実現するための力強い推進力となります。
近年、企業の意識には変化が見られます。環境に関する取組について、「社会貢献の一つ」から、「企業の業績を左右する重要な要素」又は「企業の最も重要な戦略の一つ」ととらえて企業活動の中に取り込んでいくという動きに変わろうとしています(図1-2-13)。
一方、市民の意識も確実に高まっていることを様々な調査結果が裏付けています。
例えば、国立環境研究所が行った調査においては、「環境保全のために生活が不便になっても構わない」という回答(「そう思う」+「どちらかといえばそう思う」)が全体の54.6%を占めるまでになっています(図1-2-14)。
企業の意識・行動の変革と個人の意識・行動の変革は車の両輪の働きをするものです。政府の適切な政策の枠組みの構築により、これらの企業と個人が相互に作用しながら、環境保全への意識の向上と取組をさらに推進することができるのです。
*循環型社会形成推進基本法
平成12年6月2日法律第110号
*環境物品
環境負荷の低減に資する物品・役務
*グリーン購入法
国等の環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成11年法律第105号)同法に基づく基本方針により14分野101品目の特定調達品目を規定→講じた施策第3章第3節2参照
*トップランナー方式
省エネ基準を、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているものの性能、技術開発の見直し等を勘案して定める考え方
コラム 里山林を介した循環等にみる地域資源の活用
里山林は、薪炭林や農用林として形成され、かつての地域内にあった有機物循環の中で重要な役割を果たしていました。
例えば、里山林から採取された薪炭は、農家で煮炊きや暖をとるために使われ、その結果生成された木灰は、同じく里山林の落葉や下草とともに農地の肥料(酸性化しやすい日本の土壌を中和する土壌改良材)として使用されました。農地で生産された農産物は自らの食糧源となり、薪炭を出発点とする物質循環は、里山林→農家→農地→農家と地域内で完結する連鎖的なものとなっていました。
しかし、昭和30年代以降の工業化の進展と石炭・石油エネルギーへの転換に伴い、里山林は低利用地とされ、工業用地や住宅地への開発、生産林としての活用の放棄が進行しました。
現在、環境緑化や環境保全意識の向上や自然体験などの環境教育といった観点から、各地のNPO、企業等を主体に里山林の再生を目指す取り組みが数多く行われています。