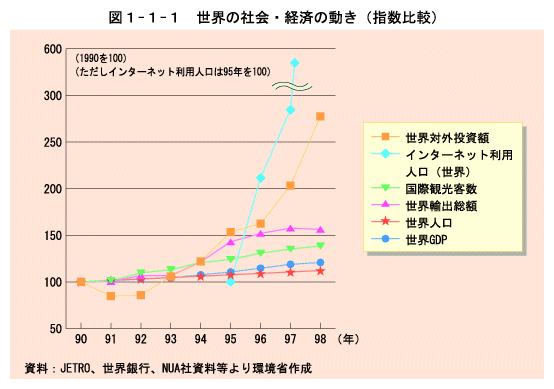
1 社会経済の構造変化と環境問題の変容
(1)21世紀初頭の社会経済の構造変化
20世紀最後の10年間、わが国の社会経済の構造変化を加速させた2つの世界的な潮流が「情報化」と「グローバル化」でした。
IT革命とも呼ばれる情報化の進展は、コンピュータや通信網の発達を通じ、情報流通量を大きく拡大させました。その結果、企業は生産や流通を効率化し、新たなビジネスチャンスを模索し、私たち生活者もいながらにして様々な情報を入手できるようになりました。
また、こうした情報化の進展や世界貿易の拡大などを背景に、人、物、資金、情報の国境を越えた流れも飛躍的に増大しました。例えば、国境を越えた投資の総額は世界全体で、1990年(平成2年)から1998年(平成10年)の間に約3倍に増加しており、世界観光機関(WTO)によれば、世界の海外旅行者数(国際観光客到着数)も1989年(平成元年)から1998年にかけて約1.5倍に増加しています(図1-1-1)。このようなグローバル化の進展によ り、企業における時価会計基準*や通信機器の規格など、多くの分野で世界標準化の動きも出てきています。さらに文化や情報等の分野でもボーダーレス化が起こっており、人々の価値観へ及ぼす影響も多大であるといえるでしょう。
21世紀初頭にかけても続くと考えられる、これら社会経済の潮流は、国際間の物流量や情報関連機器製造量の増加、情報化による輸送や移動の代替効果といった直接的な影響 だけではなく、産業構造やライフスタイルの変化など、社会経済の構造に様々な影響を及ぼしています。
*時価会計基準
資産や負債を、簿価(取得時点の価格)ではなく、時価(市場で売買される価値)によって計上する会計基準
ア 人口・世帯構成、地域分布
医療技術の進歩や出生率の低下を受けて、わが国では急速に少子高齢化が進んでいます。昭和25年、平成7年及び平成37年(推計)における年齢別人口ピラミッドを見ると、富士山型を示していた昭和25年に対し、平成7年は子どもの年齢層が成年層に比べて小さく、かつ老年層も大きいいわゆるつぼ型になっています。平成37年にはこの傾向はより強まり、4人に1人以上が65歳以上という超高齢化社会が予想されています(図1-1-2)。また同時に、図1-1-3世帯人員別世帯構成の推移総人口は平成19年をピークに減少すると予想されています。
一方で世帯数が増え、1世帯当たりの人数は一貫して減少する傾向が続いています。特に、世帯人員が1人の単独世帯や2人世帯が増加しています(図1-1-3)。さらに、地域的な人口の偏りの拡大も続いています。高度成長期(1965年前後)の時期に比較すれば穏かになりましたが、現在でも地方圏における過疎の進行と都市部への人口の集中は確実に進行しています(図1-1-4)。
世帯数の増加は家庭部門でのエネルギー消費の増加や自動車保有台数の増加などにつながり、人口の偏在は都市環境の悪化や過疎地域での自然管理不足による荒廃などをもたらすことが懸念されます。
イ ライフスタイルの変化
都市型で小人数世帯のライフスタイルは、生活時間帯や嗜好の多様化をもたらすとともに、より快適性を志向する傾向にあるといえます。
NHKによる生活時間調査によれば、昭和45年には約60%の人が夜11時頃すでに就寝していましたが、平成7年にはその割合が約35%にまで下がるなど、生活時間の夜型化が顕著に見られます(図1-1-5)。
また、私たちの家計消費支出の中で、自動車関連費用や教養娯楽関連費用、外食などが特に増加していることから、趣味や余暇活動への支出割合が増えていることもうかがわれます(図1-1-6)。
携帯電話やインターネット、衛星放送等の多チャンネル放送の普及など情報化の進展のおかげで、より個別の情報や嗜好を追求できるようになってきているため、この傾向は今後、いっそう強まるものと考えられます。
そして、経済成長と技術改革の恩恵により、私たちは様々な快適さを簡単に手に入れられるようになっています。昭和55年頃に登場したVTRはすでに70%以上の世帯に普及しており、それ以降に登場したパソコンや温水洗浄便座も急速に普及し始めているなど、私たちの生活はますます豊かで快適なものとなっています(図1-1-7)。
ウ 産業構造の変化
産業構造の変化について見てみると、平成11年の第三次産業のウェイトは昭和45年に比較し、19.6ポイントも上昇しています(図1-1-9)。これは、物質的資源やエネルギーをあまり消費しない「情報」や「サービス」の付加価値が増大していることを示しています。
また、第二次産業の中でも、エネルギーを多く消費する重厚長大型産業から組立型産業への移行が見られ、ここでもエネルギー効率(エネルギー消費当たりのGDP)が高まっているといえます(図1-1-10)。
また、環境面での様々な技術革新も進んでおり、製造工程の省エネ化や製品における環境配慮は各段の進歩を遂げています(図1-1-11)。
(2)態様を変える環境問題
私たちのライフスタイルは、情報化やグローバル化の進展や経済成長、家族構成の変化、居住地域などの影響を受けて知らず知らずのうちに変化しています。環境への影響と生活や産業形態は密接に関わっていることから、環境問題の課題も同時に変容しています。 産業における技術革新により、各種電気機器の省エネ化が進みましたが、同時に次々と新しい製品需要を生み出しています。私たち消費者も、環境に配慮された製品を意識的に購入する一方で、無意識のうちに購入量が増えていたり、製品の買い替え期間が短くなっていたりすることもあります。
例えば、カラーテレビは1970年(昭和45年)から1985年頃にかけて、技術開発等により大幅な省エネルギー化が実現しましたが、その後の大型モデルの普及などにより、1台当たりの消費電力量は一時期かえって増大しました。また、普及台数の増加により家庭におけるカラーテレビの消費電力量は増加を続けています(図1-1-12)。
技術や意識の向上にかかわらず、家庭でのエネルギー需要は年々増加しているという事実を正面から受け止めなくてはなりません。 産業についても同様に、環境対策が進んでいる一方で、経済活動の拡大や大量生産、大量消費の帰結としての大量の廃棄物の発生など、依然として環境への負荷は増大しています。
このような環境問題の解決のためには、社会経済活動のあり方やライフスタイルを、表面的ではなく根源に遡って考え直す必要があります(図1-1-13)。
さらに、私たちの経済活動、産業活動、そして日常生活による環境への影響は、深刻な地球環境問題を発生させています。地球環境問題とは、主として「影響が国境を越え地球規模に及ぶ環境問題」を指しますが、こうした問題には、影響が明らかになるまで長期間を要する問題やその影響が長期間にわたる問題、発生の仕組みやその影響の科学的解明が十分でない問題が増えているなどの特徴があります。
代表的な地球環境問題には、地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、生物多様性の減少、廃棄物輸出、残留性有機汚染物質などが挙げられます。これらの個別の原因や影響は様々ですが、突き詰めていくと、有限な地球上での人口増加と経済活動の拡大が主な原因であるといえます。また、グローバル化などの社会経済の変化が問題の深刻化に影響を与えているのです。
地球環境問題に関わる様々な事象を、(1)私たちの生活や経済活動の維持に伴う諸活動、(2)地球環境への影響、(3)直接的に被害を及ぼす事象というように整理しました(図1-1-14)。個別の環境問題が相互に複雑に関連しながら、自然の物質循環や生態系へ大きな影響を及ぼすことを通じて、人類の存続を脅かす存在となるのです。
*ITS
高度道路交通システム。最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報でネットワークすることにより、交通事故、渋滞などといった道路交通問題の解決を目的に構築する新しい交通システムのこと
コラム 20世紀のくらしを変えたもの
20世紀は、様々な商品、サービスが発明された世紀でした。そのどれもが、私たちの生活に多かれ少なかれ影響を与えてきました。 日本経済新聞社がインターネットを用いて、20世紀に日本で登場、普及した商品・サービスのうち、「人々の生活や、行動、ライフスタイルを大きく変えたもの」について調査を行っています。
この調査によれば、「コンビニエンスストア」が第1位となり、以下「携帯電話・PHS・ポケベル」、「電子ネット」と続いています。
同新聞社では、「いつでも、どこでも」志向を満たす点が上位の項目の多くに共通する特徴であり、場所や所持金、時間、社会的立場など、消費やコミュニケーションに関する様々な制約を取り除いた点が評価されていると分析しています。一方で、「我慢することが減った」、「自分の時間がなくなった」などの「負の変化」についても指摘しています。
コラム 移入種による生態系への影響
近年、国外又は国内の他の地域から本来の野生生物が持つ移動能力を遙かに超えて意図的・非意図的に移動・移入した種(移入種)が増加しており、地域固有の生態系や生物相の存続に対する大きな脅威となっています。 移入種の影響は、在来の希少種等の捕食、競合する在来種の駆逐などの直接的影響だけでなく、近縁種との交雑による遺伝的汚染、採餌行為による植生の破壊などの間接的な影響など広範囲にわたります。
これらの移入種は、食用等の産業目的のために輸入されたり、害獣等の天敵として移入されたものや家畜が野生化したものなど、人間の都合により持ち込まれたものが少なくありません。グローバル化の進展に伴い、海外からペットとして輸入されたものが、国内で飼育中に逃げ出したり、持て余されて捨てられたりして野生化している事例も増えてきています。
このような、移入種問題に関する国際的取決めとして、生物多様性条約*第8条において、「生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種*の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは撲滅すること」と記述されており、生物多様性条約締約国会議及び補助機関会合において、対策の推進について議論が進められているところです。
現在、絶滅の危機にある世界の脊椎動物のおよそ20%は外来種の圧力によるものであるともいわれており、グローバル化や経済活動の発展などが、その要因の一つになっていると考えられます。
*生物多様性条約
1993年(平成5年)12月発効。生物多様性の保全、持続可能な利用及び利益の配分を条約目的とし、国家戦略の策定、生息域内保全、持続可能な利用、研究、情報交換、遺伝子操作生物の安全性確保、技術移転、資金協力などが規定されている。わが国の「生物多様性国家戦略」は平成7年10月31日に地球環境保全関係閣僚会議において決定された。
*外来種
移入種と同義に使われる。他に「帰化種」とも呼ばれることがある。