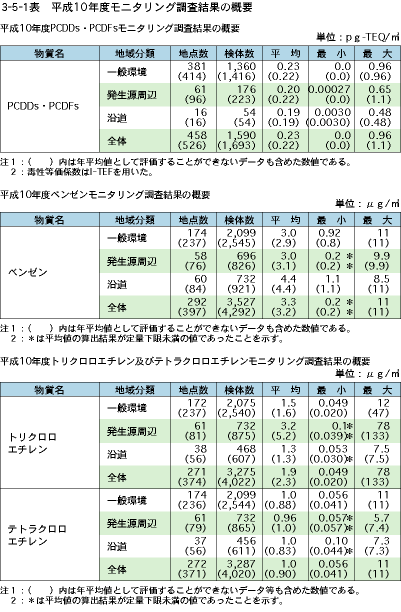
1 様々な化学物質による問題
(1)大気環境中の化学物質についてモニタリング調査や残留状況の調査が行われている
ア 有害大気汚染物質による汚染の現状
大気中には、濃度が低くとも人体が長期的に曝露された場合に健康影響が懸念される有害物質が存在する。また、ダイオキシン類のように意図せずに生成され、大気中に排出される有害化学物質による環境汚染が社会問題となっている。
平成8年10月及び12月の中央環境審議会答申は、有害大気汚染物質の中から健康リスクが高いと考えられる22種類の物質を優先取組物質として選定し、重点的に対策を推進すること等を提言した。これを受けて、平成9年1月に、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについて排出抑制基準を定め、同年2月には環境基準を定めた(年平均値でベンゼン0.003mg/m3以下、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン0.2mg/m3以下)。
また、平成9年8月には、ダイオキシン類について排出抑制基準を定め、同年9月に大気環境指針を定めた(年平均値で0.8pg-TEQ/m3)。さらに、平成11年7月に制定・公布されたダイオキシン法を受けて、ダイオキシン類大気環境基準については、年平均値0.6pg-TEQ/m3と定められた。
有害大気汚染物質のモニタリング調査は昭和60年から実施されているが、平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、平成9年度から地方公共団体(都道府県、大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングが開始され、さらに平成10年度には調査規模が大幅に拡大された。
平成10年度に実施したモニタリング調査のうち、ダイオキシン類及び大気汚染防止法に基づき指定物質に指定されている物質(ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン)に関わる測定結果は以下のとおりであった(3-5-1表)。
ダイオキシン類については、全国458地点で行った環境大気中での測定結果によれば、平成10年度におけるPCDD+PCDFの濃度は算術平均値で0.22pg-TEQ/m3であった。また、平成9年度及び平成10年度の継続調査地点(52地点)においては、平成9年度におけるPCDD+PCDFの平均値0.56pg-TEQ/m3から平成10年度には0.31pg-TEQ/m3と大気環境濃度が大きく低減している。
ベンゼンについては、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における測定結果を平成9年2月に設定された環境基準値(0.003mg/m3)と比較すると、292地点中135地点について環境基準値を超過していた。
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、すべての地点において環境基準値(ともに0.2mg/m3)を下回っていた。
(注)ダイオキシン法においては、PCDD(ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン)、PCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)、コプラナーPCB(コプラナーポリ塩化ビフェニル)を併せてダイオキシン類と定義している。従来においては、PCDDとPCDFをあわせてダイオキシン類と呼んでいた。
イ 化学物質の大気残留状況
一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度のレベルの把握を目的とした平成10年度化学物質環境調査(大気系)の結果、調査対象物質32物質(群)のうち29物質(群)が検出された。そのうち1,2,4-トリメチルベンゼンなどについては、今後も環境調査を行い、その推移を監視するとともに、情報収集に努めることが必要と考えられる。
指定化学物質については、環境中の残留状況を把握するため、「指定化学物質等検討調査」を行っている。平成10年度指定化学物質等検討調査は、製造・輸入量、化学的性状等を考慮に入れて、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等10物質について行った。このうち、大気を媒介とするものとして調査されたのは4種類であり、いずれも残留状況及び曝露状況に大きな変化は見られなかった。しかし、環境中に広範囲に残留しているものも多く、今後とも引き続き調査を実施していく必要がある。
(2)水環境中の化学物質について水質と底質への残留状況が調査されている
一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした、平成10年度の水質と底質の化学物質環境調査結果によると、水質の調査対象24物質(群)のうち8物質(群)が、底質の調査対象24物質(群)のうち16物質(群)が、魚類の調査対象3物質のうち2物質が検出された。これらのうちジブチルスズ化合物については、今後より詳細な環境調査を行い、その推移を監視するとともに、情報収集に努めることが必要があると考えられる。また、そのほかの検出された物質についても、検出頻度や濃度に応じた対応が必要と考えられる。
環境調査の結果等により水質と底質への残留が確認されている化学物質について、残留による環境汚染の経年監視を行うため、水質と底質のモニタリングを実施している。平成10年度の調査の結果、対象20物質のうち、水質から5物質、底質から20物質すべてが検出された。底質からの検出状況は水質に比べ全体的に高かった。また、調査対象物質ごとの最高値を記録した地点を見ると、大和川河口(9物質)、洞海湾(5物質)、大阪港(3物質)、隅田川河口(2物質)及び石狩川河口(1物質)であり、閉鎖性水域の内湾部の汚染レベルが高いことが示唆される。
平成10年度の非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査においても底質及び魚類について臭素化ダイオキシン類の調査を行った。臭素化ダイオキシン類の一般環境への汚染は、現在の調査・測定方法では認められないが、今後、さらに高感度の分析法を開発し、これを用いた調査により環境中の残留状況を把握していくことが必要である。
また、臭素化ダイオキシン類に関する関連情報が少ないため、今後、その関連情報を収集し、発生源や環境中挙動などの汚染機構の解明に努めるほか、毒性関連知見の収集に努めることも必要である。
(3)土壌環境中の化学物質としてダイオキシン類が注目されている
ダイオキシン類は、廃棄物の焼却過程等で非意図的に発生し、これが環境中に排出された場合、その一部は土壌に蓄積される。平成10年4月に、一般廃棄物焼却施設の周辺土壌から高濃度のダイオキシン類が検出される事例が判明し、土壌中のダイオキシン類に由来する健康影響の評価や対策手法が大きな社会的関心を集めている。
土壌中のダイオキシン類が人体に取り込まれる経路としては、?手などに付着した土壌の「摂取」や「皮膚接触」による直接摂取の経路、?農用地土壌中のダイオキシン類が当該土壌の上で生産される農畜産物に移行し、それらが人に摂取される経路、?土壌の粒子が水域に移行し、さらに食物連鎖を経て水産物を経由する経路の三つが考えられる(3-5-1図)。環境基準の設定に当たっては、?の直接摂取の経路に着目して検討を行っている。なお、農作物や水域への移行に係る環境影響については、知見の制約の大きい状況であるが、今後化学的知見の集積に努めていく必要がある。
また、ダイオキシン類だけではなく、金属の脱脂洗浄や溶剤として使われるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる土壌汚染が判明した事例もある。
(4)最終処分場の化学物質としてダイオキシン類の濃度の調査が行われている
廃棄物の最終処分場は、日常生活等に伴い発生する廃棄物及びそれらに含まれた有害物による環境汚染を防止するため、それらを一定の空間に封じ込めることにより埋立処分するための施設である。その防止対策として、廃棄物処理法により、埋め立てられる廃棄物についてはあらかじめ一定の性状となるように処理の基準が定められているとともに、最終処分場については埋立物あるいは汚水などの周囲への漏洩を防止し、汚水等を適切に処理するための構造の基準及び維持管理の基準が定められている。
環境庁による平成10年度及び11年度に実施された最終処分場周辺環境等のダイオキシン類濃度の調査結果によると、周辺土壌については、多くは一般環境中と同様の濃度範囲であったが、一部においては埋立地からの距離が近いほど高濃度になる傾向を示す地点、局地的には濃度が高い地点があった。また、周辺地下水では、一般環境中の地下水と比較しても十分低く、最終処分場からの放流水では、おおむね一般環境中の公共用水域における水質結果の範囲内であった。なお、わが国におけるダイオキシンの排出量目録によれば、最終処分場(放流水)からの環境中への排出割合は、全排出量に対して0.003%と非常に小さい。
上記結果を見る限り、現状においては最終処分場が適切に維持管理されていればダイオキシン類について特段問題がないことが分かるが、高濃度ダイオキシン類含有物が低減処理されるようにすること(平成11年、廃棄物焼却施設から排出されたばいじん、燃え殻及び汚泥のうち、3ng-TEQ/g以上のダイオキシン類を含むものについて特別管理廃棄物に指定し低減処理することを規定)、飛散・流出防止策を具体化していくこと、最終処分場の維持管理基準を設定すること等の措置により、より一層のダイオキシン類による一般環境への汚染防止が期待される。
(5)内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)について引き続き調査・研究が必要である
平成8年に刊行された「Our Stolen Future」(邦訳「奪われし未来」)という本では、DDT、クロルデン、ノニルフェノールなどの化学物質が人の健康影響(男性の精子数減少、女性の乳がん罹患率の上昇)や、野生生物への影響(ワニの生殖器の奇形、ニジマス等の魚類の雌性化、鳥類の生殖行動異常等)をもたらしている可能性が指摘されている。また、わが国においては、イボニシという巻き貝のメスが雄性化するという現象が見られ、詳しいメカニズムは解明されていないが、船底塗料として使用されていた有機スズ化合物が原因ではないかとの報告もある。
このような、生体内に取り込まれて内分泌系(ホルモン)に影響を及ぼす化学物質は、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)と呼ばれている。
平成10年度に実施された環境ホルモン緊急全国一斉調査は、内分泌かく乱作用が疑われている67物質を中心に、大気、水等の環境媒体の濃度状況を全国2,430地点(検体)(延べ)で調査したもので、おそらく世界で類を見ない大規模調査であったと考えられる。この調査結果によると、ノニルフェノールなどが広い範囲で検出されたほか、野生生物のうち、食物連鎖で上位に位置するクジラ類や猛禽類において、PCBなどの蓄積が見られた。大気、水質、底質、土壌、水生生物、野生生物それぞれの調査結果は、3-5-2表のとおりである。
ダイオキシン類対策特別措置法について
平成11年7月に、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等を図るため、議員立法により「ダイオキシン類対策特別措置法」(以下「ダイオキシン法」という)が制定された。この法律の概要は、以下のとおりである。
a 施策の基本とすべき基準の設定
耐容一日摂取量(生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない、一日当たりの摂取量)を政令で人の体重1kg当たり4ピコグラム以下に定めるとともに、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染に関する環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい、環境中の濃度条件についての基準)を設定する。
b 排出ガス及び排出水に関する規制
大気汚染防止法、水質汚濁防止法と同様の仕組みにより、大気、公共用水域へのダイオキシン類の排出を規制する。具体的には、規制対象施設からの排出ガス排出水中のダイオキシン類の濃度について基準を定めその遵守を義務づけ、違反に対しては都道府県知事等の改善命令、罰則の適用により対処することとなる。
また、規制対象施設を設置している事業者に、排出ガス・排出水の測定、都道府県への報告が義務付けられる。測定の結果は、都道府県知事が公表することとなる。
c 廃棄物処理に関する規制
廃棄物処理に関する規制として、bの規制が廃棄物焼却炉に適用されることのほか、廃棄物焼却炉からのばいじん・焼却灰を処分する際のダイオキシン類の濃度に関する規制、最終処分場の維持管理に関する規制が行われる。
d 汚染状況の調査
都道府県は大気、水質、土壌の汚染状況を常時監視し、環境庁に報告する。
e 汚染土壌対策
都道府県が、土壌環境基準を満たさない地域のうちから対策が必要な地域を指定し、汚染除去事業の実施などを内容とする対策計画を策定する。対策事業については、通常より高い国庫補助率が適用され、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づき明確な場合には、汚染事業者により費用が負担される。
f ダイオキシン類排出削減計画の策定
内閣総理大臣が、事業分野別のダイオキシン類排出の削減目標量及びその達成のための措置、廃棄物減量化のための施策などを内容とする計画を策定する。
g 今後検討すべき事項
臭素系ダイオキシンに関する調査研究を推進するとともに、健康被害対策、食品への蓄積への対策について科学的知見に基づく検討を行う。