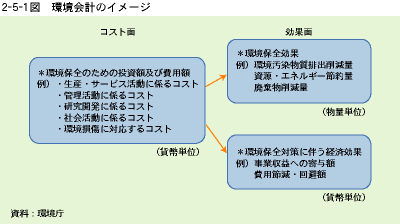
1 個人、行政、企業等各主体間のパートナーシップを確立するための条件
(1)各主体間の環境コミュニケーションを確立し社会全体に広げる
ア 環境コミュニケーションのあり方
環境コミュニケーションの発展段階として、大きく三つのレベルが考えられる。
第一段階は、情報の受け手がよく理解し納得したかは全く考慮しないで、技術的情報を何の工夫もなく単純に提供、開示する段階である。第二段階は、情報発信者の意図が受け手に受け入れられることに関心が寄せられ、このため内容などを工夫するが、相手の意見を聞くことは全く考えていない段階である。この時提供される情報は、発信者に都合のよい点を強調する場合が多い。この第一、第二段階のような相手の意見を聞かない一方的な情報提供をコミュニケーションと考える傾向がある。しかし、関係者に説明するだけでなく、相手の意見を聞き、討議して初めて、インフォメーション(情報)ではなく、コミュニケーション(話し合い)という要素が入ってくるのであり、この第三段階こそ文字通り環境コミュニケーションといえる。例えば、ごみ処分場の設置推進者と立地予定地の住民の考え方は違うことが多いが、むしろ考え方や立場の違いを認めつつも、なぜ違うか議論し、ともに回答を模索することが重要なのである。実際に、企業の環境報告書の中には、意見送付用のアンケート用紙を添付し、読者からの意見や要望を聴取し積極的に対処しようとする姿勢を明確に示すものも増えつつある。
以下では、企業活動に関する環境情報の開示を例として、円滑な環境コミュニケーションを実現するために必要な要件について具体的に考察する。
イ 企業活動における環境情報の開示
近年、企業において、自らの事業活動による環境への負荷や環境対策の状況などに関する情報を公開する動きが広がっている。環境庁が実施している「環境にやさしい企業行動に関するアンケート調査」の平成11年度の結果によれば、環境に関するデータ、取組等の情報を公開している企業は、上場企業で40.9%、非上場企業で25.8%であった。これは、平成10年度の結果と比べると、上場企業で5.2ポイント、非上場企業で4.9ポイント増加している。
このように、企業が自らの活動を積極的に情報開示するようになった理由、意義として、大きく二つ考えられる。
その一つが、環境アカウンタビリティ(説明責任)の履行である。環境アカウンタビリティとは企業の環境保全活動に関する利害関係者への説明責任を意味する。例えば、株主は経営者に自己資金を委託するため、経営者は株主に環境保全活動に関して説明する義務を負っている。また、環境が地球上の人々すべての共有財産であるとすれば、企業は、資源を消費し環境汚染物質を排出することによって、共有財産を消費していることになるため、企業は市民に対して環境保全活動に関して説明する義務を負うとも考えられる。
二つ目として、消費者、投資者、地域住民等の利害関係者からの支持の獲得である。つまり、企業の環境情報は、本章第3節でも示したとおり、グリーン購入やエコファンドなどの環境投資、さらには就職先企業の選別など、各利害関係者が意思決定を行う際の大きな判断材料となりつつある。
企業が環境情報を開示する手段として、環境報告書、環境会計、PRTR制度、環境ラベル等があげられるが、以下でそれぞれについて具体的に考察したい(ただし、PRTR制度は第1章第3節、環境ラベルに関しては、本章第3節を参照)。
(ア)環境報告書
環境報告書とは、企業が自らの環境方針を明確にし、事業活動に伴って発生する環境に対する影響の程度やその影響を削減するための自主的な取組をとりまとめて公表するものである。記載内容としては、環境に関する経営方針、組織体制など環境マネジメントシステムに関わる内容、二酸化炭素や有害化学物質等の環境負荷物質の排出状況や環境負荷の低減に向けた取組などがある。
環境庁が実施している「環境にやさしい企業行動に関するアンケート調査」の平成11年度の結果によれば、わが国の上場企業約15%、非上場企業6%が環境報告書等による情報を提供している(なお、上場企業2,441社、非上場企業3,855社を対象とし、有効回収数がそれぞれ1,147件、1,620件)。各企業は、環境報告書の作成方法や内容に独自の工夫を凝らしている。最近の傾向として、環境基準や独自目標の達成について定量的な表現が多くなってきたこと、グリーン調達やライフサイクルアセスメント(LCA)、有害化学物質の排出等に関する記述が増えたこと、事業所別情報が増えたこと、環境会計を示す企業が出てきていること等があげられる。また、環境報告書の信頼性を高めるために、独立した外部機関に環境報告書の内容の審査を依頼する第三者検証を行う企業も現れている。
(イ)環境会計
環境会計とは、持続可能な発展を目指し、企業等が環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全に関するコスト(投資額及び費用額)とその効果を可能な限り定量的(金額又は物量ベース)に把握し公表するための仕組みである(2-5-1図)。企業による環境に配慮した取組は近年ますます活発になっているが、投資や費用の変化が環境保全に関してどれだけ効果を上げたかを把握することについて関心が高まっており、こうした作業を行うためのツールとして注目されている。平成12年3月現在、環境会計情報を公表した企業等は数十社にのぼる。
環境会計に期待される機能として、大きく内部機能と外部機能に分けられる。
内部機能とは、企業の内部管理情報のシステムとして、年々負担の増大する環境保全コストの管理や、環境対策の費用対効果分析を可能にし、効率的かつ効果的な環境投資、さらには健全な事業経営を促すものである。一方、外部機能とは、企業の環境保全への取組状況を定量的に公表するシステムとして、利害関係者の意思決定などに影響を与える機能を果たす。また、企業の環境格付けや経営リスク・収益性に関わる情報となって、株価安定や円滑な資金調達の面でのメリットも期待される。積極的に環境経営を進める企業を社会全体で支援するためには、両方の機能がバランスよく発揮されることが望まれる(2-5-2図)。
ウ 円滑な環境コミュニケーションを確立するために必要な条件
(ア)環境情報の公開と提供の拡大
環境報告書を公表する企業は増加しつつあり、また、製品に関する情報提供も自主宣言を中心として増加するなど、環境情報の公開と提供は進みつつある。さらに、環境コミュニケーションを社会全体に広げていくには、より多くの企業、製品等に関する情報が公開、提供されていくことが重要である。
このためには、例えば、中小企業などにおいては、環境報告書などの形式に縛られるよりも、簡易な形でもまずは環境コミュニケーションを始めることにより、取組の輪を広げていくことが重要である。
(イ)環境情報の内容の充実
環境情報の公開は、PRTRなどのように法律で規定されるものを除けば、企業等の特性やねらいにより様々な形があり得る。同時に、提供される環境情報が、消費者や投資家などの意思決定に活かされ、環境保全に真に役立つものとなるためには、環境問題の状況や重要度を適切に反映し、できるだけ相互比較が可能なものとなることが望ましい。
環境情報の内容については、こうした観点からの充実、改善が継続的に進められることが重要である。このため、個々の企業がその特性を踏まえて創意工夫していくと同時に、その基盤として、共通的な情報項目や評価手法について検討を進めることが重要である。
例えば、国際的には、国際標準化機構(ISO)がライフサイクルアセスメント(LCA)手法や環境パフォーマンス評価手法の規格化を進めているとともに、GRI(Global Reporting Initiative)などが環境報告書に関してガイドラインを作成しているほか、国内においては、環境庁で環境報告書、環境会計に関しガイドラインを作成し、公表している。
今後は、環境会計と、環境負荷の抑制効果などの環境パフォーマンス指標を適切に連携させることも検討課題である。
また、公表、提供された情報の信頼性を確保することも、今後重要となってくる課題である。信頼性の確保のためには、双方向のコミュニケーションを行うことなど様々な手法があり得るが、その中で、中立的、独立的な第三者による審査や検証等を受けることも重要な手法である。すでにEUでは、1993年(平成5年)にEU規則により整備された「環境マネジメント・監査制度(EMAS)」により、公認の環境検証人による環境報告書の検証の制度が施行されている。わが国でも、環境報告書や環境会計について、環境問題の専門家や会計監査法人などによる検証等が行われている事例が出てきているが、現時点では、その手法や用語が確立されていないため、その意義について誤解を与えるおそれがあるなどの問題があり、今後、さらに検討を進めていくことが必要である。
(ウ)環境情報が円滑に流通するための基盤づくり
環境コミュニケーションを社会全体に広げていくためには、提供される多種多様な情報に、受け手が理解しやすい形でアクセスできる環境が整えられることが重要である。
このためには、行政、民間非営利団体、研究機関、マスコミ等が、適切な役割分担と協力の下で、情報の仲介者として機能していくことが重要と考えられる(2-5-3図)。
具体的に、アメリカにおける化学物質管理でのコミュニケーション手法を見てみよう。
アメリカは、「緊急対処計画及び地域住民の知る権利法」に基づく有害物質排出目録制度によって、個別施設からの有害物質排出量などを行政に報告し、それを一般に公表する制度となっている。そして、環境保護庁においては、インターネットホームページで、内容別の情報案内だけでなく、子供、学生・教師、関心のある市民、研究者、企業、地方の行政官という相手別の情報案内を用意し、問い合わせに回答する窓口が設けられている。また、一部の民間非営利団体においても、インターネットを利用してオンラインで個別事業所情報、地域別、物質の毒性別など様々な切り口で情報を発信するなど、環境コミュニケーションの橋渡しとしての役割を担っている。
(2)個人の環境保全施策への参加プロセスを確立する
各主体が連携して環境保全への取組を実践する際のプロセスとして、一般的に現状把握─計画策定─実施という流れが考えられる。しかし現状では、現状把握や計画そのものの策定段階では、主に行政主導的な形態が多く、個人レベルでは参加しにくい。一方、実施の段階になると各主体にそれぞれの役割が期待される。このように、参加の現状には各主体の間でかなりの偏りがあると考えられる。こうした状況は、各主体の参加意欲を阻害しかねない。特に、近年の環境問題への個人の関心の高まりに加え、地球温暖化問題などのように注目されている多くの環境問題は、個人の活動とそれによる環境負荷や環境保全効果の関係が見えにくく、その点からも取組の早い段階からの個人の参加が必要である。
第1章第3節でも述べたとおり、環境基本計画策定以後いくつかの制度が生まれつつある。
例えば、環境アセスメントに関する制度化である。環境影響評価法が平成9年に成立し、環境影響を評価する枠組み設定、すなわちスコーピングの段階で地域住民の参加機会が盛り込まれた。そのほか、平成11年には情報公開法が成立し、各種施策の策定過程において他の主体から意見を募集するパブリックコメント手続きが行われていることなども施策の意思決定段階での各主体の参加を促進するものと考えられる。
(3)地域住民が主体となることが可能な地域コミュニティの基盤を整備する
外部からの援助者や地方公共団体などの支援が地域の環境保全に有効な場合が少なくないことは事実である。だが、地域の環境保全において大きな力となるのは、とりわけ地元の住民や民間団体である。そして、その住民がバラバラに活動しているのではなく、小さくとも地域コミュニティをすでに持っているか、持っていても弱体化、形式化していないかどうかが環境を保全する力の強弱を大きく左右する。そのため、地域住民や民間団体が環境保全への取組を行うとき、その地元の地域コミュニティをどう育成、強化するかあるいはどう支援するか、ということが一つの具体的な課題となろう。
(4)具体的行動につながる環境教育・環境学習を推進する
持続可能な社会を構築するためには、個人が環境への関心や、環境の現状や人間と環境との関わりについての正しい認識を持ち、日常生活や社会活動において具体的行動に結びつけていくことが重要である。このためには、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会の創造に主体的に参画できる人材を育成することが何より必要である。
わが国においては、従来から、様々な主体により多様な実践活動が積み重ねられてきているが、環境基本計画においても示されているとおり、幼児から高齢者までのそれぞれの年齢層に対して、学校、地域、家庭、職場、野外活動の場等多様な場において互いに連携を図りながら、環境教育・環境学習を総合的に推進していくことが重要である。
平成7年度から環境庁は、地方公共団体との連携の下「こどもエコクラブ事業」を実施しているが、全国各地で子どもたちの興味、関心に基づいた地域性豊かな活動が多様かつ活発に展開されている。子どもたちが、日常の生活の中で見つけた身近なテーマ、切り口から活動を始めながら、自分たちでテーマを深化させたり、活動の成果を積極的に社会に訴え掛けるなど、地域を巻き込んだ活動を展開している例も多い。また、地域の民間団体、企業、ボランティア、行政の様々な部局などが連携し、子どもたちの活動を応援するとともに、自らの活動、学習の輪を広げている例も各地で見られる。なお、こどもエコクラブは、平成11年に、国連環境計画(UNEP)からグローバル500賞青少年部門を贈られるなど国際的にも評価が高まりつつある。
このように子どもを始めとする各年齢層が、地域において環境学習や環境活動を継続的に行うには、日常の生活圏内に、実践体験活動を行うことができる場や機会が多数存在することが望まれる。こうした趣旨から、平成11年12月に、中央環境審議会が、持続可能な社会の実現に向けた環境教育・環境学習の今後の推進方策について答申をとりまとめた。同答申においては、環境教育・環境学習の推進の方向について、特定の場において学習、活動するだけでなく、生活や社会活動のそれぞれの場で具体的な行動につなげていくことを促すことが重要との観点から、?既存の取組を積極的に活用しながら、様々な「場をつなぐ」こと、?多様な「主体をつなぐ」ことや、そのための仕組みを地域に根付かせること、さらに、?環境教育・環境学習と様々な政策手法、各主体との活動との連携を図ることや、持続可能な地域づくりという視点から行政の様々な「施策をつなぐ」ことなど、横断的、総合的な展開が必要であるとしている。
環境庁では、総合的に環境教育・環境学習を推進するための仕組み、基盤づくりとして、環境学習支援事業を通じたプログラムの整備、環境カウンセラー登録制度や自然解説指導者育成事業等による指導者の養成、確保などを実施している。さらに、多様な学習機会の充実と体験を重視した学習の実践という観点から、こどもエコクラブ事業を始め、子どもパークレンジャー事業、こども葉っぱ判定士事業、全国水生生物調査などを実施、推進しており、多くの子ども、市民の参加を得ているところである。
学校教育においては、従来から、小・中・高等学校を通じて、社会科、理科、家庭科などで児童生徒の発展段階に応じた環境教育に関する指導がなされてきたが、平成10年12月に小・中学校の学習指導要領が、平成11年3月には高等学校学習指導要領が改訂され、これまでの各教科等に加え、「総合的な学習の時間」が新設されることになった。「総合的な学習の時間」においては、各学校の創意工夫を活かして、例えば、環境や国際理解などの横断的、総合的な課題などについて学習活動が行われる。また、開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めるとの方向性が示されている。
さらに、文部省の生涯学習審議会は、完全学校週5日制の実施に向け、家庭や地域社会で、子どもたちのために、様々な体験活動を意図的、計画的に提供する必要があることや、そのための体制整備に向けた提言などを盛り込んだ答申を平成11年6月にまとめた。文部省では、答申等も踏まえ「全国子どもプラン(緊急3ヶ年戦略)」を策定し、関係省庁と連携して、様々な取組を推進している。
なお、わが国は、本格的な高齢社会の到来を控えている。環境学習や環境保全活動は、子どもから高齢者までの各年齢層の取組が不可欠であるが、高齢者層は、社会経験や職業、家庭生活を通して習得した専門知識や生活の知恵が豊富であり、モノを大切にするという価値意識を次世代に継承する存在としても、環境学習や環境保全活動における指導者、実践者としての活躍が特に期待される。
環境教育・環境学習の推進に当たっては、高齢化、少子化、情報化など、わが国社会の動向にも適切に対応していく必要があろう。
こども環境活動支援協会(兵庫県西宮市)
兵庫県西宮市では、一地方公共団体の枠を超えて広く子どもたちの環境学習活動を支援する任意団体の設立を市民、事業者に呼び掛け、平成10年4月に「こども環境活動支援協会」を発足させた。同協会では、各主体とのパートナーシップを重視し、企業会員と連携した学習プログラムづくりなど、学校、地域団体、店舗等を巻き込んだ地域に根ざした学習システムを実践し、文部省の「子どもセンター」事業の地域拠点ともなっている。
エコライフの実践
今日の環境教育・環境学習には、日常生活や社会活動において環境負荷の少ない行動様式を具体的に現実のものとしていくことが期待されている。
大阪府では、「ECOPAL探検隊─環境にやさしい学校生活推進の手引き─」を教職員用に作成している。学校のエコライフ活動を分かりやすく解説したもので、児童、生徒と教職員が一体となって活動を始める際の手引き書である。学校内でこまめな消灯、ごみの減量などに日常的に取り組むことで、児童、生徒が、学校という場を離れても、身近な人々に呼び掛け、同様な実践を広げることをねらいとしている。
神戸市では、学校教育と連携し「総合的な学習の時間」に活用するべく、「子どもの目から見たくらしのエコチェック推進事業」を実施している。子どもたちが「エコチェックシート」を使いながら、暮らしと地球環境問題の関係を学習するとともに、水、エネルギー、ごみの排出量などを自ら点検し、自ら目標を定め、自ら取り組む力の芽を伸ばそうとするものである。さらに、本事業を通じて、子どもたちの自主的な活動を学校や家庭が支える仕組みづくりを行うことを目指している。
日本生活協同組合連合会では、各地域の会員生協を通じて、組合員を対象に「エコファミリープログラム」を提案し、各家庭が暮らしの現状や問題意識に合わせて、自主的に目標を設定し、実際に暮らしを変えてみる取組を支援している。家族のコミュニケーションを軸に目標を決めていくためのツールとして「エコファミリーワークブック」が用意されているほか、家族の気づきが広がり、やる気が持続するよう「エコファミリー通信」の発行などにより、各家族の交流支援も行っている。
自然体験と環境保全活動
半世紀前の子ども達はどんな遊びをしていたか。現代との比較から「野山での鬼ごっこ、海や川での魚とり」といった自然の中での遊びを想像しがちである。実際、海辺近くで子ども時代を過ごしたお年寄りの中には、ウミガメの産卵を見たり、ウニの投げあいをした経験を持つ人もいる。その一方で、東京に限らず「街中」で育ったお年寄りは自然とふれあった経験は遠足のときくらいで、ほとんど思い出の中にないという人もいる。こうした都市部と郊外部での自然経験の差は、子どもの行動範囲の中に「海」や「山」といった自然の遊び場があったかどうかで決まると考えられる。
平成8年度に環境庁が実施した「児童期における遊びに関する調査」によると、自然とふれあう遊びは、成長後も環境に対する思いを支える原体験となっているが、その「思い」は必ずしも実際の行動につながっておらず、むしろ、公害や環境に関する本を読んだり、人の話を聞いたことがあるという原体験のある人の方が行動の実施率が高い傾向を示しているという分析もあり、環境に配慮した行動は、自然とのふれあいによって醸成される自然への親しみと人によって提供される知識とによって相乗的に促されるものと考えられる。