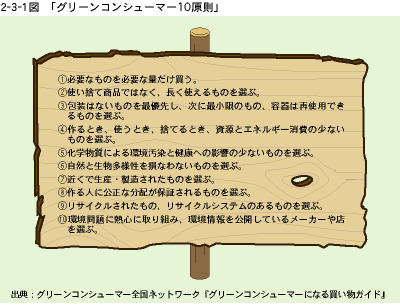
1 消費者による環境保全への取組の広がりとその社会的影響
(1)グリーン購入は経済社会システムを変える可能性がある
個人は様々な形で社会とのつながりを持っており、その中でも市場経済を通じたつながりはとりわけ大きな存在である。特にモノを媒体とする製品市場においては、個人は「消費者」という名の需要者であり、供給者である事業者と相対する位置にある。
製品市場ではモノを供給する事業者が主導権を握ると考えられがちだが、市場における参加者は皆対等な存在であり、消費者の側から事業者にアプローチし、ひいては社会システム全体を変革していくことも不可能ではない。そのために消費者が持つ手段は「モノを選択する」ことであり、環境負荷を低減し持続的発展が可能な社会を構築するための今後の消費のあり方が、製品市場を通じて経済社会システム全体を循環型社会に変革していく大きな力となり得る。
モノの購入を通じた環境負荷低減への意思表示の方法は、現在「グリーン購入」と呼ばれている。ここではグリーン購入の手法を通じて、製品市場において消費者が取り得るアプローチを考えてみたい。
ア グリーン購入とは
ここでいう「グリーン購入」とは、市場に供給される製品・サービスの中から環境への負荷が少ないものを優先的に購入することによって、これらを供給する事業者の環境負荷低減への取組に影響を与えていこうとする消費者一人一人の消費行動のことである。
グリーン購入が注目されるようになった契機は、1988年(昭和63年)にイギリスで「The Green Consumer Guide(緑の消費者ガイド)」が発売されたことである。この中で定義された「グリーンな消費」の考え方が、現在のグリーン購入の考え方につながっている。この「グリーンな消費」のあり方を具体的に示す例として、わが国の複数の民間団体で構成されたグリーンコンシューマー全国ネットワークが提唱した「グリーンコンシューマー10原則」があげられる(2-3-1図)。
イ グリーン購入は事業者の活動にどう影響を与えるか
グリーン購入という行動は、果たしてどれだけ事業者の活動に影響を与えるのだろうか。
事業者は一般に利益の極大化を追求する経済主体である。このため事業者はコスト増大要因となる環境対策を行わないという論理があるが、これは誤った認識である。事業者は単独では存在し得ず、市場経済や社会環境の中にその身を置いているので、極大利潤の追求を企図しつつも、その行動は市場経済、社会環境から様々な制約を受け、その中で活動を行うことになる。
環境保全に関する事業者の行動を決定し得る要素は大きく二つある。
一つは法的な規制である。法的な環境規制に反することは、違法行為として罰せられることはもちろんであるが、事前の環境配慮が欠けていたために環境汚染が引き起こされ、事業者に莫大な汚染浄化費用や損害補償金の負担を強いることになる。
もう一つは市場である。事業者は環境問題に限らず様々な制約を、製品市場、金融市場、労働市場等から常に受けている。環境への配慮が欠けていると、例えば、消費者などから批判を受け、製品の売上が落ちることが考えられる。この場合は、製品市場が事業者の環境配慮を求めて影響を与えたということができ、こうした事態を招かないよう、事業者の行動はより一層環境への負荷を低減する方向に向かうことになる(2-3-2図)。
グリーン購入はこの市場の面からのアプローチであり、環境への配慮を欠いた事業者に対する批判であると同時に、環境対策に積極的な事業者に対する支援であるといえる。
それでは消費者自身は実際にグリーン購入によりどれだけ事業者の活動に影響を与え得ると考えているのだろうか。平成10年度に国立環境研究所が行った調査によれば、「できる」が11.2%、「ある程度できる」が56.6%であり、全体の約7割が積極的なグリーン購入が事業者を変え得ると考えている(2-3-3図)。
このような環境保全に対する消費者の意識の高まりは、事業者の環境保全に対する意識にも影響を与えている。平成11年度の環境庁の調査では、事業者の環境への取組と事業活動のあり方についてどう考えるかという設問に対し、上場企業、非上場企業とも「環境への取組は社会貢献の一つである」と回答した割合がそれぞれ33.2%、51.5%と最も高く、「環境に関する取組は今後の業績を左右する重要な要素の一つとして取り組んでいる」、「環境に関する取組を最も重要な戦略の一つとして位置づけ事業活動に取り込んでいる」がそれに続いており、事業者が環境保全に対する取組に大きなウェイトを置いていることを示している(2-3-4図)。
(2)グリーン購入はまだ十分に消費行動の基準になり得ていない
グリーン購入に対する消費者の意識は、今のところまだ十分な行動に結び付いていない。
平成10年度に東京都が実施した調査によれば、日頃から環境に配慮した消費行動をしている人が多いと思うかという設問に対して、全体の約9割(86.0%)が「少ないと思う」と回答しており、社会全体としてグリーン購入がまだ十分に進んでいないことを示した結果となっている(2-3-5図)。
その要因はどこにあるのか。同じ調査において、普段あまり環境に配慮した消費行動をしていないとした人にその理由をたずねたところ、「製品購入に当たっては価格や機能を重視しているから」、「商品を選択する際の情報が不足しているから」、「環境に配慮した製品が少ないから」といった回答が多くなっている(2-3-6図)。このことは、個人消費者だけではなく、事業者などの組織単位でのグリーン購入においても当てはまり、事業者や地方公共団体、消費者団体などで構成される「グリーン購入ネットワーク」(後述)が平成11年に行った調査においても、グリーン購入を行う際の障害として、「環境に配慮した製品の価格の高さ」、「商品や情報が多くてもその選択が困難」、「商品情報が入手できない」といったことがあげられている(2-3-7図)。
グリーン購入がいまだ消費行動の大きな潮流になり得ていない背景には、このように大きく分けると、「環境に配慮した製品は価格が高い」という価格面の問題と、「環境に配慮した製品に関する適切な情報が少ない」といった情報面の問題があるといえる。
(3)環境に配慮した製品の価格は必ずしも高いとは言い切れない
ア ライフサイクルから見た製品の価格
平成11年度の経済企画庁の調査によれば、「同じ価格、もしくは価格が許容範囲であれば省エネルギー性や環境配慮を重視して製品を選択する」と考えている割合は、家電製品の購入では全体の88.3%、自動車では96.3%、住宅では96.8%とかなり高くなっている。一方、その許容できる価格差は、最も価格が低い家電製品(10万円前後のエアコン)の場合、1万円(10%)の差ならば80.4%が許容できるとしているが、2万円(20%)の差になると許容できるとした割合は大きく減って半分以下(38.3%)に下がっており、購入時の価格差が消費行動を大きく制約していることを示している。
一般に、環境に配慮した製品の購入価格は環境に配慮していない製品よりも高い。しかし、製品に対する支出という行為は、購入時だけではなくその製品が廃棄されるまでのライフサイクルにわたって継続的に行われるものであり、購入時に支出するイニシャル・コスト(導入に要するコスト)に加え、使用、修繕や廃棄時に支出するランニング・コスト(運用に要するコスト)もあわせて考慮しなければならない。
例として、年間を通じてほぼ一定の電力を消費し、家庭の電力消費量の17.6%(平成9年度)を占める電気冷蔵庫についてのイニシャル・コストと、電力消費の点から見たランニング・コストを考えてみたい。電気冷蔵庫のライフサイクルからは約4.3tのCO2が排出されるとの試算があるが、そのうち約95%は使用時の消費電力から排出されているため、消費電力を抑えた省エネルギー型機器を購入することは環境負荷の低減に大きな役割を果たすことになる。
電気冷蔵庫の平均的な電力消費量(平成8年度)は、10年前(昭和61年)に比べて約8.5kwh/月減っている。この両者をそれぞれ省エネルギー型機器、非省エネルギー型機器と仮定し、平均的な電力料金(平成8年度)で使用すると、1年当たり約2,530円の節約効果が発生する。これが省エネルギー型機器の経済的メリットといえるランニング・コストの低減部分である。一方、イニシャル・コストについては、非省エネルギー型機器と仮定した平成8年度の電気冷蔵庫の平均小売価格21万円に対して、省エネルギー型機器が2万円(約10%)高い価格であるとした場合、年間約2,530円の電気代の節減によってこの価格差は約8.3年でなくなることになる。電気冷蔵庫の平均使用年数はここ数年10〜11年で推移していることから、電気冷蔵庫のライフサイクルにおける消費者の支出は省エネルギー型機器の購入によって最終的に低減され、また同時に環境負荷の低減にもつながることになる。
このことは、製品の長期使用を続ければそれだけランニング・コストと環境負荷の低減が可能となることを意味しているが、一方で製品の省エネルギー効率は年々向上しており、早期に新製品に買い替えた方が経済的な場合もある。また、省エネルギー効率が向上しても、その他の機能が拡大(例えば冷蔵容量が増えるなど)すれば全体ではその効果が十分に発揮されない場合もあり、単純な比較が成り立たない場合もある。
電力消費面以外でも、例えば、製品のリサイクル容易性は年々向上しており、そのために支払うイニシャル・コストが最終的に廃棄時に生じる費用と環境負荷を低減することも考えられる。このように、製品の価格の高低はより多角的な観点から考えられるべきである。製品のイニシャル・コストだけでなくランニング・コストまでを含めた価格で考えた場合、環境に配慮した製品は常に価格が高いとは必ずしも言い切れない。したがって、製品の販売の際にこうした情報を分かりやすく示し、環境に配慮した製品の購入を促すことが重要である。
イ 組織単位のグリーン購入が価格に及ぼす影響
グリーン購入の直接的なインセンティブとして、現時点ではやはりイニシャル・コストの低減も重要である。そのためには需要が環境に配慮した製品にシフトし、大量に生産・販売されることにより価格低下に結び付く必要がある。
しかし、消費者一人一人のグリーン購入への取組には時間がかかるため、事業者や団体などの組織単位でグリーン購入を推進し、より効果的に製品市場を環境に配慮したものに変えていこうという取組が、先に述べたグリーン購入ネットワークを中心に進められている。そして、このような組織単位でのグリーン購入が、環境に配慮した製品の価格を下げる効果を発揮することが期待される。
グリーン購入ネットワークは、わが国におけるグリーン購入の取組を促進するために平成8年2月に設立された事業者、地方公共団体、民間団体の非常に緩やかなネットワークである。会員は積極的にグリーン購入に取り組むことが求められるが、あくまでも個々の実状に応じた自主的な取組が重視されている。
平成11年度にグリーン購入ネットワークがその会員及び非会員を対象に行った調査では、グリーン購入を取り巻く最近の状況の変化の一つとして「環境に配慮した製品の価格が低下した(43%)」ことがあげられ、1年前の同じ調査に比べて約2倍の伸びとなっていることが示された(2-3-8図)。もちろん、このことが直ちにグリーン購入ネットワークの活動による成果と結び付けられるわけではないが、平成8年の設立時に73団体であった会員数が、4年後の平成11年12月時点では事業者1,480、地方公共団体308、民間団体225の計2,013団体に増え、特に都道府県では40団体が会員になるなど、組織的な需要者の増加が価格の低下に好影響を与えているのではないかと考えられる。
現在、地域レベルでも事業者、地方公共団体などによるグリーン購入のための組織化が進みつつある。滋賀県においては平成11年12月に県が中心となって県内事業者、消費者団体、市町村など約200団体からなる「滋賀グリーン購入ネットワーク」が設立された。このような地域の実状に即した組織単位でのグリーン購入が促進されることによって、環境に配慮した製品の価格の低下がより一層進むことが期待される。
また、第1章第3節で述べたとおり、政府も平成7年6月に閣議決定された「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画(率先実行計画)」に基づき、紙類、OA機器、公用車などの購入について環境に配慮した製品の購入に取り組んでいる。その取組は同節で検証したとおり、決してまだ十分とはいえないため、これらの製品の積極的な導入により、環境に配慮した製品の価格の低下に資するよう引き続き努力していく必要がある。
(4)グリーン購入の進展には環境に関する適切な情報が欠かせない
環境に配慮した製品の購入を阻害しているもう一つの大きな要因として、「環境に配慮した製品に関する適切な情報が少ない」という点が指摘されている。
消費行動と情報は常に密接な関係の下にある。今後多くの消費者が自然にグリーン購入に取り組めるようになるためには、環境に配慮した製品や店舗についての確かな情報が様々な媒体によって伝えられ、必要なときにいつでもそれを得られることが必要不可欠である。
ア 環境に配慮した製品に関する情報の現状
消費者は環境問題に関する情報を何からどの程度得ているのだろうか。ここでは平成10年度に国立環境研究所がとりまとめた「地球環境問題をめぐる消費者の意識と行動が企業戦略に及ぼす影響〈消費者編:日独比較〉」における調査を下に、平成6年に「循環経済・廃棄物法」が制定され、すでに先駆的な取組が行われているドイツの消費者の意識と行動をわが国の消費者と比較することによって考えてみたい。
まず、環境問題に関して自身が有する情報・知識量が豊富であるかどうかについて、わが国の消費者はドイツの消費者に比べて全般的に「豊富である」とした割合が低い。そのうちグリーン購入に関わりの深い項目として、「環境に良い製品・サービスについての情報・知識量」について質問したところ、豊富であると答えた割合は全体の10.3%にすぎなかった。これはドイツの47.6%に比較して37.3ポイントも低い(2-3-9図)。
また、入手した情報にどの程度信頼を置いているかについての設問では、「環境問題について何が正しい情報かわからない」と答えた割合は「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」を合わせてドイツは40.4%であったのに対し、わが国では57.6%と17.2ポイントも高くなっており、ここでも環境に関する確かな情報や知識が十分でない実態が表れている(2-3-10図)。
環境問題に対する情報そのものは新聞やテレビなどのマスコミ、あるいは雑誌、行政機関の情報誌などで取り上げられる機会も増え、比較的接する場面が多くなってきたように思われる。しかし、実際に環境問題に対する適切な認識を与える情報や、環境に配慮した製品を購入あるいは適切な使用や廃棄を実践するためのより具体的な情報、あるいは消費者がそれらの製品によって低減できる環境負荷を具体的にイメージできる情報はまだ不十分である。
イ 環境ラベルによる情報の提供
グリーン購入を促進するためには、環境に配慮した製品やサービスについてのより適切な情報が必要となる。製品・サービスに関する広い意味での環境に関する情報を「環境ラベル」という。
(ア)第三者機関の認定・推奨による環境ラベル
環境ラベルの中に、環境に関する一定の要件を満たすことを第三者機関が認定・推奨し、特定のマークにより示す方法がある。マーク表示によって製品の差異化を図り、グリーン購入の促進につなげるものである。
わが国におけるこうした環境ラベルとしては、環境保全全般に関する負荷の低減を図った製品を第三者機関が認定するものとしてエコマークが、また省エネルギーやリサイクルなどの環境の特定の側面について優れている製品を第三者機関が認定・推奨するものとしてグリーンマーク、エネルギースターなどがある。
エコマークは、平成元年2月から環境庁の指導の下で(財)日本環境協会が実施している制度であり、平成11年12月現在68商品類型について認定基準が定められており、事業者の申請に応じて、認定基準に適合する3,448商品に貼付されている(2-3-11図)。
これまでは特定の環境負荷の低減を考慮した認定基準であったが、平成8年3月に、製品の製造、流通、消費、廃棄の各段階からなるライフサイクル全体を通して、様々な環境負荷の総合的な低減を考慮した認定基準が作成される仕組みとなり、グリーン購入の総合的な指針としての役割が果たせるよう機能の拡充が図られた。この方法はライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方を部分的に取り入れたものであり、こうした制度の改善により、国際標準化機構(ISO)規格に基づいたタイプ?型(第三者認証型)の環境ラベルとして、一層の充実が図られている。
諸外国においても、グリーン購入を促進するためのマーク表示による環境ラベルの整備が行われている(2-3-12図)。
わが国のエコマークのように、独立した第三者機関が環境負荷の低減を考慮したラベルの使用を認定・推奨する仕組みは1978年(昭和53年)に旧西ドイツで実施された「ブルーエンジェル」から始まった。その後世界各国に拡大し、現在25前後の制度が運用されており、中にはグリーン購入に非常に大きな影響力を持っている国もある。例えば、スウェーデンでは、あまり知られていない洗濯洗剤のブランドに環境ラベルが貼付された結果、有名ブランドとのシェアが逆転したという事例がある。
(イ)事業者による自己宣言に基づく環境ラベル
第三者機関の認定・推奨によるのではなく、生産者や販売者である事業者自身が、製品などの環境保全上の特性について、製品やそのパンフレット、取扱説明書などに表示すること(自己宣言)も、広い意味での環境ラベルの一つである。
近年、消費者の環境意識の向上に対応して、こうした形での情報提供が広く見られるようになっている。
こうした自己宣言に基づく環境ラベルは、消費者が情報を入手する上で重要なチャンネルであり、情報提供の一層の充実が期待される。同時に、虚偽の表現や消費者に誤解を与えるような表現は避ける必要がある。
自己宣言のあり方については、国際標準化機構(ISO)において規格(タイプ?型(自己宣言型))が発行されており、今後、これに基づいた適切な環境情報が広がっていくことが期待される。
(ウ)環境負荷情報の表示と提供
上記のような第三者の認定・推奨や自己宣言に基づく環境ラベルのうち、マーク表示によるものは、一見して判別できる視認性は高いものの、その製品がどの程度環境負荷を低減しているのかを定量的な基準や数値で示すことは難しい。このため、こうした環境ラベルの普及、発展とともに、環境負荷に関するより具体的な情報を表示、提供する仕組みの必要性が認識されてきている。
このような状況の下、通商産業省では平成10年度から「環境調和型社会における環境ラベルのあり方検討会報告書(平成10年5月)」を受けて、定量的環境情報表示ラベルの検討に着手している。また、本年夏ごろを目途に家電製品の省エネルギー効果をラベルで表示するJIS規格の改正が行われる予定である。
エコマークについても、環境庁が設置した「21世紀に向けた環境ラベルの今後のあり方に関する検討会」の中間報告を受けて、環境負荷などに関してより詳細な情報を盛り込む方向での取組と検討が進められている。
これらの環境ラベルの他にも、製品の環境負荷に関する情報を収集・整理して提供する様々な取組が行われている。例えば、グリーン購入ネットワークにおいては、現在パソコン、冷蔵庫、自動車などの13品目について、「商品選択のための環境データブック」を作成している。また、環境庁と国際連合大学が共同で運営する地球環境パートナーシッププラザでは、乗用車と家電製品について、各製品の二酸化炭素排出量を調査し、「ChoCO2(チョコツー…Choice by CO2)」というデータ集を取りまとめている。(財)省エネルギーセンターにおいても、毎年夏と冬に「省エネ性能比較カタログ」を作成し、省エネルギーの観点から、個々の製品についての詳細な情報の提供を行っている。
これらの取組も、製品の具体的な環境負荷情報を比較可能な形で提供する有効な方法である。
(エ)環境ラベルと消費者の関わりのあり方
今後は国際標準化機構(ISO)による環境ラベルの国際規格化の動きと相まって、事業者の環境ラベルなどへの積極的な取組が急速に進展すると考えられる。消費者としてはこの動きをどのようにとらえ、活用していけばよいのか。
これまで消費者はグリーン購入に対する情報、知識を十分に自らのものとしていない面があった。しかし、環境ラベルなどの種類や内容がより充実するにつれて、消費者が自ら意識的に環境ラベルを読み解き、環境に配慮した製品やサービスを購入するための確かな判断を下すのに十分な知識を持つことが重要な意味を持ってくる。
平成10年度に東京ガス(株)都市生活研究所とグリーン購入ネットワークが実施した調査では、家電製品の購入に関して今後もっと欲しい環境情報として、省エネ性や節水性、リサイクル容易性などが高い反面、二酸化炭素発生量については低い値となっている(2-3-13図)。これは二酸化炭素発生量についての情報や知識をすでに十分有しているから必要がないというわけではなく、家電製品と二酸化炭素排出の関係についての情報が、十分な知識として消費者に定着しておらず、それに基づいた購入の判断が行われていないことを反映した結果と考えられる。
グリーン購入に際して最も分かりやすい目印ともいえる環境ラベルが一層有効に機能するためには、消費者が環境問題や環境負荷の低減についての確かな情報や知識を蓄積していくことが欠かせない。提供される情報が増え、その内容が充実するにつれて、入手した情報を自ら咀嚼し、確認し、消費行動の原動力としていくという消費者の主体的な取組の存在が大きくなり、また事業者に対し大きな力を持つことになる。
ウ 様々な情報提供を通じたグリーン購入への取組
グリーン購入に関する情報の提供は、その他にも様々な民間団体や地方公共団体によるガイドブックの作成などを通じて、積極的な取組が行われている。
その内容は、民間団体が各地域の身近な店舗における環境配慮の状況などを取りまとめたものが中心となっているが、中には全国規模で大手小売業者の環境負荷低減への取組を評価したガイドブックが民間団体のネットワークによって作成されており、そこでは「包装材の削減と素材の見直し」、「エネルギー消費、ごみの削減、物流対策」などの分野別評価が行われ、最終的に星の数でのランク付けがなされている。近年では石川県や鳥取県などの地方公共団体においてもグリーン購入のための買い物ガイドブックを作成する動きが進んでいる。
また、「グリーンコンシューマー東京ネット」では、多くの店舗の協力の下、グリーン購入のための月間を設けて情報提供を行い、積極的なグリーン購入を進めるといった取組なども行われている。
(5)様々な取組から「消費のグリーン化」の道筋を考える
ここまで考えてきた「グリーン購入」は、環境に配慮した製品の優先的な購入という環境保全への取組であるが、環境負荷の低減につながる消費のあり方についてはこのほかにも様々なものが考えられる。これらは、平成11年版環境白書の記述にならえば、消費者がその活動の中に、環境保全への配慮を段階的に組み込んでいく「消費のグリーン化」ということもできよう。グリーン購入の発展型ともいえる、様々な取組による「消費のグリーン化」へのアプローチを考えてみたい。
ア 農産物の選択購入による「消費のグリーン化」
はじめに、日常の代表的な消費財である農産物の消費について考えてみたい。
例えば、野菜等については、周年安定供給を求める消費者ニーズへの対応もあり、本来夏や秋を旬とする農産物を冬や春に収穫するために温室で栽培する場合が見られるが、石油などを用いて加温する温室での栽培は、それ以外の栽培方法と比較して、多くのエネルギーを消費することになり、二酸化炭素の排出量を増加させることにつながると考えられる(2-3-14図)。
また、化学肥料や農薬の不適切な使用は、水質等の汚染の一因となっている。そのため、減化学肥料や減農薬の農産物を選択して購入することはこれらによる環境負荷の低減に資することになる。
さらに、一般的に物資の輸送距離が長くなれば、運搬に伴うエネルギー消費により発生する環境負荷も増加する。このことは農産物についてもいえることであり、輸送距離が短い地場産の農産物を選択して購入することも、環境負荷の低減につながると考えられる。
農産物の産地、栽培方法等に係る表示制度については、平成11年の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)の一部改正によって一連の整備が行われ、有機農産物の検査認証・表示制度が導入された。地方公共団体でも長野県の「環境にやさしい農産物表示認証制度」のような独自の仕組みを整備しているところがあり、また大分県久住町で行われている「くじゅう地球村農園」のように、化学肥料や農薬をできる限り使用せず、農業の持つ自然循環機能の発揮を指向する地域も増えてきていることから、今後はこれらの認証や表示が活用される機会がより増加すると考えられる。
このような認証や表示を活用し、地場産の農産物についての知識を持つことによって化学肥料や農薬の使用を低減したもの、あるいは地場産のものなど比較的エネルギー消費の少ない農産物をなるべく選択することは、環境負荷の軽減につながる「消費のグリーン化」の取組の一つといえる。
イ 家庭における省エネルギー行動による「消費のグリーン化」
不要な家電製品のスイッチを切る、節水に努める、通勤を自家用車からバスに切り替えるといった家庭における省エネルギー行動は、一般的に省資源の意味で行われる。しかし、このような行動は資源の有効利用に資すると同時に二酸化炭素などの環境負荷を低減する行動でもある。
例えば節水という行動を考えてみたい。上水道の運用に投入されるエネルギーはそのほとんどが電力によってまかなわれている(2-3-15図)。つまり節水は水資源の節約と同時に水道水供給に要する電力を節約することになり、同時に電力使用に伴う二酸化炭素を削減することになる。つまり、家庭における省エネルギー行動は資源、経済的負担の節約と同時に環境負荷の低減を図ることができるという点で「消費のグリーン化」であるといえる。
ウ 電力の選択購入による「消費のグリーン化」
家庭における省エネルギー行動による「消費のグリーン化」は、家庭におけるエネルギーの使用方法を見直すことによって環境負荷の低減を図るものであるが、より積極的な動きとして、環境負荷の低減を図った電力を選択して購入しようという取組が始まりつつある。
この仕組みは消費者が太陽光、風力などの環境負荷低減を図ったエネルギーで発電された電力を選択購入し、電力事業者のこのようなエネルギーの電源設備への投資を促すというものであり、すでに欧米ではいくつかの事例が知られている。
スウェーデンでは1996年(平成8年)に電力市場が自由化され、電気事業者及び電源の種類を自由に選択できる制度が取り入れられている。また消費者の選択指針として、前に述べた環境ラベルの仕組みが電力の選択に利用され、太陽光、風力といった電源別に一定の基準を満たせばスウェーデン自然保護協会が認証する環境ラベルが表示される。この仕組みはすでにノルウェーやフィンランドにも拡大されており、1999年(平成11年)1月には、スウェーデン国鉄はこの環境ラベルの認証を受けた電力しか購入しないことを決定した。
アメリカのカリフォルニア州では1997年(平成9年)から、ペンシルバニア州ではその翌年から太陽光、風力などによって発電された電力を選択購入できる制度が始まり、再生可能エネルギーから発電された電力であることを保証する統一基準とそれを保証する機関(Green-e)が設立された。この機関ではスウェーデンと同様に環境ラベルの認証を行い、消費者の選択の指針となっている(2-3-16図)。
わが国では実際に消費者個人が環境負荷の低減を図った電力を自由に選択購入できる状況にはなっていない。しかし、すでに民間団体である生活クラブ北海道と北海道電力が共同して「北海道グリーンファンド」の取組を進めているほか、東京電力では新エネルギーの導入に際して、通常の電力料金に一定額を上乗せして太陽光や風力発電設備の整備費として利用することを選択できる料金制度の検討を行っているなど、いくつかの動きが現れてきている。環境負荷を低減した電力の選択購入は、新たな「消費のグリーン化」の方法として今後大いに注目される。
エ モノの消費から機能・サービスの利用への転換による「消費のグリーン化」
消費者による環境保全へのアプローチである「消費のグリーン化」のもう一つの方向として、モノそのものの豊かさにこだわるのではなく、モノが提供する機能やサービスを利用するという消費のあり方が考えられる。モノの消費から離れることは、その製造のための資源、エネルギー、環境負荷が大幅に低減するというメリットを持つ。同時に、モノの消費に伴って支出するコスト、例えば維持管理費、設置収納のためのスペースなどが節減でき、経済的な負担軽減につながる可能性もある。
ここでは、人々の欲求が徐々にモノの量から質へ、さらにモノから機能・サービスへと移るという、「モノの消費から機能の享受」とでもいうべきニーズの変化に対応した取組について、「消費のグリーン化」の観点から考えてみたい。
(ア)自動車の共用化による「移動」という機能・サービスの利用
自動車は製造過程において大量の資源・エネルギーを消費し、走行時に多くの環境負荷を与えている。また家計に占める自動車の維持経費は鉄道、バス、タクシー、航空機など自動車以外の交通機関に支出する経費の総額を上回っており、経済的な負担も大きい。しかし、その利便性は他の交通機関を大きく上回っており、今後は利便性を維持しながら環境負荷を低減する自動車利用の方法が求められると考えられる。
その一つとして提案されているのが、1台の自動車を複数の世帯が共同で利用する「カーシェアリング(自動車共用)」の方式であり、現在ドイツのフライブルク市、イギリスのリーズ市などで実際の取組が行われている。
また、アメリカのサンフランシスコ地域で行われたカーシェアリングの実証試験では、近年技術的に改良が進んでいる電気自動車(Electric Vehicle=EV)が利用されるなど、走行面でも環境負荷低減に大きな役割を果たすことが期待されている。
国内でもいくつかの取組が始まっているが、ここでは、横浜市と神戸市における取組を取り上げてみたい。
a 横浜市における取組
横浜市のみなとみらい21地区においては、電気自動車(EV)を活用した都心における自動車共同利用システムの実証試験が行われている。これは平成11年9月から(財)自動車走行電子技術協会が行っているもので、都心地域において多人数で小型電気自動車を共同利用する仕組みである(2-3-17図)。
この試みは、同時に多摩ニュータウン内(東京都稲城市)で進められている、住宅地での自動車(セカンドカー)共同利用システム実証試験と連携している。この二つの取組は、鉄道を軸に、都心と郊外における自動車共同利用システムを有機的に連結する交通システムを目指すものであり、今後の取組が注目される(2-3-18図)。
b 神戸市における取組
神戸市においては、複数の民間企業の出資により電気自動車などをレンタルする会社が平成10年に設立され、市内移動の手段として利用されている。平成11年現在電気自動車40台を中心に53台の低公害車を導入し、また市内26か所に給電スタンドを設け、個人及び法人向けレンタルを行っている。
この会社が行っている自動車共用の取組が、「エコレンタカー定期券」と呼ばれるシステムである。これは定期券を購入した複数人で自動車を共用するもので、人数が多くなるほど金額が低くなる仕組みになっており、特に高層マンションが多く、駐車場の確保が困難な地域における自動車共用のあり方として注目されている(2-3-19図)。
c カーシェアリング(自動車共用)の可能性
国内のその他の地域においても、電気自動車などを活用したカーシェアリングの取組が行われている。愛知県豊田市での「Crayonシステム」と呼ばれる電気自動車の共同利用実験、神奈川県海老名市での電気自動車共用実験などが進行しており、各地域の実状に合わせた自動車共用の可能性が模索されている。
これらの取組はまだ始まったばかりであり、成果の検証は今後を待たなければならないが、環境負荷を抑えると同時に共用化による維持管理の負担軽減につながるというカーシェアリングの利点は次第に現実のものとなりつつある。将来的に多くの地域に導入されることになれば、消費者のモノの消費に対する考え方に変化を及ぼすことも考えられ、環境負荷の低減を図りつつ利便性、快適性を維持するための一つのモデルともなり得るであろう。
(イ)住宅ストックを活用した「居住」という機能・サービスの利用
a 住宅を取り巻く環境負荷
住宅投資は、わが国の国内総生産(GDP)の約6%を占める非常に大きな分野である。
その一方で、住宅建設などに伴って多くの資源やエネルギーが消費され、建築や解体などの建築工事に伴う廃棄物も大量に排出されている。例えば建築工事に伴って排出される建築系廃棄物は約3,800万t(平成7年度)と推計されており、土木系廃棄物と合わせた建設廃棄物全体の約4割に当たる。
加えて(社)住宅生産団体連合会によれば、建築から使用、解体に至る住宅のすべてのライフサイクルから排出される二酸化炭素(CO2)の量は約1億9,000万t(平成7年度。CO2換算。)と試算されており、わが国の二酸化炭素年間排出量の約15%に相当している。
また、住宅ストック戸数をフロー戸数(新規着工戸数)で除したものを住宅の建替サイクルと見る考え方もあり、これによるとわが国の住宅建替サイクルは約40年と試算され、諸外国に比べて短くなっている(2-3-20図)。住宅の建築解体に伴う環境負荷を低減していく上では、この点についても考える必要があろう。
このような状況に対応し、建設廃棄物の分別・再資源化への取組を一層強化するため、平成12年3月、第147回国会に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案」が提出された。
また、廃棄物に対する取組と同時に、省資源、省エネルギーや環境負荷の低減に資するような、長期間の利用に耐えうる良質なストックとしての住宅の建設も今後一層強く求められる。
b ライフステージに応じた居住の動き
今後は第1章第2節で述べたように、高齢夫婦世帯の増加や三世代同居世帯の減少などの少子高齢化による世帯構造の変化に伴い、後世代に引き継ぐ資産としての住宅の価値よりも、より利便性に富んだ居住空間としての住居を重視する動きが高まってくることが考えられる。
その一つが、人生のライフステージに応じた自由な住み替えである。例えば夫婦世帯の増加は必ずしも大きな床面積を持つ住宅を必要としないため、必要に応じて小さな住宅に住み替えたり、労働年齢に当たる期間では都市のマンションなどの共同住宅に住み、必要に応じてより広い一戸建ての住居への住み替え、高齢期を迎えて安全性、利便性の高い都市マンションへ再び移り住むといった居住スタイルが考えられる。これは住宅の機能面である「住む」というサービスを享受する住宅所有の考え方の一つであり、新規住宅建設に伴う環境負荷を大幅に低減するとともに、同時に各ライフステージにおいて重視する事柄(通勤や趣味など)との距離を最も短くするという生活の利便性や効用を高くする効果も得られると考えられる。
また、平成3年の借地借家法の制定により導入された定期借地権、あるいは平成11年12月に成立した「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により、平成12年3月から導入された定期借家権を活用し、従来の「住宅の所有」という概念にとらわれず、経済的負担を抑えつつ長期居住を行う方法も提案されている。環境負荷を低減しながら、よりよい居住空間と経済的負担の軽減を目指す事例の一つとして、建設省建築研究所が中心となって開発した「つくば方式」があげられる。
(ウ)広がりつつある機能・サービス利用の可能性
機能・サービスを利用するという、いわばストック活用型の消費形態はその他の分野でも進行しつつある。例えばアメリカのあるカーペット会社では、フロアカバーがパッチ状になっており、摩耗したところだけ持ち帰り、そこだけ取り替えるというサービスを行っている。また家電業界では、冷蔵庫を組み立てキットにし、家族構成の変化などに応じて冷凍庫や冷蔵部分の容積を変更可能にするアイデアに取り組んでいるところがあるなど、新しい「消費のグリーン化」の胎動を示唆する事例が現れ始めている。
しかし一方では、機能・サービスの利用による「モノを所有しない気楽さ」が、購入、使用、廃棄の流れを早めてしまい、結果として環境負荷を増大させる危険性を持っていることも忘れてはならない。今後、消費者には、環境負荷低減に向けて何が最も良い選択なのかを時と場合に応じて判断する能力が今まで以上に求められてくるであろう。
製品を供給する事業者サイドの環境配慮への取組
モノづくりのライフサイクルを通じて、事業者がその各段階において環境配慮のために以下のような具体的取組を進めていることを、平成11年版環境白書では記述した。
? 原材料調達段階での環境負荷については、まだ取組が遅れている。
? 製造段階では、原材料の使用量の削減、省エネルギー、再生資源の積極的利用によるリサイクルの促進や汚染物質の少ない製造工程への転換、廃棄物の減量などのように、同時にコストの削減に資する取組が多い。
? 流通・販売段階では、容器包装の減量化、環境負荷の少ない包装材料などの利用や物流の効率化に資する取組が行われている。
? 製品利用段階では、長期利用を進めるため、メンテナンス体制の整備、製品の性能追加のための体制整備や中古市場の確立などの取組が求められる。
? 廃棄・リサイクル段階では、産業廃棄物については、その性状に応じたリサイクルや適正処理を確保するため、分別、加工・処理、委託先への情報の伝達などを行うことが求められる。一定の製品廃棄物については、その製造業者などが引き取り、リサイクルを行うといった取組も進められている。
さらに、こうしたライフサイクル全体を見通して環境負荷を少なくする製品設計や製造のあり方をあらかじめ構築する「環境設計」が進展しつつある。
グリーン購入ネットワーク会員の取組と外部への波及
グリーン購入ネットワーク会員の取組には、その事業所内だけでなく、例えば取引先との関係を通じて外部に広く波及しているものもある。
例えば、ある事業所では「グリーン調達ガイドライン」を策定し、製品調達取引先に対して、有害化学物質の抑制、リサイクルの推進、省エネルギー設計といった環境配慮を盛り込んだ製品調達の考え方を提示し、理解・協力を求めている。また、調達する製品だけではなく、取引先の事業者のグリーン購入に対する姿勢そのものも評価し、より環境負荷低減につながる製品の調達を進めている事業所もある。
このような取組は、取引先事業所などのグリーン購入に対する方針にも影響を与え、その結果、環境に配慮した製品がより多く市場に出回ることになり、価格の低下に影響を与える効果を誘発すると考えられる。
また、特に地方経済にとって大きな役割を果たす地方公共団体がグリーン購入に取り組むことは、事業所の場合と同様に、価格低下に対して大きな波及効果を持つといえる。第1章第3節でも述べたとおり、都道府県や政令市に比べて区市町村のグリーン購入への取組はまだ十分進んでいないが、今後、これらの団体における取組が進めば、価格低下の動きはさらに進行すると考えられる。
ライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方
製品のもたらす環境負荷の低減を図るためには、原料採取・製造から廃棄・リサイクルに至る、製品のライフサイクル全体における環境負荷の低減を図る必要がある。
ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment:LCA)とは、その製品に関わる資源の採取から製造、使用、廃棄、輸送などのすべての段階を通して、投入された資源・エネルギーや、排出された環境負荷及びそれらによる地球や生態系への環境影響を定量的、客観的に評価する手法のことである。
LCAには定量的、客観的な評価が重要であるが、その困難さから手法についての共通の合意が得られておらず、現在ではまだ確立されたものとはなっていない。しかし、枠組み・段階についてはほぼ共通の認識が得られており、おおよそ次のようにまとめられる。
? ライフサイクルインベントリ分析
製品のライフサイクルにおける各過程において投入される資源・エネルギー(インプット)、排出される環境負荷、廃棄物(アウトプット)についての「入出力明細表(インベントリ)」を作成する段階である。
? ライフサイクル影響評価
?で得られた結果を基に、環境への影響の大きさと重要度を定量的、客観的に分析評価する段階である。
? ライフサイクル解釈
?及び?の結果から、環境負荷低減のための具体的な改善点を分析評価・解釈する段階である。
ここでは大きく3段階に分けたが、ISO14040では、これに加え「目的及び調査範囲の設定」、「報告」、「クリティカルレビュー(実施方法の適正さの確認)」についてもLCAの枠組みとして定義されている。
わが国でもすでにいくつかの事業者がLCA手法に取り組んでおり、製品の最適化設計を推し進める上で欠かせないものとなりつつある。
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル規格
環境ラベルについては、国際標準化機構(ISO)による国際規格化が進んでいる。
ISOでは環境ラベルをタイプ?型(第三者認証型)、タイプ?型(自己宣言型)、タイプ?型(環境情報表示型)に分類しており、その規格の概要と発行状況は、現在図のとおりとなっている。
事業者による環境負荷情報の表示例
事業者の中には、製品の環境負荷情報の表示に積極的に取り組んでいるところがある。
ある事業者では、「環境調和型社会における環境ラベルのあり方検討会報告書」に示された製品環境情報開示シートを基に、国際標準化機構(ISO)の分類によるタイプ?型(環境情報表示型)の環境ラベルを作成し、環境情報を詳しく表示している。
グリーンコンシューマー東京ネットの取組
東京都では、安全で環境への負荷の少ない消費生活を推進するため、環境に配慮した製品・サービスを積極的に選択、購入することを実践し、普及を図る都民運動の母体として、平成9年12月に「グリーンコンシューマー東京ネット」を設置した。
同ネットでは、毎年10月に「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施しており、再生紙利用商品、詰め替え商品、省エネ商品などの環境配慮型製品の普及や減包装、マイバッグ持参運動に取り組んでいる。平成10年に初めてこのキャンペーンを実施した時点では、都内のスーパー、生協などを中心に462店舗が参加したが、平成11年にはさらに拡大し、大手コンビニエンスストアから百貨店まで5,108店舗の参加を得て実施された。
キャンペーン期間中、店舗側は環境配慮型製品の専用コーナーの設置や割引販売などの取組を展開し、消費者団体側は参加店舗の店頭でのPR活動を担うなど、消費者、事業者、行政の3者の連携による取組が行われた。
このキャンペーンに合わせてプライベートブランドの環境配慮型製品を開発した流通業者や、ナショナルブランドの製品を開発した製造業者が出るなど、事業者の活動に影響を与えるとともに、消費者の関心が、ようやく環境に配慮した生活の入り口である「製品・サービスの選択、購入」へ向かう兆しが見えてきたと同ネットでは分析している。
同ネットでは、今後さらにこのキャンペーンへの参加を他府県にも働きかけ、規模の拡大と内容の充実を図り、積極的なグリーン購入に努めていくこととしている。
「つくば方式」による高耐久住宅への取組
つくば方式は正式には「スケルトン型定期借地権住宅」といい、建設省建築研究所が中心となって開発した仕組みである。
これは集合住宅を、建物を支える構造躯体などの基本性能部分(スケルトン)と間取り・内装に当たる部分(インフィル)に分け、スケルトンは100年以上使用できる高耐久性を持つよう建築し、インフィルは家族構成の変化や子供の成長、あるいは高齢者の生活様式にあわせて自由に配置、変更できるようにしたものである。
土地を所有すると相当の経費がかかるため、30年以上経過後に土地所有者が借地上の建物を買い取ることができる「建物譲渡特約付き定期借地権」に基づいて居住希望者は30年間の借地権を得て、その上に建築する。30年後には土地を返却するが、特約に基づいて土地所有者に良好に管理されたスケルトン部分のみを買い取ってもらい、今度はスケルトンの借家権を得て引き続き居住を続ける。この借家の家賃が高ければ一般の借家と変わりがないが、つくば方式では、居住者はスケルトン部分の売却によって得た金額を向こう30年間分の家賃として土地所有者に預託し、月々支払うべき家賃と30年間に渡って相殺することで、低家賃での居住を可能にしている。もちろんこの間のインフィルの自由な変更は可能であり、高齢者になっても低廉な家賃で居住することができる。
60年後にはスケルトンの借家権も終了し、居住者はすべて土地所有者に返却するか、あるいは市場価格による家賃で再契約するかを選択することになるが、60年間は低家賃で自由度の高い居住が可能となり、かつ高耐久性を持つスケルトンの建築により、建物の取り壊しに伴う建築廃棄物を大幅に低減することも可能となる。
つくば方式では住居は最終的に居住者の「所有」にはならないが、快適な住生活を十分に享受することができる。すでにつくば市に2棟、東京都世田谷区に1棟がこの方式で建てられており、今後の居住のあり方の一つとして注目されている。