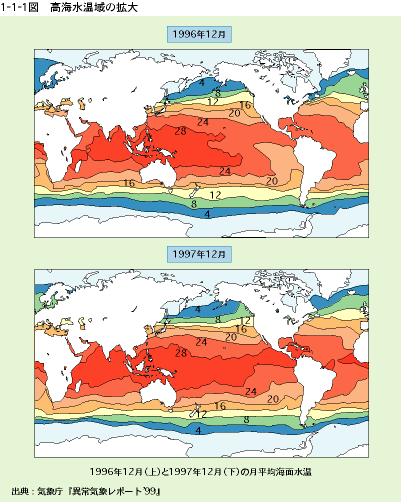
1 地球規模での環境問題の深刻化と認識の深まり
(1)地球温暖化への国際的対策が急務である
ア 海面の上昇
気温の上昇は、海水の膨張、極地及び高山地の氷の融解を引き起こし、その結果として海面の上昇を招く。この場合、海岸線の移動により多大な影響が生じると考えられる。人口1,000万人以上の世界の大都市のうち、16都市は沿岸域にあり、沿岸の人口は世界的に急増している。特に海面上昇の影響を受けるおそれがあるのは、モルディヴやマーシャル群島、キリバスやトンガなど、今でも土地の高さが海面から数mしかない小島嶼国や、バングラデシュのガンジス・ブラマプトラ川やエジプトのナイル川、ナイジェリアのニジェール川などの河口のデルタ地帯であろう。仮に海面が50cm上昇した場合、適応策がとられなければ、高潮被害を受けやすい世界の人口は、人口増加を考慮しなくても、現在の約4,600万人から9,200万人に増加すると予測されている。また、バングラデシュは、海面が1m上昇すると総国土面積の17%が冠水し、現在の人口密度から約7,000万人が影響を受けることになるという予測もある。
また、北極で海水が融解すると北大西洋の塩分濃度が下がり、表層水の深層への潜り込みが阻害される。この変化によって、北向きの熱輸送と赤道を横切る熱交換が弱まり、海洋の循環が変化するおそれも指摘されている。
イ 災害の増加
平均的な地球の気候がほんのわずかに変化しただけで、ハリケーン(台風)や激しい雷雨、それに暴風といった異常気象の程度が変化する可能性があるとの意見もある。実際、高海水温域の拡大(1-1-1図)がハリケーンの発生頻度を高めた例として、1995年(平成7年)の大西洋があげられる。大西洋の海面水温の最高記録を更新したこの年、同地域では過去49年の平均年間発生数の2倍である19個のハリケーンが発生している。
前述のデルタ地帯のように海面の上昇による洪水のリスクが増加している地域で、この暴風雨による被害が加わると、激甚な被害を発生させることが予想される。
ウ 食料危機
異常気象や病害虫の増加を考慮しなければ、世界全体としての食料需給はバランスするとされているが、増産地域、減産地域が生じ、格差は大きくなる。熱帯、亜熱帯では、人口が増加する一方で、食料生産量が低下し、乾燥、半乾燥地域を含め、貧困地域の飢饉、難民の危険が増大するといわれている。
エ 生態系への影響
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)地球温暖化第2次評価報告書などによれば地球の年間平均気温の上昇は、多くの地域の森林の生育・再生能力に影響を与える地域気候の変動を引き起こし、気温と降水量の変化により現存する世界の森林の約3分の1が植生タイプの変化にさらされると予想されている。今後100年間に予想される地球平均で1℃から3.5℃という温暖化は、国土が赤道方向へ150〜550km移動する、あるいは高度が下方へ150〜550m移動する場合に相当する。これは、100年間での樹種の移動速度4〜200kmと同等もしくはこれを超えるため、植生が気温の変化に適応できず、新たな樹種によって更新される前に消滅する森林が現れると予想される。また、森林の転換期には森林の喪失による炭素の放出と、森林の成長までの炭素の取り込み量のバランスにより、大量の炭素が大気中に放出されると予想される。さらに、地球温暖化が進んで、シベリアの永久凍土(ツンドラ)が解凍されると、1分子当たり二酸化炭素の21倍という温暖化効果の高いメタンガスが大量に放出される可能性があり、温暖化に歯止めがかからなくなるおそれがある。
気候変動は動物の生息域にも影響を及ぼし得る。最も影響が予想されるのは極地方であろう。北極圏は覆った氷が鏡のように太陽熱を跳ね返しているが、氷が解けて海面や陸地が露出すると熱を吸収しやすくなり、温暖化が特に加速される。「米国地球変動研究計画」によるとアラスカは過去30年間、10年ごとに1℃ずつ気温が上昇していると報告されており、北米最大のベーリング氷河が年々縮小している。このような温暖化が続くと、より温暖な気候に適した動植物の侵入やエサになる動植物の減少などを招き、シロクマやペンギンといった極地固有の種が絶滅することも考えられる。極地以外においても、1994年(平成6年)にジンバブエでネズミの個体数が増え、穀物が壊滅的被害を受けたが、これは、それに先立つ6年間の干ばつにより、ネズミを捕食する動物がいなくなってしまったためと推測されている。このように、気候条件の変化は自然の中で病害虫等の個体数を一定に保っている捕食者と被食者の関係を崩し、生態系に著しい影響を及ぼすと考えられる。
また、海中においても温度の変化は生物に影響を与える。例えばサンゴ礁の白化現象については、これが初めて知られるようになったのは1980年代半ばで、季節風、海洋学的要因、気候要因の複雑な組合せによるとされてきたが、1998年(平成10年)に観測された熱帯地域の多くの海域での白化現象は、海洋温度が上昇したエルニーニョ現象もその一因と考えられている。
オ 健康への影響
温暖化の影響として、熱波の激しさと回数の増加もあげられる。激しい熱波に見舞われると、暑さのために死亡する人が急増する。1995年(平成7年)7月にシカゴを襲った熱波は4日間続き、その間に726人が熱中症や脱水症などで亡くなっている。
また、温度や降雨量などの要因が、感染症の病気の媒介動物や病原菌の数、分布に変化を与え、そして人々の健康に影響を及ぼすと考えられる。例えば、蚊は、気温と降雨量の変化に極めて反応しやすく、自分に好ましい環境条件が整ったときにその分布域を拡大していく。したがって、気温が上昇すれば、蚊が媒介するマラリアやデング熱、黄熱病、数種類の脳炎といった病気の発生数が増加するおそれがある。気温の上昇が直ちに降雨量の増加をもたらすものではないため、降雨量に影響される蚊が一概に増加するとはいえないが、すでにマダガスカルやエチオピアの高地では、マラリア患者数の増加が報告されており、また、ルワンダでも、1987年(昭和62年)に記録的な高温と降雨に見舞われ、免疫のない住民の住む高地でマラリアが発生するなど、これまで病気が発生していなかった地域での流行が報告されている(1-1-1表)。
カ 地球温暖化への国際的対策の強化
地球温暖化を促進させている温室効果ガスについては序章で触れたところであるが、これらガスの排出原因として、まず二酸化炭素は化石燃料の燃焼が主な原因であり、メタンについては農業(家畜の反すう、し尿や水田等)や廃棄物の埋立て、一酸化二窒素については燃料の燃焼や廃棄物の焼却などがあげられる。ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、オゾン層破壊物質であるCFC等の代替物質として、冷蔵庫、空調機器等の冷媒などとして近年使用が急増している。なお、クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)も温室効果を有するが、すでにオゾン層保護の観点から規制が実施されている。
温暖化の寄与度が最も大きい二酸化炭素の1996年(平成8年)の国別排出状況を見ると、アメリカが22.2%、中国が14.1%、ロシアが6.6%、日本が4.9%で、この4か国で全体のおよそ半分を占めている(1-1-2図)。温室効果ガスの排出量については、1997年(平成9年)12月、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において、2008年から2012年までの間の削減目標を定めた「京都議定書」が採択された(1-1-2表)。この議定書は、遅くとも2002年までに発効させることが必要であることから、現在、この議定書の実施に必要となる京都メカニズムのルール等について2000年11月のCOP6で合意すべく、1998年(平成10年)11月にアルゼンチンのブエノスアイレスで開催されたCOP4において、今後の国際交渉の道筋を定めた「ブエノスアイレス行動計画」が採択されている。また、1999年(平成11年)10月ドイツのボンで開催されたCOP5でも、COP6に向けた準備作業を強化することを確認している。
さらに、世界の二酸化炭素の排出量の推移を見ると、産業革命以後、特に第2次世界大戦以後、大きく増加している。西側先進国は、1970年代の2度の石油危機を経ながらも経済成長をしつつ二酸化炭素の排出を減少させた時期を経験したが、近年は増加傾向にある。一方、開発途上国の排出量はほぼ一貫して増加しており、近年特に増加傾向が著しくなっている(1-1-3図)。こうした状況を受けて、これまで地球環境に大きな負荷を与えてきた先進国としてはトップランナー方式に基づく自動車、家庭用電気製品、OA機器等に対する厳しい省エネ基準の設定、燃費の良い自動車の普及促進や、太陽光、風力発電、燃料電池等の新エネルギー普及促進のための技術の研究開発、導入補助、電力会社による電力買上げ、また、ヨーロッパの一部の国で導入が進んでいる炭素税を含む税、課徴金、今後導入が予定される排出量取引等による経済的措置など、各国ごとの事情を踏まえつつ様々な二酸化炭素排出削減対策を推進するとともに、途上国に対し資金面での支援と技術面での支援を行っていく必要がある。
(2)オゾン層の保護対策の徹底が必要である
地球上のオゾン(O3)はその大部分が成層圏に存在しており、オゾン層を形成している。このオゾン層は太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を守っているが、この大切なオゾン層が近年クロロフルオロカーボン(いわゆるフロン)などの人工の化学物質によって破壊されていることが明らかになってきた。フロンは炭化水素の水素を塩素やフッ素に置き換えた物質の総称で、ほとんど無毒なため冷蔵庫やエアコン等の冷媒などとして、現代の生活を支える上で広く使用されてきた。フロンは化学的に安定しているため、対流圏ではほとんど分解されず成層圏に達し、ここで強い紫外線によって分解され塩素原子を放出する。この塩素原子1個が数万個のオゾン分子を連鎖的に破壊するため、オゾン層の破壊が長期にわたって続く。
成層圏オゾン層の破壊により、地上に到達する有害な紫外線の量が増加し、人の健康や生態系などに悪影響を及ぼすおそれがある。オゾン層破壊に伴って皮膚ガンの発生率がどの程度上昇するかは、ガンのかかりやすさの個人差や日焼け止めなどの個人的予防行為など不確定な要素が大きいため、大まかな推定しかできないが、国連環境計画(UNEP)がモントリオール議定書に基づき設置した環境影響パネルの1994年(平成6年)の報告では、成層圏オゾンの1%の減少で皮膚ガンの発生が2%増加すると推定されており、また、オゾン全量が1%減少すると、白内障の発生率が0.6から0.8%増加すると予想されている。
このように、オゾン層の破壊は生物に大きな影響を与えると予想されるが、国連環境計画(UNEP)の1998年(平成10年)の報告によると、1997年(平成9年)に改正された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(モントリオール議定書)に基づく生産規制等を全ての締約国が遵守すれば、オゾン層を破壊する要因となっている成層圏中の塩素及び臭素濃度は、2000年より前にピークに達し、オゾン層破壊のピークは2020年までに訪れる。また、成層圏中のオゾン層破壊物質濃度は、2050年までには1980年以前のレベルに戻ると予想されている。
モントリオール議定書には、クロロフルオロカーボン(CFC)の生産を先進国では1995年(平成7年)までに、開発途上国では2009年までに、全廃することが定められており、議定書採択当時スプレー缶の高圧ガス、成型用の発泡材、溶剤、冷蔵庫やエアコンの冷媒等として広く使用されていたCFCの生産はUNEPの報告によると、1986年(昭和61年)から1997年(平成9年)までの間で85%も減少している。CFCの他に、四塩化炭素、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハロン、臭化メチル、1,1,1-トリクロロエタンなどのオゾン層破壊物質が制限対象となっており、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンの生産は減少しているものの、HCFCと臭化メチルの生産はなお増加している。
同議定書では、先進国におけるHCFCと臭化メチルの段階的削減に関して、臭化メチルは2004年末までに全廃、HCFCも2019年までに現存する機器への補充用を除いて消費量(=生産量+輸入量−輸出量)の全廃を定めている。また、1999年(平成11年)12月に開催された、同議定書第11回締約国会合で、HCFCの生産量についても先進国は2004年から、途上国は2016年から規制を導入することが決定された。
先進工業国におけるCFC生産がすでに禁止されたため、取組の焦点は開発途上国に移りつつあり、同議定書では、途上国における生産量を1999年(平成11年)から段階的に削減し、そして2009年末までに生産を全廃することを定めている。実際に、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エジプト、ガーナ、ベネズエラなどではすでに消費量が減少し始めているが、この一方、中国、インド、フィリピンといった人口の多い国々では増加し続けている。UNEPの報告によると、例えば中国では、1986年(昭和61年)と比較すると1997年(平成9年)では42%増加している。
モントリオール議定書締約当初、先進国の取組によって大きく前進したオゾン層破壊物質規制であるが、途上国での消費量が増加している今日、先進国、途上国いずれにおいても、オゾン層破壊物質からの完全な脱却を図るための様々な行動をとっていく必要がある。開発途上国に対する支援措置として、同議定書に基づく削減、全廃スケジュールの達成を支援するための「モントリオール議定書多数国間基金」が設立され、先進各国が同基金を通じて途上国の転換プロジェクトに積極的に資金提供を続けている。途上国における円滑な規制実施のためには、資金援助及び技術移転等による一層の支援が必要である。
また、過去に生産されたオゾン層破壊物質を充填した冷蔵庫等の機器が廃棄される際、オゾン層破壊物質が大気中に放出されるおそれがあるので、その回収等の推進も必要である。
(3)酸性雨対策として原因解明と国際的な取組が重要である
酸性雨とは、石炭や石油などの化石燃料の燃焼などに伴って、硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中へ放出されることにより、これらのガスが雲粒に取り込まれて複雑な化学反応を繰り返して最終的には硫酸イオン、硝酸イオンなどに変化して降下する現象をいう。現在、酸性雨という言葉は、酸性の降雨のみを意味することは少なく、乾性降下物も含む概念として使われている。酸性雨は植物の葉の代謝を妨げたり、土壌を酸性化させ、また、湖沼水の水素指数(pH)の低下を招き、湖沼の生物や周辺の森林など生態系にも影響を及ぼすことが懸念されている。
「酸性雨(acid rain)」という用語を初めて使ったのはイギリスの化学者ロバート・スミスである。イギリスは早くから燃料を石炭に頼っていたため、大都市や工業地帯で18世紀からばい煙や硫黄酸化物に悩まされており、1852年にすでに酸性雨に関する報告書が著され、都市域で硫酸による織物の退色や金属の腐食が生じることが報告されている。
さらに、酸性雨はこうした局地的な問題にとどまらず、気流などにより長い距離を移動し、発生源から500〜1,000kmも離れた地点で観測されるなど、国境を越えた国際的な問題ともなっている。また、森林植物の枯死や建築物、銅像、石像やステンドグラスなどの毀損と酸性雨の関係なども指摘されている。
スウェーデンでは湖沼の酸性化が進行し、1977年(昭和52年)から湖沼への石灰の散布を始め、1980年代半ばからは農地にも石灰を散布し始めた。酸性雨の深刻な影響を受けてきたヨーロッパ諸国は、1979年(昭和54年)に「長距離越境大気汚染条約」を締結し、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量を規制するといった国際的な酸性雨対策を講じている。
同様の事態はアメリカとカナダの国境付近でも生じており、1980年(昭和55年)には両国間で越境大気汚染に関する合意を発展させるための覚書を交わし、越境大気汚染条約締結交渉を行うための調整委員会を設けることを合意している。
酸性雨対策はヨーロッパや北アメリカにおいて進んでいるが、他方、世界人口の3分の1強を占め、めざましい経済発展を遂げている東アジアでは、発電などのエネルギーを石炭に依存する国が多く、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量が大幅に増加している。
大気汚染や酸性雨の影響の深刻化が懸念される東アジアでは、酸性雨の影響の未然防止を図るため、地域協力の推進が急がれている。雨水、土壌・植生、陸水などのモニタリングとそのネットワーク化を行い、関係各国が酸性雨に関する測定データや酸性雨問題についての共通認識を持ち、その原因物質の排出抑制対策を共同し、協調して着実に進めていくために、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク」(平成12年3月現在、10か国が参加)の構築に向けた取組が行われており、1998年(平成10年)4月から試行稼働が実施されている。
酸性雨の防止のためには、その主たる原因となる硫黄酸化物、窒素酸化物の排出を抑えることが重要である。このための排煙脱硫や脱硝の装置が開発されているが、こうした装置の設置には費用がかかるため、経済的余裕のない開発途上国などではなかなか導入が進んでいない。経済発展のめざましい地域への火力発電プラントなどの輸出に際して地域環境の保全を図るといった国際ルールを導入するとともに、現地の事情に合わせた小型、簡易、安価な装置を開発し、その技術を供与して相手国の環境産業の育成に協力することも必要であろう。
(4)生物多様性の減少への対応が求められている
ア 熱帯林の減少
森林は海岸線から亜高山帯に、熱帯から亜寒帯に広がり、その形態も多様性に富んでいる。例えば常緑と落葉、針葉と広葉、閉鎖林と疎林などである。森林は地球の生命を維持している体系のうちの重要な部分を占め、何百万という生物種を育んでおり、この多様な生物が広範な資源を提供している。また、大気と気候を調節するための重要な役割を果たしており、炭素の大貯蔵庫となっている。同一地域内の森林のある地域とない地域を比較すると、前者の方が概して穏やかで湿気があり、変化の少ない状態を提供して局地的な気候を緩和するとともに、水の循環を調整し、過度の侵食から土壌を保護するとともに氾濫などの害を与える流水量の変化を緩和している。この流水量の緩和は魚類の産卵地保護につながり、主要な漁業の維持にも役立っている。
熱帯林の減少はその地域の生態系の破壊のみにとどまらない。森林の働きについては前述のとおりであるが、この中でも顕著に影響が現れると考えられるのは「水系」の崩壊である。赤道を挟む南北15度の熱帯地方の多くは年間降雨量が3,000mmを超え、全陸地の降雨量の半分が集中している。降雨の破壊力を緩和し、流出速度を緩めている森林が減少すると、山崩れなどの災害や、土壌流出をもたらし、さらに、植物の蒸散作用による冷却効果も失われ、苛酷な気象条件に支配されるようになると予想される。この結果として、動植物は減少し、様々な民族固有の森林文化も失われていくと考えられる。
イ 野生動植物種の減少
国際自然保護連合(IUCN)によると、近年の試算では、恐竜が絶滅した今から約7,000万年前と比べて、動植物の絶滅の割合が1,000から10,000倍程度に増加しているといわれている。
絶滅の原因の39%が種の移入、36%が生息・生育地の破壊、23%が狩猟と意図的な根絶とされている。種の移入については、在来の近縁種との交雑の進行、同種の在来個体群との交雑による遺伝的汚染、他の種の捕食や生息場所の占奪による在来種の圧迫などによって生態系がかく乱されるおそれがあり、特に島嶼に生息・生育する種は家畜、ペットその他の移入種の影響を受けやすい。また、生息地の破壊については、本来人の手が加わらないことで種を保ってきた湿原植生や高山帯植生などの生息・生育地が荒らされる例や、逆に二次林や農耕地のように適度に人の手が加わることで多様な生物相を保ってきた二次的自然環境が、レクリエーション施設や住宅地への転換の進行に伴い減少しつつある例があげられる。狩猟と意図的な根絶については、特定種への重大な脅威になると同時に、食物連鎖を通じて他の多くの種に影響を及ぼしている。例えばオオカミは家畜や人への被害を理由に次々と絶滅に追いやられていったが、これに伴って草食獣が増加し、植林地や本来保護すべき植生が被害を受けるといった影響が現れている。アメリカのイエローストーン国立公園では、1923年(大正12年)以降姿が見られなくなったシンリンオオカミを、本来の生態系を取り戻すため、1995年(平成7年)に公園内に放した。
全ての種は種内に遺伝的多様性を保持しており、この遺伝子レベルでの多様性を保全することは生物多様性を保全する上での重要な課題である。
同一種と分類される中にあっても、島嶼や山地等地理的に隔離された地域個体群の間では、一般に、地域ごとに適応した異なる遺伝子を持っており、種内における遺伝的多様性を保持している。種内の遺伝的多様性を保全するためには、こうした地域個体群を保全することが重要であるが、現在、様々な人為的な影響により、地域個体群の消滅が進行している。個体の人為的な移動・移入や生息環境の悪化、移入種との競合などがその例で、個体数が著しく減少している種については、遺伝的多様性の低下が懸念される。
また、農牧業の発展も単一種に依存する傾向を強めると、生物多様性の減少をもたらすと考えられる。農業は12,000年前から発達し、数千種もの作物が栽培されてきたが、今日では百種にも満たない作物が世界の食料のほとんどを占めているといわれる。広い範囲で単一種が栽培されることにより、地域的な多様性が失われ、環境の変化や病害虫に対して壊滅的な被害が生じるおそれが高まっている。
しかし、遺伝的多様性の保全は、生物多様性保全の中でも比較的新しい概念であり、その構造やかく乱などの状況は十分に把握されておらず、現状では、遺伝的多様性が把握されないまま多くの地域個体群が消滅している。今後遺伝的多様性を適正に保全していくために、地域ごとのレッドデータブックの作成などを通じ、現状を正確に把握し問題点を抽出することが急務である。
野生生物の減少の原因としては、装飾品やペット、医薬品の原料としての世界的な取引や、密猟などが考えられる。不正取引については1-1-6図に示すとおり原産地域としてアフリカ、アジアが全体の約65%を占め、密輸先としてヨーロッパが40%を超えている。
このような野生生物の国際取引を輸出国と輸入国が協力して規制することで、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図ろうとするのが、1973年(昭和48年)3月にワシントンで採択された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(いわゆるワシントン条約)である。また、1975年(昭和50年)には、特に水鳥に注目し、その生息地として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を進めることと、湿地の適正な利用を進めることを目的にした「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(いわゆるラムサール条約)がイランのラムサールで採択された。
しかしながら、いずれも特定の行為や特定の生息地のみを保全の対象としており、例えば熱帯雨林のように、多様な生物の生息地を保全する国際的な取り決めはなかった。そこで、このような生物の多様性を保全するため、1992年(平成4年)地球上のあらゆる生物の多様さをそれらの生息環境とともに最大限に保全し、その持続的な利用を実現し、さらに生物の持つ遺伝資源から得られる利益の公平な分配を目的とした生物多様性条約が採択された。この条約は、生物多様性保全のための国家戦略の策定、保全及び持続可能な利用のために重要な生物多様性の構成要素の特定及び監視、保護地域体系の確立、絶滅のおそれのある種の保護・回復、生物資源の持続的な利用、アセスメント制度の導入などを締約国に求めている。
(5)廃棄物の輸出を規制する必要がある
有害廃棄物の越境移動は、セベソ事件に代表されるように1980年代前半はヨーロッパ内での移動にとどまっていたが、1980年代後半になるとアフリカや南米諸国に急速に広がり始め、越境移動した有害廃棄物が適正に処理されない事例が発生している。
有害廃棄物の越境移動による不適切な処理事例を契機として経済協力開発機構(OECD)や国連環境計画(UNEP)等で防止対策が検討され、「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が1989年(平成元年)3月、スイスのバーゼルで開かれていたUNEP主催の外交会議で採択された。
このバーゼル条約で規制の対象となるのは、?有害廃棄物、?その他の廃棄物である(1-1-3表)。
加盟国の一般的責務としては、発生国での処分、輸入禁止を宣言した加盟国への輸出や非加盟国との輸出入の禁止があげられる。また、輸出を行うに際しては、輸入国及び輸送の通過国に対し、その旨を通知し、事前に同意を得ることとされている。
また、通報・同意なしに、又は虚偽の記載の下に越境移動をすることや結果的に不適切な処分を行わざるを得なくなる越境移動行為は不法取引となり、その原因が輸出国又は輸入国のいずれかにあるかが明らかな場合は、その原因国の関係者が原則として30日以内に回収等の措置を講じることとされている。
バーゼル条約による有害廃棄物などの越境移動に関する国際的な仕組みができたものの、その実効性を確保していかなければならない。
これまで、四方を海で囲まれている日本では、廃棄物が外国から輸入されたり、外国に輸出されて処理されることは困難であろうと考えられていた。しかし、平成11年12月には、「再生用古紙」と偽って注射器など医療廃棄物を含むゴミが日本からフィリピンに違法に輸出されていたことが判明し、翌12年1月に日本へ送り返されるという事件が発生した。今後、こうした事件を繰り返さないために、水際での取締りが重要さを増すとともに、排出者の責任についても検討が必要になってこよう。
なお、1995年(平成7年)第3回バーゼル条約締約国会議において先進国から開発途上国への有害廃棄物の移動を禁止する趣旨の条約改正が採択されたが、開発途上国における環境対策を防止する上でいかなる国への有害廃棄物の移動を禁止することが効果的かといった観点から、今なお国際的な議論が継続して行われていることもあり、現在のところ発効の目途は立っていない。
(6)残留性有機汚染物質が拡散している
残留性有機汚染物質(POPs)とは、DDTやPCB、ダイオキシン等残留性などの性質を持つ化学物質のことである。アジェンダ21を受けて1995年(平成7年)に国連環境計画(UNEP)が開催した政府間会合において「陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」(世界行動計画)が採択され、この中で国際的にPOPsの排出の根絶・低減等を図るため国際条約等の法的拘束力のある文書を策定することを求めている。
POPsは、排出された国において人や環境に悪影響を及ぼした後、海流や気流、渡り鳥や回遊魚など様々な移動メカニズムによって地球全体に広がり、最終的には極域に集積する。また、一般に脂溶性であり生物によって高濃度に濃縮される。このため、北極圏地方に住むイヌイット族やシロクマ、海獣の体内に高濃度で検出されるほか、北欧、カナダ等の高緯度地域における人や環境への影響が生じている。
このように、POPsは第一義的には排出国においてその国民の健康に被害が生じる問題であることから、主な使用国である途上国においても積極的に対策を講じようとする意欲は強い。しかしながら、化学物質の適切な管理に必要な能力開発、組織体制の整備等が不十分であること、POPsと代替品の価格差が大きく代替品の購入が困難であること、POPsの生産を中止し、代替物質を生産するための技術と資本が不足していることなどが障害となっている。現在行われている条約化の作業を進めるとともに、先進国による途上国への支援が望まれる。
(7)環境への認識の深まりが環境保全行動につながる
従来、環境問題は、環境汚染、生態系破壊などの問題がそれぞれ個別の問題として認識されているだけであったが、テレビ、パーソナルコンピュータなどの情報機器やマスコミ、インターネットなどの媒体といったものの普遍化に伴って、多くの地域で共通して起こっている問題であるという認識が浸透し、気候変動、生物多様性の減少といった、国・地域単位だけでなく、地球規模での対応が求められる問題になっていった。
世界の科学者、経済学者などからなるローマクラブは、人口増加や環境悪化などの現在の傾向が続けば、100年以内に地球上の成長は限界に達するという「成長の限界」報告書を1972年(昭和47年)に公表し、成長から世界的な均衡へ移ることの必要性を唱え、環境問題が地球規模のものと認識される第一歩となった。さらに1980年(昭和55年)には、アメリカが、漁業資源・森林・動植物種の減少、地球の水や大気の悪化などが生じるであろうと結論付けた「西暦2000年の地球」報告書を公表している。この報告書では、オゾン層の破壊や地球温暖化などの問題についても予測しており、これによって「地球環境問題」という認識が確立した。
こうした地球環境保全の動きと歩調を合わせるように、国連でも1972年(昭和47年)スウェーデンのストックホルムで「かけがえのない地球(Only One Earth)」をキャッチフレーズにした国連人間環境会議が開催され、先進工業国においては経済成長から環境保護への転換が、途上国においては開発の推進と援助の増強が重要であるとされた。
さらに、これから20年後の1992年(平成4年)には、ブラジルのリオデジャネイロで、環境と開発に関する国連会議が開催された。「地球サミット」と呼ばれるこの会議では、温暖化防止のための「気候変動枠組条約」や「生物多様性条約」への署名が始まるとともに、この会議で明らかにされた「持続可能な開発」という考え方に基づき、「環境と開発に関するリオ宣言」、「アジェンダ21」、「森林原則声明」が合意された。この会議は、国連加盟の約180か国が参加し、このうち約100か国で元首又は首相が出席するという、かつてない大規模かつハイレベルの会議となった。
このように、国連など国家間で世界的な枠組みが検討される一方、個人や民間団体レベルでも環境保全を目的とする世界的な団体が組織され、多くの人々の支持を受けて活動を行っている。例えば1961年(昭和36年)に設立された世界自然保護基金(WWF)は、全世界で会員数470万人を数え、更に1万の会社、団体が会員や寄付者となっている。
酸性雨に代表されるような環境問題が起こっているヨーロッパにおいては、規制よりも、もっぱら超高層煙突による排気の拡散に頼っていたイギリスが1987年(昭和62年)に酸性雨対策を実施する方針を打ち出し、サンデー・タイムズ紙に「環境問題は今や最大の政治問題になった」旨の評が掲載されるなど、環境問題への認識が高まった。ドイツにおいては1998年(平成10年)の国政選挙後、「社会民主党」と「90年連合・緑の党」による連立政権が誕生したが、環境問題を政治活動の主目的に掲げる「緑の党」は、エコロジー運動の思想に支えられて、ドイツの他にもベルギー、フィンランド、ルクセンブルク、スウェーデン、イタリアなどで相次いで国会に議席を得ており、ヨーロッパの人々の環境問題への意識の高まりが国政面に影響を与えている。
環境への影響が目に見えて分かることで環境問題に関する認識が深まり、環境保全の行動へとつながっていくと考えられる。こうした意味でテレビ、新聞といったマスメディアや、インターネットのような手軽な発信手段の充実が地球規模での環境問題に対する認識の深化に役立っていると考えられる。
情報化社会においては、生活の様々な場面で利便性が向上するものと考えられているが、同時に環境に対しても大きな影響を及ぼすものと予想される。
情報通信の活用は、人や物の移動の代替、ペーパーレス化、エネルギー消費の的確化などを通じ、様々な分野で省エネルギー効果を有し、二酸化炭素排出量を削減するなど、環境負荷の軽減につながることが期待される。
他方で、情報通信の活用は、情報提供による活動の動機づけ、効率化による余暇時間などの創出などにより、諸活動の活性化を促すほか、情報通信設備の製造や運営に伴う資源やエネルギー消費を増大させるなど、環境負荷を大きくすると懸念される面もある。したがって、情報と環境の関係を考える場合、プラスとマイナスの双方の効果を総合的に考慮する必要がある。
これまで、情報化を含め社会経済活動の拡大、高度化により、人と物の流れは加速化し、また相互に誘発され、物流は高速化かつ拡大してきた。これにより、エネルギー消費などを通じた環境への負荷は増加し続けている。先に見たように情報化の一層の進展は、環境への負荷を削減する可能性を有し、また、環境情報の適切な活用による環境対策の一層の効率化に資するものと考えられる。しかしながら、これまでの情報化の過程で、業務部門の電力消費が増大を続けていることも事実である。これら情報化と環境への影響については、第2節で詳しく検討する。
サンゴ礁の白化現象
サンゴ礁は「海中の熱帯林」と言われるほど生物多様性の豊かな生態系である。サンゴ礁域でとれる魚は年間25,000tにも及ぶと推定されており、特にフィリピンからインドネシアにかけては、約2,500種、全海洋魚種の4分の1が生息するとされている。
サンゴの組織中には、褐虫藻と呼ばれる単細胞の藻が共生してサンゴに栄養を供給している。この藻は水温に敏感で、海水温が上がるとサンゴから離脱するため、サンゴは色を失って白くなり、やがて栄養不足になって死滅してしまう。
森林の減少と文化の喪失
イースター島はほとんど樹木のない不毛な景観を呈しているが、近年の花粉などの分析によると、この島に初めて人が住み着いたといわれる5世紀頃は、種類数こそ少ないものの高木を含む植生が島を覆っていたと予想されている。しかしながら、もともと火山島で、年間を通して流れる川はなく、火口湖以外には湖もない厳しい環境のため、栽培できる作物はサツマイモ程度で、人々は外から持ち込んだサツマイモと鶏で生活していたと推測される。
サツマイモの栽培は手間がかからなかったため、人口は徐々に増え、開墾や住居やカヌーを作るため森林が伐採されていった。農耕にあまり時間を要さなかったため、人々は余った時間を祭礼に向けることとなり、やがて墓とも祭祀用の像ともいわれる巨大な石像(モアイ)が作られるようになった。動力となる家畜のいないイースター島では石切り場から祭祀場までの石像の運搬が大きな問題となったが、人力で引いて移動させることで解決し、運搬を容易にするためのコロや石像を立てるためのテコなど、各種用途に木を使用したため森林減少が加速された。木材の欠乏のため、長距離移動が可能な木製のカヌーが作れなくなり、最も近い有人の島まで2,000km以上もある絶海の孤島であるこの島から脱出できなくなり、また、布や魚網の材料に使われていたカジノキも入手できなくなったため、漁もできなくなったと予想される。さらに、植生を剥奪したため裸地が増加し、土壌の流出が起こったため作物の収量が低下した。枯渇する資源をめぐり恒常的な戦乱状態となり、さらには蛋白源が不足したため、食人が始まったとされる。
同島には最大時7,000人が居住していたと考えられているが、1774年イギリス人ジェームズ・クックがこの島の調査をしたときには600〜700人程度になっていたといわれる。
遺伝的多様性の低下による影響
一般に、生息数が減少し近親交配の頻度が高まると、種内の遺伝的多様性が低下し、奇形率の増加、生存率の低下など、様々な障害が生じることが知られている。例えばアメリカ、フロリダ半島のピューマでは、個体数が減少し、遺伝的多様性が低下することで、尾の奇形などの障害が出ているといわれる。遺伝的多様性を維持し、個体群を安定的に維持するためには、交配可能な性的成熟個体が適切な性比で一定個体以上生息することが重要である。
また、作物の病虫害防止や生産性改良のためには、病虫害抵抗性を持った遺伝子や高生産性遺伝子の導入が常に必要である。1991年(平成3年)にブラジルで発生した柑橘類の潰瘍病の流行は、オレンジの木が遺伝的に均質であったことが被害を大きくした主要因であったといわれる。こうしたことからも、栽培する作物が遺伝的に偏らないようにするとともに、作物の原種を野生の状態で保全することを通じ、その遺伝的多様性を維持しておくことが極めて重要である。
セベソ事件
1976年イタリアのセベソで発生した農薬工場の爆発事故とその後の火災のため、工場周辺の土壌がダイオキシンを含む有害化学物質で汚染された。この汚染土壌はドラム缶に入れられて保管されていたが、1982年3月にこのドラム缶がいずれかに搬出され、数か月にわたって行方不明になった。結局、北フランスで発見されたが、ドラム缶の引き取りをめぐってフランス政府とイタリア政府が対立した。
事故を起こした農薬工場の親会社がスイスのバーゼルにあったためスイス政府が引き取ることで決着した。
有害廃棄物越境移動の原因
1989年(平成元年)に発表されたOECDの報告書では、有害廃棄物の越境移動が起こる原因として、以下の9点があげられている。
? 有害廃棄物の発生国においてその処理費用が値上がりすること
? 発生国において特定の廃棄物の処分容量が減少すること
? 発生国において陸上処分し、将来環境汚染が生じた場合には、多額の被害補償が必要な可能性があること
? 発生国において有機溶剤など特定の廃棄物の処理に関する規制が強化されること
? 発生国において排出業者による廃棄物の発生場所での処理に関する規制が強化されること
? 発生国において経済成長により廃棄物の発生量が増大すること
? 受入国において複数の国が利用できる処理施設が存在すること
? 発生国においては最終処分されてしまう廃棄物から有価物を回収するため、取引される国際市場が存在すること
? 発生国よりも、他国の処理施設のほうが近くにあること
これらのうち、?〜?については受入国において適正な処理が期待されず、環境汚染を引き起こす可能性が高い。特に?、?のような場合は有害性の高いものが多いため、規制が緩やかな国での投棄を目的として越境移動が起こると考えられる。
フィリピンへのゴミ違法輸出事件
栃木県の産業廃棄物処理業者が注射針や点滴用チューブなどの医療系とみられる廃棄物を含む貨物をリサイクル用古紙などと偽ってフィリピンに輸出した事件。
平成11年12月2日、在マニラ日本大使館より、バーゼル条約に抵触するおそれのある貨物がマニラ港に放置されているコンテナに詰められている旨、第一報が入り、同13日、フィリピン国から日本国あてバーゼル条約に基づく回収の要請があった。これにより、30日以内に日本に回収する義務が発生したため、同24日に国は、輸出業者あて回収を求める旨の措置命令を行った。
しかし、同事業者が期限までに回収に着手しなかったため、同31日、国が回収の代執行に着手。その後焼却が行われ、国の代執行が終了した。
エコロジー運動
エコロジー運動は、1968年(昭和43年)にアメリカのカリフォルニア大学の学生が起こしたのが始まりとされ、産業活動による環境破壊を告発し、生態系と調和した社会の発展を追求するものであった。1970年代後半、原子力発電の導入などをめぐって政治運動に発達し、その主張は生態系の重視など環境問題を中心に、南北問題、労働環境の改善など多様な領域に及んでいる。