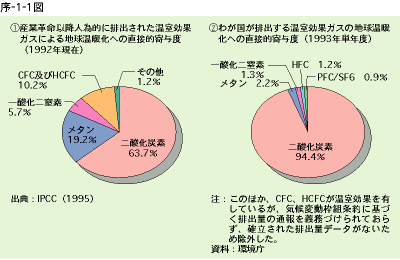
1 地球環境のマクロ的変貌と将来予測
(1)地球温暖化は確実に進行している
地球は、太陽の放射するエネルギーを受けて暖められ、宇宙空間へのエネルギー放出により冷える。このエネルギーの収支が均衡している状態では地球の温度は平均して安定している。しかし、人為的な影響により温室効果ガスの濃度が上昇し、宇宙空間へのエネルギー放出が妨げられると、地表の温度は上昇する。この温度上昇が、気候の変化を引き起こし、生態系などを始めとする人類の生存基盤に多大な影響を及ぼす。これが、「地球温暖化」の問題である。
自然に存在する温室効果ガスには、水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、オゾン等がある。人為的に発生する温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン(HFC)等がある。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告によれば、メタン、一酸化二窒素、HFC等の一定量当たりの温室効果は二酸化炭素に比べてはるかに高い。しかし、二酸化炭素はその排出量が膨大であるため、温暖化への寄与度は全世界における産業革命以降の累積で約64%、近年の日本の場合は94%以上を占めている(序-1-1図)。このため、今後の温暖化対策としては、特に二酸化炭素排出量の削減が重要な課題であるといえる。
IPCCは、政府レベルの地球温暖化問題に関する検討の場として、WMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)が共同して1988年11月に設立した組織で世界の科学者の集まりである。IPCCは1995年にとりまとめた第2次評価報告書の中で、19世紀以降の気候を解析し、産業革命以後の温室効果ガスの発生量の増大等により地球温暖化がすでに起こりつつあることを確認している。以下、IPCC第2次評価報告書等により温暖化の影響を見てみる。
ア 温室効果ガスの濃度の上昇
温室効果ガスの大気中濃度は産業革命(1750〜1800年)以前は、おおむね一定の水準にあったが、産業革命以後は著しく増加している。WMO温室効果ガス世界資料センターが収集した最新のデータを解析した結果、1997年(平成9年)の世界の二酸化炭素濃度は約280ppmvから363ppmv(ppmvは100万分の1、容積比)に、メタン濃度は700ppbvから1,740ppbv(ppbvは10億分の1、容積比)に、1996年(平成8年)までに一酸化二窒素濃度は約275ppbvから約312ppbvに上昇している。これら温室効果ガスの濃度は、特に最近20〜30年に著しく増加している。
こうした傾向は大部分人間活動に起因するものであり、その多くは化石燃料の使用、土地利用の変化、農業の営み等による。この他、近年開発されたHFC等の濃度も増加している(序-1-2図)。
イ 地球温暖化を裏付ける事実
気温は、日較差や年較差をもって周期的に変動しているが、その変動は大きな問題を起こすものではない。しかし、全体としての平均気温の上昇はその数値が日較差に比べ微細であっても環境に大きく影響するおそれがある。気象庁によると、地球表面の平均温度の100年間の長期傾向では約0.6℃上昇しており、1998年(平成10年)の平均温度は、1880年(明治13年)以降で最高であった(序-1-3図)。この変化には、人の活動による影響が含まれることは否定できない。
気温の上昇は、海水の膨張、極地及び高山地の氷の融解を通して海面の上昇を招く。地球規模での海水面の上昇は過去100年間に10〜25cmであり、これらの変化は地球の平均気温上昇に関連があると見られる。今世紀に入ってからは、氷河の衰退傾向は観測データによって明確になっており、他の地域においても、極端な高温現象、洪水や干ばつの増加といった深刻な問題となり得る変化が現れている。
ウ 地球温暖化に関する将来予測
IPCCによると、2100年の二酸化炭素の排出量が1990年の3倍弱(二酸化炭素の大気中濃度は1990年レベルの2倍)となるシナリオ(中位の予測)では、2100年には地球全体の平均気温は1990年と比較して2℃上昇、海面水位は約50cm上昇すると予測されており、その後も気温上昇は続くとされている。また、一度排出された温室効果ガスは長期にわたり大気中にとどまることに加え、海洋は大気に比べゆっくりと温度変化するため、この影響を受けて地球の平均気温の変化も遅れて現れる。このため、仮に温室効果ガスの濃度上昇を21世紀末までに止められたとしても、それ以降数世紀にわたって、気温の上昇や海面の上昇は続くと考えられる。こうして地球温暖化が進行するのに伴い、世界各地において、海面の上昇以外にも、自然災害の増加、食糧生産の不均衡、生態系への打撃、人の健康への悪影響などの深刻な問題が懸念されている。この点については、第1章第1節で詳しく述べることとしたい。
(2)森林の減少・劣化は途上国で顕著である
森林は、世界の陸地(グリーンランド及び南極を除く。)の約4分の1を占めており、1995年(平成7年)時点での森林面積は34億5,400万haである。しかし、FAO(国連食糧農業機関)によると地球上の森林は熱帯林を主として、1990年から1995年の5年間に全世界で5,630万ha減少しているという。年平均1,130万haの森林が失われている計算になるが、これは日本の面積(3,770万ha)の約30%、本州の約半分の面積に相当する。森林面積は、1990年から1995年の間に先進国では878万ha(年平均176万ha)増加しているのに対し、途上国ではこの7倍を超える6,513万ha(年平均1,303万ha)が減少している。1980年から1990年までの途上国の年平均森林減少面積は1,226万haであるから、途上国で森林の減少は引き続き進行しているといえる(序-1-4図)。
ストックホルム環境研究所の1998年報告によれば、仮に年間約1,200万haのペースで今後も森林の減少が続く基本シナリオの下では、1995年から2050年の間には約6億ha、既存の森林面積の17%が消滅する計算になる。一方、各途上国が適切な森林保全政策や土地利用の改革を実施する改革シナリオの下では、森林破壊の面積は2025年までに徐々にゼロに近づき、その後は森林面積は拡大傾向に向かうと予測している。
途上国の中でも、特に熱帯地域で森林の減少・劣化が進んでいる。途上国の非熱帯地域における1990年から1995年の間の年平均森林減少面積が43万haであるのに対し、熱帯地域の同期間の減少面積は1,259万haとなっている。
熱帯林減少の原因は、農地等への転用、過放牧、薪炭材の過剰採取、非伝統的な焼畑等が指摘されているが、これらは、森林面積を減少させるだけでなく、閉鎖林から疎林というように森林の質的変化による劣化をもたらしている。こうした森林の減少・劣化の原因の背景には途上国における貧困、人口増加、土地制度等の社会的、経済的な要因がある。
熱帯林には、地球上に生存している生物種の50〜80%が生息するといわれ、生物多様性の保全に重要な役割を果たしている。熱帯林の減少によりこれらの動植物種が絶滅したり、種の維持が困難なほどに生息域が狭められたりすることが懸念されている。
また、森林は二酸化炭素の吸収源、貯蔵庫としても重要な役割を果たしている。樹木は光合成により大気中の二酸化炭素を有機物に変え、幹や枝、葉、根をつくっている。樹木は乾燥重量の5割を炭素が占めているといわれ、森林の減少により大気中への二酸化炭素の放出が地球温暖化を加速させるおそれがある。
(3)土壌劣化や砂漠化が乾燥地域で進行している
土壌には、食糧生産のための農業基盤、保水能力や地下水の形成、多様な生態系の維持等の機能があり、その劣化や喪失は、人間を始めとする生物の生存や生態系に大きな影響を与える。土壌劣化の態様には、降雨による流失や風により表土が吹き飛ばされるといった侵食、塩類集積やアルカリ化、湛水化等がある。
乾燥地における土壌の劣化や喪失、いわゆる砂漠化の問題には、気候的要因と人為的要因の二つがある。気候的要因としては、下降気流の発生や水分輸送量の減少による乾燥の進行、人為的要因としては、草地の再生能力を超えた家畜の放牧(過放牧)、休耕期間の短縮等による地力の低下(過耕作)、薪炭材の過剰な採取が考えられる。
1991年にUNEP(国連環境計画)が発表した「砂漠化の現状及び砂漠化対処行動計画の実施状況について」によると、世界には61億ha以上の乾燥地が存在し、そのうち9億haは極めて乾燥した地域、すなわち砂漠である。残りの52億haは、乾燥、半乾燥及び乾燥半湿潤地域であり、耕作可能な乾燥地である。この耕作可能な土地のうち、70%に当たる36億ha(世界の全陸地の約4分の1)が砂漠化の影響を受けており、そこでは9億人(世界人口の約6分の1)が生活している(序-1-5図、序-1-6図)。
これを大陸別に見ると、被害面積が最も大きいのはアジアであり、次いでアフリカ、北アメリカとなる。
(4)生物多様性が熱帯地域で急激に減少している
地球上には多くの種が存在しているが、その総数は正確には把握されていない。UNEP(国連環境計画)によれば、未知の種も合わせると種の総数は300万種から1億1,100万種に及ぶとも推定されており(序-1-7図)、そのうち現在確認されている数は約175万種程度である。特に、世界の陸地面積の7%を占めるにすぎない熱帯多雨林には種全体の半数以上が生息しているといわれ、熱帯地域は世界の種の多様性の核心である。なお、このような種の多様性のほか、遺伝子レベルの多様性、生態系の多様性をも含めて、「生物多様性」と総称されている。
生物多様性には、人類を含む生物自身にとって良好な環境をつくり、それを健全に保つ生存基盤としての価値、食物、薬等の資源としての価値、また、自然とのふれあいを通じて心の安らぎを得、さらにレクリエーションやスポーツを楽しむ場としての文化的価値がある。
種の絶滅は、自然界の進化の過程で絶えず起こってきたことであるが、その速度は極めて緩やかであった。今日の種の絶滅は、自然のプロセスではなく、人類の経済社会活動が主たる原因であり、地球の歴史始まって以来の速さで進行している。
IUCN(世界自然保護連合)は、専門家を交えた総合的評価の結果から、絶滅のおそれのある種の現状をまとめて1966年以降「レッドデータブック」として出版してきた。これを見ると、次のような生物多様性を脅かす厳しい現実が明らかにされている(序-1-1表)。1996年度版の「絶滅のおそれのある動物レッドリスト」によると、全種調査を行った哺乳類と鳥類については、哺乳類の25%、鳥類の11%が絶滅のおそれがあることが判明した。他の動物については、保存状況の調査が行われた種に限っていえば、爬虫類の20%、両生類の25%、魚類の34%が絶滅のおそれがあるという結果となった。また、1997年度版の「絶滅のおそれのある植物レッドリスト」によると、現在27万種にものぼると推定される維管束植物のうち約24万種を調査対象にしたが、最低でも33,798種、12.5%が絶滅のおそれがあるという結果となった。
(5)水資源の安定的利用が難しくなりつつある
水は、人類を含む生物にとって不可欠な生存基盤であり、経済社会の発展になくてはならない資源である。しかし、世界人口の増加、水質の悪化等を背景に、多くの地域で水資源の安定的利用が困難になりつつある。
WMO(世界気象機関)の資料によれば、地球上に存在する水の量は、約14億km3であると考えられているが、その約97.5%が海水等であり、淡水は残りの約2.5%にすぎない。淡水の大部分は極地などの氷として存在しており、残る淡水の大部分が地下水であるため、比較的容易に利用できると考えられる河川や湖沼の水は、地球上の水のわずか約0.01%にすぎない約10兆m3である(序-1-2表)。ただし、これは一時点をとったものであり、水は蒸発、降雨という流れを辿り持続的に循環しているので、1年間に実際に利用可能な水の量はこれよりもかなり多い。この点に関しては、UNESCO(国際教育科学文化機関)の資料(World Water Resources)によると、地球上の年間降水量は約577兆m3であり、このうち約119兆m3が陸上に降るという。そして、このうち蒸発散によって失われた残りの約45兆m3が世界全体の水資源賦存量であり、地下水として涵養される年間約2兆m3を除く約43兆m3が「河川水等」となると報告されている。
また、この河川水等の多くを占める河川水は、南アメリカやアジアなど大河川が流れる限られた地域に多く存在する一方で、世界の陸地総面積の約40%を占める乾燥・準乾燥地域における河川流量は、世界全体の約2%にすぎない(序-1-8図)。
水資源の利用動向をWMO(世界気象機関)の資料から見ると、1995年(平成7年)における世界の年間水使用量は約3兆5,720億m3であり、1950年の約2.6倍となっている。この水使用量の伸びは同期間の人口の伸びより大きく、1人当たりの水利用量でみると、1995年(平成7年)には1日1,756リットルと過去25年間で約17.6%増加した。これを地域別に見ると、アジアでの水使用量が年間2兆850億m3と最も多く、続いて北アメリカ、ヨーロッパの順となっている。同様に1人当たりでは、北アメリカが1日3,924リットルと最も多く、続いてオセアニア、ヨーロッパの順となっている。先進国の人口が比較的多い地域で、水が多く使われている構図となっている。この資料における将来の水需要量に関する予測を見ると、世界人口の増加などに伴い、2025年の水需要量は1995年の約1.4倍に増加すると見込まれている(序-1-3表)。
このような将来の水需要の動向に対し、利用可能な淡水の存在は、地理、気候などの地域性に大きく依存しており、水資源に関する量的な問題は、この地域偏在性に起因していることが多い。国連事務総長報告「世界の淡水資源についての総括的アセスメント」では、水不足の状態におかれる人口の割合は、1995年(平成7年)には約3分の1であったのが、2025年には約3分の2になると報告している。
一方、水資源の質的問題としての水質悪化には、生活や産業の排水、その他多くの人間活動に起因する汚染や、富栄養化、海水による塩化などがある。様々な原因で安全な水の供給を受けることのできない人々の数は、WHO(世界保健機関)によれば、1994年(平成6年)時点ですでに約11億人に達していると報告されており、世界人口の増加などにより一層増加することが予想される。世界銀行の推計(World Development Report 1992)によれば、このままでいくと2020年(平成32年)で約20億人が安全な水の供給を得られなくなるとしている。
(6)エネルギー資源の枯渇が懸念される
地球環境と並んで持続可能性に大きな影響を与えるものにエネルギー資源がある。エネルギーは、まさに経済発展の推進力となり、人類社会の物質的な繁栄を支えてきた。20世紀においてめざましい変貌を遂げたものの一つが、消費されるエネルギーの絶対量に加え、その源としてのエネルギー資源の中身であろう。
20世紀当初は、エネルギー源の過半が石炭であり、木材、水力等の再生可能資源がこれを補うという構造であった。これに対し近年のエネルギー消費量を資源別にみると、現在は石油への依存が約4割と圧倒的に高く、石炭、天然ガスを含め化石燃料に大きく依存している実態が分かる(序-1-9図)。また、世界のエネルギー消費量を地域別にみると、特にアジアを中心とした発展途上国で大きく伸びており、世界人口の増加と経済成長に伴って、今後も大きく増え続けることが予想される(序-1-10図)。
主要なエネルギー資源の確認可採埋蔵量について、可採年数でみると、石炭が最も長く231年となっている以外では、石油、天然ガス、ウランの順で21世紀中に枯渇することが懸念されている。一方、地域別にみた場合には、石油、天然ガスについてはかなり偏りがあるが、ウランは比較的広い地域に分布している。また、アジア太平洋地域では石炭やウランが、石油、天然ガスに比べ多量に埋蔵されていることが分かる(序-1-11図)。
このようにエネルギー資源は有限であり、近い将来のうちに枯渇が懸念されている。限られたエネルギー資源を未来世代に残すためには、エネルギー資源の有効利用はもちろん、新エネルギーの開発や再生可能資源の持続的利用など将来へ向けたエネルギー対策が重要な課題である。