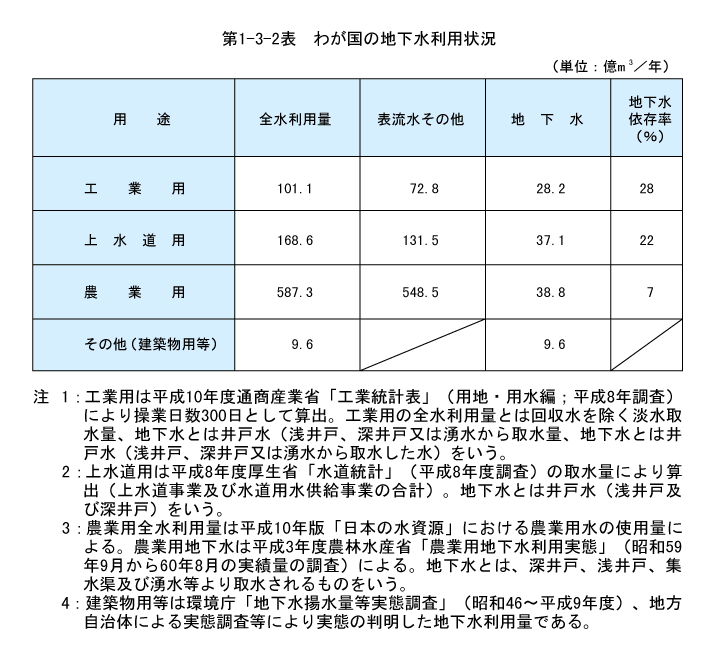
2 地盤環境の保全
(1) 地盤環境の現況
地盤沈下は地下水の過剰な採取が主な原因となるものであり、また、地下水の採取は工業用、建築物用のみならず、水道用、農業用、水産養殖用、消雪用等多岐にわたっている(第1-3-2表 )。
代表的な地域における地盤沈下の経年変化は、第1-3-1図 に示すとおりであり、平成9年度までに、地盤沈下が認められている主な地域は47都道府県のうち37都道府県62地域となっている。
最近における我が国の地盤沈下の特徴をあげると次のようになる。
? 平成9年度の地盤沈下は、年間2cm以上沈下した地域数は前年度と比較して減少したが、沈下した面積は一部地域で大幅に拡大したため、ほぼ前年度並みとなった(第1-3-2図 )。
? かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪市、名古屋市等では、地下水採取規制等の対策の結果、地盤沈下の進行は鈍化あるいはほとんど停止している。しかし、渇水時を中心とする地盤沈下が広域的に発生している関東平野北部地域、消雪用地下水汲み上げによる沈下が進行している新潟県南魚沼など一部地域では依然として地盤沈下が進行している。
? 長年継続した地盤沈下により、多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じており、海抜ゼロメートル地域では洪水、高潮、津波等による甚大な災害の危険性のある地域も少なくない。
(2) 地盤環境保全対策
ア 地下水保全対策等
地盤沈下の防止のため、工業用水法及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(「ビル用水法」)に基づき地下水採取の規制が行われており、現在、両法によりそれぞれ10都府県、4都府県の一部が地域指定されている。また、多くの地域では地方公共団体の条例等に基づく規制のほか、工業用地下水採取の自主規制、使用合理化等行政指導を行うことにより地下水の採取量の減少を図っている。
地下水採取量を削減するための代替水対策としては、代替水源を確保する事業、代替水供給事業が進められているが、工業用水で特に対策の必要な地域については、地盤沈下防止対策工業用水道事業が進められている。
既に著しく地盤が沈下している地域については、この結果生じた被害を復旧するとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備、土地改良等の事業が実施された。
また、雨水浸透ますの設置等、地下水かん養の促進等による健全な水循環を確保するための事業を国庫補助事業として実施した。
イ 地盤沈下防止等対策要綱
地域の実情に応じた地盤沈下対策を総合的に推進するため、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議において、濃尾平野及び筑後・佐賀平野については昭和60年4月(平成7年9月一部改正)に、関東平野北部については平成3年11月にそれぞれ地盤沈下防止等対策要綱が策定され、代替水源の確保等の各種の施策が推進されている。
ウ 調査研究等
地盤環境の保全のための調査としては、関東平野北部地盤沈下防止等広域対策調査、局地急速型地盤沈下防止手法策定調査、市街化進展地域における地盤沈下危険度に関する調査研究、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農地・農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下調査等各種の調査を実施した。
さらに、地下水採取の規制地域等の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対して補助を行うとともに、地下水位等をリアルタイムで監視するためのシステムの整備を進めている。地盤沈下の実態把握のための水準測量、地下水揚水量等実態調査を実施した。
また、地盤沈下の防止に向けた意識の啓発のため、地下水の利用状況、地盤沈下等の状況等に関する情報を整理した「全国地盤環境情報ディレクトリ」を環境庁ホームページに掲載し(http://www.eic.or.jp/eanet/jiban/index.html)、平成10年9月には地盤沈下の被害写真等の情報を加えて内容を更新した。