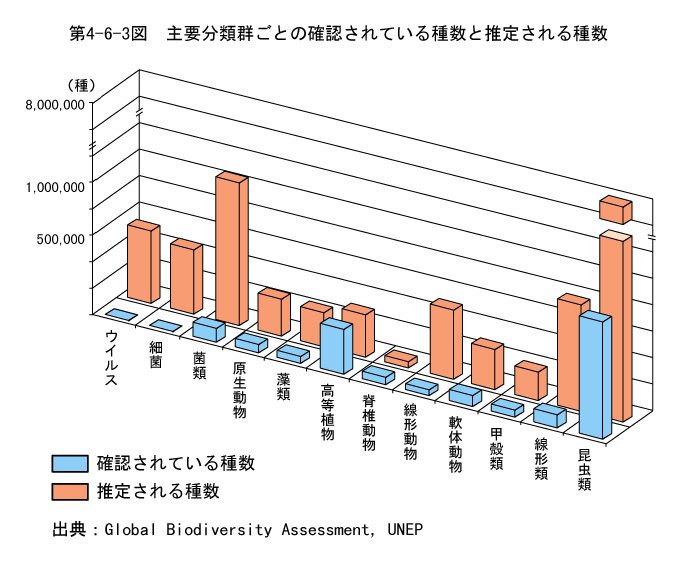
4 生物多様性の保全
地球上には多くの種が存在しているが、その総数は正確には把握されていない。国連環境計画(UNEP)によれば、未知の種も合わせると種の総数は300万種から1億1,100万種に及ぶとも推定されており(第4-6-3図)、そのうち現在確認されている数は約175万種程度である。特に、世界の陸地面積の7%を占めるに過ぎない熱帯多雨林には種全体の半数以上が生息していると言われ、熱帯地域は世界の種の多様性の核心である。このような種の多様性の他、遺伝子レベルの多様性、生態系の多様性をも含め、生物多様性と呼ばれている。
生物多様性には、我々人類を含む生物自身にとって良好な環境を作り、健全に保つ生存基盤としての価値、食物や薬等資源としての価値、また、自然とのふれあいを通して心の安らぎを得、さらにレクリエーションやスポーツを楽しむ場としての文化的価値がある。
しかしこのような生物多様性は、生息・生育地の破壊により急速に失われている。このままの割合で森林破壊が続くと熱帯の閉鎖林に生息する種の4〜8%が今後25年の間に絶滅するという試算もある。
種の絶滅は、自然界の進化の過程で絶えず起こってきたことであるが、その速度はきわめて緩やかであった。今日の種の絶滅は、自然のプロセスではなく、人類の経済社会活動が主たる原因であり、地球の歴史始まって以来の速さで進行している。
種の絶滅は地球環境問題の重要な課題として捉えられ、国際的な取組が進められている。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制することにより、それらの種を保護することを目的としている。この条約は、絶滅のおそれのある野生動植物を、国際取引の規制による保護の必要性に応じて附属書?〜?に掲載し、その附属書の区分に応じて段階的に輸出入を規制する仕組みとなっている。トキやゴリラなど附属書?に掲げられている種については学術研究目的などの限られた場合を除いてその国際取引が禁止される。ワシントン条約の対象種についてはおよそ2年に1回開催される締約国会議において随時見直しが行われており、現在、1,000分類群(*1)以上がその対象となっている。
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、湿地の保全を目的とした条約である。我が国では、釧路湿原、クッチャロ湖、ウトナイ湖、霧多布湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原(北海道)、伊豆沼・内沼(宮城県)、谷津干潟(千葉県)、片野鴨池(石川県)、琵琶湖(滋賀県)及び佐潟(新潟県)の10ヶ所に加えて、1999年(平成11年)に開催されるラムサール条約第7回締約国会議(コスタリカ)の際に、漫湖(沖縄県)が新たに登録される予定である。
また、日本とアメリカ、オーストラリア、中国、ロシアの各国との間で渡り鳥等保護条約(協定)を締結し、ツルやシギ・チドリなど渡り鳥の保護を推進しているほか、日本と中国の間では、中国におけるトキの生息地保全に向けた取組を両国が協力して行うなど、二国間においても種の保存へ向けた取組がなされている。
地球上の生物の多様性を包括的に保全するための国際条約として「生物の多様性に関する条約」が締結されている。これは、特定の動植物や生息地の保全にとどまらず、地球上のあらゆる生物の遺伝子、種、生態系の3つのレベルの多様性をそれらの生息環境と共に最大限に保全し、その持続可能な利用を実現し、さらに生物のもつ遺伝的資源から得られる利益を公正かつ衡平に配分することを目的としている。
この条約を受け、我が国は、平成7年10月に生物多様性国家戦略を策定した。その中で、生物多様性の現状を把握するとともに、その保全と持続可能な利用のための長期的目標を定めた。すなわち、第一に、現存する生物多様性の保全及び持続可能な利用、第二に、生物間の多様な相互関係の保全及び生物の再生産、繁殖の場としての保護地域の保全を掲げている。さらに、長期目標達成に向けた当面の政策目標及びその達成に向けた施策を示している。国家戦略実現のため、環境庁は平成10年4月、生物多様性センターを設置し、生物多様性に関する情報の収集・管理・提供等を開始している。
現在、「生物の多様性に関する条約」の下では、遺伝子組換え生物などの国際取引に際し、生物多様性への悪影響の可能性について事前に評価するための手続などを定める「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」の作成交渉が行われている。