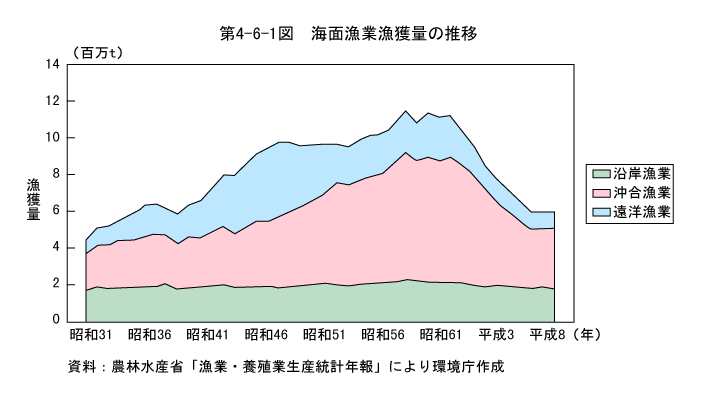
2 水産資源・野生鳥獣の現状
(1) 水産資源
四方を海に囲まれた我が国は、周囲に寒流、暖流が交錯する生物多様性に富む豊かな漁場を有している。我が国は伝統的に水産物を重要な蛋白質として活用してきており、多様な水産資源の恩恵を受けている。
水産物の生産量は、戦後ほぼ一貫して増加し、昭和56年に養殖業を除く海面漁業の生産量が1,000万tを超え、昭和59年には1,150万tに達した。しかし、平成元年以降生産量が減少し、平成9年の生産量は昭和59年に比べ約48%減の約599万tにまで低下した(第4-6-1図)。主要魚種別生産量の推移を見るとマイワシ・スケトウダラの生産量が減少している(第4-6-2図)。我が国周辺水域では漁船性能の向上等による漁獲強度の増大等もあって底魚類を中心に総じて資源状態が低水準にある。マイワシ、マサバ、マアジ等の浮魚資源は海洋環境の影響等を受けて、資源状態が大きく変動しており、この中で現在減少傾向にあるマイワシ資源については今後の動向を注視していく必要がある。
国内の水産資源の保護については、漁業法、水産資源保護法の適正な運用により、野生水生生物の保護を図っている。また、水産資源の維持・増大と合理的利用を図る資源管理型漁業の推進、生物多様性に配慮しつつ、栽培漁業、養殖漁業等を推進し、併せて漁場の造成と改良により生産力の向上や希少水産生物の保護・管理を推進している。
(2) 野生鳥獣
狩猟は人間の生業やスポーツ等として行われてきたが、野生鳥獣を自然の収容力に見合った生息数に管理する手段としても役割を果たしている。
我が国に生息する哺乳類及び鳥類については、一部を除き全種が「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」によって保護の対象とされており、狩猟ができる種は47種に限定されている。狩猟については、期間(狩猟期間)、場所(鳥獣保護区の指定等による狩猟の禁止)、資格(狩猟免許)等の制限が定められており、これらの捕獲規制によって鳥獣の保護を図っている。
また、鳥獣保護区として設定された地域のうち、特に鳥獣の生息環境として重要な地域については、開発行為等が規制される特別保護地区に指定することにより鳥獣の生息環境の保全を図っている。これらの鳥獣保護区については、今後とも渡り鳥等の移動性等を踏まえた適切な配置や多様な鳥獣の確保に留意しつつ、また多様な生物群集のタイプが含まれるように努めながら、積極的に設定を進めることとしている。鳥獣保護区は平成10年3月末で3,767か所,3,602千ha(国設54か所、491千ha、都道府県設3,713か所、3,111千ha)が設定されている。
狩猟対象については、農作物への被害が増加している種や生態系への影響などが懸念される外来種等を追加している。最近では、平成6年5月に、ヒヨドリ、アライグマ等5種が追加され、リス、ムササビ、ビロウドキンクロ、コオリガモ、ウミアイサの5種が削除された。
狩猟者人口は、昭和51年度の約53万人が平成8年度には約25万人にまで減少しており、しかも高齢化がかなり進んでいる。平成8年度に狩猟により捕獲された鳥類は約289万羽、獣類約28万頭である。環境庁長官または都道府県知事は有害鳥獣駆除等の目的で野生鳥獣の捕獲を許可することができるが、平成8年度にこの許可を受けて捕獲された鳥獣は、鳥類約107万羽、獣類約12万頭であった。近年の狩猟による捕獲数の減少と農林業被害の増加を反映して、例えばシカについては、捕獲数に占める有害鳥獣駆除の割合が昭和55年度の約9%から平成8年度には約38%と高くなっている。これは、農林業被害を及ぼす種について狩猟によってその生息数を管理することが難しくなってきている状況を示している。