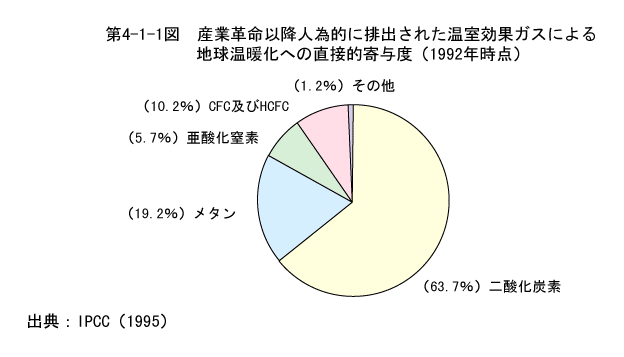
1 大気の組成等の変化による地球規模の大気環境の現状
(1) 地球温暖化
地球は、太陽の放射するエネルギーを受けて暖められ、宇宙空間へのエネルギー放出により冷える。このエネルギーの収支が均衡している状態では地球の温度は平均して安定している。しかし人為的な影響により温室効果ガスの濃度が上昇し、宇宙空間へのエネルギー放出が妨げられると、地表の温度は上昇する。この温度上昇が、気候の変化を引き起こし、生態系等をはじめとする人類の生存基盤に多大な影響を及ぼす。これが、地球温暖化の問題である。
自然に存在する温室効果ガスには、水蒸気(H2O)、CO2、メタン、一酸化二窒素、オゾン等がある。人為的に発生する温室効果ガスには、CO2、メタン、一酸化二窒素、HFC(ハイドロフルオロカーボン)等がある。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告によれば、メタン、一酸化二窒素、HFC等の一定量あたりの温室効果はCO2に比べてはるかに高い。しかし、CO2の排出量は膨大であるため温暖化への寄与度は約64%を占めている(第4-1-1図)。このため、CO2排出量の削減が重要な課題である。
我が国の平成8年度のCO2排出量は、炭素換算で3億3,700万t、1人当たりの排出量は2.68tであり、前年度と比べ排出量で1.2%、1人当たり排出量で1.0%の増加であった(第4-1-2図)。
ア 既に生じている地球温暖化の影響
地球温暖化の徴候は、既に、温室効果ガスの濃度上昇、地球の平均気温の上昇、海面水位の上昇という形で現れている。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化問題に関する政府レベルの検討の場として、WMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)が共同して1988年11月に設立した国連の組織である。IPCCは1995年にとりまとめた第2次評価報告書の中で、19世紀以降の気候を解析し、産業革命以後の温室効果ガスの発生量の増大等の人為的影響により地球温暖化が既に起こりつつあることを確認している。
以下、IPCC第2次評価報告書等により温暖化の影響を見てみる。
(ア) 温室効果ガスの濃度の上昇
温室効果ガスの大気中濃度は産業革命(1750〜1800年)以前は、比較的一定の水準であったが、産業革命以後は著しく増加している。1994年(平成6年)までにCO2濃度は約280ppmvから358ppmvに、メタン濃度は700ppbvから1,720ppbv(ppbvは10億分の1、容積比)へ、一酸化二窒素濃度は約275ppbvから約312ppbvに上昇している。これら温室効果ガスの濃度は、特に最近20〜30年に著しく増加している。
こうした傾向は大部分人間活動に起因するものであり、その多くは化石燃料使用、土地利用変化及び農業による。この他、近年開発されたHFC等の濃度も増加している(第4-1-3図)。
(イ) 気候変動や海面上昇等
気温は、日較差や年較差としては大きな問題もなく周期的に変動しているが、全体としての平均気温の上昇はその数値が日較差に比べ微細であっても環境に大きく影響するおそれがある。気象庁によると、第4-1-4図に示すとおり、地球表面の平均温度の100年間の長期傾向では約0.6℃上昇しており、1998年(平成10年)には、これまで最も高かった1995(平成7年)を抜いて、1880年(明治13年)以降で最高となった。この変化は、その全てを気候系の自然変動によるものとは考えにくい。
気温の上昇は、海水の膨張、極地及び高山地の氷の融解を通して海面の上昇を招く。地球規模での海水面の上昇は過去100年間に10〜25cmであり、これらの変化は地球の平均気温上昇に関連があると見られる。今世紀に入ってからは、氷河の衰退は観測データによって示されており、他の地域においても、極端な高温現象、洪水や干ばつの増加といった深刻な問題となりうる変化が現われている。
イ 地球温暖化に関する世界的な影響
IPCCによると、2100年のCO2の排出量が1990年の3倍弱(CO2の大気中濃度は1990年レベルの2倍)となるシナリオ(中位の予測)では、2100年には全球平均気温は1990年と比較して2℃上昇、海面水位は約50cm上昇すると予測されており、さらにその後も気温上昇は続くとされている。また、一度排出された温室効果ガスは長期にわたり大気中にとどまること、及び、海洋は大気に比べゆっくりと温度変化するため、この影響を受けて地球の平均気温の変化も遅れることから、仮に温室効果ガスの濃度上昇を21世紀末までに止められたとしても、それ以降数世紀にわたって、気温の上昇や海面の上昇は続くと考えられる。
(ア) 異常気象
雨の降る場所が変わり、降雨や乾燥が極端に現れると予測されており、そうした場合利水や治水の手法を変更する必要が生じる。台風が増加する可能性も指摘されている。最近、異常高温、洪水、干ばつ等のいわゆる異常気象が世界各地で頻発し、これら自然災害の増加と地球温暖化との因果関係が関心を集めている。
(イ) 海面の上昇による影響
海面の上昇と気象の極端化は、沿岸地域における洪水、高潮の被害を増加させるおそれがある。仮に海面が50cm上昇した場合、適応策がとられなければ、高潮被害を受けやすい世界の人口は、現在の約4,600万人から約9,200万人に増加すると予測されている。
(ウ) 健康への影響
マラリア、黄熱病など媒介性感染症の患者数が増加する。IPCCによれば、特にマラリアは、3〜5℃の温度上昇により、熱帯、亜熱帯のみならず、日本などが属する温帯を含めて、年間5,000〜8,000万人程度、患者数が増加するおそれがある。温帯地方では、マラリアを媒介する蚊の数が10倍以上に増加すると予想される。また、コレラ、サルモネラ感染症等の感染症についてもその増加が懸念されている。
(エ) 自然環境への影響
IPCCによると、世界全体の平均気温が2℃上昇した場合、地球の全森林の3分の1で、現存する植物種の構成が変化するなどの大きな影響を受ける。これに伴い、微生物や動物を含めた生態系全体が各地で変化するものと考えられている。植物種の構成が変化する過程では、温暖化のスピードに森林の変化が追いつかず、一時的に森林生態系が破壊され、大量のCO2放出が起こる可能性も指摘されている。
(オ) 食料生産への影響
IPCCによると、異常気象や害虫の増加を考慮しなければ、世界全体としての食料需給はバランスするとされているが、増産地域、減産地域が生じ、格差が拡大する。熱帯、亜熱帯では、人口が増加する一方で、食料生産量が低下し、乾燥、半乾燥地域も含め、貧困地域の飢饉、難民の危険が増大すると言われている。
ウ 我が国における影響に関わる事実
(ア) 気温上昇
気象庁の観測によると、我が国でも年平均気温はこの100年間で約1.0℃上昇している。特に、1980年代後半から上昇が著しく、1998年(平成10年)は1898年(明治31年)以降最も高い年であった(第4-1-5図)。
(イ) 海面上昇
環境庁が取りまとめた「地球温暖化の日本への影響1996」によれば、我が国周辺の海面水位は、過去数十年の観測結果によると、地域的なばらつきは大きいが、北日本から中部にかけて1.5〜1.8mm/年の上昇傾向、西日本では1.0mm/年程度の下降傾向を示している。
(ウ) 異常気象等
平成6年は年平均気温でみると平年より約1℃高かったが、少雨による激しい渇水や冷夏による農業被害、猛暑による電力需要の増大や熱射病の頻発等、年々の気候の変動により産業活動や日常生活に大きな影響があった。
エ 我が国における影響
IPCCの予測シナリオに従い、温室効果ガスが産業革命前のレベルに比べ倍増(中程度の予測で2050年頃に相当)したとすると、我が国付近における年平均気温は1〜2.5℃程度の上昇、年降水量で-5〜+10%の変化の範囲に分布する。
(ア) 水資源への影響
冬期の寒気の吹き出しが弱まり、南岸を通過する低気圧の頻度が増加し、太平洋沿岸沿いの降水量の増加が見込まれる。夏期はアジアモンスーンが強まり、現在降水量の多い地域ではますます降水量は増加し、少ない地域ではますます減少する。水害や渇水の危険性が増加するおそれがある。
(イ) 自然生態系への影響
温暖化により今後100年間に平均気温が3℃上昇するとすれば、現在の生態系分布は緯度方向に約500km、標高では500mは移動しなければならない。これはそれぞれ5km/年、5m/年に相当する速度である。樹木が風や動物の力を借りて種子をとばしながら分布を広げる速度は、最も速いもので2km/年といわれている。これらの植生は、気候の変化に追いつけず枯れたり生育出来なくなるおそれがある。自力で移動する動物でも、山岳や海峡等の地形や、都市や道路等の人工物が移動の妨げとなり生息域の変化に適応出来ないおそれがある。
(ウ) 農業への影響
国内生産量の数量的な変化予測については、地球温暖化の結果、水稲では、北日本で増収、西日本で減収が予想され、国内全体では-6%から+9%と予測されている。また、一定した気候条件の上に成立している果樹栽培等も、温暖化によって大きな影響を受けることが予想される。
(エ) 沿岸域への影響
海面が30cmまたは100cm上昇した場合、現存する砂浜のそれぞれ57%、90%が消失すると見込まれている。現在でも浸食の進んでいる日本の海岸は、海面の上昇により、更に深刻な影響を受ける。
日本では満潮位に海面より低い土地に200万人の人が居住しているが、温暖化により海面が上昇し台風の勢力が増大すると高潮などの災害の危険が増加する。
(オ) 人の健康への影響
気温の上昇は、熱射病等の発生率や死亡率の増加を招くおそれがある。疫学的に、日平均気温が27℃、日最高気温が32℃を超えると熱中症患者が急増するという調査結果もある。また、特に高齢者の死亡が増加するということも分かっている。マラリアやデング熱等の媒介性感染症の危険地域に入るおそれもある。
(カ) 公害との複合影響
気温の上昇は大気の光化学反応を加速するため、多くの都市で光化学オキシダント濃度が増加し光化学スモッグによる健康影響が拡大すると予想される。他に、渇水に伴う河川や湖沼の水質汚濁、地下水利用の増加に伴う地盤沈下等間接的に多くの公害問題を加速する可能性がある。
オ 地球温暖化問題への取組
平成9年12月、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において、2008年から2012年までの間の温室効果ガスの排出量についての削減目標等を内容とした「京都議定書」が採択された(第4-1-1表)。平成10年5月には、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が改正され、トップランナー方式の導入による自動車、家電・OA機器等のエネルギー効率の更なる改善の推進や工場・事業場におけるエネルギー使用合理化の徹底等が盛り込まれた。また同年10月には、国、地方公共団体、事業者、国民のすべての主体の役割を明らかにした「地球温暖化対策の推進に関する法律」が成立した。同年11月にはアルゼンチンのブエノスアイレスで気候変動枠組条約第4回締約国会議(COP4)が開催され、今後の国際交渉の道筋を定めた「ブエノスアイレス行動計画」が採択された。
(2) オゾン層の破壊
人工的な化学物質であるCFC(クロロフルオロカーボン:いわゆるフロンの一種)等のオゾン層破壊物質が大気中に放出された後成層圏(地上約10〜50km上空にわたる大気圏)に達し、そこで太陽からの紫外線により分解されて塩素原子や臭素原子を放出し、これらが触媒となって成層圏のオゾン層を破壊することが、近年問題になっている。オゾン層は太陽光線に含まれる有害紫外線(UV-B)の大部分を吸収しているため、オゾン層が破壊されると有害紫外線の地上への到達量が増加し、人の健康や生態系に悪影響を及ぼす。地上への有害紫外線到達量の増大は、皮膚がん、白内障、免疫抑制等の人の健康に対する悪影響や陸上植物や水界生態系等への悪影響を招くおそれがある。
オゾン層を破壊する物質は、CFCの他に、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、臭化メチル等が知られている。
成層圏に到達する塩素等の量は、人為起源のものが自然からの寄与によるものを遥かに凌いでいる(第4-1-6図)。
我が国では、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」等に基づき、オゾン層破壊物質の生産規制、排出抑制及び使用合理化等が実施されている。
ア オゾン層の状況
近年、南極上空では、毎年南極の春に当たる9月から11月頃にかけて成層圏のオゾン量が著しく少なくなる「オゾンホール」と呼ばれる現象が現れるようになり、1998年(平成10年)には過去最大規模のオゾンホールの出現が確認された(第4-1-7図)。また、北半球高緯度地域においても、1997年の冬から春先にかけて、顕著なオゾン量の減少が確認され、特に1997年3月及び4月には、北極域上空で平年より30%を超える減少が観測された。
オゾン層の長期的傾向としては、熱帯域を除き、全球的にほぼオゾン量が減少傾向にあり、高緯度ほどその傾向が強い(第4-1-8図)。我が国上空においても、国内5観測地点(札幌、つくば、鹿児島、那覇及び南鳥島)のうち、札幌で統計的に有意な減少傾向が確認されている。
イ オゾン層破壊物質の大気中濃度の状況
北半球中緯度においては、CFCの対流圏(地表〜地上約10km上空にわたる大気圏)中濃度の増加がほとんど止まっているほか、大気中の寿命の短い1,1,1-トリクロロエタンの対流圏中濃度については、減少に転じている(第4-1-9図)。一方、HCFCについては、最近増加傾向にある。また、南極においても、CFC等の対流圏中濃度の増加率の低下が始まっている。
さらに、対流圏中のCFC等に由来する塩素等の濃度は、1994年初頭にピークを迎え、その後1995年には減少傾向に転じたことが米国海洋大気庁(NOAA)により確認されている。
これらは、モントリオール議定書に基づき、我が国を含む先進国において既にCFC等の生産が全廃されたことによるものと考えられる。
なお、国連環境計画(UNEP)の報告(1998年)では、全ての締約国が1997年に改正されたモントリオール議定書を遵守すれば、?成層圏中の塩素及び臭素濃度の合計は2000年以前にピークに達する、?オゾン層破壊のピークは2020年までに訪れる、?成層圏中のオゾン破壊物質濃度は2050年までに1980年以前(オゾンホールが観測される前)のレベルに戻る、と予測されている。
ウ 有害紫外線の状況
晴天時等の同一条件下では、オゾン全量が減少すれば紫外線の地上到達量が増加する関係にあることが確認されているが、我が国におけるこれまでの観測結果によると、オゾン量の減少傾向が確認されている札幌を含め、有害紫外線(UV-B)の地上到達量の観測値には、明らかな増加傾向は確認されていない。しかしながら、地上に到達する有害紫外線の量は、オゾン全量のほか、天候(雲量)や大気混濁度の影響を受けることに留意する必要がある。
我が国ではオゾン層保護対策を一層推進するため、オゾン層保護法に基づく施策のほか、カーエアコンや家庭用冷蔵庫等の機器に冷媒として充填されているCFCの回収、破壊の促進のための取組を行っている。