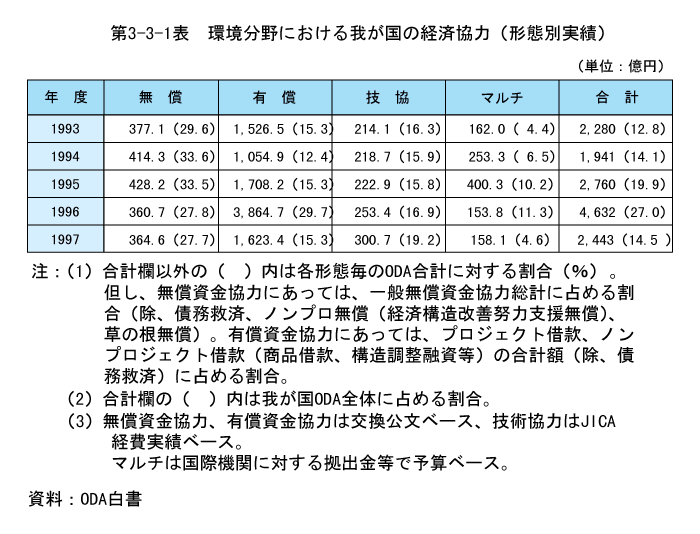
1 我が国の環境協力等の現状
(1) 行政主導の取組
ア 環境政策対話
相手国との政策対話は、相手国の要請や考え方を十分把握しつつ、当方より働きかけを行うことを通じ、持続可能な開発に関する基本認識を相手国との間で共有し協力の基礎とするために重要な手段である。
環境庁では、アジア太平洋地域の持続可能な開発に貢献するため、地域環境フォーラムでの協力、国際機関への協力、2国間環境協力の推進を通じて、同地域の環境政策対話を以下のように推進している。
地域的なフォーラムを通じた環境政策対話としては、アジア太平洋地域環境会議(エコ・アジア)、環日本海環境協力会議、日中韓3か国環境大臣会合等が挙げられる。
アジア太平洋地域環境会議(エコ・アジア)は、アジア太平洋地域等の環境大臣、国際機関の代表者等による政策対話を目的とし、1991年(平成3年)以来開催されている。エコ・アジアでは、科学的予測に基づく政策対話を図るため、?2025年の環境の状況を展望し、持続可能な開発を実現するための政策オプションを提示するための「長期展望プロジェクト」、?インターネットを活用した環境情報交換ネットワークであるエコ・アジア・ネットを推進している。なお、2002年に開催が予定されている,UNCEDから10年目のフォローアップ会合であるリオ+10に向け、有益なインプットをすべく、「長期展望プロジェクト」等による検討を進めており、国連アジア太平洋経済社会理事会(ESCAP)が2000年に開催する環境大臣会合とも連携を図ることを予定している。
環日本海環境協力会議は、北東アジア地域の環境改善を目的とし、日本、中国、韓国、ロシア、モンゴルの5か国で環境問題、技術協力等に関する情報交換、政策対話を行うため1992年(平成4年)以来毎年開催しており、我が国はこの会議に積極的に貢献している。
日中韓3か国環境大臣会合は1999年(平成11年)1月に、日本、中国、韓国の3か国の環境大臣が集まり、北東アジア地域、さらには、地球規模での環境問題に率直な意見交換を行い、環境協力を推進するための会合として初めて開催された。北東アジアにおける緊密な協力や3か国のイニシアチブの発揮、優先すべき環境協力分野等が討議され、今後も1年に1度開催することが確認された。
国際機関活動を通じた協力としては、アジア太平洋地域においては、ESCAP、国連環境計画(UNEP)、APECなどの国際的な機関や枠組が環境政策対話を推進しているが、我が国は、こうした国際的な機関や枠組の活動に積極的に貢献している。例えば、ESCAPにおいては、北東アジア環境協力会議のプロジェクトとして、エネルギーと大気汚染等のプロジェクトを推進しているが,我が国はこれに積極的に参加している。
また、2国間の政策対話についても、2国間の首脳レベル/閣僚レベルの会合で様々な取組を行っている。例えば、1998年(平成10年)に首脳間で作成した、「日韓での21世紀に向けたパートナーシップ宣言」や「日本/サウジアラビア=アジェンダ」では環境分野での協力を重要な分野として位置づけている。このほか、前述のエコ・アジアや、気候変動枠組条約締約国会議(COP)等において、2国間の政策対話の場を積極的に設定して対話を進めている。
とりわけ、中国については、近年、日中環境協力の重要性から、環境政策対話が緊密に行われており、1998年11月には、「21世紀に向けた日中環境協力に関する共同発表」が署名され、日中間で協力して推進すべき具体的項目を確認している。その柱として「日中環境開発モデル都市構想」、「環境ネットワーク構築」に協力している。
アジア地域における2国間協定による環境協力については、我が国は、中国と「日中環境保護協力協定」、韓国と「日韓環境保護協力協定」を締結しており、環境政策担当者間で継続して政策対話を行っている。
囲み3-3-1 日中環境開発モデル都市構想
「21世紀に向けた日中環境協力に関する共同発表」の1つの柱として「日中環境開発モデル都市構想」がある。内容は、中国の数都市を選んで、大気汚染等の環境対策に円借款をはじめとする我が国の政府開発援助を集中的・効果的に投入し、中国側の実効性のある規則等の努力と組み合わせていくことにより、環境対策のモデルとしようとするものである。
この構想は、1997年(平成9年)に我が国が主唱して日中双方の首脳間で一致をみたものであり、政府開発援助における「共同形成主義」の代表例とも言えるものである。現在、日中双方の専門家委員会により、モデル都市として重慶、貴陽、大連が選ばれ、1999年4月には、都市毎の対策の基本方針と具体的プロジェクトについての提言がなされた。
イ 政府開発援助における取組方針
我が国の政府開発援助(ODA)による環境協力は、1989年(平成元年)のアルシュ・サミットにおいて「1989年より1991年までの3年間に環境分野のODAを3,000億円を目途として拡充・強化に努める」と表明したことから意識的な努力が行われるようになった。この目標は3年間で4,075億円の実積をもって達成されている。1992年(平成4年)6月の環境と開発に関する国連会議(UNCED)においては「1992年度より5年間にわたり、環境分野への二国間及び多国間政府開発援助を9,000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化する」という目標を発表した。この目標は1兆4,400億円の実績をもって達成されている。
同じく1992年(平成4年)6月には、日本のODAの基本理念、原則等を示す政府開発援助大綱(ODA大綱)が閣議決定されている。
ODA大綱では、その基本理念の中で、環境の保全が先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全人類的な課題であることを掲げるとともに、その原則においてODAの実施に当たって環境と開発を両立させるということを示している。
1997年(平成9年)には、「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD構想)」の推進をUNGASSで表明し、我が国政府の環境協力に関する基本理念を以下のように明らかにしている。
? 環境問題は人類生存の脅威であり、広い意味での安全保障の問題である。
? 先進国の努力だけで途上国の環境問題を解決することは不可能であり、途上国が第一義的な責任と役割を担って主体的に取り組むことに対して先進国が支援することが重要である。
? 経済発展と環境保全の両立を図る持続可能な開発は、世界全体の課題である。途上国が持続可能な開発を達成するためには、先進国が途上国の経済的・社会的状態を勘案しつつ開発に際して必要な環境配慮に対する支援や環境保全を目的とした協力を実施していくことが重要である。
ウ アジア太平洋地域環境協力プログラム(ECO-PAC)
環境庁では、これまでのアジア太平洋地域における環境協力の取組実績等を踏まえ、21世紀における同地域の持続可能な開発の実現を目標とした将来の環境協力の在り方を「アジア太平洋地域環境協力プログラム」(ECO-PAC)として取りまとめている。ECO-PACの機軸としてパートナーシップの確立・強化を掲げ、具体的には地域環境フォーラム等の政策対話、すべての主体による参加、重点課題への取組の強化を進めることとしている。
エ グリーン・エイド・プラン
通商産業省では、平成4年度から、アジア地域の開発途上国の発展と環境の両立を目的として、産業公害分野や省エネルギー分野における技術協力としてグリーン・エイド・プランを実施している。この事業は、相手国政府や民間企業の公害問題に対する認識を高め、途上国の環境対策の充実を図るために、我が国の公害対策の経験や技術を踏まえたエネルギー・環境技術の移転・普及等を行う自助努力の支援プログラムと位置付けられている。
オ 国際機関を通じた環境協力
地球環境ファシリティー(GEF)は、途上国における気候変動対策、生物多様性の保全、オゾン層保護等の対策プロジェクトに対する国際的資金供与メカニズムとして作られたものであり、我が国も資金拠出や専門的知見からのアドバイス等により支援を行っている。また、生物多様性条約、気候変動枠組条約等の環境に関する条約には、技術移転、資金問題等の途上国の支援についての条項があり、これに基づく取組がなされている。技術移転や情報提供に関しては、国連環境計画(UNEP)等がセンターを整備して、研修や情報提供を実施している。このような、途上国支援の国際的枠組の整備やその活動への支援を進めることが環境問題に対処していく上でも重要である。
OECDの開発援助委員会(DAC)は、援助国間の連携を図る場であり、その開発援助と環境に関する作業部会は、先進各国が協調・連携して効果的・効率的な環境協力を進めるための様々な活動(ガイドラインの作成、ベストプラクティス集の作成やセミナー等による情報交換、地球環境関連条約事務局と連携した調査の実施等)を行っている。
また、開発援助委員会では、我が国が主唱して、「新開発戦略」を定めたが、これにおいては、開発の目標として以下のような指標を含めている。
・ 2015年までに貧困人口の割合を半減する
・ 2015年までに乳幼児死亡率を1/3に削減する
・ 2005年までに環境保全のための国家戦略を策定し、更に2015年までに森林、水産資源等における環境破壊の傾向を逆転させる
地域の環境対策を進める枠組としては、環日本海環境協力会議、中東欧環境行動計画(EAP)等が近年設立された。チャイナ・カウンシルは、中国の持続可能な開発のあり方を検討し、中国政府に提言するための国際フォーラムであり、中国政府関係者・研究者と先進国の有識者、国際機関からの出席者で構成されているが、そこでの調査・検討は、中国の環境政策のみならず、経済政策への働きかけでもあり、各国各機関の中国支援の連携も期待されている。
カ 政府開発援助(ODA)等の実施
先に述べたような方針に基づき我が国は、ODAにより環境分野の途上国支援を積極的に進めている。具体的には、無償・有償の資金協力のほか、専門家の派遣、研修員の受け入れ、地域の公害対策計画づくり等のための開発調査などの技術協力、国際援助機関への拠出等を行っている。(第3-3-1表)また、2国間協力における環境個別分野別の援助実績は第3-3-2表のとおりである。
(ア) 国際協力事業団
国際協力事業団(JICA)は、ODAの2国間援助のうち、技術協力や無償資金協力業務を担っている。環境協力分野では、具体的には、開発途上国からの環境行政職員の研修受入れや、日本からの環境専門家の派遣、環境協力に関する調査団の派遣等の技術協力に加え、環境研修センターの建設、関連機材の供与等のための無償資金協力に係る実施促近業務を行っている。
また、環境配慮については、農業、林業、道路、港湾開発などの20分野について開発調査における「環境配慮ガイドライン」を作成し、開発プロジェクトの計画策定の際の環境配慮の対象と手順を明らかにしている。
(イ) 海外経済協力基金
海外経済協力基金(OECF)は途上国への経済協力を推進するため昭和36年に設立された。OECFはODAの二国間援助のうち円借款(有償資金協力)を担っており、開発途上国の政府・政府関係機関等に対して低利かつ長期返済という緩やかな条件での融資を行っている。特に、公害対策や地球環境問題(温暖化対策等)を目的とした事業向けに円借款の活用を促進するため、国際的に見ても最も優遇された条件(金利0.75%、償還期間40年)を適用している。
環境協力分野では、規模が大きく無償資金協力や技術協力では対応が容易でない、上下水道整備、公害対策事業や植林を含む森林保全事業等が行われている。
また、環境配慮については、「環境配慮のためのOECFガイドライン」を策定し途上国自身がOECFの対象事業において効果的に環境配慮を行うよう促すとともに、融資などの審査に当たって配慮すべき事項を定めている。
(ウ) その他の資金協力
日本輸出入銀行の行う融資は、ODAではないものの、中進国などの行う省エネやクリーナー・プロダクションへの融資を通じて環境協力となっている。
キ 環境協力に関わる民間団体等に対する支援
NGO等の活動は、小規模の開発プロジェクトに対してきめ細かい支援が可能である、現地の要望を反映した協力を素早く行うことができる等の特徴を有している。NGO等の活動では途上国の環境問題への対応も数多く取り組まれており、政府としても支援を行っている。(第3-3-1図)。
環境事業団は、生活環境の維持改善・自然環境の保全及び産業の健全な発展に資することを目的として設立された政府の特殊法人であり、「地球環境基金」事業を実施している。
「地球環境基金」は、1992年(平成4年)に開催された地球サミットの成果を受け、1993年(平成5年)5月に国と民間の拠出によって創出されたもので、環境保全に取り組む内外の民間団体(NGO)の活動を支援している。支援内容は、第3-3-2図に示すとおり、NGOの環境保全活動への助成と、これらNGOの活動の振興に必要な情報提供や研修等である。
外務省では、必ずしも環境に特化したものではないが、平成元年度から、国際開発協力関係民間公益団体補助金(NGO事業補助金)や草の根無償資金協力を実施している。
NGO事業補助金制度は、我が国のNGOが途上国で行う開発協力事業費の2分の1を上限として政府が補助するものである。事業開始時は約1億円が計上されていたが、取扱い額は年々増加し、平成9年度は総額12億円が計上されている。
草の根無償資金協力は、途上国の地方公共団体や研究・医療機関、途上国で活動する内外のNGOなどが実施する比較的小規模な事業に対し、我が国の在外公館が直接資金協力するものである。事業開始当初は3億円であった予算も、平成9年度には50億円の規模になっている。
(2) 地方公共団体の取組
近年は、地方公共団体の環境行政も地球環境を視野に入れた、より広範な対応が求められるようになってきている。
我が国の地方公共団体では、四日市市や北九州市など、自らの公害経験を活かして公害対策を中心とした環境協力を進めている。また、大阪府や滋賀県のようにUNEPの施設を誘致し人材育成の拠点とする等、国際的なイニシアチブを発揮する積極的な取組が見られる。更に、単独で協力を行うのではなく、ODAとの連携や横断的取組も行われている。
ア 北九州市による大連環境モデル地区計画の提案
環境協力の地方公共団体の取組の好例として、北九州市の「大連環境モデル地区」計画があげられる。
この計画は、中国における環境改善のパイロットモデル事業として、大連市を自然が豊かで環境水準の高い都市にすることを目的に、平成5年12月、北九州市の提案により始まったものである。以来、北九州市と大連市は計画の実現に向け協議を重ねるとともに、平成6年度にまとめた「大連市との環境国際協力の在り方に関する調査報告書」に基づき、マスタープランの策定をODAで行うことを提案している。これを踏まえ、平成8年より我が国は、中国政府からの要請に基づき「大連市環境モデル地区整備計画調査」を実施している。本調査は、「都市環境と社会・経済発展が調和した」モデルとなる「環境モデル地区」建設計画に対し、大気汚染や水質汚濁等への対応策を含め、環境への負荷の少ない持続可能な社会開発に必要な総合的な環境基本計画を策定し、その中で選定された優先プロジェクトの準備的実施可能性調査を実施するものである。日本の自治体レベルでの国際協力が、途上国における都市の総合的な環境改善プロジェクトとしてODAの対象に取り上げられたのも、JICAと地方公共団体が連携して共同調査を行うことになったのも、これが初めてのケースである。これは北九州市が持つ公害克服の経験と技術を活かし、特に行政分野や工場プロセス(特にクリーナープロダクション技術)分野での協力を目指すものである。
イ 国際環境自治体協議会(ICLEI)の活動
国際環境自治体協議会は、地球環境の保全を目指す地方公共団体などの国際的ネットワークである。1990年(平成2年)9月、国連の「持続可能な未来のための世界会議」(ニューヨーク)の席上、参加した42か国、200以上の自治体と、国連環境計画(UNEP)、国際地方自治体連合(IULA)などの国際機関の提唱で設立されたものである。現在、IULA公認の国際環境協議機関として活動しており、世界約50か国、約240の自治体が加入し、日本からも50近くの自治体が加入している。国境を越えた自治体の環境ネットワークを広げ、自治体レベルの地球環境問題への取組を、国際的な運動に高めようというのが、活動目的である。1993年6月、東京の(財)地球・人間環境フォーラム内にアジア・太平洋地域をカバーする日本事務所が開設された。アジア太平洋地域における加盟状況は、10か国74自治体・団体であり、日本をはじめとして、インド、インドネシア、韓国、ネパール、バングラデシュ、フィリピンなど自治体間のアジア太平洋地域でのネットワーク化が進んできている。
囲み3-3-2 環日本海圏4自治体の取組
平成9年8月、鳥取県で開催された「第4回環日本海圏地方政府国際交流・協力フォーラム」の主席代表会議において環境面に関する国際交流と協力方策が合意された。
共同発表の中で、「地球の環境保全は、人類共通の課題であることについて共通の認識を持つとともに、特に、4地域(鳥取県、中国吉林省、韓国江原道、ロシア沿海地方)における環境面での相互協力を図るため、地域間の情報交換、研究者の相互派遣等についての取組を共同で進めていくこととした。」としている。さらに、学術研究者会議で、水環境情報や調査研究、環境法令等の参考となる事項についての情報交換や4地域での共同研究テーマとして「湖沼の富栄養化のメカニズムの解明とその防止について」を定め、他分野等を含めた相互の国際協力を推進している。
(3) 事業者による取組
事業者による途上国の環境保全に関する取組としては、?非営利的活動として、社会的貢献として行われる環境協力のほか、?途上国内における事業活動における環境配慮を通じた、環境保全のための技術移転・環境教育・意識啓発、?環境保全のための事業活動として、エコビジネス(環境関連産業)としての技術移転があげられる。また、?環境ODAにおける案件の発掘や実施においても民間事業者が大きな担い手となっていることも事実である。さらに、?民間は途上国の企業等に投融資を行っているが、その際の環境配慮、あるいは、エコビジネスそのものへの投融資も大きな役割を果たしうる。
これらの取組については、?について、植林活動や、環境モニタリング機材の贈与、技術的調査、人材育成、研究支援などの取組が知られているほかは、資料が限られており、必ずしも全貌が明らかではない。ここでは、既存の資料より、その一端を紹介するにとどめる。
ア 在外日系企業の環境配慮
海外に進出している日系企業による環境配慮に関しては、平成7年度に環境庁が実施したアンケート調査を紹介したい。この調査は、フィリピン、タイ、インドネシア、マレーシアの東南アジア4か国において事業活動を行っている日系企業を対象に、現地の日本商工会議所の協力を得て実施したものである。
調査によると、進出に当たっての環境対策として、第3-3-3図のとおり法的義務はなくとも自主的に環境アセスメントを実施した企業が15.5%あり、環境問題に取り組むための部署や担当者を置いている企業が51.3%あった。環境保全のための経費や投資等の支出についても、現行規制をクリアするために最小限必要なもの以上に行いたいと考えている企業が74.1%にも上っている。
以上のように、少なくともこの4か国に進出している事業者においては、事業活動の環境配慮には積極的な姿勢が伺える。
環境庁が平成8年度から、フィリピン、インドネシア等を対象に実施している「日系企業の海外活動に係る環境配慮動向調査」の結果を見ると、これらの国では厳しい環境規制やアセス制度が既に導入されており、日系企業としても、?我が国よりも厳しい基準に対し技術開発をしつつ積極的に対応している事例、?地域住民に、工場の環境対策を積極的に公開している事例、?相手国技術者に環境技術を積極的に移転している事例等が見られ、事業者の積極的な取組姿勢が伺える。
イ 経団連の取組
(社)経済団体連合会の環境対策では、平成3年の「経団連地球環境憲章」の制定を皮切りに自主的な取組が進められている。平成8年に発表された、「経団連環境アピール」では、地球温暖化問題をはじめ環境問題への取組の重要性が近年ますます高まっていることを踏まえ、環境保全とその恵沢の次世代への継承のため「持続可能な発展」を実現しなければならないとしている。その際のキーワードとして、?個人や組織の有り様としての「環境倫理」の再確認、?技術力の向上等、経済性の改善を通じて環境負荷の低減を図る「エコ・エフィシェンシー(環境効率性)」の実現、?「自主的取り組み」の強化、の3つが重要としており、自主的かつ積極的な責任ある取組をさらに進める旨の宣言がなされている。
宣言では、企業も同様に「地球企業市民」としての意識を持ち、政府や消費者・市民・NGOとの連携を図り、行動する必要がある。また、こうした国民の自覚を促すためにも、企業としても環境教育を支援し、社内外における環境啓発活動に積極的に取り組むことが有効である、としている。海外に向けた取組としては、地球温暖化対策について、政府との緊密な連携の下、途上国への技術移転のための「共同実施活動」への積極的な参加や、企業自ら、森林保護や植林の推進等を掲げている。
海外事業展開に当たっての環境配慮について、海外生産・開発輸入をはじめ、わが国企業の事業活動の国際的展開は、製造業のみならず金融・物流・サービス等に至るまで、急速に拡大していることを踏まえ、経団連地球環境憲章に盛り込まれた「海外事業展開における10の環境配慮事項」遵守はもちろんのこと、海外における事業活動の多様化・増大等に応じた環境配慮に一段と積極的に取り組むと記している。
また、平成10年に発表された「経団連環境自主行動計画」およびその毎年の進捗状況をレビューする「行動計画フォローアップ」では、海外事業活動における環境保全活動の実施状況等を毎年フォローアップしている。
経団連では、92年に経団連自然保護基金を設立して、法人・個人からの寄付をもとに、アジア地域を中心とする発展途上国において、内外のNGOが実施する自然保護プロジェクトに対して支援を行なっている。
(4) NGOによる取組
NGO(Nongovernmental Organization)は直訳すれば非政府組織であるが、一般には広く民間公益団体を意味するものとして用いられており、ここではNPOを含め民間援助団体をNGOとして扱うことにする。
NGOの環境協力に関する活動形態は様々な分野にわたり、各種の調査・分析、技術移転、情報の普及啓発の他、植林や砂漠化防止のように環境の回復そのものを活動内容とするものもある。NGOの活動は、近年は高度に専門化された分野においても活発な取組が見られるようになっており、今後の一層の活躍が期待される。
以下、環境協力を行ってきている我が国のNGOの中からいくつかの取組を紹介する。
ア オイスカ・インターナショナルの活動
オイスカ(Organization for Industrial, Spiritual and CulturalAdvancement)は、「産業・精神・文化という人間の生存に不可欠な三要素のバランスを保ちながら発展させていくことが、人類の繁栄と幸福につながる」との信念に立ち、それを「全地球規模で促進していくこと」を目的として1961年(昭和36年)に設立された。アジア・太平洋地域を中心として「土に根ざす農業を中心とした人づくり、国づくり」を目指して活動している。 オイスカの開発協力は、技術援助だけでなく地域を担う人材育成に力を入れている。アジア太平洋地域の各地に設置している研修センターは、自助努力のための人づくりの場として、かつ開発・環境協力の拠点として、現地の青年に研修の機会を提供している。また、国内の4つの研修センターは、途上国から地域開発のリーダーを目指す青年を招き、独自の方式による技術研修を行っている。現在国内で研修を受けた青年だけで31か国、6,000名を超え、途上国地域のリーダーとして各分野で活躍している。
イ アジア民間交流ぐるーぷの活動
アジア民間交流ぐるーぷ(APEX)は、1987年(昭和62年)の発足以来、主としてインドネシアの中部ジャワ州を活動の舞台として、低価格住宅供給、職業訓練、環境保全等の分野で活動を続けている。まず現地へ入って、現地の人々とともに何が必要とされているかを考え、尊敬に値するような活動をしている現地のNGOと協力し、それらのNGOの活動を支えていくのがAPEXの基本的な活動のスタンスである。活動にあたっては、それぞれの地域の社会条件に適合的で環境にも負荷をかけない適正な技術の選択を重視している。環境分野では、ジョクジャカルタ市のNGOと協力して実施している現地向けの排水処理技術の開発と普及の活動が、現在もっとも大きく展開しつつある事業である。
ウ 日本国際民間協力会の活動
日本国際民間協力会(NICCO)の活動目的は、地球規模的な視野に立って、途上国の生活困窮者へさまざまな「自立支援プロジェクト」を展開することにより、経済的・精神的な自立を図ることにある。NICCOは1979年(昭和54年)12月カンボジア難民救援会(KRRP)として発足し、徹底した人道主義に基づいての救援活動を20年間展開してきている。現在NICCOは、貧困の解決に向けた取組に加えて地球環境を保全するため、熱帯雨林や絶滅の危機に瀕している植物の再生、非木材パルプの研究、牛銀行や家畜銀行などの長期無利子資材貸与返済制度の実施、洋裁や編物、語学の技術訓練等を、ベトナム、ラオス、ネパール、ヨルダンなどの国々で展開している。また、日本国内では、各種イベントのほか、今後の国際社会を担う人材の育成事業としてインターンシッププログラムを実施している。