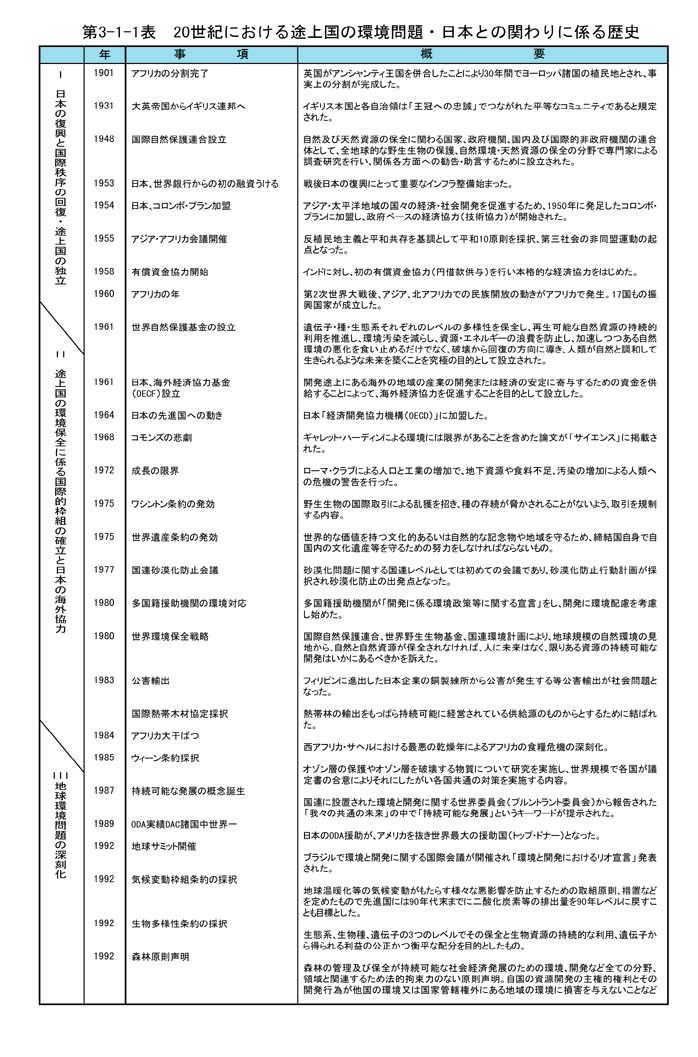
1 環境問題をめぐる国際的議論の推移
人間活動に起因する環境問題、とりわけ地球規模の広がりを見せるものに対処していくためには、すべての国が共通の目標に向かって足並みのそろった努力をしていかなければならない。特定の国のみが環境対策を講じることによる利益を他の国が一方的に受けたり、特定の国が環境対策を講じないことによる不利益を他の国が一方的に受けるようでは、各国の真剣な取組を促すことは難しいであろう。そこで、それぞれの国が地球環境保全のための努力を行うと同時に、すべての国が適正に責任を分担して参加できるような国際的合意づくりが必要となる。
しかし、国際的合意の形成は必ずしも容易なものではない。特に先進国と途上国の環境問題に関する立場の違いが障害となっている。本章では、まず地球環境問題に対する国際的取組の動きを概観してみよう。
(1) 国連人間環境会議 1972年(昭和47年)
国連人間環境会議は、1972年6月5日からスウェーデンのストックホルムで開催された。
スウェーデンは1968年(昭和43年)のOECDの国際科学協力政策委員会の特別会議において、国境を越える大気汚染物質の移動によりスカンジナビア半島の森や湖が被害を受けていることを示した。そして、国連総会で環境問題のために地球規模での国際協力の必要を訴えた結果開催されたのが、国連人間環境会議である。
当時の社会的背景は、以下のようなものであった。
第一は、先進工業国における1950年代、60年代の急速な経済発展である。先進工業国では飛躍的な経済成長に伴って、排気ガス、排水、廃棄物等の環境負荷が局地的に急速に増加した。これらの環境負荷が自然の浄化能力を超えつつあり、無限と考えられがちであった自然の許容量の限界が認識されるようになった。
第二は、地球の有限性、一体性の認識である。人口、資源など地球上ではあらゆる要素が複雑微妙に相互依存しているため、これを一体のものととらえて協力して守っていかなければならないと考えられるようになった。地球を「宇宙船地球号」と呼ぶ考え方に端的に表れている。
第三は、開発途上国の環境問題である。途上国では、工業活動に起因する汚染の直接的な環境破壊よりも、人口の増加、低い栄養摂取量、住宅、教育施設の不足、自然災害、疫病のおそれといった貧困からの脱出が最大の問題となっていた。
南北の問題についてこの国連人間環境会議では、開発が環境汚染や自然破壊を引き起こすことを強調する先進国と、未開発・貧困などが最も重要な人間環境の問題であると主張する開発途上国とが鋭く対立した。事務局長は、環境に関する行動に与えられる優先順位について先進国と開発途上国の間で明確な差があることを認めた上で、「開発途上国においては、食料、住宅、仕事、教育または保健という生活に不可欠なものより将来の不確かな必要性を優先させることなど到底できないことは明らかである。」と述べている。ここで採択された宣言や行動計画には、先進国と開発途上国のそれぞれの国々の主張が並列的に盛られることとなった。
(2) ナイロビ会議 1982年(昭和57年)
ナイロビ会議(UNEP管理理事会特別会合)は1982年5月にケニヤのナイロビで開催された。
この会議で採択されたナイロビ宣言では、
「過去10年間に、新たな認識が生まれた。すなわち、環境の管理および評価の必要性、環境、開発、人口、資源の間の密接かつ複雑な相互関係、並びに特に都市において人口増加により生じた環境への圧迫が広く認識されるようになった。この相互関係を重視した総合的で、かつ、地域ごとに統一された方策に従うことは、環境的に健全で、かつ、持続的な社会経済の発展を実現させる。」
また、
「環境に対する脅威は、浪費的な消費形態のほか貧困によっても増大する。双方とも人々に環境を過度に利用させる可能性がある。」
と述べている。こうして先進国と開発途上国との環境と開発をめぐる議論についての共通の土俵ができた。
(3) 環境と開発に関する世界委員会 1984〜1987年(昭和59〜62年)
環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)は、21世紀の地球環境の理想像を模索し、これを実現するための戦略を策定するための特別委員会を国連に新設すべきであるという日本からの提案に基づいて設けられた。この委員会は、1984年(昭和59年)から1987年(昭和62年)までの間活動を行い、報告書「われら共有の未来」を国連総会に提出した。報告書では、環境と開発の関係について「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」という「持続可能な開発」の概念を打ち出し、これはその後の地球環境保全のための取組の重要な道しるべとなっている。
(4) 国連環境開発会議 1992年(平成4年)
国連環境開発会議(地球サミット、UNCED)は1992年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された。
この会合において「環境と開発に関するリオ宣言」は、全世界的なパートナーシップを構築し持続可能な開発を実現するための行動原則、環境と開発をめぐって先進国と開発途上国の間で交わされた議論の到達点を集約したものとして採択された。
それまでの対立の論点をまとめると以下の3点に集約される。
ア 環境問題の責任論
環境問題の責任に関する開発途上国の主張は、経済発展を追求するあまり、枯渇性資源等を過剰に消費し、大量の廃棄物を放出してきたのは先進国であり、先進国にこそ今日の環境問題の責任があるというものである。開発途上国では、人口増加とそれに伴い加速する貧困により生存のためにやむなく自然を犠牲にし、自然環境の悪化がさらに貧困を加速するという悪循環がある。このような悪循環からの脱却のためにも経済的発展を必要としている。従って先進国に起因する環境問題を理由に、開発途上国の工業発展や森林伐採を制約されることには強い反発を表している。
これに対し、先進国の主張は、今日の環境問題は全世界共通の問題であり、地球環境悪化による被害は、先進国、開発途上国の区別なく受けるのだから協力して取り組まなくてはならないというものであった。今後、開発途上国が、かつての先進国のように経済発展を優先して環境保全対策を怠ることとなれば、近い将来の地球環境への負荷の大半を途上国が占め、先進国の負荷と相まって地球環境の悪化は取り返しのつかないほど進んでしまうという懸念がある。そのために、環境問題に対する途上国の取組の重要性を訴えている。
イ 開発の権利の問題
開発の権利に関して開発途上国は、自国の資源は、自国の環境・開発政策に従って自由に利用する権利を尊重されるべきであり、地球上の全ての人間は適切な生活水準を享受する権利があり、そのために開発する権利を有することを主張した。
これに対する先進国側の主張は、環境上の制約から開発が制限されることもあり得るというものであった。
ウ 資金、技術移転の問題
環境対策に係る資金の問題に関して開発途上国は、温暖化等の地球環境問題はもとより、貧困などの途上国の問題は先進国にその原因があるため、問題解決に必要な資金は「補償」的な性格を有しており、先進国は義務としてこれを拠出するべきであると主張した。また、この資金は開発途上国の意見が反映される新たな国際的資金供給メカニズムを通じてもたらされるべきことを要求した。
これに対し先進国は、追加的資金の必要性は認めるが、資金供給は先進国の義務として負うものではなく、資金供給メカニズムの創設についても、2国間及び多国間の既存の援助システムの活用が重要であるとした。
技術移転について途上国は、環境保全のための技術の移転は地球環境問題の解決に不可欠であるため、移転は非営利的条件で行うべきであり、民間の保有する技術であっても、金利や返済期間等の条件が緩和された譲許的な条件での移転を行うべきであると主張した。先進国は、技術移転については受け入れ側の能力向上が重要である、民間に対して非営利的条件での技術移転の要求は不可能であり、技術開発の停滞を防ぐためにも知的所有権の尊重が必要であるとした。
囲み3-1-1 地球サミット
国連環境開発会議は、1992年6月3日から14日にわたって、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて開催された。この会議には、180か国が参加し、100か国余の元首、首脳が自ら出席、世界各国から地方公共団体やNGOが多数参加するなど、地球サミットと呼ぶにふさわしい史上かつてない大規模な会議であった。
この会議の開催は、1989年の国連総会で決議され、3年間の準備期間を通じて4回の公式な準備会合をはじめ、多数の準備のための会合を経てなされたものである。その結果、環境保全に重点をおく先進国と開発や貧困問題の解決を重視する開発途上国の間で様々な論点について議論を深め、環境問題に関して世界的に認識が一致した。
具体的には、21世紀に向けて国家と個人の行動原則である「環境と開発に関するリオ宣言」、その諸原則を実行するための行動計画である「アジェンダ21」等が採択された。これらの成果は、その後の環境問題の取組の方向を示す礎として重要な役割を果たしている。
(5) 国連環境開発特別総会 1997年(平成9年)
国連環境開発特別総会は、1997年ニューヨークで開催された。この総会は国連環境開発会議から5年目を節目として、その後の各国の取組を振り返り、今後の取組姿勢を確認するためのものであった。
この間の国際的な取組の進展としては、生物多様性保全等のため「生物多様性条約」が1993年(平成5年)12月に、地球温暖化対策として「気候変動枠組条約」が1994年(平成6年)3月に、「砂漠化対処条約」が1996年(平成8年)12月にそれぞれ発効している。しかし、総会で採択された文書では、国連環境開発会議で確認された対策は進んでおらず、地球環境の全般的な傾向は悪化しているという認識が示された。
このように南北間の議論は確実に前進しているものの、まだ数多くの問題は残っており、一歩ずつお互いの立場を理解して地球規模の問題に対し協力して取り組めるようになることが必要である。
(6) 地球温暖化問題にみる南北間の対立
では、これまでの議論の成果は具体的な環境問題への対策にはどのように反映されているのだろうか。1997年に開催された京都会議(COP3)、1998年(平成10年)に開催されたブエノスアイレス会議(COP4)においても、相変わらず先進国と開発途上国の姿勢の違いが地球温暖化問題に関する国際的取組の進展の障害となっている。以下で直近の状況として、温暖化問題における先進国と開発途上国の間の議論もまとめておきたい。
ア COP3(京都会議)
COP3は、1997年(平成9年)12月に京都において開催された。この会議では温暖化防止のために先進国における温室効果ガスの削減目標に関して合意が得られたという点で大いに意義がある。
南北間の議論として先進国側は、今後途上国からのCO2排出の増大が見込まれるため途上国の削減目標設定等の参加が欠かせないとした。これに対し途上国側は、CO2排出削減は現状に至らしめた先進国が先に着手するべきである、先進国の現在の取組は不十分であると反論した。
京都議定書の発効には、?55ヶ国以上の締結、?締結した先進国の1990年の二酸化炭素排出量の合計が先進国の総排出量の55%以上を占める、という条件を充足する必要がある。?の条件充足には、先進国の二酸化炭素総排出量の約36%を占めるアメリカの締結が極めて重要であるが、アメリカは締結のためには途上国の意味のある参加を要求している。このように、途上国の参加が地球温暖化防止に係わる国際交渉上重要な課題となっている。
囲み3-1-2 地球温暖化防止京都会議
地球温暖化防止京都会議は、平成9年12月1日、京都国際会館において開幕した。参加は、158か国の締約国政府代表団及び6か国のオブザーバー代表団に加え、各国から集まったNGO及び報道関係者を含めると10,000人近くであり、環境問題に関連して我が国が招致した国際会議としてはかつてない規模のものであった。
この会議に向けて、半年以上も前から民間や市民団体等においても様々な準備作業が行われ、会期中もNGO等がロビー活動を精力的に展開した。
検討の対象が、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減量の数値目標の設定を始めとした、各国の経済活動に深い関わりを持つ重要な内容であったため「京都議定書」の調整は難航し、夜を徹した協議の末にようやく議定書が採択されたのは本来の会期最終日を過ぎていた。こうして温室効果ガスの削減という困難な課題の解決に向けて第一歩を記した点で、京都会議は成功の評価に値する。
今後我が国が主導して国際的に環境問題への取組を進めていく上でも、重要な意味を持った会議であったと言える。
イ COP4(ブエノスアイレス会議)
COP4は1998年(平成10年)11月にアルゼンチンのブエノスアイレスにおいて開催され、今後の国際交渉の道筋を定めた「ブエノスアイレス行動計画」が作成された。この会議では主要な論点として、排出量取引等の制度の具体化と同様に、途上国の参加問題が注目されていた。しかし、途上国の自主的約束を議題とするかどうかで会議は初日から紛糾し、結局この問題は議題から削除された。
このように途上国は、温室効果ガスの排出削減に関するコミットメントに参加することに従来と同様強力な反発を示したが、従来の一枚岩の対応が崩れ、一部の途上国が自主的約束に前向きな姿勢を見せるなど、変化の兆しも見えている。