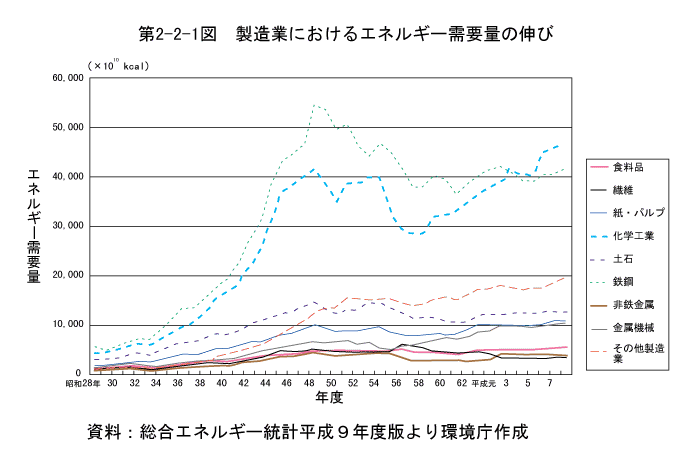
1 化学物質に依存する現代社会と環境問題
(1) 化学物質に依存する今日の社会の現状
今日、工業的に生産される化学物質は、世界では約10万種、我が国でも約5万種とされており、その生産量、種類数は年々増加している。化学物質は、石油化学製品やナトリウム化合物といった工業原料として用いられる基礎的な化学製品から、合成洗剤、塗料、化粧品、医薬品といった身近な製品に至るまで、多種多様な製品の製造等に用いられている(第2-2-1図、第2-2-2図)。
我々の身の回りでも化学物質を用いた多くの製品が使用されている。例えば、台所まわりを例にとってみると、食品を密閉して保存するプラスチック容器や、食品を包むラップ、飲料のペットボトル、ビニールの買い物袋や包装袋など、食品を包んだり保存したりするだけでも用途に対応して多様なプラスチック類が使われている。また、これらの化学製品の機能を高めるために可塑剤、難燃剤、抗菌剤等を含有する場合もある。また、合成洗剤やスプレー式殺虫剤なども、洗い物や虫の駆除などに大変便利である(第2-2-3図)。この他にも、住宅に用いる断熱材や断熱ガラスなどがもたらす省エネルギー効果、医薬品や衛生用品の開発などによる医療、衛生分野の改善など、日常生活に化学物質が貢献している事例は多い。
このように、現在の我々の利便性は、多種多様な化学物質によって多くを支えられていると言える。
一方、一部の化学製品においては、その製造、使用、廃棄の過程で、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質が環境に排出され、環境中へ拡散・蓄積することによって、環境汚染をもたらしたことも事実である。その背景には、利便性を追求し、多種多様な化学物質を大量に生産、消費、廃棄する社会経済活動や生活様式を我々が受け入れてきたということがある(第2-2-1表)。
(2) 化学物質問題への対応
ア 化学物質問題とそれに対する国内外の対応の状況
化学物質による汚染は、我が国では、明治時代の足尾銅山鉱毒事件にまでさかのぼることができる。鉱毒による渡良瀬川流域の土壌等の汚染により農作物などに被害が生じ、住民を移住させ遊水池を建設する措置がとられた。さらに、第1節でも述べたとおり、第二次世界大戦後の急速な経済復興の中、昭和31年に水俣病が公式に発見されるとともに、高度経済成長期には、新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病などさらに広い範囲で公害問題が発生した。これらは、環境中に排出された化学物質が長期間にわたり摂取され蓄積することで大きな健康被害が生じた歴史的な事例である。
また、1962年(昭和37年)にレイチェル・カーソン女史が発表した「沈黙の春」は、科学者の間に多くの議論を巻き起こすと同時に多くの分野に影響を与え、人々の環境に対する認識を変えさせた。この著書の中で、DDT等有害な化学物質が生態系に入り込むと、食物連鎖の過程で生物体内に濃縮され、上位の動物ほど体内から高濃度のDDT等が検出されることを明らかにした。DDTは、1930年代に強い殺虫作用が注目され、戦後我が国でもシラミなどの駆除のため大量に使われたが、こうした残留性の強い有機塩素化合物による環境汚染への認識の高まりの中で、低毒性、低残留性農薬の開発・利用への転換が進んだ。日本では昭和46年に、アメリカではその翌年にDDTの使用が禁止された。
また、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけとして、環境中のPCB汚染がクローズアップされ、国民の関心が急激に高まった。PCBのように、国民生活や産業等に有用な製品として使用される化学物質であっても、人の健康を損なうおそれがある化学物質が、消費、廃棄を通じて環境を汚染することによって健康影響を生じさせる可能性があることが指摘された。このPCBのような難分解性で蓄積性のある化学物質による人の健康への影響を防止するため、昭和48年、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定され、事前審査制度を導入するとともに、PCBと同様の難分解性、高蓄積性、長期毒性の性状を有する化学物質の製造、輸入及び使用を規制する措置が取られた。その後、昭和57年のトリクロロエチレン等による地下水汚染を契機とした同法改正により、トリクロロエチレン、有機スズ化合物等の、生物の体内への蓄積性は低いものの難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質に対しても規制が導入された。
環境庁においては、化学物質による環境汚染を的確に把握し、評価し、必要な対策を講ずることが急務とされた。このため、膨大な数の化学物質から調査対象とすべき優先物質を決定し、それらの測定・分析手法を確立することを急いだ。昭和54年度からは第一次化学物質環境安全性総点検調査、平成元年度からは第二次総点検調査が実施された。これらは、排出源の特定されない一般環境での汚染の実態把握に貢献した。
一方、アメリカのサンタクララバレーにおける地下水汚染を契機に、昭和57年に行われた地下水調査で、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが全国各地で飲用に適さない高い濃度で検出された。これを受けて有害物質を含む水の地下浸透を禁止する水質汚濁防止法の改正等が行われた。
その後、平成に入り、ベンゼン等の揮発性有機化学物質等による大気汚染が注目を集めるようになり、健康影響の未然防止の観点から大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質対策が位置づけられた。
このように、環境汚染の実態の把握(モニタリング)と科学的知見の進展を踏まえて、化学物質対策は漸次強化、充実が行われてきた。
化学物質による環境汚染に対しては、国際的な取組も進められてきた。陸上で発生した廃棄物の海洋投棄及び洋上焼却に関しては、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(通称「ロンドン条約」)が1975年(昭和50年)に発効している。1978年(昭和53年)には、船舶などからの油、有害液体物質及び船舶発生廃棄物の排出による海洋汚染を防止する「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が採択された。国連環境計画(UNEP)では、1982年(昭和57年)に起こった「セベソ事件」(1976年(昭和51年)にイタリアのセベソの化学工場の爆発事故で生じたダイオキシン類を含む汚染土壌が保管場所から持ち出され、北フランスの小さな村で見つかった)によって明らかになった有害廃棄物の越境移動の問題や、1988年(昭和63年)にナイジェリアのココ港付近にヨーロッパから輸出されたPCBを含む廃トランスなどの有害廃棄物が多量に不法投棄された「ココ事件」等を契機に、1989年(平成元年)3月に「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が採択された。
これらの国際的な取決めに対し、我が国も必要な国内法制度を整備、条約への加入を進めるとともに、化学物質対策に反映してきた。
そして最近では、ある種の有害化学物質がもたらす潜在的な被害から人の健康と環境を保護し、これらの有害化学物質の環境上適正な使用に資するため、使用が禁止又は厳しく規制されている化学物質の貿易時における情報交換の手続き及び輸出先国への事前通報・承認(PICすなわちPrior Informed Consent)手続きを定めたロンドンガイドラインを条約化したロッテルダム条約が1998年(平成10年)9月に採択された。さらに、PCBやDDTなどの残留性が高く生物濃縮されやすい有害な化学物質(POPs)による地球規模の汚染が問題とされ、1997年(平成9年)2月のUNEP管理理事会においてそれらの削減又は排出を廃絶することを目的とした国際的拘束力のある手段を2000年(平成12年)中を目途に確立することが決議されたことを受け、1998年(平成10年)6月に第1回、翌1999年(平成11年)1月に第2回の条約化政府間交渉委員会が開催されるなど、国際的な取組が進んでいる(第2-2-4図)。
イ 新たな化学物質問題
最近では、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題や、ダイオキシン類による人の健康への影響や環境汚染に国民の関心が高まっている(第2-2-5図)。
内分泌かく乱化学物質を例に取ると、平成10年9月に東京都が実施した「環境に関する世論調査」では、内分泌かく乱化学物質に対して、「非常に不安である(47.9%)」と「少し不安である(36.6%)」を合わせて8割以上の回答者が、「不安である」と回答した。また、岩波書店「広辞苑第5版(平成10年11月)」には、「環境ホルモン」という言葉が初めて登場した。これだけ内分泌かく乱化学物質問題が国民にとって不安なものとして認識された理由は、内分泌かく乱化学物質問題が注目された当初、人体に対する内分泌かく乱作用を科学的に評価するための試験、評価手法が未整備であるにもかかわらず、研究室レベルでの実験や野生動物を対象とした調査等の結果(次項に述べる)と、日常生活の中で生活者がさらされる状態が同じレベルで認識されたことによるところが大きい。
このため、一時期内分泌かく乱作用を疑われた食品容器等を忌避する動きが一部で見られたが、人の健康に重大な影響が生じるという科学的知見が得られておらず、当面使用禁止等の措置を講ずる必要はないとの厚生省の見解が浸透するにつれて、次第に平静化に向かっている。
以下では、内分泌かく乱化学物質、いわゆる環境ホルモン問題と、ダイオキシン問題という新たな化学物質問題と、それらへの対応を概観する。