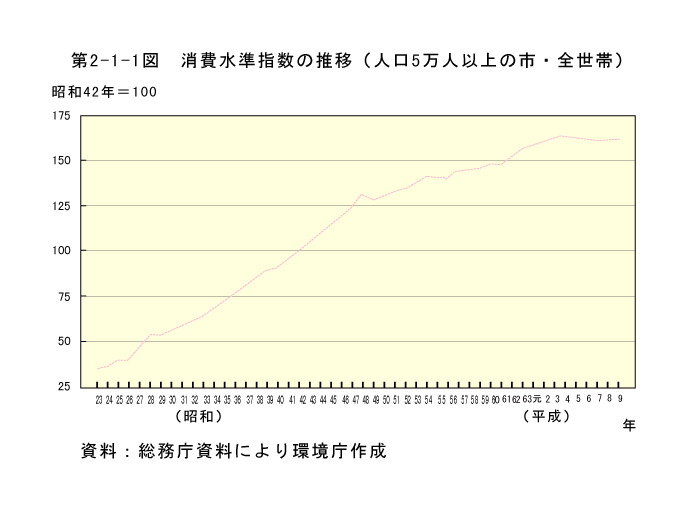
2 利便性を追求する生活様式と環境負荷との関わり
次に、まず生活様式がどのように変化したのかを踏まえた上で、利便性の追求と環境負荷との関わりについて、資源・エネルギーの消費、廃棄物、水まわり、自動車の利用のそれぞれの観点から概観する。
(1) 消費生活等から見た生活様式の変化
国民の生活様式の変化を、この30年間の家計における消費水準指数(名目消費支出の伸びを実質化した指数)の推移で見てみると、戦後ほぼ一貫して伸びており、平成4年にはピークに達していることが分かる。その後横這いが続いているものの、平成8年では消費水準は30年前に比べ約1.6倍になっている(第2-1-1図)。
この間、家計の消費支出に占める各費目の割合も変化している(第2-1-2図)。食料費、被服及び履物費の割合が減少している一方で、光熱・水道費、交通・通信費、教養娯楽費等は割合が増加している。特に自家用車の普及に伴う自動車関係費の増加、耐久消費財の大型化・高級化に伴う支出の増加、エネルギー使用の増加に伴う光熱・水道費の増加などから、国民の利便性の追求や快適志向がうかがわれる。
また、財・サービス区分別の割合で消費支出を見てみると、耐久財、半耐久財、非耐久財の合計の消費割合が減少している一方、サービスの消費割合が増加している。消費のサービス化の一例として、食料費に占める中食(調理済み食品)費、外食費の占める割合を見てみると、年々上昇傾向にあり、この25年間で中食費の割合は約2.5倍、外食費の割合は約2.0倍になっている。全体の消費水準が上昇していることを考えると、消費のサービス化は、モノの消費が減少したということではなく、消費のサービス化がモノの消費以上に進行していることを意味している。
次に生活時間の使い方の変化を見てみると、まず労働時間については、平成元年4月から一部の職場を除いて労働時間の週44時間制が実施され、平成9年4月に週40時間労働時間制が全面的に施行されたことを受けて、年間総労働時間は昭和63年の2,111時間から平成9年には1,900時間に減少している。こうした労働時間の減少や家事の省力化に伴い、テレビを見たり新聞を読んだり、レジャー活動を行ったりする自由時間が増加している。日本放送協会の生活時間調査を基に昭和45年と平成7年の自由時間を比較すると、平日では3時間36分から4時間23分へ、土曜では4時間8分から5時間57分へ、日曜では5時間49分から6時間56分へと大きく伸びてきている(第2-1-3図)。
生活の志向や習慣の変化は、例えば利便性や快適性の追求による自動車利用の増加、自由時間の増加によるレジャー活動の活発化、生活リズムの夜型化による照明用エネルギーの使用量の増加など、環境負荷と密接な関係を持っている。生活の志向や習慣の変化により、環境負荷がどのように変化してきたのか、以下ではより具体的に考えてみたい。
(2) 日常生活において発生する環境負荷
ア 資源消費とエネルギー消費
日常の生活は、大量の資源やエネルギーを消費することで便利で快適になり、生活様式は大きく変わってきた。しかしその一方で、自然界からの資源採取量は増加し、資源利用の持続可能性が失われるおそれも生じている。
我が国の平成8年における1人当たりの一次エネルギー消費量は石油換算で4.06tであり、アメリカの50.4%、OECD諸国平均(4.61t)の88.1%にとどまるものの、世界平均(1.48t)の2.7倍以上、中国の5.5倍以上、インドの14.6倍以上にのぼっている。また、平成8年における1人当たりの紙消費量は245.2kgで、アメリカの76.7%にとどまるものの、世界平均(54.9kg)の4.4倍以上にものぼる。経年的に見ても、1人当たりのエネルギー消費量や紙、プラスチック等の物質消費量は、第2-1-4図のとおり、高度成長期以降増大している。
日常生活における利便性と環境負荷との関わりを具体的に考える例として、自動販売機の普及と電力消費について考えてみたい。自動販売機は街の至る所に設置されており、手軽に利用できるため、社会に広く浸透しており、販売されている商品も、清涼飲料、酒類、たばこ、食品等、多岐にわたっている。日本自動販売機工業会によると、我が国においては平成10年末で約550万台の自動販売機が普及しており、その半数近い260万台を、清涼飲料、牛乳、コーヒー、酒類を含む飲料自動販売機が占めている。自動販売機による販売金額も堅調に伸びており、平成10年では自動販売機を通じて国民1人当たり年間5万円以上の商品を購入した計算になる(第2-1-5図)。
このように、いつでも、どこでも、手軽に利用できることから広く普及し利用されている自動販売機であるが、そのうちの飲料自動販売機の年間電力消費量は平成8年度で78億kwh(国内年間総発電量の0.77%)、1台当たりでは約3千kWh消費している。これは1世帯の年間電力消費量のおおよそ6割に相当すると推計される。生活者の利便性、快適性の追求により多くのエネルギーが消費されていることが分かる。
囲み2-1-3 自動販売機業界の省エネルギー対策
日本自動販売機工業会では、平成3年に飲料自動販売機の中でも最も普及台数の多い清涼缶飲料自販機1台当たりの消費電力を5年間で20%低減する省電力計画を実施し、平成8年に目標値を達成している。また、平成13年までにカップ式コーヒー自動販売機や牛乳自動販売機などを含むすべての飲料自動販売機の消費電力量をさらに15%低減する計画を実行している。
また、電力会社と飲料メーカー、自動販売機メーカーが共同で、7〜9月の電力ピーク時(午後1〜4時)に冷却運転をストップできるよう、午前中に機内の飲料を十分に冷やして冷温を維持することにより、従来タイプに比べ消費電力量が年間10〜15%節約できる、「省エネ型清涼飲料自動販売機(エコ・ベンダー)」を開発した。これまでに約30万台のエコ・ベンダーが全国に設置されている。
次に、家庭内におけるエネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量の用途別内訳推移を見てみると、第2-1-6図のとおり、排出量は30年前の2倍近くになっている。中でも、照明動力による排出量の伸びは著しく、30年前の約3.8倍に達している。
また、家庭で消費される商品やサービスは、その生産、流通の過程、さらには廃棄の各段階でも環境負荷を発生させている。例えば、二酸化炭素について、そのような消費に伴う間接的な排出量まで含めると、我が国の二酸化炭素排出量のおよそ半分は消費に伴って誘発されているとする推計もある。
家庭からの二酸化炭素排出量が増えている背景の一つに、家庭の使用でエネルギーを消費する電気製品や自動車などの耐久消費財の大型化、高級化、大量普及が挙げられる。例えば電気製品については、省エネルギー技術の発達によって1台1台のエネルギー消費量は低下してきているが、その一方で家庭への普及量の増大は著しい。冷蔵庫、エアコン、カラーテレビを二台以上所有している家庭も増加してきており、「一家に1台」から「1人に1台」という傾向が強まっている(第2-1-7図)。また、エネルギー消費量の多い大型のものや高性能のものが選好される傾向にある(第2-1-8図)。技術の発達によって1台1台の機器から生ずる環境負荷量が削減されても、大量消費、大型・高級志向という生活様式の選好によってその効果が打ち消され、全体としては二酸化炭素排出量が増大するパターンが出来上がっていると言える。
イ 廃棄
日常生活で不用とされたものはごみとして排出される。一般廃棄物の1人1日当たりの排出量を見てみると、昭和50年度には1,033gだったものが平成2年度には1,120gへと15年間で8.4%増加し、その後横這いが続いている(第4章第4節参照)。廃棄物の処理に当たっては、不適切な処理が行われた場合、焼却過程における窒素酸化物、ダイオキシン類の発生、埋立による自然の損失や最終処分場からの排水等の環境負荷が生じる場合もある。また、廃棄物の質も多様化しており、プラスチック等自然の中で分解されにくい物質が増加するとともに、家庭からのごみの中にも、フロンを冷媒として使用している冷蔵庫など、処分の方法によっては環境負荷を与える製品が含まれている。
次に、どのようなものが廃棄物として捨てられているのか、京都市における家庭ごみの組成調査の結果を参考に考えてみたい。京都市でもごみの排出量は増加しており、1人1日当たりの家庭ごみの排出量は、昭和56年度には551gだったものが平成9年度には621gに増加している。ごみの内容について見てみると、厨芥類、紙類、プラスチック類の3種類が湿重量ベースで家庭ごみ全体の約8割を占めており、近年増加傾向にある(第2-1-9図)。また、家庭ごみが捨てられる前の使用用途別に見ると、湿重量ベースで、食料品が約4割、容器・包装類が約2割、使い捨て商品が約1割を占めている。
また、厨芥類の内訳について見てみると、35.7%が食べ残しであり、湿重量で13.4%の食品が手つかずのまま捨てられている。野菜や果物がそのまま捨てられている以外に、調理食品や加工食品類がパックされたまま捨てられている場合が多く、品質保持期限又は消費期限前に捨てられている食品も多い。厨芥類の量は、昭和56年度に1人1日当たり262gだったものが、平成9年度には240gと減少している。厨芥類の中身の変化について見てみると、調理済み食品の普及や外食化により調理くずの占める割合が昭和56年の59.8%から平成9年では52.8%へと減少する一方、食べ残しは27.8%から35.7%へと上昇している.(第2-1-2表)。
これらの調査結果から見ると、家庭からのごみの内訳は、食べ残しの増加や容器・包装類の増加といった我々の消費生活をそのまま反映したものとなっている。このような生活様式から生じるごみの質・量の変化が環境負荷を大きくする要因となっている。
ウ 水まわり
日常生活においては、台所、風呂、洗濯、水洗便所等で水が使用され、生活排水として排出されている。これらの排水中には、様々な有機物や栄養塩類が含まれており、海や河川、湖沼における有機汚濁や富栄養化を引き起こす原因の一つとなっている。生活排水による環境負荷は、これらの原因の大きな割合を占めている場合が多い。主な湖沼における発生源別汚濁負荷量をCODについてみると、生活系の寄与が3割前後を占めている(第2-1-10図)。また、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の閉鎖性海域のCODについても、いずれも生活系が5割〜7割を占めている(第2-1-11図)。
これら日常生活からの水質汚濁の原因の内訳(1日当たりの負荷割合(BOD))は、し尿が30%(BOD13g)であるのに対して、台所や洗濯等の生活雑排水が70%(BOD30g)を占めている(第2-1-12図)。台所からの負荷が大きいのは、台所で使用、排出される調味量や油脂等に汚濁負荷量が大きい物質が含まれているためである。これらを用いた食料品を直接排水口に流してしまうと水質に大きな汚濁負荷をかけることになる。
国土庁では、水資源の開発や利用等に係わるエネルギー消費の分析を行い、節水や排水に配慮した水の使用が重要であると指摘した。
エ 自動車の利用
我々の日常の生活様式は、自動車の利用を前提として成り立っている。
我が国の旅客輸送量を人キロベースで見てみると、鉄道、航空に比べ、自動車による輸送量が絶対量も多く、かつ堅調な伸びを示しており、特に地方圏では、自動車交通の役割が都市部よりも大きくなる傾向が見られる(第2-1-13図)。自動車保有台数については、昭和30年代半ばから一貫して増加してきており、また国際的に見ても、我が国の自動車普及率はアメリカには及ばないものの既にヨーロッパ諸国とほぼ同じ水準に達している。
自動車の一人一人の使用状況を見てみると、通勤・通学目的の利用が減少し、買い物・用足し、レジャー目的の利用が増加する傾向にある(第2-1-14図)。また、都市郊外での人口増を反映して、道路交通の便利な郊外に大規模駐車場を設けたショッピングセンター、レジャー施設、レストラン等が増加しており、自動車の利用に一層依存する結果となっている。我が国の場合、ショッピングセンターは昭和40年代半ばまでは中心商業地に立地していたが、道路交通、駐車場確保等の容易さ等から現在では郊外化が進んでいる。平成5年から平成9年の5年間に開店した大型小売店のうち、郊外幹線道路沿いに立地しているものは半数以上となっている(第2-1-15図)。
自家用乗用車は、利用したい時にいつでも利用できるという随伴性、出発地から目的地まで直接ドア・トゥー・ドアで移動することができるという機動性、荷物を持たずに済むといった快適性等、バスや鉄道という公共交通機関にはない利便性を備え、便利で快適な生活を支えている。
しかしその一方、燃料の燃焼に伴って、地球温暖化の原因となる二酸化炭素等を排出している。輸送機関別のエネルギー消費量の推移を見てみると、自家用乗用車のエネルギー消費が大きな割合を占めるとともに、著しく伸びているのが分かる(第2-1-16図)。