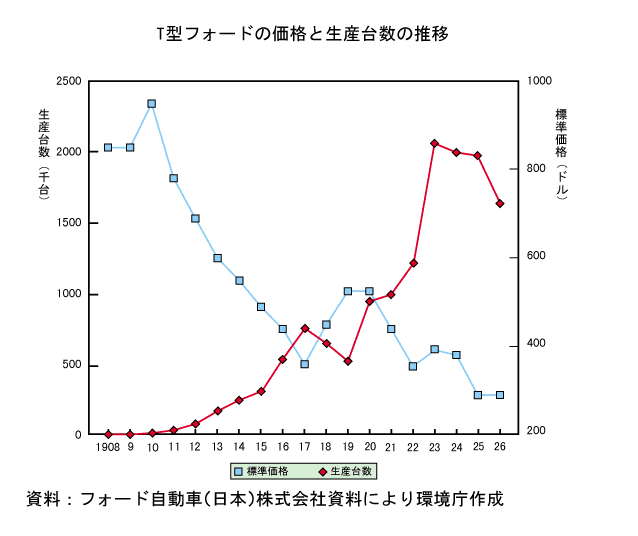
1 20世紀の利便性向上の歴史と環境問題
科学技術の進歩と経済成長、それらに伴う生活行動の変化という観点から、20世紀を以下の4期間に分類し、それぞれの時代区分毎に概観したい(第2-1-1表)。
(1) 科学技術の急速な進歩と都市型消費社会の始まり(1900年代〜20年代)
1908年(明治41年)アメリカ・フォード社が革命的なT型大衆車を発売した。さらに、同社は1913年(大正2年)に流れ作業を基本とする大量生産方式を導入し、1908年には850ドルだった大衆車の価格を600ドルに、1917年(大正6年)には360ドルまで引き下げることに成功した。これにより一般の人々が車を持てる時代が到来した。また、1910年(明治43年)アメリカの電気会社ジェネラル・エレクトリック社によりタングステン・フィラメントを使った白熱電球が発売され、1915年(大正4年)にはアメリカで大陸横断の電話網が開設されるなど、この時期は科学技術が急速に発達した。
我が国においても、大正3年(1914年)の東京大正博覧会の頃から、既に人口200万人を超えていた東京では、都市における高次の消費生活が始まっており、娯楽、ショッピングが人々の楽しみの一つとなった。写真や映画が社会に定着したのもこの頃である。しかし、我が国を始めとする途上国においては、このような都市的な消費活動はほんの一握りの生活者のものにすぎなかった。
囲み2-1-1 「フォード型」開発による生産システムの発展
1908年にフォード社が発売したT型大衆車は、頑丈で軽い車体、4気筒エンジンや速やかな方向転換が可能なセミオートマティックのトランスミッション等の先端技術の使用、そして生産過程の合理化による低価格化から、1年もたたないうちにアメリカ全土にあふれ、1927年(昭和2年)の生産中止まで約1,500万台が普及した。
特にT型大衆車の革新性は、アクセルからギアボックスに至る全ての構成部品が規格化されたことであり、それが1913年(大正2年)にハイランドパーク工場でのコンベア組立ラインによる大量生産方式(フォード・システム)の導入をもたらした。こうして生産効率が向上したT型大衆車は、価格が年を追うごとに安くなり、国民の消費意欲を刺激した。
この生産システムは、後に他の産業にも波及し、今世紀を象徴する「大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システム」を生み出す大きな要因となった。
(2) 利便性の追求と大量消費・大量廃棄パターンの始まり(1940年代半ば〜60年代)
第二次世界大戦が終了したこの時期になると、利便性追求に対する欲望が大きくなり、所得が増加した生活者は、消費行動に向かった。特に、我が国における家庭用電化製品の普及はめざましく、電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビの「三種の神器」は1960年代にほぼ100%の普及率を達成した。1950年代にはテレビ放送が開始され、昭和34年(1959年)の皇太子(当時)御成婚を機に白黒テレビが一気に普及した。さらに、昭和39年(1964年)の東京オリンピック中継を契機にカラーテレビへの買い換え需要が起きた。テレビは、「文明のショーウインドウ」の役割を果たし、視聴者の消費意欲をかき立てることに一役買うとともに、画一的な情報を提供することで、都市型生活様式の全国的な標準化をも実現した。
また、交通面では、昭和30年代半ば以降、モータリゼーション化が急速に進んだ。我が国においては、人口の集中、産業の集積により都市部における移動量が増大し、所得の増加等とあいまって、乗用車保有台数が昭和30年代半ばから急激な増加を続け、昭和46年には1千万台に達した。これに対応するため、行政は道路整備等により交通容量の拡大を進めた。特に、昭和37年に我が国初のハイウェーである首都高速1号線の東京・京橋−芝浦間が開通したのを皮切りに、全国各地で高速道路網が整備され始めた。
しかしその一方で、急速な技術開発からモデルチェンジが加速され、製品の買い換えが進む一方で、まだ使用可能な製品が大量に廃棄されることとなった。
(3) 生活者による環境保護運動の進展(1960年代〜70年代)
ア 産業公害による健康被害と住民運動の活発化
第二次世界大戦後の急速な経済復興とそれに続く高度経済成長の裏側で、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の様々な環境問題が表面化し、住民の生活環境を破壊していった。特に、昭和31年には水俣病が発見され、その後新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病等さらに広い範囲で公害問題が発生した。
このように、全国に拡大する産業公害の被害は、企業中心的な大量生産指向型経済成長への批判となり、昭和42年から昭和44年にかけて相次いで提訴された4大公害訴訟を始めとして、全国で300を超える被害者や住民の団体が激しい反対運動を展開した。
また、1962年(昭和37年)、レイチェル・カーソン女史がその著書「沈黙の春」において、DDT等の生物によって分解されない化学物質は、食物連鎖を通して、上位の動物になればなるほど生物体内に高濃度で蓄積されるため、野生生物や人の健康に影響を及ぼすことを発表した。さらに昭和43年には、製造過程で熱媒体であるPCBが混入した米ぬか油を摂取した1,800人以上の人々が皮膚炎等を発症するというカネミ油症事件が起こった。こうしたことをきっかけに、化学物質による環境汚染に対する国民の関心が高まり、昭和46年にDDTが、その翌年にはPCBの使用が禁止された。
イ 地球的規模での環境に対する危機感の高まりと環境保護運動の進展
1965年(昭和40年)国連経済社会理事会で、アメリカの国連大使(当時)のアドレイ・スティブンソンが、「私たちは、全員が共に小さな宇宙船に乗って旅行している乗客で、わずかな空気と土に依存している」という演説を行った。1972年にはローマ・クラブがこの「宇宙船地球号」の発想をさらに発展させた「成長の限界」を発表したことを機に、地球が閉鎖系でかつ有限であるとの認識が高まり、将来の環境や資源に対する危機感が加速していった。
こうした危機感の高まりは、1970年(昭和45年)4月22日に世界各地で開かれた「アースデー」の催しにつながり、以後1972年(昭和47年)にはストックホルムで国連人間環境会議が開催され、1980年(昭和55年)にはドイツのブレーメンで「緑の党」が誕生するなど、その後の環境保護運動の進展に大きな影響力を持つに至った。
囲み2-1-2 世界における環境保護運動の歴史
我が国においては、平成10年に「特定非営利活動促進法」が成立し、NGOが育つ基盤が整備され始めたところだが、世界における環境保護運動は19世紀末から既に組織化され、社会的に大きな影響を与えてきた。こうした環境NGOによる環境保護運動の歴史には、大きく3つのピークが存在すると考えられる。
第1期は、19世紀末から1920年代にかけてであり、アメリカ、イギリスの中産階級層が中心となって原生的自然や野生生物等の保護を目的とした運動が展開された。例えば、イギリスの「ナショナル・トラスト」(1894年(明治27年)設立)による運動は、1907年(明治40年)に「ナショナル・トラスト法」を制定させるとともに、後に非課税措置を獲得するなど、自然保護の制度化を大きく推進させる原動力となった。
第2期は、1960年代から70年代にかけてであり、経済成長を追求する結果公害問題や有害化学物質問題が生じ、それに対する社会的な抗議運動が活発化した。この運動は、日本、欧米で広く起こるとともに、その対象も、第1期に見られる自然保護だけでなく広く環境問題に拡大することとなった。
第3期は、1980年代後半以降で、環境NGOは、環境問題に敏感な国民世論を背景に、個別問題毎に行政、産業界と対峙し、行政サイドの計画決定プロセスに関与することとなった。環境NGOにおける専門性の強化、その前提となる専従スタッフの増加、組織間での機能分担という特徴も、こうした新しい活動の展開に伴って備わってきたと考えられる。その一方で、例えば、ドイツのWWFドイツやBUNDに見られるように、企業と共同して、環境にやさしい製品の共同展開や地球温暖化防止策の推進のための共同体形成等を行うなど、企業活動に環境NGOが介在することも一般化してきた。
(4) 地球環境問題等の表面化と生活様式に対する問題提起(1980年代以降)
1980年代に入ると、大都市地域においては、自動車から排出される窒素酸化物等による大気汚染や生活排水等による水質汚濁といった都市・生活型公害が深刻化した。また、経済規模の拡大等に伴い、廃棄物の発生量が増大した。
地球的規模で見ると、地上から放出されるCFC(クロロフルオロカーボン)等によるオゾン層破壊の問題や、大気中の温室効果ガス濃度の上昇による地球温暖化問題などがクローズアップされるようになった。また、1996年(平成8年)には、シーア・コルボーンらが「奪われし未来」を出版し、野生生物等に現れた生殖異常の原因が内分泌かく乱化学物質である可能性を指摘、警鐘を鳴らした。
こうした問題は、生活者が、直接的、間接的に被害者かつ加害者である問題であり、その対策として生活様式の在り方まで問い直すことが必要である。平成5年制定の環境基本法においても、「国民の責務」として、「日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない」と規定された。こうした中、消費(商品購入)の段階で環境保全を意識したり、環境家計簿などを利用して消費生活を見直すなどの動きが見え始めた。