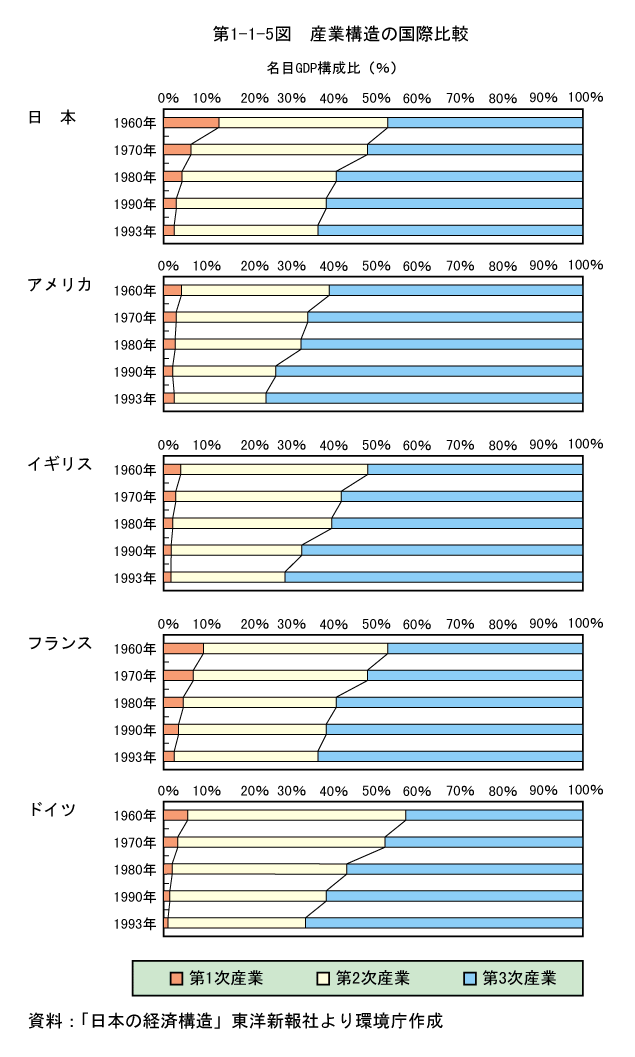
2 我が国の産業構造と物質収支に関する考察
(1) 我が国の産業構造と貿易構造
我が国の産業構造の変化を名目GDPをベースにして時系列でみると(第1-1-2図)、高度成長期を境に70年以降急激に第一次産業のウェイトが低下し、第二次産業も特に製造業を中心に徐々にウェイトを低下させている。一方で第三次産業は一貫してウェイトを高めており、こうした傾向は当面継続することが予想される。
また、日本、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスの産業構造を名目GDPをベースにして国際比較を行うと(第1-1-5図)、アメリカでは第3次産業のウェイトが75%という高水準に達しているのが目立っており、イギリスとフランスも7割とアメリカとの差は縮小しつつある。一方で日本とドイツは類似の傾向にあり、他国に比較して第二次産業、特に製造業のウェイトが高いのが特徴である。
さらに、貿易構造に関し、1993年(平成5年)の日本、アメリカ、ドイツにおける商品別輸出入構造の国際比較を行うと、我が国の輸入商品については、食料自給率の低さや鉱物資源の乏しさを反映して他国に比較し圧倒的に食料品と原燃料のウェイトが高いのが特徴である(第1-1-6図)。同様に輸出商品においては、製品特に電気機器や自動車に代表される機械類のウェイトが他国に比較して高いことが特徴である。
(2) 我が国の物質収支と産業活動
経済活動に投入される総投入物質量や総廃棄物発生量は両者とも年々増大傾向にあり、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済構造が維持されていることが明らかであり(第1-1-7図)、特に、産業廃棄物の排出量は近年4億トン前後で推移している。
また、一部の鉱物資源の枯渇可能性が指摘されるようになっているが、平成9年度の物質収支(第1-1-8図)を見ると、自然界からの資源採取は国内、輸入を含めて全体の投入量の約9割以上を占めている一方、資源の再生利用率は約1割にすぎず、国内の物質収支は、循環性が低く資源採取から廃棄に向かう一方通行の流れであることがわかる。
さらに、建設工事による掘削、鉱滓、畑地等の土壌浸食等の物質量(以下「隠れたフロー」という)は、資源採取量の約1.5倍生じており、海外における隠れたフローが特に多くなっている。
(3) 産業構造と環境負荷との関わり
我が国の経済構造は、大量の原材料を輸入し、それを加工し製品として相当量を輸出する加工貿易を基礎に成り立っているものであり、これは国内需要に加え輸出需要に対応した大量な物質フローやエネルギーフローを生まざるをえない構造とも言える。また、こうした経済構造に起因するグローバルな環境負荷の問題を考えると、第3章でも述べるとおり、諸外国に対し資源採取や製品の製造段階で相当程度の環境負荷をかけている構図が浮き彫りにされる。このような我が国の経済構造や(1)でみた産業構造の変化の特徴を踏まえると、?シェアを拡大しつつある第三次産業における環境負荷の問題にこれまで以上に注意を払うべきこと、?依然として基幹産業と言える第二次産業における生産・物流を中心とした環境負荷の問題にも注目すべきであり、国内での製品製造に伴う国内での環境負荷の発生や原材料、製品の輸入に伴う海外での環境負荷の発生等を削減していくことが必要であることがわかる。さらに?環境管理機能も有する第一次産業のシェアの低下に伴う環境への影響についても着目すべきことがわかる。このような課題を踏まえ、次節では、各産業部門における生産、流通、消費、廃棄段階での環境負荷を低減させる産業活動の方向性について論じていきたい。