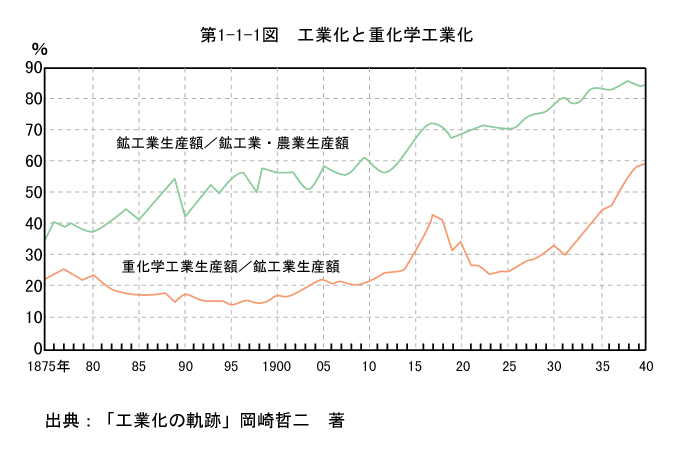
1 我が国の産業構造の変化と環境問題との関わり
(1) 産業革命と重化学工業化の進展(明治中期〜第二次世界大戦)
明治中期以降日本経済は、製糸業、綿紡績業の軽工業を中核として近代産業の基礎を築き、引き続き鉄鋼、機械等の重化学工業の拡充を図ってきた(第1-1-1図)。これらの主要工業のエネルギー源は石炭であり、既に当時、大阪、八幡等の工業都市において石炭燃焼に伴うばい煙による大気汚染現象が見られた。このため、明治39年に大阪府では、有害な活動を行う工場の立地を制限する区域の指定と立地の許可等を内容とする「製造場取締規則」を制定した。また、各地方公共団体においても工業化に応じて工場取締規則の制定や公害規制担当部局(例えば、工場課、保安課等)の設置等が進んだ。
当時、産業活動による被害が社会問題化したケースとして鉱物の採掘等に伴う鉱害問題が挙げられる。明治20年頃からの足尾鉱山の鉱毒事件、明治30年頃からの別子鉱山の煙害事件などは、特定の事業場における事業活動に伴う環境汚染が地域住民の健康や農林水産業などの生活基盤に広範囲かつ重大な被害を与えた事件として、大きな社会問題にまで発展した。
第一次世界大戦前後から我が国の産業活動はますます活発化し、人口の都市集中が始まり、都市の一部に生活環境の悪化も見られるようになってきた。工場等における生産活動に伴って発生するばい煙や排水による汚染、騒音、悪臭等の公害のほとんどがこの時期までに発生している。しかし、生産力、国防力の増強を最優先する体制が次第に強化されていった当時においては、これらの事象も公害問題として特別に取り上げられることはなく、個々の被害について住民からの苦情があった場合に必要な処理を行うにどどまったのが実情であった。
(2) 廃墟から復興へ(戦後復興期)
第2次世界大戦後の昭和20年代前半は、敗戦後の国家復興の旗印の下、産業振興が至上の要請とされ、傾斜生産方式による優先的な資源・資金の配分が行われ、石炭と鉄鋼という素材を供給する基幹産業の育成・振興が行われた。その一方で、公害対策はほぼ戦前と変わらない状態が続いた。しかし、昭和20年代後半に入ると、朝鮮戦争に伴う特需により、産業活動が活発になり、それに伴い各種の公害も顕在化の兆しを見せ、公害問題に対する住民や地方公共団体等の認識も徐々に高まってきた。
(3) 公害問題の顕在化(高度経済成長期)
我が国の経済は、戦後の復興期を脱し、昭和30年代に入ると、急激な経済成長期を迎え、産業構造の変革、エネルギー転換、技術革新等に伴う生産活動の著しい高度化、大規模化が進行していった。
高度経済成長期における産業構造の推移を見ると、高度経済成長期初期の昭和30年からオイルショックの起きた昭和48年の間に、第一次産業(農林水産業)はウェイトを19%から6%まで落としている。その一方で、第二次産業は34%から42%、第三次産業は47%から52%へとウェイトを高めている(第1-1-2図)。中でも、製造業が28%から34%へと大幅に拡大しており、この時期の産業構造変化の中で最も重要な役割を担ったと言えるが、その製造業内部でも大きな構造の変化が起こった。
その1つが、「重化学工業化」である。軽工業、重化学工業それぞれの製造業全体に占める比率を見ると、昭和30年(1955年)では軽工業が55.4%、重化学工業が44.6%であったが、昭和35年にはそれぞれが43.6%と56.4%と逆転し、その差は拡大していった(第1-1-1図)。その後、重化学工業内部における相互作用が需要を拡大し合い、それが積極的な設備投資を引き起こして、日本経済を高度成長に導いたのである。
もう一つが、「エネルギー革命」の進展である。当時の我が国のエネルギー消費量は小さく、石油を輸入する外貨が十分ではなかったため、一次エネルギー供給の大部分を国内炭でまかなっている状況にあった。しかし、我が国のエネルギー消費量の増加、経済成長による外貨事情の改善、石油燃料の利便性等の理由から、昭和36年を境に我が国の石油需要が石炭需要を上回ることとなった。
こうして、工業生産やエネルギー消費量は急激に高まり、これに伴い、工場からのばい煙や排水等の排出量が増大し、広域的な大気の汚染や水質汚濁等の問題を発生させた。特に、エネルギー消費量の増加や巨大コンビナートの形成に伴って、火力発電所や石油化学工場等から排出されるばい煙の中に含まれる硫黄酸化物等による大気汚染が新たな問題として登場した。
こうした問題に対応して、東京都を始めとする大工業地帯を有する地方公共団体において公害防止条例の制定や公害防止協定の締結が相次いで行われた。また、一足遅れて、国も昭和33年の水質汚濁防止に係る法律を制定したのを皮切りに、様々な公害防止のための法律の立法化を進めた。しかし、水俣病やイタイイタイ病等の公害がますます深刻な状況となっていった。そこで、昭和42年に公害対策を総合的かつ計画的に実施していくべく公害対策基本法を制定するとともに、昭和45年にはいわゆる「公害国会」にて14の法律が制定又は改正された。(第序-1-1表)
企業は、規制に追随する形でエンド・オブ・パイプ型の公害対策のための設備投資等を進めた。その一方で、こうした投資需要を見込んで公害防止技術の開発を積極的に進め事業化する企業も現れた。
(4) 省エネ・省資源への取組の進展等(1970年代〜80年代)
1970年代は、オイルショックに伴う資源・エネルギーの価格の高騰、一般社会における節約の風潮、省エネルギー法の制定等により、産業活動における省エネ・省資源の取組が一気に進められることとなった。
第1-1-3図は、製造業におけるエネルギー消費変動要因の寄与度を示したものである。これを見ると、オイルショックから平成2年頃にかけてのエネルギー消費減少要因として、IIP(鉱工業生産指数)当たりのエネルギー消費原単位の低下と製造業における業種シェアの変化によるところが大きい。さらに、第1-1-4図の業種シェアの変化を見ると、1970年代後半から、加工組立産業のウェイトが高くなる一方で、生活関連産業が下がり、1980年代に入ってからは、素材型産業が成熟化して、加工組立産業のウエイトが高まり、製造業における省エネルギー化が進んだ。こうした省エネ・省資源の取組は、主に費用削減のために行われた対策であったが、結果的に環境保全にも資するものであった。
その一方で、このような産業構造の変化により先端技術を利用したエレクトロニクス産業等が発展したが、有機溶剤等による地下水汚染など未規制物質の使用の増大等による新たな公害が生み出された。また、80年代後半からは資源・エネルギー価格が国際的に低下したため、省資源・省エネルギーを推進する経済的動機が低下し、エネルギー消費原単位が低下したにもかかわらずエネルギー消費量が増大した。
また、自動車については、排ガス対策の飛躍的な進展により、アメリカのマスキー法施行や78年の排ガス規制の強化を見事に克服し、その後の日本の自動車の国際競争力を上げることとなった。以上の世界的に類のない厳しい規制に対応するための技術開発がこの時代かなり進んだ。
(5) 環境保全に対する積極的な産業活動への模索(1990年代)
地球環境問題や廃棄物問題等の様々な環境問題の顕在化に対応する形で、廃棄物処理、リサイクル等様々なエコビジネスが形成されてきた。
また、国際的には、国連に設置されたブルントラント委員会が、1987年(昭和62年)に「我ら共通の未来(OurCommon Future)」をまとめ、「持続可能な開発(Sustainable Development)」というキーワードを提示し、事業者側でもその在り方について議論されるようになった。さらに、アメリカの投資家と環境保護団体による「環境に責任を持つ経済のための連合(CERES)」が事業者に環境破壊行為を極力避けること等10項目の倫理綱領を遵守する旨を認めさせる「バルディーズ原則」を発表し、世界の産業界に大きな影響を与えた。
こうした中、平成2年には、経済団体連合会が地球環境問題への対応を包括的に明らかにした提言を取りまとめた。また、平成3年の世界産業会議で、「持続可能な開発のための産業界憲章」に基づく行動計画が採択されたのを受けて、同年4月に経済団体連合会は「経団連地球環境憲章」を発表すると同時に、日本化学工業協会や日本建設業団体連合会によって各業界ごとの環境保全の取組に係る基本指針が作成された。
地球サミットが開催された1992年(平成4年)には、持続可能な発展のための経済人会議(BCSD)が、「チェインジングコース」を出版し、世界の企業の経営者の環境問題への認識の変化を明確にした。日本においては、平成4年に、通商産業省が「ボランタリープラン」作成に関して協力要請を行うとともに、平成5年には、環境庁において「環境にやさしい企業行動指針」が策定され、環境行動計画によって全社的な環境管理を推進する企業が出てきた。こうした状況に加え、企業の地球温暖化対策に対する社会的ニーズを受け、平成8年には、経団連地球環境憲章を発展させた「経団連環境アピール」を発表し、地球温暖化対策、環境管理システムの構築と環境監査、海外事業展開に当たっての環境配慮に向けて具体的な方針を宣言した。これに沿って、会員団体は「環境自主行動計画」を策定し、41業種142団体(1999年1月現在)が参加するに至った。このように、事業者の取組には積極的なものが見られるようになった。(第1-1-1表)