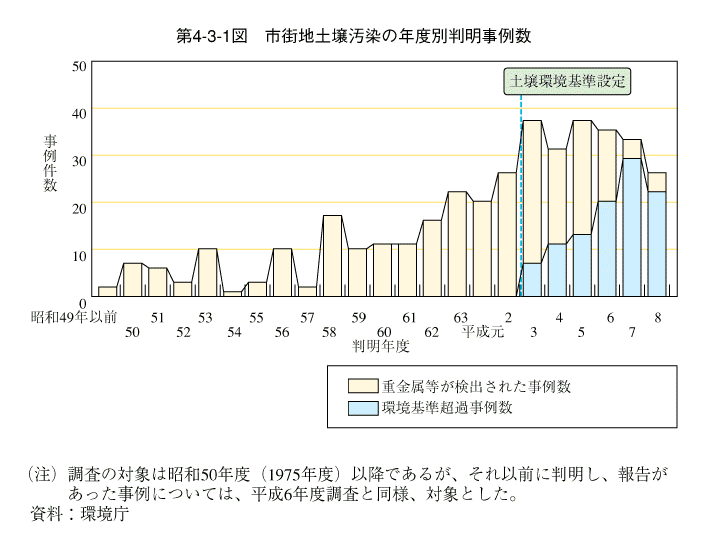
1 土壌環境の現状
土壌は環境の面から見ると様々な働きがある。土壌は物質・エネルギー循環の構成要素の一つであり、無機物、有機物、微生物及び動植物は土壌を媒介の一つとして循環している。また、人間生活の面からみても、農業基盤、天然資源、保水能力及び地下水の形成、多様な生態系の維持など必須のものといえる。従って、土壌の機能が損なわれると、人間をはじめとする生物の生存や、生態系が脅かされるおそれがある。
土壌汚染は、汚染物質が直接土壌に混入する場合と、大気汚染や水質汚濁を通じ間接的に土壌を汚染する場合がある。土壌汚染は一旦生じると農作物や地下水等に長期にわたり影響する蓄積性があり、改善が困難である。また、有機塩素系化合物等による土壌汚染は、地下水汚染につながることが多く、水質汚濁の問題と密接に関わっている。
(1) 農用地の土壌汚染
農用地の土壌汚染については、「水質汚濁防止法」等による汚染発生源対策が行われている。加えて、人の健康を損なう農畜産物が生産されたり、農作物等の生育が阻害されることを防止するため「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(以下「土壌汚染防止法」という)が施行されている。土壌汚染防止法では、カドミウム、銅、砒素について基準値を設け、これを超えて汚染された農用地には客土等の対策事業を行うこととしている。平成8年度は、カドミウム、砒素について、土壌が汚染されている地域のうち汚染範囲の未確定な地域及び汚染のおそれのある地域を対象に調査を行った。この結果、新たに汚染地域として追加された地域はなかった。平成9年10月末時点の汚染検出面積に対する対策事業等完了面積は、検出面積7,140haに対して5,410ha、割合は75.8%(平成7年度は74.2%)となっている。
(2) 市街地の土壌汚染
市街地土壌については全国で汚染が顕在化するケースが増加しており、特に工場跡地等の再利用で土地改変に伴って土壌調査が行われ、土壌中から重金属等が検出される例が頻出している。
これらを物質別にみると、鉛、六価クロム、水銀等の重金属が多い。近年では、金属の脱脂洗浄や溶剤として使われるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる事例も多くなっている。
平成3年8月に「土壌の汚染に係る環境基準」(以下「土壌環境基準」)が設定されて以来、有害物質が土壌環境基準を超過して検出されたとして地方自治体が把握している土壌汚染事例は、平成9年3月までに102件に上っている(第4-3-1図)。
(3) 土壌の浸食
土壌への負荷は汚染だけでなく浸食がある。土壌は、かつては、生成と流亡を繰り返しながら全体としては均衡していた。しかし、現在の土壌の流亡は生成を上回っており、土壌浸食を引き起こしている。土壌浸食は水や風の作用によって起こり、浸食量は気候、地形、植生、土壌種類、人為的要因等により影響される。人為的要因とは過放牧、過度の森林伐採、不適正な農業、大規模開発などである。
我が国は、傾斜地が多く多雨なので浸食を受けやすいが、水田によって、表土流出防止が図られている。しかし、近年の農山村の人口減少等により、水田や森林の保全管理が十分されなくなるおそれがあり、留意する必要がある。