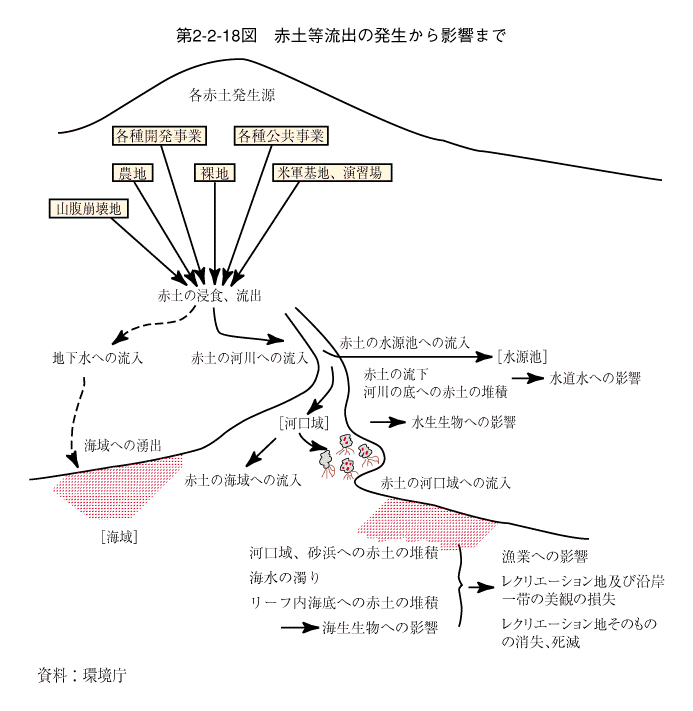
2 流域圏を意識した取組
(1) 流域における自然のメカニズム
自然のメカニズムを全体的にとらえるために適切な範囲として「流域圏」という観点から考察してみる。
流域とは、降水に由来する表流水が一つの水域に集まってくる、そのような領域のことをいうが、ここでは地形、水、生物等にかかる自然のメカニズムと人間活動との調整を行うために適当だと考えられるまとまりとして「流域圏」を取りあげる。流域圏とは、流域と関連する水利用地域や氾濫原よりなる水循環に関する一定の地域的なまとまりとして捉えられるものである。
流域圏を構成する自然的要素の相互関係を示す一つのモデルとして、森林、水(河川、湖沼、海洋)、土及びその中で営まれている生態系との関係をとりあげて具体的に見てみよう。
森林は、様々な生態系が営まれる場となるとともに、水、土の環境資源を保全・涵養する役割を担い、また水、土による豊かな森林形成が行われている。水は、海面等から蒸発した水蒸気が降水となり、森林土壌等に一時貯留され、その後地下水や表流水として流域を流下して海へ至る水循環を形成する環境資源であり、表流水(河川、湖沼、海洋)、表面水(水田、溜め池等)地下水を含む循環系を形成しているが、生活用水、工業・農業用水として人為的にも利用されている。この循環の過程で、森林、河畔林等から供給される栄養塩類、土砂を運ぶとともに、水生生物等の生態系が営まれる場を提供している。土は、様々な生態系が営まれる場であるとともに、森林、水循環を健全に保つ基盤であり、一方森林、水によって豊かな土壌が形成されている。また、水の循環とともに山腹から海域に至るまで、土砂として移動し海岸を形成している。生物は、森林、水、土によって構成されるビオトープに生息、移動、繁殖し、様々な物質循環の一端をになっている。
このように、森林、水、土、生物等は相互に密接な関連を有しているが、このような自然のメカニズムを尊重した形で、人間の経済社会活動を行っていくことが重要であろう。
(2) 流域と人間活動の関係の歴史
明治以前の日本においては、水田を中心とする農業、沢沿いに進展してきた林業だけでなく、人々の生活や物流においても河川や沿海での舟運を活用されることも多く、河川を中心とする流域圏が広域的な生活経済圏を構成していた。日本の農業、林業は森林、水、土資源を利用、保全しながら営まれてきた地域資源を活用した産業であった。この意味で、基本的には流域を構成する自然的要素と人間の経済社会活動の調和が図られていた。一方、急峻な地形条件や厳しい気候条件を持つ流域も多く、水害等、人々の生活は自然から悪影響を受けることもしばしばあった。また、江戸時代における産業の進展により土砂の流出、洪水が生じたり、舟運の発達による流通の活発化に伴い、窯業等が発達し、その結果、燃料材の調達により森林が減少する等、流域の荒廃が人間活動によりもたらされる事例も生じていた。
さらに、戦後の高度経済成長以後は、流域を中心とした地域資源管理システムが急激に変容していった。農山村地域からの人口の流出、第1次産業中心型から、第2、第3次産業中心型への産業構造の変化、自然素材の生産物から各種の工業生産物への代替、食料、用材等の海外輸入の増加等流域資源に依存しない産業形態が進展していった。またダムの築造、用水路の改修、上下水道の発達等による大規模な社会資本に支えられた水利用への転換は、人々を水環境から遠ざけることになった。また流域の雑木林でとれる薪炭を燃料源としていた生活も、水力や火力等の大規模発電所から得られる電気利用にとってかわった。さらに流域と直交するような交通軸と情報ネットワークの形成、経済社会活動の展開が地域資源依存社会を変容させていった。
このようにして、地域の環境資源を活用しつつ保全を図っていたシステムが崩れ、経済社会活動と地域資源とが分離されたことにより、一部の水域において自然浄化能力を超える水質の汚濁負荷が流入しているように、流域の環境容量を越える人口、産業の集中をひきおこし、流域環境は急激に変化してしまった。
(3) 流域圏で捉えることの意義
このような歴史を踏まえ、具体的な事例の紹介を通して、流域圏という圏域の中で、自然のメカニズムと人間活動との調和のあり方を捉えることの意義を明らかにする。
ア 森と川と海と生物との関わり−森は海の恋人−
「森は海の恋人」(畠山重篤著)から少し引用してみよう。
(「 」が一部要約・抜粋部分)
「宮城県の気仙沼湾は、リアス式海岸独特の波静かで水深のある比類なき良港で、全国有数の漁港であると同時に、養殖業も盛んで、牡蠣、ホタテ貝、昆布などが生産されている。この湾の漁場の価値を高めているのが、岩手県室根村に源を発する大川であり、気仙沼湾に注いで遠く唐桑半島まで森の養分を運んでいる。かつて大川河口の三角州は最高の品質の浅草海苔の種場として、そこに続く松岩、階上の海は良質の海藻の取れる漁場として有名であった。これだけ優れた品質と量を誇っていた気仙沼湾の海苔養殖であったが、昭和36年頃を境に異変が生じ、壊滅状態になった。」
このような状況下、唐桑町で漁業を営んでいる畠山氏は、気仙沼周辺の変化に気がついた。「気仙沼の中心地に貫流し気仙沼湾に注ぐ大川では、その河口の干潟が埋め立てられ、湾にそそぎ込む河川のコンクリートブロック化がなされ、さらに河川の水量が減少している。」
大川の上流の月立三ヶ二山は、木炭、薪材に供されていた広大な広葉樹の山であったが、燃料革命により薪や木材の需要が激減するとともに建築材として有用な針葉樹が植えられていた。
「これらの流域の変化が、川や海の生態系に影響を与えなかったか。海苔や牡蠣の漁場がどこでも河口だということは、川が、その上流の森が健全でなければならないのではないか。海は海だけで捉えるのではなく、森、川、海と続く連続性において考えなければ次の世代が生きてゆける優れた環境の海を引き渡せないのではないか?」畠山氏はこのような認識にいたり、まずは、川周辺や森に住む人々と話をする必要があると考え、牡蠣の養殖の漁協組合の人々と大川沿いに住む人々との交流が始まった。上流の林業経営、ダム計画等大川上流域の状況の把握、室根の人々の気仙沼への出稼ぎ等歴史的、経済的にもつながりのあった村に住む人々の再会等々、交流はどんどん広がり、漁民による上流域の植林活動へと発展した。その過程で上流の村である室根村も「今まで大川下流の気仙沼市からは川の水を汚さないでくれとの苦情ばかりいわれてきたが、今では、海の民が川の水、森の恵みに感謝し、植林までもしてくれる。こんな嬉しいことはない、これを機会に海と川との交流をしよう。」と協力が約束された。
現在は、この室根山の植林が進み、ミズナラ、ブナなどの森を「牡蠣の森」と命名し保護されている。
この運動は流域で発生した環境問題をその部分のみでとらえるのではなく、森、川、海と続く一連の生態系の中で考える、すなわち流域圏で捉える必要があることを示している。そして上下流の人同士の交流、経済的な交流等、流域圏の中で環境保全と地域の活性化に向けた取組が行われている事例であるといえよう。
イ 流域の土地利用と川と海と生物 −沖縄の赤土汚染−
沖縄では、降雨等の気候要因、土壌の性質、地形等の特性に加え、昭和47年の本土復帰に伴い、沖縄の振興開発を行うため、農業基盤整備、河川事業、道路整備等の公共工事が集中的に実施されてきたことや、民間企業によるレクリエーション施設、大型観光レジャー産業関連施設等の建設、人口増加による宅地開発、米軍演習場の建設が行われたこと等により、赤土流出による環境汚染が広がった。(第2-2-18図)その結果、サンゴ礁の荒廃、養殖モズクや魚介類等水生生物への悪影響や観光、リクリエーション関連被害、さらに土壌流出による農地、森林への悪影響が生じている。
囲み2-2-1 森は海の恋人
大川上流に暮らす歌人、熊谷龍子氏もこの活動に賛同し以下のような歌を詠んでいる。
「森は此方に海は彼方に生きている 天の配剤と密かに呼ばむ森は海を海は森を恋いながら悠久より愛紡ぎゆく……森は海の恋人………」
海の民と山の民との出会い、交流、植林活動等この美しい活動を支える言葉として「森は海の恋人」という言葉が生み出された。
この問題に対処するため、沖縄県内部での赤土等流出防止対策協議会や関係省庁の連絡会議が設置され、さらに平成7年には赤土等流出防止条例が制定されるなど、発生源対策、流出抑制対策等様々な対策がとられるようになってきた。これらの対策により、一時の赤土等の流出情況等に比べて改善は見られるものの、現在においても赤土等の流出はなお続いている。
平成9年度には沖縄県、関係省庁、事業者等からなる赤土流出防止等対策検討委員会において、流域協議会の設置による流域全体を視野に入れた総合的な赤土流出防止対策が提言されているところである。今後は、流域における各主体の連携した取組が実施されることが望まれる。
(4) 流域の環境保全のための取組
流域保全に関し行政は、土地問題に関しては土地政策、水問題については水質保全、河川管理としての利水、治水等の水政策がそれぞれ別々の行政機関により推進されてきた。流域全体を視野に入れてみると、森林については林業生産、農地については農業生産、河川については水の効率的な排水というように、それぞれの分野での効率化を図るための政策が行われてきた。そのような状況下、水環境は、流域の経済活動に対して受け身がちな立場におかれており、政策としても流域を視野にいれたものは、あまり無かったといえよう。
しかし、昭和52年に閣議決定された3全総において提言された定住圏の一つとして、流域圏が掲げられ、流域の単位で地域のあり方を考えることの必要性が始めて明確に打ち出された。また、平成3年には、森林計画を改めて158の流域単位で編成する森林法改正が行われた。森林の流域管理システムとは、森林を管理する上で合理的な地域の広がりである流域を基本単位として、流域内の市町村、森林、林業、木材産業関係者等の多様な関係者の協議・合意の下に、その流域の特性に応じた、民有林・国有林を通じた適切な森林整備と林業・林産業の活性化を図り、森林の諸機能の維持・向上をめざすものである。さらに新しい全総計画において、「流域圏」に着目した国土の保全と管理に向けた総合的な施策を展開する必要性が示されたところである。
流域保全に当たって重要な問題は森林、水田等の農地、都市である。森林の荒廃、水田の減少、都市の宅地化等の状況の中で、一方「流域」という観点から政策を展開する必要性が認識されてきている。今後、流域環境保全をどのような形で行っていくべきかが大きな課題であろう。以下内外で行われている流域の環境保全に係る取組をいくつか紹介したい。
ア 兵庫県の「流域水環境保全創造指針」
兵庫県では「流域水環境保全創造指針」が策定され、流域一体となった取組が開始されている。
兵庫県では、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、平成8年6月に流域における水質、水生生物、水辺地等の水環境の保全と創造のための指針として「流域水環境保全創造指針」を策定した。これは、県及び関係行政機関の水環境に関する施策間の連携並びに県民・事業者・行政の参画と協働のもとに、流域の特性に応じて水環境の保全と創造を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方向を示すものである。(「協働」は、上記の条例において「様々な主体が協力して働く」ことを意味する造語)指針は、それぞれの流域の特性に応じて水質、水量、生物、親水性、水文化についてそれぞれ水環境保全創造目標を設定し、目標達成のための方策として流域の総合的環境保全、汚濁負荷の低減、水辺空間の保全と創造等を掲げている。流域の総合的環境保全としては、土地利用の際の水環境への配慮、森林の保全等をうたっている。前者に関しては、上、中、下流域一体となった水環境の保全の観点からみてバランスのとれた土地利用及び、流域全体として水と緑のネットワークの形成が可能な土地利用となっていること、さらに流域の水循環における水の貯留と流出入のバランスをとるため、水面の面積を確保することによるストック機能の向上、農地の水環境保全機能向上に努めることを指針に示している。後者においては、森林の有する水源かん養機能等に配慮し、森林地域における樹種、及び樹齢の多様性を確保し、人と森林との共生を図る。このため多様な森林の保全と創造のための支援や公有林化による公益的機能の向上を図ることとしている。
兵庫県においては主要な河川において「流域水環境保全創造方策」(以下「方策」という。)を策定する予定であり、平成7年度から市川を対象流域に選定し、本指針に基づき市川流域の水環境保全にかかる方策を検討しているところである。兵庫県では、本指針及び方策の策定に当たっては、学識者による検討委員会に加え、環境(自然、大気、廃棄物等)はもとより、河川、都市計画、森林、農地、水道等に係る関係部局と共同作業により進め、本指針及び方策が関係各局の施策に反映されるように努めている。例えば、市川の河川環境管理計画は、水環境保全創造指針の内容に配慮して策定されることになっている。
また、本方策は、流域の市町村で検討されている「市川流域アメニティ推進計画」と密接な連携を持って検討されている。さらに兵庫県では、本指針の考え方をさらに沿岸域の環境保全まで発展させるべく、「沿岸域環境保全創造計画」の策定が予定されており、流域圏を捉えた先進的な取組として今後の展開が期待される。
イ 生物多様性保全の観点からみた流域の環境保全
生態圏で紹介した生物多様性保全モデル地域計画においては、現在、流域タイプの生態系のモデル地域として、東京都の町田市と神奈川県の横浜市、川崎市にまたがる鶴見川流域で検討が行われている。
鶴見川流域は、多数の谷戸地形の複合体である。しかし、市街化率は83%におよび、源流の湧水や小川を留める谷戸の生態系は壊滅に近づいている。自然の流れがあり、ドジョウが生息し続けることができそうな谷戸は非常に減ってきており、鶴見川流域で未来の流域市民に引き渡せる可能性のある「ドジョウの暮らせる源流の谷戸」は、おそらく、全流域で、近い将来10カ所あまりに限定されてしまうおそれがある。一方、本流域では、各流域の市民団体の緩やかな連帯組織として、「鶴見川流域ネットワーキング(TRネット)」が組織され、川を軸に行政区画を越えた交流・連携を行っており、鶴見川の再生と水と緑の街づくりを目指して、市民提案やイベントの共同開催など、行政と市民団体とのパートナーシップ事業等による実験的な取組も行われている。
モデル地域計画では、流域地形の入れ子構造配置(多数の谷戸が集まって支流流域となり、複数の支流流域が集まって全体流域となる配置)と生態系のコリドーとしてとらえられる河川の配置を基盤に、地域の多種多様な生物種から構成される生物群集が存続できるような生息・生育地の保全の基盤となるランドスケープ(地形及びその上に成立する動植物で構成される相観の生態系)に着目して、生物多様性保全の拠点となる地域を「生物多様性重点配慮地域」として抽出するとともに、生物多様性回復のための戦略的なプロジェクトとして、学校の多自然化や調整池・ため池の多自然化等を提言し、これらにより本流・支流の各流域ごとに、流域頂点の谷戸(1次流域)を拠点とした生物多様性保全拠点のネットワーク化を図ることが目標とされている(第2-2-19図)。
計画の具体化には、地域一体となった取組が欠かせないことから、流域市民、行政、事業者、学校等の多様な主体の参加による組織的、継続的な連携・推進体制の構築についても検討されている。
このような生物多様性保全施策は、生物多様性保全の観点だけでなく、水環境の保全等、流域の環境保全と密接な関わりを持っている。したがって、流域圏において両者は区別して別々に行われるべきではなく、一体的に行われる必要があろう。
ウ 米国の治水対策の動向
ここでは、米国における治水対策の動向について記述する。どのような方法で洪水による被害を防止・軽減させるかによって、流域の環境に与える影響は異なってくると考えられる。
アメリカ合衆国では、この30年間、河川の氾濫原における都市開発を抑制することで洪水被害を未然に防止する方策も採っている。
近代の土木技術の発達により、アメリカ合衆国においてもダムを造り、堤防を築くことで洪水災害を減らすことに成功したが、それは同時に洪水の危険性の高い氾濫原への定住を促進する結果を招き、かえって洪水災害の大規模化の危険性を高めてしまったとも言われている。また、年々増大する洪水被害援助費用の問題もあり、1968年(昭和43年)に制定された国家洪水保険法では、?洪水による損害の危機に対する適切な保護の住民への提供、?洪水による損害に財産をさらすことの最小化による適切な土地利用(soundland use)の促進、という考えが打ち出された。
1977年(昭和52年)5月の「大統領命令第11988号 氾濫原の管理」の中では、洪水による損失の軽減と氾濫原の自然的価値を保存するため、?氾濫原の占有(occupancy)または改変に起因する長期的・短期的悪影響を、最大限可能な限り回避し、?氾濫原の開発は実施可能な現実的代替案が存在する場合に回避される、という目的を明示している。
また、氾濫原での開発行為の決定権者である当該政府機関は、当該開発行為の代替案を考え、なおも行為が代替不可能な場合には、その理由を公に説明し、氾濫原内に与える影響を最小に抑えるため計画を変更する措置を講じなければならないとし、氾濫原内での行為の計画または提案を一般国民に早期閲覧するよう命令している(参考:「アメリカの自然生態系を守る制度とダム」(財)日本生態系協会)。また、治水対策担当部局の一つである陸軍工兵隊では、従来のダム、堤防等といった構造的アプローチだけでなく、上流域における保水機能の充実等非構造的アプローチを導入する方向性を示している。
国土の75%が山地で、居住可能な平野部が少ない日本では、人口・資産・開発可能区域が氾濫原に集中しており、このような施策の展開は相当困難であるが、洪水被害軽減のソフトな一手法として参考となる部分もある。
このような取組や、充実した社会資本整備を達成した現状を背景に、1994年(平成6年)5月、西部14州における灌漑用水の開発・保全を担当する内務省開墾局の当時の総裁ビアード氏は、「アメリカにおけるダム建設の時代は終わった」と述べている。現在、開墾局はダム建設を行っていない。米国全体でも35のダム(高さ15m以上のものに限る)が建設されているのみである。また、既存ダムのいくつかでは撤去や放流を行う動きがある。例えば、エルワ川のエルワ・グラインズキャニオン両ダムは、先住民族に対する権利侵害等を背景に、撤去されることが決定されており、生態系回復にも資することが期待されている。
エ 流域の人々のネットワークによる取組
複数の都道府県にわたって流れている河川においては、従来は利害の対立する上下流の自治体間の調整がなかなか取れていなかったが、近年河川を軸とした、上下流一体となった自治体や市民を中心とした様々な取組が始められている。宮崎県の大淀川では流域市町村が一体となって統一的な条例が制定され、北上川では民間、行政、事業者を調整するNPO組織である流域連携推進機構が設立され、鶴見川では流域の市民団体でネットワークを作ることに加え、流域の環境保全活動をコーディネートをする法人が設立されるなど、様々な取組が開始されている。
(ア) 桂川・相模川の流域アジェンダ
平成10年に、桂川、相模川では、市民、事業者、行政で構成する流域協議会を設立し、この協議会がアジェンダ21桂川・相模川を策定した。
桂川・相模川は山中湖を水源として、神奈川県を流れ相模湾に注ぐ全長113kmの1級河川で、山梨県内では桂川、神奈川県内では相模川と呼ばれている。(第2-2-20図)桂川・相模川は、横浜市水道による給水や発電、相模ダム、城山ダムなどの築造により、人間活動において様々な形で利用されてきた。そのような状況下、桂川・相模川の水質悪化が進み、下流側の上流側への水質改善の要望が高まってきたが、桂川・相模川の飲料水としての利用状況の相違、人口、産業動向の相違から、水質保全の取組の主体たる上流側と恩恵を受ける主体たる下流側とは、様々な利害関係が生じ、両者はあまり良好な関係ではなかった。さらに、道路交通体系が各県と東京を結ぶ形で形成され、上下流を行き来する交通は十分でなく、また桂川で発電された電気も東京で用いられている等、山梨県と神奈川県との人的、経済的関係も薄かった。
また桂川・相模川の利水者は、流域だけでなく、横浜市等の流域を越えた地域にも広がっており、桂川・相模川の水環境は自然的要素から設定される流域圏を越え他地域とも密接に関わっている状況にある。
このような背景を持つ山梨県と神奈川県であったが、両県にとってかけがえのない桂川・相模川の流域環境を保全するため、昭和55年ごろから両県の対話、協議が始められ、平成4年には「山梨県・神奈川県水質保全連絡会議」が設置され、平成7年から9年度までの3カ年で山梨県・神奈川県との共同事業として、「桂川・相模川流域環境保全行動推進事業」が開始されるまでになった。本事業では、両県で構成する委員会や両県と流域の25市町村で構成され環境庁と建設省がアドバイザーとなった連絡会議が設置され、アジェンダ策定に係る調査・検討が開始されてきた。この間、流域サミット、流域シンポジウム、上下流合同クリーンキャンペーン、住民参加型環境調査等により上下流の住民と行政、事業者との交流が深められた。このような様々な取組を経て本年1月に桂川・相模川流域協議会が設立され、2月には流域環境保全の行動計画となるアジェンダ21桂川・相模川(以下、アジェンダという。)が策定された。
このアジェンダは、策定段階から多くの市民、事業者が参加していることが大きな特徴である。従来の行政計画は、素案が決まった後に市民に公開されており、策定段階から市民参加の下に行われるものはまだまだ少数である。アジェンダは関係するすべての主体に対して具体的な行動方針や行動項目を示すものであり、市民、事業者、行政の協同参画のもとに策定し、自らの行動指針と位置づけていくことが不可欠である。そこで、平成9年度においては、合宿形式の2日間の会議が開催され、市民、事業者、行政がそれぞれの流域の課題について整理しその成果を踏まえ、7月からアジェンダ21桂川・相模川(仮称)検討委員会で、アジェンダの策定協議が行われた。この検討会も、流域住民、電力、酒造、農協、漁協等の各分野の事業者、両県、国の行政機関等の参画のもとに進められた。市民から提出されたアジェンダ市民案の中から、流域の課題の整理を中心に議論が進められたが、市民と行政の間には進め方、課題の考え方等について様々な違いがあり、なかなかスムーズには進まなかった。また、行政の対応の考え方のなかに市民の提案がなかなか反映されなかったり、それぞれの立場のもと意見が対立する場面もよくあった。このような検討委員会における活発な議論、協議の末、「アジェンダ21桂川・相模川」が策定されたのである。
アジェンダは、以下の事項を確認している。
流域の市民・事業者・行政の各主体は
? 未来に引き継ぐ桂川・相模川流域に共通した理想像を想定する。
? この理想像を実現するために、流域に関係する各主体は、所属する社会的グループや居住地域の違いを越えて、協働し努力していく。
? そのために、具体的で効果的な行動計画であるアジェンダ21桂川・相模川を策定、推進していく。
? アジェンダ21桂川・相模川を推進していくため、流域の各主体に平等に開かれた桂川・相模川流域協議会及び地域の自発性に基づき設置される地域協議会を設置する。
? 桂川・相模川流域協議会では構成する各主体の理解と納得の上に立った合意を目指していく。
さらに、アジェンダは桂川・相模川流域の水質保全だけでなく、環境保全にかかる幅広い分野に渡って設定されている。
「良好な森づくり」「多様な生物との共生」「水質・水量の保全」「散乱ゴミや不法投棄のない地域づくり」「開発事業や公共事業においての環境の視点の重視」「市民、事業者、行政の連携した取組」の各項ごとに現状と課題を整理し、環境保全の基本的な方向を示し、具体的な対策に向けた検討事項を提示している。
「良好な森づくり」に関しては、森林を流域の財産と位置づけ、森林の公益的機能を将来的にわたり享受するには、これらの森林を守ってきた山村に活力を取りもどすとともに、上流と下流の広範な関係者が、連携を強化して進めていくことが提示され、上流域で生産される木材を活用して、木製の机を製造し、下流の学校で利用することや下流の住民による森林体験等流域一帯となった、活用システムのありかたについて検討を始めることも関係者では考えられている。
また、上流域で生産された無農薬のクレソンを水源保全のための活動への寄附を上乗せした形で販売するという環境保全を組み込んだ経済活動を行っている団体もある。このような状況下、水質保全に関し、市民による基金づくりの必要性も議論されてきており、上下流の経済活動や、上下流交流という住民の新しいライフスタイルを形成するような取組が検討されている。
さらに、開発事業や公共事業等いままで住民と行政が対立しがちであった分野についても、流域協議会の場で、早い段階で情報を交換し、合意形成を進めていくことが掲げられているのが特徴的である。
桂川・相模川流域協議会は、利害の対立しがちな上下流の市民、様々な事業者、行政がともに組織した流域協議会としては、非常に大規模な組織であり、アジェンダ21の策定に際して、十分な議論が出来なかった課題が多く残されているようである。
しかし、流域協議会という「場」の設定、パートナーシップのもと策定された礎たる「アジェンダ」がきっかけとなって、いままでは個別に取り組まれていた活動が、さらに有機的な連携へと発展していき、流域の適切な環境保全の取組が進められることが期待されよう。
(イ) 北海道の「豊かな海と森づくりネットワーク構想」
北海道は水産資源が豊かなところであるが、「北海道の豊かな海を育て、未来につなぐ」という基本理念のもとに「豊かな海と森づくりネットワーク構想」が平成9年に策定された。北海道の漁村婦人2万人で組織する北海道漁協婦人部連絡協議会では昭和63年から「お魚を殖やすには森林の機能が有効である」との認識のもと、百年かけて百年前の自然の浜を」を合い言葉に植樹運動を続けていこうと「お魚を殖やす植樹運動」に取り組んでいた。このような市民の動きの中、地球規模での環境問題の顕在化、「海洋環境の保全」と「資源の持続的な利用」とのバランスの必要性が高まる等の状況下、北海道では庁内の水産林務部、農政部、建設部、環境生活課の4部の関係部課が連携して本構想が検討されてきた。
本構想では、各種多様な生物が生息する「豊かな海の環境づくり」を実現するためには、森・川・海に至るそれぞれの分野において、行政、事業者、住民が環境保全に向けて主体的に考え、そして共に行動することが最も大切なこととし、そのために沿岸地域の漁業、農業、林業の連携及び農山村、都市住民との連携を推進することとしている。
さらに、この取組を流域上流の都市や農山村地域まで拡大し、森・川・海をつなぐ全道民的な運動として展開することで実現されるものであり、豊かな海の環境づくりによる新しい漁業・漁村の活性化を行うとともに、市町村など関係機関の理解と協力を得ながら、農林漁業者等の事業者と流域住民による森・川・海に至る自主的な環境保全運動を促進して、総合的に豊かな海の環境づくりを進めるものである。また、北海道では、この取組に加え、河川の水質管理と汚染防止に加え、広葉樹林が持つ保水力の保全等を組み合わせる総合的な水対策プロジェクトを開始している。
(ウ) フランスの総合的な流域管理
フランスにおいては、総合的な水環境に関する法律が制定され、流域の取組が制度的に保証されている。この法律の特徴は、生態系の保護、湿地の保全を含めている点に加え、水管理について管理主体と組織を整備することにより、分権化された地方団体を流域単位で組織化しているところにある。流域委員会により、流域、又は流域群ごとに、水の保全、利用及び使用可能な資源の開発にかかる基本方針を定める「水の開発及び管理に関する基本計画」が策定され、この中で、水質、水量の目標及びそれを達成するための事業が定められる。この計画のもと、小流域毎に、国、地方行政関係者、利水者、河岸の土地所有者、農業、商工関係者、自然保護団体等で構成される地域水委員会において小流域レベルでの計画が策定されるという、2段階の仕組みがとられている。小流域における計画は、地域水委員会で案が策定され、関連市町村議会、商工会議所、職工会議所、農業会議所等、さらに流域委員会に諮問されたのち、2ヶ月間住民の縦覧に付され、これらの段階で出された意見に基づき修正が加えられたのち県知事が承認するという各主体の参画が保証された手続がとられている。
この手続きを経て策定された本計画は行政機関の施策を拘束するものとなっている。
(5) 流域圏での取組の視点
流域圏を意識した様々な取組を紹介したが、これらの取組における流域圏での取組の視点は、それぞれの取組が着目する人間活動との関係により、それぞれ注目する視点が若干異なっている。
流域圏の捉え方の基本は、地形的観点からみた流域全体を一体的に捉えることである。しかし、桂川・相模川の事例では、横浜や横須賀等地形上の流域外の地域の取水がなされている関係上、流域外の人々も積極的に参画している。このように上下水道の設置の仕方等人間の経済活動との関係からは、本来の流域外の地域を含めて取り組むことも必要であろう。
また、流域内における取組においても、流域全体の地域の人々の参加によるネットワーキングや「森は海の恋人」の事例等水によってつながれた上下流の人々との連携という形がとられている。
さらに、土地利用と水環境の保全との関係でいえば、アメリカの氾濫原での取組のように、流域の中でも河川及びその周辺(河道、湿地、河畔林、氾濫原等)を中心に捉えた取組もあろう。
流域圏を捉えるに当たっては、このように地域の実情に応じ、全体として適切に流域の環境保全を行えるような形で行っていく必要がある。その際に、流域を構成する様々な自然的要素をトータルに捉えるとともに、様々な人間活動を流域単位で調整する仕組みが重要である。
ここに紹介した事例は、地域を流域圏として捉え、その中における自然のメカニズムと人間活動を調整する仕組みを模索する事例として非常に参考になろう。