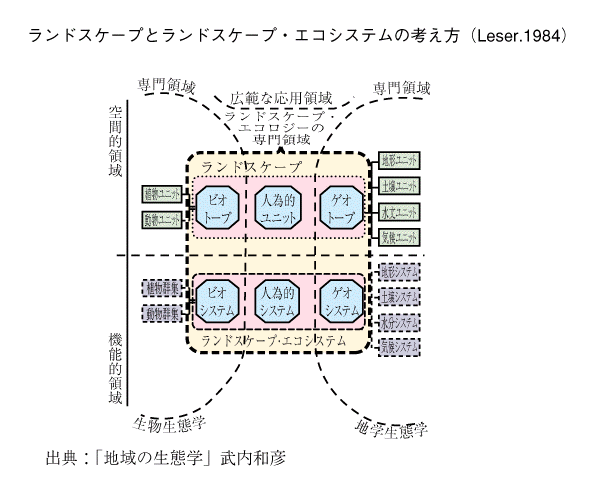
4 環境保全の観点からみた地域の捉え方
従来からも、自然のメカニズムと人間活動が乖離している状況を改善するための様々な対策は講じられてきた。例えば、3でみた生態系の維持に関しては、貴重な生物の生息空間の保全、捕獲の規制等の施策が実施され、水質汚濁、大気汚染対策も、結果として生物の生息環境の保全に役立ってきたといえよう。しかし、これらの施策は、もっぱら直接的な悪影響を緩和する施策、すなわち「配慮」を試みたものではあるが、必ずしも自然のメカニズムの「全体の把握」に基づき、これと人間活動との相互関係を十分に認識した上での施策ではなかったのではないか。
自然のメカニズムを全体として捉え、人間が自然のメカニズムに配慮した活動を行いやすい仕組みを作るためには、自然のメカニズムがある程度完結している、空間的な「まとまり」を見出し、この「まとまり」の中で交錯する、自然のメカニズムと人間の活動との関係を分析し、論じることが有効であると考えられる。
本章では、このような「まとまり」を「環境保全の観点からみた圏域」としてとらえ、その中での様々な取組を見ながら、自然のメカニズムと人間活動のありかたを論ずることとする。
ここでいう圏域とは、「地域空間において認められる空間的な単位や、その相互的に作用し合うまとまり」と定義する。これまでも、様々な形の圏域が提示されてきた。例えば、都市を中心に一体的に整備する必要がある地域として「地方生活圏」が、広域化する住民の日常生活圏に対応し、都市および周辺農山漁村地域を一体とした地域社会の振興を図る「広域市町村圏」、さらに3全総においては流域圏、通勤通学圏、広域生活圏を単位とした生活の基本的圏域としての「定住圏」構想が提示された。これらは、人間の活動の空間的な範囲から形成される圏域である。 環境保全の観点からみた圏域として、ここでは3で整理したような自然のメカニズムを構成する「国土を構成する自然的要素」、「国土を構成する人間的要素」のそれぞれを基礎とする圏域を考えてみよう。
前者について、国土を構成する自然的要素を健全に保つという観点から様々な圏域が考えられる。例えば、大気環境の観点からは、大気汚染の発生源と影響を受ける範囲を捉えたもの(酸性雨・光化学オキシダント等)や、温暖化を引き起こす物質の排出と地球温暖化の影響を受ける範囲を捉えたもの等各種の大気圏が想定される。また水環境の観点からは、一つの河川の流域や、湾や内海等閉鎖性の水域へ流れ込む河川を持つ地域全体を捉えた水圏等が考えられよう。さらに、各種の生物種の保全の観点から、一定の広がりを持った生物生息空間や、点在しているが相互に密接な関係を持った空間等(渡り鳥の生息空間)もそれぞれ圏域として捉えることができよう。
国土を構成する自然的要素は相互に関連しており、これに人間活動も加わって、さらに複雑にからみあい、国土の全体、そこでの自然のメカニズムを構成している。国土を構成する諸要素全てを同時に含んだひとつの空間的範囲を提示することは困難であるが、複数の要素をある程度まとめてとらえることのできる空間の範囲を想定することは可能であると思われる。
ここでは、仮に自然のメカニズムを全体としてとらえるための圏域として国土を構成する複数の要素をある程度まとめてとらえることのできる2つの圏域を設定してみたい。
一つは、生態系を健全に保つという観点から、様々な生物の生息域をある程度空間的な広がりで捉えることができることから、その広がりを生態域としてとらえ、それをここでは、「生態圏」と呼ぶ。もう一つには、地形、水、生物等にかかる自然のメカニズムと人間活動との調整を行うために適当だと考えられるまとまりとして「流域圏」を取りあげることとしたい。流域圏は、新しい全総計画において提唱されている視点であり、流域と関連する水利用地域や氾濫原よりなる水循環に関する一定の地域的なまとまりとして捉えられるものである。
この2つの圏域を題材に、圏域の捉え方、及びその圏域を捉えることにより可能となる自然のメカニズムと人間活動との調和のあり方を考察する。
囲み2-1-1 エコシステムマネジメント
エコシステムマネジメントとは、新しい生態学の知識を取り込み、時間・空間スケールを拡大し、景観・生態学的プロセス・人間と他の生物との相互のつながりを重視するという概念である。その内容や実行の仕方についは様々な議論、見解があり、試行錯誤で実行されつつあるところであるが、柿沢氏(北海道大学)の整理によれば、
? 単なる資源管理の手法ではなく、思想・哲学としての側面を持つ。
? 状態としての生態系の保全・回復に焦点をあてる。
? 生態系・社会・経済を統一的に考える。
? 実行にあたっては第1に市民・研究者・資源管理者が議論を尽くし、協同で決定を行うことが求められる。
? 第2に、複雑な生態系とそれを取りまく社会を前提とし、資源管理を行うため、計画・実行・モニター・モニター結果の評価とその計画への反映というサイクルを繰り返していく必要がある。
この?がエコシステムマネジメントにおいて最も重要な要素である。
(参考 Principles of Ecosystem Management WRRC College of AgricultureThe University of Arizona)
なお、このような圏域の捉え方は、最近研究が進んでいる「エコシステムマネジメント」や「ランドスケープエコロジー」の考え方とも関連性が見いだされる。
次に、人間の活動を基礎とした「まとまり」についても考えてみようここでは、人間の経済、文化、社会的活動の領域をもとに、自然のメカニズムとの調和、悪影響の緩和を図っていくのに、適当なまとまりを圏域の一つとして想定してみたい。人間の経済社会活動は多種多様にまたがるため、ここでは「生活経済的環境圏」(以下、「生活経済圏」という。)として包括的に捉えることとし、具体的な取組を通して、生活経済圏を構成する要素等について考察することとする。
(第2-1-3図)
本章では、上記の3つの圏域それぞれについて、圏域の捉え方、圏域の中での、環境保全の取組のあり方、人間の経済活動のあり方を具体的な事例の紹介を通して、「全体の把握の欠如」及び「配慮の欠如」に対処する今後の方向性を考察していくこととしたい。
平成5年に策定された環境基本計画は、持続可能な形での環境を賢明に利用することを通じて、地域地域における多様な生態系の健全性を維持・回復するとともに自然と人間との豊かなふれあいを保ち、自然と人間との共生を確保し、環境への負荷が少ない循環を基調とする経済社会システムを実現することを目指したものである。
また新しい全総計画の中でも「生態系ネットワーク」「流域圏」といった自然のメカニズムを意識した考え方や豊かな自然と都市域サービスをあわせて享受できる自立的な生活圏域である「多自然居住地域」の創造を進めることが示されている。
国土を圏域で捉え、「全体の把握の欠如」と「配慮の欠如」の解決を目指すことは、いいかえれば、環境基本計画の長期目標である「循環」と「共生」を同時に達成する手法を模索するものであるといえよう。
囲み2-1-2 ランドスケープエコロジー
近年、人間と環境とのかかわりを生態学的視点から分析・総合・評価し、人間にとって望ましい地域環境を保全し、創出する手法を考える分野として、ランドスケープエコロジーという概念のもとで、研究、実践が試みられるようになってきている。ランドスケープとは、主体ー環境系的な環境観に基づく、人間を主体においた環境の総体としてとらえたものであり、具体的には無機的な土地自然のシステムとしてのゲオトープ、有機的な生物自然のシステムとしてのビオトープに人間の活動単位を組み込んだもののことをいう。ランドスケープエコロジーでは、生態系そのものの構造・機能の解明というよりも、構成要素全体を視野に入れて、環境の質を評価し、望ましい環境の保全を図ることを目的としている。国土を構成する自然的要素と人間的要素との相互関係を考える際に、生物共同体とそれを取り巻く環境条件の間に存在する総合的かつ複合的な相互作用を捉えるランドスケープエコロジーの考え方を基礎として考察することができる。
さらに、地域の自然環境を一つの全体像として理解するためには、自然生態系を構成する要素の垂直的関係と生態系相互の水平的関係の解明が重要である。垂直的関係とは、高木層、草本層等の構成要素の相互関係、地形・地質、土壌、水、植生、動物群集、気候などの立体的な相互関係のことをいう。水平的関係とは、垂直的な構造を一つの生態系と見立て、複数の異なる生態系の地域的な広がりと相互のつながりとの関係のことをいう。 (参考 「地域の生態学」 武内和彦)