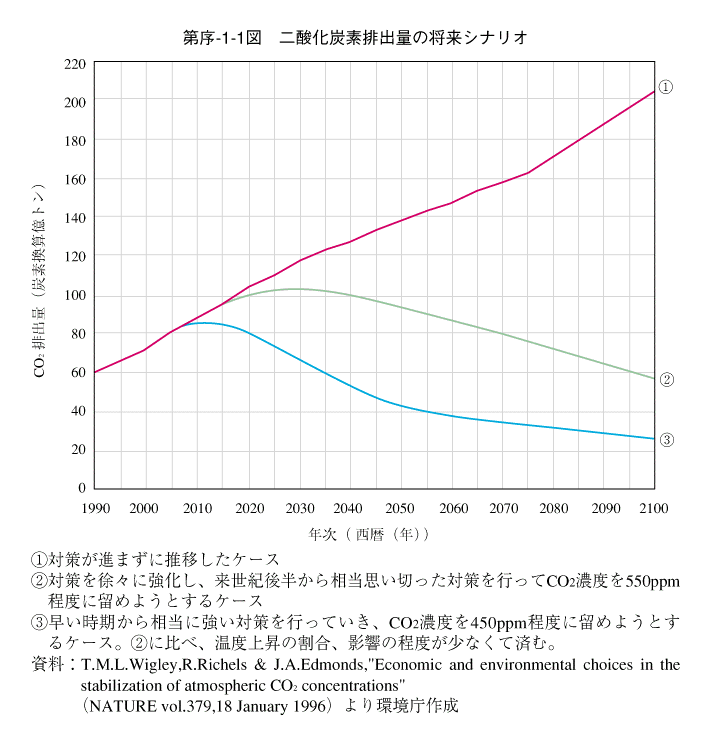
5 京都会議から見えてきた21世紀への課題
さて、困難な交渉の末、「京都議定書」という成果を生んだ京都会議について、改めてその意義を考察するとともに、今後の課題を整理してみよう。
最終日まで各国の意見が激しく対立する状況が続いたが、最後に我が国、米国、EUの3極がリーダーシップを発揮し、附属書?国全体で1990年比5%以上の削減を行うとの法的拘束力のある目標を規定した京都議定書を全会一致で採択し、温室効果ガス削減という困難な課題実現への第一歩を記したことにより、京都会議は成功として評価することができるだろう。さらに、我が国が招致した会議で議定書の採択を実現したことは、今後我が国が主導して地球環境問題の取組を進める上で、大きな意味を有するものであったということもできよう。
なお、「まず先進国が温暖化に対する責任を果たすべき」と主張してきた途上国は、結局自らの取組については自発的なものを含めて今回の会議で定めることに合意しなかった。これは途上国に新たな義務を課さないとしているベルリン・マンデートの下ではいたしかたないことではあるが、2010年にも途上国全体の排出量が先進国全体の排出量に追いつくことが予想される中、世界的な地球温暖化防止対策を進める上で今後に大きな課題を残した。最大の排出国である米国の議会が「途上国が排出抑制の具体的な約束をしない限り京都議定書を批准すべきでない」と決議していることから、途上国の問題は、議定書そのものの発効に響きかねない問題となっている。
大気中のCO2濃度とCO2排出量との関係については、IPCC第2次評価報告書がいくつかの予測を提供している。同報告書によれば、二酸化炭素の濃度を現在のレベル(約360ppmv)に抑えるためには、二酸化炭素排出量を直ちに50〜70%削減することが必要とされている。また21世紀末には、人口やGNPが大幅に増えることにより、このまま成り行きでいった場合には世界全体の二酸化炭素の排出量が今日の排出量の3倍弱(中位の予測)になるとされている。二酸化炭素の大気中濃度を産業革命前レベル(280ppmv)の2倍以内に抑えるためには、次世紀において世界全体の二酸化炭素の排出量を今日の排出量以下に減らすことが必要となり、さらに次世紀の末期以降においては大幅に減らさなければならない(第序-1-1図)。
ここで留意しなければならないのは、上記の排出抑制目標は、先進国のみのものでなく、今後人口が急速に増加することが予想され、かつ先進国を目指して経済発展を行おうとしている途上国も含んだものであるということである。上記の目標を達成するためには、現在我が国において1人当たり炭素換算で2.6トン余/年排出している二酸化炭素排出量を、2100年において世界全体で1トン/年以下にまで減らす必要がある。
途上国における二酸化炭素の排出量が急激に増大しつつある状況を踏まえると、途上国も早期に二酸化炭素排出量を抑制していくことが必要となる。しかし、途上国は排出抑制をするための財政的、技術的困難に直面しており、また、先進国が既に大量の二酸化炭素を排出している一方で途上国に二酸化炭素の排出抑制を課そうとしていることに不信感を持っている。そのためにも先進国が率先して二酸化炭素排出量の削減を行うとともに、クリーン開発メカニズム等を通じて、二酸化炭素排出量の抑制と、生活水準の向上が両立しうることを示し、途上国が二酸化炭素排出量を抑制しやすい状況を作り上げることが必要であろう。
とはいえ、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出抑制は、特に二酸化炭素が人間活動のあらゆる場面から発生しているだけに、この排出を大幅に抑制する方法を探るということは、対症療法で済むものではない。また、次節において詳しく述べるとおり、地球温暖化の問題は実のところ現在の経済社会システムがもたらしつつある様々な問題の一端であることから、これらの問題を解決するためには、とりもなおさずこれまでの我々の活動とその前提になってきた経済や社会のシステムの根本を問い直し、21世紀に生きる我々が目指すべき経済や社会のシステムの姿を明確に念頭に置きながら、地球温暖化問題をはじめとする様々な環境問題を克服していくために何をする必要があるかという航路を定め、進んでいくということが必要である。
我々がこのような重大な岐路に立たされたということを改めて認識させたという点で、京都会議は21世紀に向けての重大な節目というべき会議であるとともに、これから迎える21世紀に向けて、我々が大嵐に遭い転覆せず、無事に目的地へたどり着くための航海の出発地として位置づけることができるだろう。
今年度の白書では、上記の問題意識を踏まえ、目指すべき「目的地」である経済や社会のシステムの姿と、そこへ向けてどのように漕ぎ出せばよいかについて、現実に動きつつある数多くの事例を紹介しながら望ましい方向性を示していくこととしたい。まず、次節ではこの航海の概観として、我々の経済と社会のシステムをめぐる状況がどのようなものであり、それがもたらす環境への影響を避けるためにどのように変わる必要があるのか、おおよその方向性を描くこととしたい。