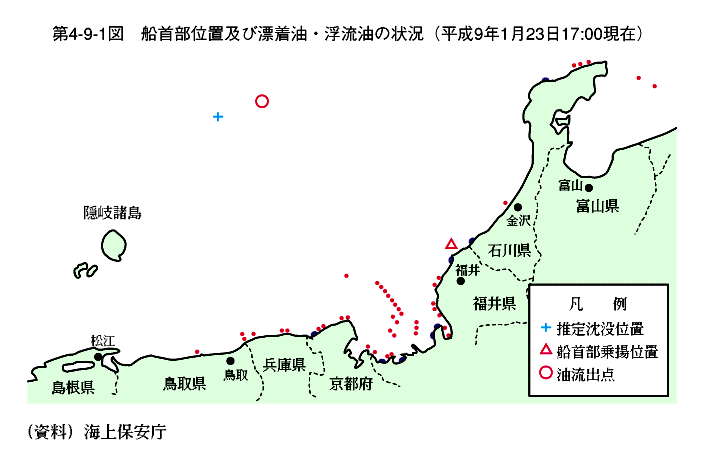
(1) これまでの油による海洋汚染
ア 油による海洋汚染の仕組み
原油は、多くの種類の炭化水素化合物から構成されており、海洋に流出すると、一部は蒸発し、その残りは海洋中で拡散しながらムース状から油塊(タールボール)へと変化する。ムース状になった油には水が分散して含まれており、粘性が高く、回収が困難になる。また、海上を浮遊するうちに比重の重くなった油塊(タールボール)の一部は海底に沈む。
海洋への油の流出は、海を生活の場とする生き物に大きな被害を与える。また、油の中に含まれる分解しにくい成分は長期間にわたって海中や海底に残留する。海岸に漂着した油は砂地にしみこむので分解にさらに時間を要し、また、波にさらされることで再び海水にしみ出したりするので、汚染は長期化する。
イ 油による海洋汚染
油による汚染については、気象庁の海洋バックグランド汚染観測では、日本周辺海域で浮遊タールボール(油塊)が観測されている。船舶の故意及び取扱不注意による流出のほか、大規模な被害に結びつくおそれのある海難事故による原油の流出が懸念されている。1989年(平成元年)のアラスカ沖での「エクソン・バルディーズ号」の座礁、1993年(平成5年)のスマトラ沖での「マークス・ナビゲーター号」の事故や、1994年(平成6年)のオマーン、フジャイラ沖での「セキ号」の事故、1996年(平成8年)のイギリス、ウェールズ沖での「シー・エンプレス号」の座礁など依然として積載原油が流出する事故が絶えない状況にある。
ウ 国際的な枠組み作りの動き
こうした流出原油は自然環境の中で分解されるまでに長い年月がかかり、海洋動植物などの自然生態系に大きな影響を与える可能性が高いため、国際海事機関(IMO)を中心として、「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)の採択、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)の改正(タンカー二重船体構造化)等の取組みが進展している。OPRC条約の締結に際して、平成7年5月、油流出事故を発見した船舶等の最寄りの沿岸国への通報、油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書の備置き等を規定するための「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の一部改正が行われた。また、OPRC条約が平成8年1月に我が国について発効することに伴い、平成7年12月に同条約に基づき締約国に義務づけられる「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」が策定された。
(2) ナホトカ号油流出事故の環境への影響
ア 事故の経緯
平成9年1月2日未明、ロシア船籍のタンカー「ナホトカ」号(13,157G/T、船長及び乗組員合計32人)がC重油19,000klを積載し航行中に荒天のため島根県の隠岐島沖で船首部を折損した。これにより、推定6,240klのC重油が流出し、また船首部分は推定約2,800klのC重油を搭載したまま漂流を続け、1月7日に福井県三国町沖に漂着した。さらに、船尾部分は推定約9,900klの重油を積載したまま水深約2,500mの海底に沈没している。流出した油は、島根県隠岐島沖から秋田県の日本海側各地沖にかけての海上を漂流し、その一部は福井県沿岸を中心に1府8県の海岸に漂着し海岸部を汚染した(第4-9-1図)。
今回の事故では、海上に流出した油の拡散、漂着を防ぐために張られたオイルフェンスが、荒天の続く日本海の高波のため破られ油の流出をくい止めることができず、また、空中散布装置にて油処理剤を使用したものの、その効果及び海洋生態系への影響等から、沿岸付近での科学的処理が制限された。海面を漂流する間に荒波にもまれ、粘性の高いムース状となった油は、機械での除去が困難となり、その多くをひしゃくなどでのくみ取りに頼らざるを得ず、また海岸に漂着した油はヘラ、バケツ等で取り除くことが必要であった。いずれの作業も人の手に頼らざるを得ず、冬の日本海での作業は厳しさを極めた。
イ 事故による影響
この事故による影響は、水棲生物や海鳥の生態系や漁業を中心に深刻である。漁業においても、大きな被害が発生した。最盛期と重なった岩ノリは大きな被害を受け、貝類及び海草類への被害、さらに定置網等の沿岸漁業への被害が懸念されている。
ウ 国における対応等
この事故への取組として、運輸大臣を本部長とする「ナホトカ号海難・流出油災害対策本部」を設置し、流出油防除等の応急対策、その他対策に取り組むとともに、内閣官房長官主宰による「ナホトカ号流出油対策関係閣僚会議」を随時開催し、応急対策のほか、流出油被害対策、再発防止対策等及び大規模油流出事故への即応体制等について総合的な取組を行った。
環境庁においては、この事故に係る環境影響について、関係省庁と連携しつつ、水質・底質の油汚染状況、魚介類中の重油含有成分等、油による大気汚染状況、景観及び海域・海浜生物への影響、海鳥類への影響及び流出油の成分の特定、環境動態の解明について、調査を行っている(第4-9-2図)。また、関係省庁・関係地方公共団体においても、環境調査等を実施している。
また、今回の事故に関しては、地元に人々による積極的な取組に加え、発生当初から全国のボランティアの活躍がめざましかったことが特筆される。3月31日現在で延べ27万人を超えるボランティアが漂着油の除去作業等に従事した。今回のように機械等による油の除去が困難で人の手によるくみ取りに頼るしかない状況において、こうした人々の自主的な協力は、環境の回復に寄与し、また地元の人たちを大きく力づけた。
今後の取組としては、油の除去作業等一日も早い環境の回復のために全力を尽くすとともに、今後への教訓として、迅速で適切な初動対応を可能にする体制等の確立が求められる。