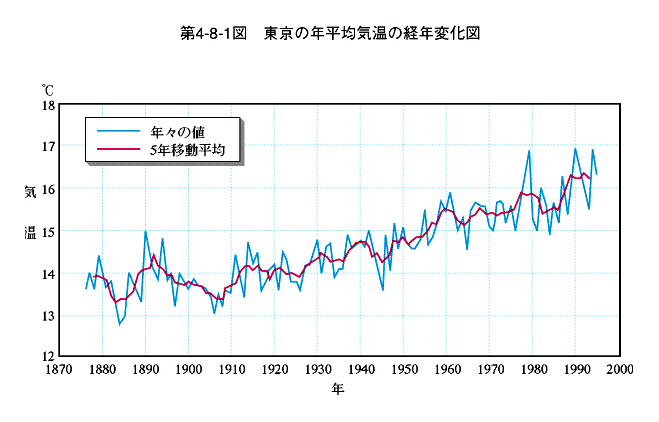
(1) ヒートアイランド
首都圏などの大都市圏においては、ヒートアイランド現象と名付けられた典型7公害とは全く異なった現象があらわれている。都市では高密度のエネルギーが消費されており、加えて都市の地面の大部分はコンクリートやアスファルトなどの乾燥した物質で覆われているため水分の蒸発による温度の低下がなく、日中蓄えた日射熱を夜間に放出するため、夜間気温が下がらない状態になる。この結果、都市部では郊外と比べて気温が高くなり等温線を描くとあたかも都市を中心とした「島」があるように見えることから、この現象はヒートアイランド現象と呼ばれている。
このような現象は東京などの大都市ではすでに日常生活の中で実感できる程までになっている。例えば東京の年平均気温を見ると、第4-8-1図にあるように1870年代の約14℃からこの120年の間に2℃も上昇し、年平均湿度も約77%から約63%へと下がっており、ヒートアイランド現象がその一因と考えられている。特に夏には、エアコンの排熱が室外の気温をさらに上昇させ、また上昇した気温がエネルギー需要もさらに増大させるという悪循環を生み出す。
これに対し、緑地は、植物が葉面から水が蒸発する際に周りの熱を奪うため気温を調節する機能を持ち、都市内河川や海域などの水辺もヒートアイランド現象を緩和する効果を持っているといわれており、緑地や水辺地などの自然地域が持つ様々な特長が注目を集め、都市における自然地域の重要性が増している。
(2) 光害(ひかりがい)
光害とは、屋外照明の光が周囲に漏れて、眩しさを感じることや動植物に悪影響が及んだりすること等をいう。夜間の照明光が上の方向に漏れ、大気による散乱で空が明るくなることにより、星が見えにくくなることも光害のひとつであり、天文観測が困難になる。また、ほうれん草や水稲等の作物は夜間の明るさと生育不良に大きな関係があることや、アカウミガメの産卵地では水銀灯等の紫外線を多く含んだ照明によって、子ガメが惑って海に向かいにくくなること等の例も報告されている。夜間の屋外照明は安全確保や都市機能維持に不可欠であるが、不適切な照明は交通安全に悪影響を及ぼす可能性があり、過剰な照明はエネルギーの浪費にもつながるものである。
環境庁が昭和63年度から実施している全国星空継続観察(スターウオッチング・ネットワーク)の結果によると、市街地を中心として夜空の明るさが増している傾向があることが報告されている。平成8年度夏の観察比較では、巨大都市と小都市では、2.0等級の明るさの違いが見られたが、これは両者の間で約6.25倍も明るさが違うことを示す(第4-8-1表、第4-8-2図)。
平成6年度の光害に関する環境モニター・アンケート調査からも、過剰な光の氾濫は、エネルギーの無駄遣いと考えている人が多く、また、都市の規模が大きくなるにつれ、星空が見えにくくなっていること等が明らかになっている(第4-8-3図、第4-8-4図)。
このため、平成8年3月には「百武すい星」の接近を中心に星空観察とライトダウンの呼びかけが行われ、381団体の観察会実施と62地区でのライトダウンの協力がなされた。さらに、へール・ボップすい星の接近に際しては、「環境庁へール・ボップすい星ライトダウンキャンペーン」(呼びかけの期間:平成9年4月1日〜4月6日)を展開し、全国各地で地域ぐるみのライトダウンが行われた。こうした取組は、屋外照明の適切な使用のあり方を考え、省エネルギーに対する取組を促進する上で絶好の機会である。
夜空の明るさの問題等に対して、国内では岡山県小田郡美星町が、全国に先駆けて光害防止条例を制定し、屋外照明に基準を設けているほか、海外では、アメリカのアリゾナ州ツーソン市をはじめ、欧米の各地で条例が制定されている。
(3) 日照阻害、風害、電波障害、電磁界による健康影響、花粉症
典型7公害以外の苦情の種類別苦情件数の推移を日照阻害、電波障害、風害(通風)について見てみると、日照阻害は平成7年度は53件と連続して低水準を維持している(平成6年度,42件)。日照阻害についての苦情件数は、地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数であるが、実際は別の窓口で受け付けているものも多くあり、必ずしも改善されたとは判断できない。また、地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた電波障害についての苦情件数は平成7年度は387件となっており、最近5年間では減少している(平成6年度,414件)。同様に通風についての苦情件数は平成7年度18件(平成6年度17件)であり、他の苦情件数と比較して低い水準で推移している(第4-8-5図)。
電磁界による健康への影響については、国内外で数々の報告がなされているものの、未だに関係が明らかではない。このため環境庁は平成6年度に超低周波電磁界について「電磁環境の健康影響に関する調査研究」を実施し、電磁界暴露の健康影響の有無については結論づけることができないため、疫学的研究等に必要な技術的事項に関する課題を解決し、具体的な研究方法を確立することが必要であるとの報告を取りまとめた。今後は、この指摘をふまえ、家庭や職場などの個人の日常生活の違いを考慮した電磁界暴露量推定方法等について調査研究を続けていくこととしている。
また、毎年2月から4月の春先にかけて悩む人の多いスギ花粉症については、発症メカニズム等について未だ不明な点が多く、ディーゼル排気微粒子(DEP)などの大気汚染物質との関係を指摘する研究報告もあることから、環境庁では、ディーゼル排気微粒子(DEP)と花粉症の関係について動物を用いた研究、花粉症情報の提供方法のあり方に関する研究や花粉症発生の素因に関する研究を行っている。